『The Way Back』 by ジェイミー・フューワリー 訳 藍(2021年07月09日~2022年07月03日)

トムとエズミーの話と同じ作家の小説です。(トムとエズミーの話はまだ途中ですが、藍はパラレルワールドを行ったり来たりしていないと、頭の風通しが良くないというか、息が詰まるので、またまた平行翻訳します!!)←知らね~よ!笑
〔『帰る道すがら』を5行で要約〕←1行でまとめろや!笑
最初に登場するジェリー・カドガンは亡くなります。ジェリー(父親)には心残りがありまして、3人の子供(パトリック、カースティ、ジェシカ)がいるのですが、3人とも仲が悪くて、ちっとも実家に帰ってこないのです。そこで、遺書的なメモに、「俺の車に乗って、俺の遺灰をどこどこまでみんなで運んでくれ」と書き残します。そして彼の死後、彼の子供たちは、父親の車に乗って、道すがら、父親のことや、自分たちのことを話しながら、家族として仲直りし、ホームへ帰る、という話です。
なんですが、藍は結婚したこともなければ、父親にもなったことないし、実年齢こそ40代半ばですが、人生の経験値的には、たぶん20代半ばの人でも、藍より経験ある人がたくさんいるんですよね...泣(まあ、読書量はそこそこあるので、想像でカバーします!)←そもそもお前には想像以外何もないだろ!!笑笑
話の流れはざっとこんな感じですが、話の展開はわかっていても、藍の書く文章で、藍の文体で読みたいと思わせ、最後まで読ませてみせる!!(感情を訳文に乗っけられる翻訳家は、野崎孝さんか藍くらいだから...)
プロローグ
ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス
彼は羽毛布団から片足を出した。部屋が寒かったのか、それとも彼の体に寒気が走ったのか。最近の彼は、一年中温暖な地で静養していても、簡単に風邪をひくようになってしまった。彼はコホコホと咳をして、握った拳(こぶし)で胸元を叩き、一晩のうちに溜まったタンを吐き出そうとした。何十年にもわたってタバコを吸い、ビールを飲み続けてきた彼は、毎朝目覚めとともに体調の悪さを痛感するのだ。ジェリー・カドガンはもう15年以上、気持ちのよい爽やかな朝、というものを経験していなかった。
もうすぐティナがここにやって来る。彼女は、おはようございます、と言いながら玄関を開け、いつものようにキッチンに入ると、まずは紅茶を入れてくれるだろう。彼女は私の体を気遣って、紅茶に砂糖を入れようとしない。それが私にはどうにも理解できないのだ。この年になって、今さら糖分を控えたところで、健康状態には何ら影響がない。もう改善などするものか。だが、そんなことで口論するのは煩(わずら)わしいだけだから、何も言わない。目くじらを立てながら死ぬなんてごめんだ。
ジェリーは、彼女がやって来る前にすべてを仕上げなければならなかった。彼が起き上がって何かをしていれば、間違いなく彼女は、安静にしていてください、と、彼をソファに引き戻すに決まっている。安静にしていることとは、すなわち、何時間も何時間もテレビの前で座っていることだと、彼女は見なしている節(ふし)がある。今日もまた、ブルーのジャケットを着た冴えない司会者が、金持ち連中の持ち寄った骨董品やら、価値ある品を買い叩くのを、まさに他人事(ひとごと)のように眺めていろというのか。時々、彼は散歩に出かける、と主張し、この邸宅を出る。近くの海辺に行くと、カモメたちの鳴き声を聞くことができ、いくぶん気分がすっきりするのだ。海の方から飛んできたカモメたちが、海岸沿いの道の上空を風に吹かれながら飛び回る姿を、そして、路上にスナック菓子の欠片(かけら)でも落ちていようものなら、目ざとく見つけて急降下してくる様(さま)を、この目で目撃できるから。
彼はサンドラがいてくれたらな、と思った。彼女は厚かましいところがあるのだが、いつもルールをゆるめてくれた。彼女が近くにいると、ジェリーは、自分がただのがん患者以上の存在だと感じられたのだ。しかし、数ヶ月前に彼女が新しい仕事に就いて、ここを去って以来、一度も連絡がないことを考えると、私はただのがん患者、というのが彼女の見方だったのだろう。
「さてと、やるか」彼はそう声に出して言うと、ベッドから両足を出し、スリッパを足に引っ掛けるように履いた。今ではほとんどの服がそうであるように、スリッパもぶかぶかだ。健康状態が悪化してからというもの、体重が減り続け、彼は以前の半分ほどにやせ細ってしまった。見る影もないとはこのことか、と鏡を見て思う。せっせとウォーキングしたり、ビールの量を減らすよりも、肝臓がんになったほうが手っ取り早くダイエットできる、なんて彼は冗談を言った。もっとも、そんな冗談を面白がってくれる人など、ほとんどいなかったが。
彼はベッド脇のテーブルに手を伸ばし、ピルケースを開けた。ピルケースの横には、スパイ小説『裏切りのサーカス』が置いてある。彼はその日に飲む分の薬を喉に落とし込み、水を口に含んで、ごくんと体内に流し込んだ。彼は立ち上がると、〈ワトフォードFC〉のチームロゴが胸元についたパーカーを羽織った。サッカー好きのパトリックが、去年の誕生日プレゼントに買ってくれたものだ。そして、おそるおそる慎重に階段を下りていった。
昔の彼なら、この時間、家中(じゅう)を駆け回るように朝の支度をしていた。朝の紅茶を入れ、トーストを作りながら、お喋りするのが好きだった。大体は妻のスーと、たわいもないことを言い合っていた。「ほら、やかんが湯気を吹いてるじゃない」とか、「今日はマーマレードの気分ね、愛してるわ」とか、そんな穏やかな声が、彼女の姿とともに目の前で舞っているかのようで、彼女亡き後も、一人で紅茶を入れながら、昔みたいに喋っていた。
しかし半年ほど前、ふと馬鹿馬鹿しいと思えてきて、記憶の中の妻を巻き込んで会話をするのをやめてしまった。自分が常軌(じょうき)を逸したゴルフ解説者のごとく、やばい奴に思えてきたのだ。亡くなったパートナーと話している、なんて話はよく聞くが、―実際にそうしている人はどのくらいいるのだろうか?
自分で入れた紅茶を手に持ち、ジェリーはかつての仕事部屋へのそのそと向かった。今朝のうちにやっておきたい事があるのだ。部屋に入ると、彼をぐるりと取り囲むように、壁にはたくさんの写真が飾られている。人生の全盛期、まだ調子に乗っていた頃の自分が写っていて、それぞれの写真に注目すれば懐かしい思い出が蘇るが、記憶に深入りせずに視線を中央に戻した。中央には古い机があり、その上には未開封の郵便物が山のように積まれ、ランプが一つ置かれている。それから、いまだに使いこなせていないノートパソコンは閉じたままで、その上にメモ帳と、昔から愛用している〈パーカー〉の万年筆が乗っかっている。
椅子の上の壁には、一枚の家族写真が飾ってある。彼が今住んでいるこの家の前で、家族6人全員が並んで立っている写真だ。その写真は、ここの鍵を受け取った日に撮ったもので、彼とスーが、「カドガン・ファミリー・建築士事務所―ホーブで最も信頼できる会社です!」と書かれた看板を二人で掲げている。
「本当にここでいいの?」と彼女は言った。彼がこの家の購入を提案した時だ。ここは二人が想定していたよりも、はるかに大きな邸宅だった。しかし同時に、難破船のように古びた物件でもあり、建物全体を暖かくする中央暖房設備はなく、屋根にはいくつも穴が開いていて、ネズミが大量に入り込んでいた。最上階で人が暮らすのは無理なほど、荒れ果てた状態だった。だからこそ、大邸宅でも、金銭的にぎりぎり手の届く範囲内に収まってくれたのだ。
「3ヶ月はかかるな。屋根まで丸ごと修繕となると」と彼は言いつつ、内心では最低でも9ヶ月はかかるだろうな、と思っていた。(実際には、完成までに丸2年かかった。)彼は、自分が立ち上げた会社の実力を示すためにも、自分が単なる独立建築士以上の腕があることを、この地域の人々に納得させるためにも、この家を修繕したかったのだ。
最近、ジェリーは繰り返し考えてしまう。もし自分が会社を設立せずに、雇われの身のまま、他の人の会社を転々としていたら、人生はどう違っていただろう。カドガン家は、今みたいに金銭的に裕福にはなれなかっただろうが、もしかしたら、家族は今より幸せだったかもしれない。
机の上、ランプの後ろには、いくつかの写真フレームが立っている。彼の視界の片隅に入るような、いつでもチラッと見ることができるような位置に立ててある。彼が夜遅くまで図面を描いていたり、会社の帳簿を整理したりしている時に、ふと見たくなるのだ。当時からずっと、夜中にデスクでウイスキーを飲む時の、彼の心の支えになっていた。それらはすべて子供たちの写真で、休日に家族で出かけた時に撮ったものや、クリスマス、誕生日などの特別な日に撮影した写真だった。彼の机の上には3冊のアルバムがあり、その中から、これだと感じた写真をフレームに入れて立てているのだ。
「よっこらしょ」と、彼は腰をかがめ、机の下から、大きな金属製の赤い釣り具箱を取り出した。この考えを思い付いた時から、机の下にそれをしまっておいたのだ。「こんなに重く感じるようになっちまったか」
ジェリーは箱の中を空っぽにしようと、リール、浮き、釣り針、重りなどの釣り具を取り出し始めた。それらのほとんどは、机の一番下の引き出しに放り込んだ。―といっても、そこにはすでにガラクタがあふれんばかりに詰まっていて、自分がついに亡くなった時、誰がこの引き出しの中を片付けるのか知らないが、その人に心から申し訳なく感じた。釣り具箱の中に入っていたボロボロに擦り切れた2冊の本(パブの名店ガイドブックと、釣りのコツの本)は、机の上方(じょうほう)の壁付け本棚に立て掛けた。ウイスキーや紅茶を入れていたフラスコ類は、後で片付けようと重ねて置いておいた。彼は空になった釣り具箱に消臭剤をシュッと吹きかけ、釣り具にこびりついた川の土の臭いや、古い餌(えさ)のかび臭さを取り除こうとした。
まず最初に、彼はその中に未開封のウイスキーボトルを入れた。自分でこの味を味わうことは叶わなかったな、と思うと、残念な気持ちがこみ上げてくる。長年、このウイスキーは家族の間で親しまれ、「ポート・エレン」と人間のように呼ばれてきた。家の中で重要な存在感を放ち続けたこのボトルは、お酒を飲む人には畏敬の念を持って見つめられ、飲まない人には、こんなものが1本1,000ドルもするなんて信じられない、と驚愕の目で見つめられてきた。
ジェリーは思わず一口だけ、とボトルに口をつけてしまいそうになった。70歳になった時に飲もうと、このボトルを大事に取っておいたのだ。今はまだその歳に到達していないし、それに、ほんの少しと飲み始めたら、その結果どんな事態になるのか。彼はその余波の大きさを想像し、思いとどまった。
次に、彼は新聞記事と、大雑把(おおざっぱ)に書かれた短い手紙を手に取った。ドイツの消印が押されたボロボロの封筒を受け取った日のことが脳裏に浮かぶ。あの日、封筒を受け取ってすぐに不安感に包まれた。彼はドイツに知り合いなんていなかった...
あの時、彼は慣れないキーボードに人差し指一本で一文字ずつ、新聞記事のドイツ語をGoogle翻訳に入力していった。しかし、その訳を見るまでもなく、彼にはその内容がもたらすものを予感できた。
悪い知らせだ。
ジェリーはその封筒を、すばやく最近の写真が収まっているアルバムに挟み込んだ。玄関のドアが開く音が聞こえたのだ。
「ったく、もう来たか」と彼は言った。玄関ホールでは、ティナが大きなひもブーツを脱いで、スリッパに履き替えている音が聞こえる。彼女がいつものように、バッグのファスナーを開け、4つのタッパーを取り出している様子が目に浮かぶようだ。タッパーにはヘルシースナックが入っていて、彼女は一日中、それをつまみ食いしているのだ。ダイエットをしている、なんて年がら年中言ってはいるが、彼女がヘルシースナックの合間に彼のポテトチップスまで口に運んでいるのを見て以来、ダイエットには大してこだわっていないのだな、と悟った。
「どこにいるんですか?」と彼女が大きなお腹から声を張り上げた。「お庭には出ないほうがいいですよ」彼女は先週のことに言及(げんきゅう)しているのだ。先週、彼は庭に出て、多年草を植えた花壇で小枝を刈り込んだり、植物の冬支度をしていたところ、彼女に見つかったのだ。(というか、植物が冬を越え、春に満開の花を咲かせたとして、その時まで彼は生き延びているのか? 彼女も彼自身も、頭にその疑問が浮かんではいたが、二人ともそれには言及しなかった。)
キッチンのセラミック製の床にスリッパがパタパタと当たる音がしている。冷蔵庫を開け閉めする音。やかんのスイッチを入れる「カチッ」という音。「まだ熱いわ。やかんを使ったのね」と彼女が叫んだ。「少なくとも、あなたはまだ死んではいないようね」
ティナが笑い声を上げた。ジェリーは首を振って、「ああ、全能の神よ」とつぶやいた。
彼女は冗談のつもりで笑っているのだ。サンドラも似たようなジョークを言ってはいたが、サンドラの方がしっくり来ていた。サンドラはイングランド北東部のタイン川沿いで育ったためか、優しく陽気な彼女の訛(なま)りが、ジョークの内容をオブラートに包んでくれた。ティナはテムズ川周辺の今時の英語を話すので、余計きつい言い方に聞こえるのだ。
ジェリーは封筒を挟んだアルバムをもう一度開き、写真が間違っていないか手早く確認した。コーンウォールでの休暇、フランス旅行、2009年の大晦日、10年置きに撮影された写真が並んでいる。よし、と確認し、彼はそのアルバムを釣り具箱の中に入れた。ウイスキーの隣にアルバムを置き、その上に、彼のキャンピングカーの鍵と、机の上に用意しておいた遺言書も入れた。
しかし、最後にもう一つやるべきことが残っている。
彼の60歳の誕生日にスーからもらったペンを握ったちょうどその時、ティナがドアを開けた。振り返ると、ピンクのナース服を着た彼女が立っていた。脂(あぶら)ぎった白髪交じりの髪を後ろで束ね、耳にはたくさんのピアスをしている。
「ここにいたんですか」と彼女が言った。「仕事してるんですか? そんな状態で仕事なんて」
「っぽいこと」
「何が『っぽいこと』なんですか?」
「いや、仕事なんてしてないよ。仕事っぽいことをね。子供たちのためにあるものを作ってたんだ」
「とにかく、安静にしてなきゃだめですよ」
ジェリーは、安静にしていることにいったい何の意味があるのか、と彼女に聞きたい気持ちを抑えた。2ヶ月後には、他のことをしたくても、安静にしている以外何もできなくなっているだろう。
「あと2分で終わる」
「休憩は取ったんですか―」
「頼むよ、ティナ」と彼は強い口調で言った。「2分だけだよ。エネルギーがあるうちに終わらせたいんだ」
彼女は気を悪くしたのか、「お好きなように」と、ふくれたように言い残し、部屋を出ていった。彼の仕事部屋はラウンジのすぐ隣にあるので、彼女が大きなソファにどかっと座る音も、テレビをつける音も丸聞こえだ。彼女はいつものように朝の情報番組にチャンネルを合わせた。相手を言い負かしたくて仕方がない男が、「裕福であるにもかかわらず、リサイクルショップで買い物するなんて何事だ?」といきり立ち、朝っぱらからゲストに説教している。
ジェリーは部屋のドアを閉めて、自分の机に戻った。机の上では、『ジェリーからの手紙』とタイトルだけ書かれた便箋(びんせん)とペンが彼を待ち構えていた。彼は自分でも何を書こうとしているのかわからなかった。彼は手紙など書いたことがなかった。彼の得意分野ではなかったのだ。スーと付き合い始めた頃、彼女はよく長い手紙を送ってくれた。ブライトンの消印が押された手紙がポストに届いているのを見るたびに、熱いものがこみ上げてきて興奮したことを覚えている。それでもジェリーはめったに返事を書かなかった。何度か書いたかもしれないが、それは酔った勢いでポストカードに2、3行、愛のメッセージを書きなぐっただけのもので、その時にいたパブの匂いをつけたポストカードが数日後、彼女の元へ届くのだった。
書き始める前に、彼はもう一度、釣り具箱の中を見下ろした。アルバム、ウイスキー、鍵。ちょっと匂いだけ、と彼は思い立ち、ウイスキーのボトルを取り出すと、コルク栓を引き開けた。ウイスキーの香りが顔の前にふわっと立ち込める。書類が詰まったファイルキャビネットの上に、親指ほどのミニチュアのウイスキーボトルがあるのが目に入り、彼はもっと良い考えを閃(ひらめ)いた。そしてその小さなボトルに、少しのウイスキーをゆっくり注いだ。その時が来たら、最期の時が来たら、これでそっと祝杯を上げよう。
彼はボトルの栓をして、釣り具箱に戻した。ようやく心の準備が整い、彼は書き始めた。
9月28日
親愛なるジェシカ、パトリック、カースティへ
〔プロローグの感想〕
ティナは出張ナースですね(一日中、彼の家にいるようですけど)。前の担当ナースはサンドラといって、彼はサンドラのことを気に入っていたみたいですが、ティナに交代してからは連絡がないようです...泣(笑)
妻はスーです。妻はもう亡くなっていて、彼とスーは、古い大邸宅を購入、修繕し、建築士事務所をやっていた。(というか、今も一応やってるのかな?)彼が住んでいるサセックス州のホーブは、イギリスの最南端にあって、南の海岸沿いなので、地中海の方から暖かな空気が流れ込んできて、比較的温暖な地域みたいです。←気象予報士でも目指すの?笑
あと、Google翻訳でドイツ語を訳す、というくだりが出てきたので、ちなみに書くと、藍はGoogle翻訳を使っていません。英文を読んだ時に、藍の中から言葉が浮かび上がってくる感覚が、やみつきになるほど気持ちいいんです💙
何にも代えがたい、言葉が浮かび来るその一瞬一瞬の快感ゆえに、ほぼ毎日訳しているわけです。←何回同じようなこと書くんだよ!!笑
パート 1
チャプター 1
ボールズブリッジ、ダブリン
パトリック
パトリックはポケットの中でスマホが、ヴーヴーと震えるのを感じた。一瞬、無視しようかとも思ったが、重要な知らせかもしれない。彼は着信画面を見ずに、片手で携帯をつかむと、右手の親指で画面の下の方をスワイプした。
「はい、もしもし」と彼は言った。
「パトリック?」カースティの声が返ってきた。今にもパリンッと割れそうな、か細い声だ。
それで彼はすぐに悟る。
「ああ、神よ」
彼女は何も言わない。
「彼は?」
「今朝、専属のナースから電話があったのよ」と彼女が言った。彼は梯子(はしご)から降りて、壁紙ローラーを窓辺に置いた。呆然(ぼうぜん)としたまま、パトリックはカーペットを貼る道具につまずきそうになる。巻かれた壁紙を肩に担(かつ)いだままだ。
「パパは死んだのよ」カースティは、それが事実であることを自分自身に言い聞かせるように言った。
「そうか」
「ごめんね」
「俺...」と彼は言った。「それは俺の台詞だよ。いつ...?」
「夜中のうちに、じゃないかって」
「ちくしょう」
二人とも黙り込んでしまった。
パトリックは新築マンションの廊下に出ると、誰もいない部屋を見つけ、中に入って壁際に腰を下ろした。天井からはむき出しのケーブルや配線が垂れ下がり、漆喰(しっくい)の壁は、まだオレンジがかったピンク色のままだ。硬質な繊維板(せんいばん)の床には埃(ほこり)が積もっている。
妹の声を聞くのは約1年ぶりだった。二人の住んでいる場所が離れていることを都合のいい言い訳にして、必要な連絡はすべてメールで行っていた。最後に話したのは、カースティが父の生体検査の結果をメールで知らせてきた時だったが、それは単に、ジェリーが自分でその結果をみんなに伝える気にはなれなかったからだ。
久しぶりに聞いた彼女の声は、見知らぬ人の声のようでもあり、慣れ親しんだ声のようでもあった。彼女の声は震えていた。父の死のショック、悲しみ、それから解放感も混じっているようだった。長い間、いつ死んでもおかしくない、という張り詰めた気持ちでいたのだろうから。
「最後に彼に会ったのはいつ?」
「土曜日」
「そうか」と彼は言った。「ちくしょう」
この二つだけが、彼がなんとか返せる言葉だった。
土曜日ということは、三日前か。すぐにパトリックの頭には、あの大きな家で孤独に過ごしていた痩せ細った父親の姿が浮かんだ。あんなにフレンドリーで社交的だった父が、人生の最後の日々を、ホスピスケアのナースだけを頼りに、たった一人で過ごしていたなんて。
「今日の午後、葬儀屋さんと会うことになってるの」と彼女が言った。唐突に彼女の声が事務的な口調に変わり、彼は不意を突かれた。「あなたが何かをしてくれるとは思ってないわ。でも、葬儀には顔を出してくれるんでしょ?」
「お前は偉いよ、カースティ。もちろん顔は出す。彼は俺の父親だからな」
「上出来」と彼女は言った。その一言だけで、彼女がパトリックに対して抱いているすべての意見や感情を表しているようだった。彼のライフスタイル、人生の選択、彼の考え方、その時々の行動に至るまで、どういうわけか「じょうでき」という、ぶっきらぼうな一言で済ませてしまえるのだ。
「何が上出来なんだ?」
今度はカースティが言葉に詰まってしまった。二人は以前にもこのようなことが何度もあった。―本来話すべき本題から逸(そ)れて、どうでもいいことで細かな点数を競い合ってしまうような、つまらない口論に発展してしまうのだ。
「なんでもないわ」と彼女が言った。今回ばかりは一触即発(いっしょくそくはつ)の状態が回避されたのを感じ、パトリックの体からふっと緊張が解(と)けた。
「じゃあ、誰もいなかったのか? そのとき、つまり」
「いなかったみたいね。彼は一人で」
パトリックは言葉に詰まる。「ちくしょう」
「ティナが今朝彼の家に行ったとき、彼を見つけたそうよ」
彼はティナとは誰なのか聞こうとしたが、すぐに思い出した。彼女はほんの3ヶ月前にホスピスケアの仕事に就いたばかりで、彼は彼女に会ったことがなかった。前任のサンドラは、彼女の夫が脳卒中で倒れたそうで、辞めてしまったのだ。サンドラには会ったことがあった。彼女は、命を脅かすような(時には死に至らしめるような)病気にかかっている患者を、「体の調子が悪いんですね」みたいな、ふんわりした感じで扱っていた。腫瘍に侵された体と、下痢(げり)や風邪と闘っている体が同じであるかのように思えてくるから、不思議と和(なご)んだ。
「ジェシは知ってるのか?」
「さっき彼女と話したわ。もっと早く電話すべきだったんだけど。でも、わかるでしょ」と彼女は言った。
彼はわからなかった。
「とにかく、パット。私はこれからあちこちに...」
「ああ、もちろん」と彼は言った。「やるべきことが山ほどあるのはわかるよ」
「山ほどはないけどね」
「俺は飛行機の便を調べてみる。空いてる席が見つかるといいけど...あ、早いうちに」と彼は言った。明日、と言おうとしたが、すぐに言葉を引っ込めた。明日は無理だ。
「急がなくていいのよ。葬儀の日程とか決まったらまた連絡する」
「ありがとう」
「いいのよ...それじゃ」と彼女は言いつつ、彼が話を締めくくるのをあからさまに待っている。
「それじゃ、その時に、バーイ」と、彼の声は癖(くせ)で、自然と陽気なトーンへとシフトしていく。昔から彼は、話題がどんなに深刻なものであっても、電話を切る時はいつも明るい口調で締めくくるようにしてきたのだ。
彼女が「バイバイ」と言うとすぐに、プープープー、と3回無機質な電子音が流れた。
パトリックは少しの間、ぼんやりと床に視線を落としていたが、無愛想な北アイルランド人の同僚が、ラミネート加工された床板を何枚か重ねて担ぎ込んできたので、視線を上げた。
「お前がこの部屋の担当だっけか?」と彼が言うと、パトリックは立ち上がった。
「いや、ここは君だな」と言って、彼はさっきまで作業していた部屋に戻ろうと廊下に出た。
「おい、大丈夫か?」若い現場監督のウィルが、彼の顔を覗き込むようにして聞いてきたが、「さっさと持ち場に戻れ」という意味だと伝わってきた。
「大丈夫です」とパトリックは答えた。
自分がどんな顔をしているのか心配になってきた。血の気が引いて、灰のように青白くなり、ショックで変に歪んでいるかもしれない。気持ちも動揺していた。しかし、それはごく普通の反応だろう。最後の一人の親が亡くなったばかりなのだから、ごくごく普通の。
「よし、いいぞ」ウィルはそう言って、イヤホンを耳にはめ直した。彼は仕事中、少なくとも6時間はイヤホンを耳に差し込んでいるのだ。そして手ぶらでぶらぶらしているのだから、いい身分だ。彼は背を向けると、リズミカルな足取りで去っていった。
パトリックは半分ほど貼った壁紙を見て、ほっとした。集中できる何かが目の前にあることが今は救いだ。
「その前に、ちょっと外の空気でも吸ってこようか」と彼は誰にともなく言った。
彼はほとんど酔っぱらったようにふらふらと、部屋を出て廊下をエレベーターの方へ進んだ。3階から1階に下りると、アングルシー・ロードに出た。広々とした空間が見たくて右折し、メリオン・クリケット・クラブを目指す。そして、クリケットのグラウンドを見渡せるベンチに座った。隣では、ブロンドの髪をした若い女性が、片手で持ったスマホを見つめながら、もう片方の手で乳母車を前後に揺らしている。
パトリックは体を前に倒し、両手の付け根のところで、両方の目を押さえた。目は涙で濡れていた。彼は大きく息を吐き出すと、むせび泣きそうになるのをこらえて、素早く深く息を吸い込み、こみ上げてくるものを、それがどんな感情なのかわからないままに、下に押し戻した。隣にいた女性が顔を上げて、彼の方を見た。一瞬、彼は「どうされましたか?」と聞かれると思い、パニックになった。こんな時、どう答えればいいのだろう?
しかし、彼女はすぐに自分のスマホに視線を戻した。パトリックもつられて、彼女のスマホを見ると、WhatsAppでメッセージのやり取りをしている最中のようだ。
彼は、ペンキが飛び散った作業ズボンのポケットから、自分のiPhoneを取り出した。ロック画面には、娘のマギー、妻のスザンヌ、そして彼の三人が水着姿で写っている。コークのビーチに行った時の写真だ。
写真の中には、今より数段良いバージョンの自分が写っている。もちろん、今よりスリムだ。当時のお腹は、今みたいにTシャツを完全に押しのけ、突き出てはいない。まだほんの少しTシャツを押し上げている程度だ。七三で分けて後ろに流している髪は、今のあごくらいまで伸びたぼさぼさの髪とは違い、きちっと整っている。そして何より、写真の自分は幸せそうだ。最近では考えられないような笑顔を浮かべている。
急に人恋しくなり、誰かと話したくなったパトリックは、最近の通話履歴を開き、スクロールする指を、スザンヌのところで止めた。彼は妻に電話をかけようとしたが、すぐに気が変わった。今彼女に電話しても、関係を悪化させるだけだろう。電話帳の画面に戻り、別の番号を選んだ。
外国につながっているのではないかと思うような、英国式の長い着信音が2回鳴った後、誰かが電話に出た。
「もしもし、俺だよ」とパトリックは言った。「ちょっといいかい、知らせたいことがあってね」
ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス
ジェシカ
彼女はカースティからその知らせを聞いて、ひとしきり泣いた。しかし、ひとしきり泣いた後は、ジェシカ・ラクランは気丈(きじょう)に振る舞っていた。彼女はストイックなのだ。「子供たちのために自信に満ちた顔をしていなくちゃ」と自分自身に言い聞かせていた。「さっき泣いたのは、ほんの気の迷いよ」くらいに気を張っていた。実際のところ、それほど動揺しなかった。父親が亡くなったのだから、もっと取り乱すかと思ったけれど、なぜか冷静でいられてしまう自分が不思議でもあった。こんな時に冷静沈着でいられるのは、次の二つのどちらかに起因(きいん)しているんでしょう、と結論を下した。
4年前の母の死が、この時のための心の準備になっていたのか。
あるいは、父の死が差し迫っていると聞かされてから、自分の中で精神的に折り合いをつけるのに十分な時間があったからか。
父が肝臓がんだと診断されてから約1年が経過していた。それが末期であることを知ってからの5ヶ月間、彼女は週末にはホーブに通っていた。
もちろん心の奥底では、父の死に対して自分の反応が薄いのは、何か別の理由があるからではないかと考えていた。おそらく、葬儀や遺言開示の際にはどうしても弟や妹に会わざるを得ない、そのことが頭の片隅にちらついていたからでしょう。彼女はその考えを頭の外へと振り払った。彼女たちの関係はギクシャクしていた。べつにいいじゃない。仲が悪い兄弟姉妹だっているでしょ。彼女たちは家族というより、同僚のような存在で、必要があれば連絡はするけど、用もないのに、あえて自分から交流を望むような間柄(あいだがら)ではなかったのだ。現実なんてそんなものよ。
夫のダンはそれが理解できなかった。一人っ子の彼にとって、大人数の家族というのは、羨望(せんぼう)のまなざしを向けるべき対象なのだ。
「うちの子供たちは仲良くしてほしい。親友みたいに」と彼は、マックスとエルスペスの二人についてよく言っている。彼女はそれに同意しつつも、どちらの家族にも、子供たちが兄妹(きょうだい)の関係を見習うべき良い手本がないことが心配だった。
ジェシカは、カースティが下の階でせわしなく動き回っている物音を聞いている。彼女の本領発揮だ。やらなきゃいけないことがたくさんあると、彼女は水を得た魚のように活き活きと動くのだ。カースティは彼女たちの中で唯一、地元に残って暮らしていたから、その日、実家に真っ先に駆けつけ、真っ先にあちこちに電話をかけて、その知らせを伝えた。ジェシカはその時の電話の、徹底して無駄を省(はぶ)いた会話を思い出した。彼女は挨拶もそこそこに、冷徹(れいてつ)に要点だけを伝えてきた。
「ちょっと単刀直入すぎるな」とダンが言った。
「他に言うことがなかったんでしょ」とジェシカは、妹の心境を説明した。
カースティの言葉を借りれば、「それが起こって」から、今日で4日目になる。ジェシカは言葉尻(ことばじり)を捕らえて、ねちねち妹を攻め立てるようなことはしなかったが、死が「起こる」ものなのかどうか、首をかしげた。そんな偶然みたいな、またそれが起こりそうな言い方は、ふさわしくないでしょ?
それはともかく。4日が経った。
1日目、彼女は夫のダンと一緒に、ホーブの実家へ向かった。実家に着くと、カースティと彼女の娘のリヴィが出迎えてくれて、みんなで大きなオーク材のキッチンテーブルを囲んだ。テーブルには子供向けの料理がずらっと多すぎるほどに並んでいたが、食べ物にはほとんど手を付けず、9月下旬のやわらいできた陽射しが窓から差し込む中で、延々と紅茶をすすっていた。
時折、父親の友人がぽつりぽつりと訪れた。彼らは紅茶をすすりながら、「こんなに残酷な病気があるなんて」とか、「あんなに優しくて、ほがらかな人がどうして」などと、ありきたりではあるが、紛れもない事実を口にした。ジェリー・カドガンが妻を亡くしてからの悲惨な数年間が、彼らの言葉を通して浮き彫りになるようで、それは誰が見ても気の毒に思う日々だったようだ。
まだ母が生きていた頃の父は、ビートに乗ってダンスをしているかのごとく、快活な一週間を繰り返していた。毎日海辺を散歩していたし(長年愛犬連れて、愛犬が亡くなった後は夫婦二人で)、お気に入りのレストランが3つあり、その日の気分でレストランを選び、ランチを食べていた。水曜日には夫婦で映画館に行って、昼間の上映を見ていた。―ビスケットをホイルに包んで家から持参し、コーヒーは映画館で買っていたようだ。―ただ、両親は映画自体には興味がなかったのだと、ジェシカは思っていた。(というのも、両親がウェス・アンダーソンの映画を見てきた日、ジェシカが母親に、彼が監督した他の作品について話したことがあったのだが、スー・カドガンは、ウェス・アンダーソンが誰なのか見当もつかず、映画談議はすぐにしぼんでしまった。母は映画の内容よりも、父と映画館で過ごす時間を楽しんでいたのだ。まるでピクニックに出かけるように...)
しかし妻が亡くなって、ジェリーは晩年を一人で過ごしていた。たまに出かける海辺の散歩も一人きりだった。新しく犬を飼うことを提案したけれど、父は拒んだ。シニア向けのランブリング・クラブに入って、ホーブ地区のみんなで散歩したら? という提案も父は断った。映画館に行くことはなくなり、家でDVDのボックスセットを毎日一話ずつ見るようになった。レストランにも行かなくなり、近くに二つあるパブのうちのどちらかに、一人で通うようになった。きっと父は、他のうらぶれた常連客たちと同類にみなされているんだろうな、とジェシカは思った。最近まで彼が、幸せな、と言ってもいいくらい仲の良い、大家族の一員だったことなど、きっとパブの誰も信じないでしょうね。
初日の夜、ジェシカはダンが運転する車でいったん家に引き上げることになった。みんなで一緒に夕食を食べようと提案したのだが、「いいのよ、ジェシ、あなたたちは帰って休んでちょうだい」とカースティが、哀(あわ)れみを誘うような表情を浮かべながら言ってきたのだ。カースティは、父の死後の片付けを一手に引き受けたことを、後々(のちのち)何かの交渉の時に、切り札として持ち出してくるだろうな、とジェシカは予見できた。
そういうわけで、すべてをカースティに任せてはいられない、とジェシカは早速(さっそく)ブライトンのホテルを予約し、自分たちが一緒に育った家の手入れをするために戻ってきた。
「あなたは本当に手伝わなくて大丈夫よ」とカースティは、何の連絡もなく南海岸の町に舞い戻ってきたジェシカに言った。「リヴと私、二人いれば、たいていのことはできちゃうから」
「手伝いたいのよ。それに、リヴに死んだおじいちゃんの遺品を整理させるなんて、良くないでしょ?」
「あら、なぜ良くないの?」とカースティは、いつものけんか腰の口調で、イライラを当てつけてくるように言った。ジェリーには4人の孫がいるのだが、自分の娘だけは他の3人とは違うのよ、というニュアンスを、カースティはどんな発言にも乗っけてくるのだ。
「彼女はまだ4歳でしょ、カースティ。遺品の整理なんて早すぎるわ」
「じゃあ、あなたのお花屋さんはどうなの? 娘に手伝わせてるんじゃないの?」とカースティが言ってきて、ジェシカは、また始まった、と思う。ジェシカが経営しているお花屋さんには余裕がなくて、従業員を一人しか雇えない、とカースティは思っているらしい。
「私は毎日店に顔を出す必要はないのよ。従業員の女の子たちがちゃんとやってくれてるからね」とジェシカは、あえて従業員の人数を口には出さずに言った。(実際は二人なんだけどね。)
最終的にはカースティが折れ、ジェシカの参加を受け入れた。まず、5日後のジェリーの葬儀までにやるべきことを一緒に計画した。棺の材質(オーク材)、葬儀で流す音楽(チャス&デイヴ、ザ・フェイセズ、エルトン・ジョン)、花(アジサイ)などの大きな決断は二人で決め、パトリックの嫌いなものが含まれていないか、一応彼にもメールで確認した。それ以外にも、プロの掃除屋さんを雇ってありとあらゆるジェリーの痕跡を消す前に、どの部屋を誰が片付けるのか、分担表を作った。この邸宅を売ることについては、概(おおむ)ね全員が同意していた。もっとも、また口げんかが始まっては面倒だと、ダン以外は誰も口には出さなかったが。
「そのお金が入ったら、休暇を取って旅行に行こう」とダンは言った。ジェシカが実家近くのホテルから、夫のいる家に電話した時だ。「もちろん、君の父親の思い出を祝う旅行だよ。わかるだろ―」
「ちょっと、『彼もそれを望んでいるよ』だとか、余計なこと言わないでちょうだいね、ダニエル」
「い、言わないよ」と彼は口ごもりながら、発言を撤回しようとした。彼女の実家を売って、そのお金でディズニーワールドに行きたいという願望を、願望の中身は伝えずに、それとなく外枠(そとわく)だけを伝える方法を、彼はこれから見つけなければならない...
今、ジェシカは2階のジェリーの寝室にいて、ズボンの後ろポケットから分担表を取り出して見ている。
ラウンジ ー カースティ
寝室 1 ー ジェシカ
寝室 2 ー カースティ
寝室 3 ー ジェシカ
バスルーム ー プロの掃除屋さん
トイレ ー プロの掃除屋さん
キッチン ー ジェシカ
書斎 ー カースティ
ロフト ー パトリック?
部屋の隅には、ゴミ袋が5つ置かれていて、リサイクルショップや古着回収箱に出す衣類がパンパンに詰まっている。ベッドの上には、ダンボール箱が2つあり、本、小物類、写真の入った写真立てが4つ、老眼鏡が3つ、それからベッドサイドの引き出しに入っていた物も、いっぱいに詰め込まれている。今、ベッドサイドの引き出しは空だ。
一般的に考えると、亡き父の寝室を片付ける行為は、もっと胸が締め付けられるものだと思っていた。しかし父の寝室からは、母が亡くなった時に、その特徴的な、親しみのある雰囲気が多かれ少なかれ取り除かれ、それ以来、ジェリーはこの部屋に彼自身の要素をほとんど加えていなかった。この家に残された自分の時間が限られていることを知っていて、今さら手を加えたくない、と思っていたのか、母が使っていたベッドサイドのテーブルも、中は空っぽのまま鎮座(ちんざ)している。
写真立てに入れられた写真を見て、ジェシカは懐かしい感覚が心の琴線(きんせん)に触れるのを感じた。彼女が長い間忘れていた家族の肖像、まだ彼女が家族の輪の中にいた時代へと通ずる窓枠をつかみながら、一瞬動きが止まる。しかし、懐かしい以上のものは何も感じなかった。
それでも、ジェリーの寝室を片付けることは、ジェシカにとって落ち着かない行為ではあった。
何か変なものや下品なものを見つけて、父への見方が変わってしまうのではないか、父性的な印象が、なんていうか、より男性的なものに置き換えられてしまうのではないか、と心配だったのだ。
「たとえばどんな?」と今朝カースティが聞いてきた。家の片付けを始める前に、少し肌寒い庭のテーブルで一緒に紅茶を飲んでいた時のことだ。
「わかるでしょ。雑誌とか、そういうものよ」
「ああ、ジェシ!」
「何?」と彼女は聞きながら、笑ってしまった。「もしかして、デレクおじさんのこと思い出した?」と彼女は言った。デレクおじさんが心臓発作で突然亡くなってしまい、彼の娘(彼女たちのいとこ)のクレアが、彼の部屋を片付けたのだが、その時、一番上の棚に彼が愛着を抱いていたものを見つけてしまったのだ。クレアは清教徒のようにピュアだった。
ジェシカはベッドの上に腰を下ろし、ベッドの向かい側、母が使っていた化粧台の鏡を見た。自分では認めたくないが、疲れているように見える。最近、自分のすらりとした顔が、―かつてははっきりと骨格を見て取れるほど、シュッとしていたのだが、―今はなんだか、顔全体を引き伸ばされてしまったようで、ぽっちゃりとふくれてしまった。カースティの顔がこんなにまん丸になることは、あり得ないだろうな。しかも、茶色がかった長い髪には白髪が混じっているのがわかる。昨夜のディナーの時から着ているシャンブレー生地のシャツに、白髪が1本くっついているのが目に入り、それをつまみ取りながら、やるせない気持ちに襲われた。
こんなこと心配してても仕方ないわね、と彼女は思った。あー、ストレスがたまる。仕事のこと、子供のこと、ダンのこと、それでもう手一杯なのに、その上、自分自身の容姿が衰えてきたとか、そんなことまで考えて、さらに自分を追い込むのは良くないわ。
ジェシカは、白いコンバースのオールスター・スニーカーを片足だけ脱ぐと、扁平足(へんぺいそく)ぎみの足裏を指でマッサージしながら、泊っているホテルに戻るのを楽しみにしていた。本、お風呂、テレビが、誰もいない空間で彼女を待っている。久しぶりに、誰にも邪魔されずに一人の時間を楽しめる。―12歳(もうすぐ13歳)と6歳の、二人の子供から離れて、ゆっくり羽を伸ばせるのだ。
彼女は今夜、ブライトンで大学時代の友人とディナーを食べる約束をしていたが、キャンセルしようと考えていた。サディ・ダーリントンは、今やライフスタイルを提案するライターで、2つの新聞と1つの雑誌でコラムの連載を抱えている売れっ子だ。ジェシカは、購読していた雑誌の表紙に華やかにサディの名前と写真が掲載されているのを見た時、その雑誌の購読をやめてしまった。
「それで、あなたは今どんなの書いてるの? ジェシ」
彼女はこの質問を恐れていた。彼女が最後にサディに会ったのは、自分も作家になろうと決意し、児童書出版の仕事を辞めた時だった。サディは、「書き終えたら教えてちょうだい。私は文芸関係のエージェントならたくさん知ってるから」と笑顔で後押ししてくれた。
あれから5年が経ち、今夜サディに会ってそう聞かれたら、ジェシカはこう答えるしかないだろう。「それがね、1万語くらいは書いたんだけど、作家の道は断念しちゃったのよ。2年前に夫を説得して、今まで貯めてきたお互いの貯金を合わせて、お花屋さんのビジネスを始めたの。それには理由があってね、ほら、クリス・ファーブレイスって覚えてる? 実は彼と、私はいい仲になっちゃって、今から考えるとゾッとするんだけど、あやうく道を踏み外すところだったわ。あの時、彼とベッドで激しくしていたら、私の人生はめちゃくちゃになってたかもしれない。なんとか一線は越えずに踏みとどまったんだけど、その代わりになる、何か大きな転機というか、私の気をそらしてくれる人生の一大事がどうしても必要だったの。クリスのことが頭にチラついて仕方なかったのよ。それで起業したってわけ。もちろん、ダンはそんなこと何も知らないけどね」
深いため息をつきながら、ジェシカはベッドから体を起こし、最後の引き出しを取り出して、振り返り、ベッドの上のダンボール箱に引き出しの中身を空けた。
「ジェーーーシー」というカースティの声が、引き出しの中身をざっと確認しようとしたところ、下の階から聞こえてきた。「ちょっと来て。見せたいものがあるから」
カースティ
大したものには見えなかった。それは赤い金属製の釣り具箱で、幅が75センチ、縦が50センチ、深さも50センチくらいで、それにしては、かなり重い。
父が昔から使っていたファイルキャビネットの一番下の引き出しを引き抜くと、中で何かがゴロゴロと重たく動く音がした。ファイルキャビネットの前面には、「カドガン・ファミリー・建築士事務所―ホーブで最も信頼できる会社です!」と書かれたステッカーが、いまだに貼られている。
釣り具箱の上部には取っ手と南京錠が付いていて、「これを読んでくれ」とジェリーの筆跡で書かれた封筒がテープで貼られていた。
「あなたが...開けたい?」とカースティは、ジェシカにその封筒を差し出しながら聞いた。
「ううん、あなたが開けて」
カースティは慎重にナイフをスライドさせ、封筒を開封した。中からA5サイズの便箋を取り出すと、そこには父が青いペンで、力を振り絞って...
これを見つけた人へ
この箱の中には、私の子供たちに渡したいアイテムがいくつか入っている。
私の葬儀が終わるまでは、この箱の鍵を開けないでほしい。葬儀の後、中のものを取り出してくれ。
ジェリー
彼の名前のすぐ下には、小さな鍵がテープで留めてあった。釣り具箱のふたを閉じている南京錠に合う鍵でしょう。―南京錠はいかにも安っぽいもので、鍵がなくても、クリップとちょっとした決意さえあれば、簡単にこじ開けられそうだ。カースティは、鍵のついたままの便箋を折りたたむと、彼女のリュックサックに入れた。
彼女はジェシカと一緒にキッチンテーブルに座り、二人してじっと、今にも爆発するのではないか、というようなまなざしで、その赤い箱を見つめていた。
「じゃあ、はっきりさせちゃうけどね。今ちょっとだけ、見てみたいと思わない?」とジェシカが言った。
「ダメ!」
「べつにそうしましょうって言ってるんじゃなくて」
「じゃあ、なんで聞くの?」
「わかるでしょ。念のためよ」
「念のためって何? 死にそうになりながらこれを書いた人の願いを裏切ってもいい念って何?」
「そんなメロドラマみたいなこと言わないでよね」ジェシカはそう言って、両目をくるりと一周させた。
「そんな風に聞こえたのなら、あなたがひねくれてるんじゃない」
「あなただって、この中に何が入ってるのか知りたくて仕方ないんでしょ。私はすごく知りたいわ。というか、彼らしいわね、自分が死んだ後まで謎めいたことを残すなんて」
「ジェシ」とカースティはショックを受けたように言ったが、反論はできなかった。
「うーん、逆に彼らしくないのかな? まったく微妙なことしてくれるわね。パパは、そんな正直な人いないでしょってくらい、正直者だったのよ。秘密を守ることなんてできなかった。それが今、墓の中から、私たちとくだらないゲームをしようとしてる」
「亡くなった人を悪く言わないで、ジェシカ」とカースティは言いながら、自分の声に敬けんな宗教家ぶった響きがあることに自分でも気づいた。
「あなたもわかってるでしょうけど、あなたって時々―」
「私は行くわ」カースティは姉が発言を終える前にそう言うと、今は着替えを保管してある昔の自分の寝室へそそくさと向かった。
私の言ったことが姉の耳にどう聞こえようと、今日は言い争いなんてしたくない。この家を空っぽにしようと、今までずっと作業してきて、すでに心身ともに消耗していた。引き出しを開けたり、戸棚の中のものを引っ張り出したりするたびに、ふいに何かに襲われたような衝撃を受け続けていたのだ。父は、眺めて感傷に浸(ひた)りたいとか、昔を懐かしみたいという理由で、いろんなものを取っておいたんでしょう。でも、それらすべてを私は捨てなければならない。だって、父以外の人が見たって、なんの感慨も湧いてこない、価値のないものばかりなんだから。そういえば、これは母が父に贈ったものだっけ。これは休暇で家族旅行に行った時のおみやげだ。どれも使い道のないものばかりで、カースティが自分の家に持ち帰って、飾っておきたいと思うようなものは何一つなかった。捨ててしまうことと、永遠に持ち続けることの間に、何か妥協点があればいいのに、と彼女は考えた。
もちろん、自分の家がもっと広ければ、持って帰ってもいいかな、と思う物もあったでしょう。一応最上階だから海を見渡せて眺めはいいけど、寝室が2つあるだけの手狭な賃貸住宅では、大した収納スペースもないし、父親みたいに何でもかんでも捨てずに取っておくなんて無理だ。
カースティは、一刻も早く体のギアをランニング・モードに切り替え、海沿いの自分の家に向かって走り出したかった。そこでは娘のリヴィが、クララと一緒に私を待っている。(クララは私の友人で、放課後、私の代わりにリヴィの面倒を見てくれている。)それからオーブンで焼いたピザと、赤ワインのボトルも私を待っているはずだ。
それと、こうしている間にも仕事はどんどん溜まっていく。私の勤めている学校は非常に寛大で、遺品の整理がすべて終わるまでの間、休暇を認めてくれた。「私一人しかいないようなものなんです」と、カースティは上司に説明した。代替(だいたい)教員の手配や、他の教員に授業を掛け持ってもらう手間を減らすために、兄弟に頼めないのか、と上司がそれとなく尋ねた時、彼女はそう答えた。あたかもジェシカとパトリックが全くの役立たずで、無責任な存在であるかのような言い方をしたが、実際は単に、彼らが少し離れたところに住んでいて、実家の近くには私しかいない、と言った方が的を射ていた。しかし、まあ、彼らにそういうイメージを植え付けておいても問題ないでしょ、と彼女はにんまりした。
それでも、宿題の採点は彼女がやらなければならない。その日の朝、彼女は学校に行って、生徒から宿題の問題集を集めてきた。すでにGCSEクラスで回収していた『二十日鼠と人間』(ジョン・スタインベックの小説)に関する40人分の感想文に、その問題集の山も加わったことになる。ちなみに、GCSEクラスとは、中学卒業時にイギリス全土で行われる統一テストのための準備クラスなのだが、みんな似たり寄ったりのことを書いてくるから、それを得点化し、優劣をつけるのはかなり骨の折れる作業なのだ。
明日から週末で、土日休みに入る。プロの掃除屋さんを呼べる状態にするには、明日の午前中いっぱいはかかりそうだ。―そして最終的に不動産屋さんを呼んでこの家を見せる時には、きれいさっぱり清潔感のある邸宅にしなければならない。その後は、火曜日の葬儀に向けてカウントダウンに入る。カースティには、すべてのことがあり得ないほど速く感じられ、同時に、十字架にはりつけにされているのではないかと思うほど、時間の経過がゆっくりにも感じられた。父親が亡くなったのが、つい最近のことだとは信じられないのと同時に、葬儀で形式的なお別れを済ますまで、まだあと何日もあることが、信じられないほど長くも感じられた。
ジェシカはキッチンで、昼食に二人が使ったマグカップやお皿を洗っているようだ。
「そっちは大丈夫?」と、カースティは声を上げた。昔の寝室でジーンズを脱ぎ、Tシャツを脱いだ彼女は、色鮮やかな柄(がら)のランニング・レギンスを穿き、長袖のトップスを着た。彼女はダークブラウンの髪を耳が全部出るほど両サイドを短く刈り上げていたが、さらにその上にカチューシャをつけて、前髪が額にかからないようにした。
「大体終わったわ」と、ジェシカの声が返ってきた。「私ももうすぐ出るから。あなたは先に帰っていいわよ」
「待ってる」と彼女は言った。姉をあの釣り具箱と一緒にここに残すわけにはいかない、と直感的に思った。きっとこっそり一人で中身を見るに決まってる。姉にはそういうところがあるのだ。二人が子供の頃、ジェシカは毎年のように、「どこかにクリスマスプレゼントが隠してあるはずだから、両親の寝室に探しに行きましょ」と、私を誘ってきたのを思い出した。「今晩の予定は?」
「あるけど、キャンセルしようと思ってるの。サディ・ダーリントンと会うことになってるのよ」とジェシは言った。まるで誰もがサディ・ダーリントンといえばあの人だ、と、ピンと来るとでも思っているかのような口ぶりだ。
「ああ、それは素敵ね」カースティが適当に答えると、洗い物を終えたジェシカが玄関までやって来た。「それじゃ、行きましょ」
おしゃれに気を遣うジェシカは、意図的に大きめのサイズを買ったファッショナブルなコートを、裾(すそ)をたなびかせるようにして羽織った。一方、機能重視のカースティは、防水加工のウインドブレーカーに袖(そで)を通すと、走っても落ちないようにリュックサックをきっちりと腰と胸の周りに留めた。そして、空中に膝(ひざ)を交互に突き上げながらウォームアップをしつつ、横目で姉を見ていた。ジェシが黒くて大きな四輪駆動車に乗り込むのを見届けてから、彼女は実家のドアに鍵をかけ、自分の家に向かって走り始めた。
ホーブの〈ギャントン通り〉から、ブライトンの〈カニング通り〉までは、5キロ弱の距離があった。つまり、実家から自宅まで、一度も休憩を取らずに走り続ければ、大体30分で着く。
カースティはアスリートとして天性の素質があったわけではない。脚(あし)は短いし、ずんぐりした体型はランナーには不向きで、彼女は昔から自分のことを「ポチャッとしたシュウマイみたい」と思っていた。しかし、母親になり、さらに間(ま)を開けずにシングルマザーになったことで、自分を卑下(ひげ)するのではなく、肯定しようと決意した。「やせてなくたって十分きれい」というボディ・ポジティブに目覚めた彼女は、毎週、背中を押してくれるネット記事を読み、それをFacebookで拡散することで気持ちを高めていた。
カースティはジェリーが亡くなってからランニングの頻度を増やし、毎日走っていた。一人で走っていると、思考を邪魔されずに自分のペースで考えることができ、いくつかのことを受け入れることができた。例えば、自分にはもう両親はいなくなり、孤児のような存在になってしまったこと。(もちろん、もうとっくに未成年ではないし、大人になってから両親を亡くしたからって、自分を「孤児」だなんて呼ぶのは適切ではないとわかっていたが、ランニング中はいいのだ。)両親がこの南海岸の町に移り住んできて建てた家のそばにいようと、姉や兄とは違い、自分だけはこの地に残ったこと。私だけになってしまった。私が唯一のカドガン家の跡取りなんだ、というようなことを考えていた。
今日は走りながら、あの箱について考えていた。中に何が入っているんだろう、と思いを巡らせていた。
ジェリーは、秘密主義者でもなければ、ドラマチックな人間でもない。むしろ実直(じっちょく)で、真実にこだわる人だった。努力すればいつかどこかにたどり着ける、という考えを実践するような生き方を貫(つらぬ)いていた。また、彼は優しかった。カースティはその優しさを今まで忘れたことがない。
だからこそ、このような意表を突くことをするなんて彼らしくない、と思った。遺言があったとしても、標準的な遺産分割の類(たぐい)だと予想していた。兄妹それぞれに、彼が身につけていた安物の時計とか、身の回り品を1個か2個ずつ分ける程度で、ドラマチックなことなんてあるはずない、と。
「お前たちはそれぞれ何かしらを手にする」と彼が言っていたのを思い出した。彼のがんが悪化の一途(いっと)をたどっていた数ヶ月前のことだ。「それから他にも、お前たち3人に渡るものがあるから、話し合って分けてくれ。喧嘩するんじゃないぞ」
その時、彼女はその言葉を意外に思いながら聞いていた。母が亡くなってから、3人の関係はますます険悪になっていたのだ。金銭的な問題でもめたわけではなく、家の中の空気が変わったというか、彼女の死によって、カドガン家を取り巻く問題が如実(にょじつ)に表面化し、その原因がそれぞれ一人一人にあることが浮き彫りになったからだ。
ブライトンの町が暗幕(あんまく)をまとい始めた。海岸沿いの歩道には街灯がともり、仕事帰り、自転車で家路を急ぐ人や、スマホを片手にゆっくり歩く人をオレンジ色に照らし出していた。カースティは人々の間を縫うようにして、見慣れた桟橋(さんばし)に向かって進んだ。その桟橋はブライトンの観光名所になっていて、薄暗くなった今もまだ観光客で賑わっていた。この町に来て日帰りで帰る観光客はあまりいない。みんなこの辺のホテルに数日泊っていくのだ。
彼女は桟橋を過ぎたところでひと休みしようと立ち止まった。イヤホンを耳から抜き、ポッドキャストのスイッチを切る。―実際にあった犯罪をフィクション風に物語る放送を聞いていたのだが、今日はその内容に集中できず、ただ聞き流していた。―青緑色に塗られた手すりにもたれ、海を眺める。
そういえば、ジェシカは今夜、大学時代の友人と夕食を一緒にするんだっけ、と思い出した。それから、ダブリンにいるパトリックは、今頃何してるのかしら、と考えた。
カースティは自分の人生を愛していると昔から思ってきた。とはいえ、姉や兄に比べると、刺激が足りない人生だな、と感じることも多々あった。ブライトンに長年居続けたことは、犠牲だったのだろうか? それとも、彼女たちにこの町を離れたことを後悔させたくて、こんなことを考えているだけだろうか? 彼女たちはここから遠く離れた場所で、それぞれの人生を築いたんだな。
「あなたは自分の人生に満足してると言えますか?」そう言ったのは彼女のセラピストのネーラだ。父親が亡くなってからはまだ一度も予約してないが、一番最近のセラピーの時にそう聞かれた。質問というより、自(おの)ずと一つの答えを引き出される指令に近かったけど。
「はい」とカースティは答えたが、それが上辺(うわべ)だけの強がりなのか、自分でもわからなかった。ネーラはスリムで美しいインド人女性で、カースティは彼女に少し惹かれつつあり、なんとか彼女に好印象を与えようと必死だった。ネーラの前だと、自分をよく見せようとしてしまうのだ。これらの点から、彼女をセラピストとして選んだことは、おそらく最悪の選択だった。しかし、彼女のセラピーを受け始めて2年が経過した今となっては、カースティはどうしても自分の間違いを認めて、セラピストを変える気にはなれなかった。「でも、自分の人生に満足してるのか、そのことを考えるたびに思うんですけど、もう2年もここに通っていて、その期間ここに来る代わりに、何か他にできたんじゃないかって」
「たとえば?」
「わからないですけど」と彼女は口では答えながら、旅行、仕事、人との交流、セックス...と思っていた。「なんか、自分自身をシェルターにかくまってるというか、からに閉じ込めてる気がするんです」
「そして、そのことで自分を責めてるのね?」
「うーん、まあそうですね」とカースティは言ったが、それも厳密には真実ではなかった。
どちらかというと、私は家族を責めている。カドガン家の人間関係が悪化したとき、国を離れたパトリックのせいにした。それから、私はジェシカも非難している。彼女は自分のビジネスや、(雑誌に載ってるような)快適な中流階級の暮らしに没頭(ぼっとう)していて、自分の身の回りのことしか眼中にないから。そして、私は両親を責めているのだ。こんなところでくすぶってないで、夢を追え、と言って、私の背中を押してくれなかった両親を。
困ったことに、彼らは誰一人、自分が悪いことをしたことに気づいていない。彼らは自分の人生を生きてきただけで、誰もそのことを批判しなかったのだ。
カースティは、前回ネーラのオフィスで、ずらっと並んだ本や、鉢植えの観葉植物や、アートのような近未来を彷彿(ほうふつ)とさせる家具に囲まれ、心理療法を受けていた時のことから心を離し、再びあの赤い箱のことを考えた。あの中には何が入っているんだろう、と色々な可能性に思いを巡らせた。そういえば、父はいつ、あれを準備したんだろう。
それから、今夜はもう考えるのをやめよう、と思った。死とか、それにまつわる思考とは一旦おさらばして、今夜は是が非でも楽しく過ごしたい。彼女はイヤホンを耳に戻すと、走り出した。
スパイア・ホテル ― ブライトン、サセックス
ジェシカ
サディとの夕食をキャンセルするメールを送信した後、その指でジェシカは、自分にいらだってる時にしか利用しないピザチェーン店の名前をググり、トートバッグから赤ワインを取り出した。お肉とガーリックをたっぷりと散りばめた12インチのピザと一緒に飲むには、あまりにも高価で上等なワインだったけど、「もうなんでもいいや」という気分だった。こういう気分になる時は大体、花屋の店番をしていても、お客さんが全然来なくて1日中(じゅう)暇だった日の夜とか、週末なのにダンが仕事に行ってしまって、ほんとに仕事なの? 今ごろ誰かと一緒に何かしてるんじゃないの? と不安になった時とか...
そういう時、思いっきりピザを食べ、ワインを飲んだとしても、通常であれば、翌日に過激なくらい運動をするから、お腹の炭水化物やチーズやお酒はすっきり帳消しにできる。しかし今回は、まだ明日の午前中、カースティと一緒に実家の片付けをしなければならない。つまり運動する時間はない。午後には子供たちや花屋の仕事、そしてダンが待っているはずの家に帰れるけど、それまではカースティと顔を合わせて、妹に色々と押しつけてしまっている罪悪感に耐えながら、しおらしく振る舞わなければならない。そのためにも今、この恐ろしく不健康な自己療養を甘受(かんじゅ)する必要があるのだ。
彼女のスマホが、ヴー、ヴーと震えた。
サディ:え、そうだったの!それはご愁傷様。私のことは全然気にしないで。わかるわ、悲しみに耐えながら遺品整理とかしてるのよね。そういえば、そういう人生の辛さについて、去年私が書いた記事を送るから読んでみて。じゃあ、次の機会に😘
直後にまたスマホが震えた。今度はその記事へのリンクだ。
「まったく」とジェシカはぼやいた。「この人なんにもわかってないじゃない」
彼女はベッドから立ち上がり、部屋の隅に置かれた半円形の人工皮革(じんこうひかく)の椅子に腰を下ろした。座り心地は悪い。ベッドの上に飾られた、1本のバラが描かれた味気ない絵をしばし見つめてから、スマホを操作し、着信履歴の1番上に表示された自宅に電話をかけてみる。
数回呼び出し音が鳴った後、彼が出た。
「ちょうど今、子供たちの夕食を作ってるところなんだ」とダンは言った。「手が離せないから、折り返していいか?」
「私は今からお風呂に入るのよ」
「じゃあ、その後話そう」
「たぶんね」と彼女は言った。彼の背後から電子レンジがチンと鳴る音が聞こえてきた。続いて、ダンが2枚のお皿をキッチンカウンターに置いた音がした。その音を聞いて、ふっと肩の力が抜ける。彼はちゃんとやると言ったことをやっている。彼が出かけている間に、彼の母親に来てもらって、食事の準備をやってもらうことも簡単にできただろうに。彼の両親は彼のためなら何でも、喜んで協力する人たちなのだ。たとえ彼が浮気を隠蔽(いんぺい)するために協力を頼んだとしても、あの親子なら示し合わせて、私を騙してくるに違いない...
「どうした?」と彼が言った。いらついてる感じだ。「今は2分しか話してる暇ないぞ」
「ねぇ、ダン。私の父が亡くなったのよ、ちゃんとわかってる?」と言ってすぐに、なんだか彼を挑発してるようで後ろめたさを感じた。これじゃ、けんかをふっかけてるみたいじゃない。私はただ、今日あったことを話したかっただけなのに。
「ごめん。ただ、なんていうか。結構大変な作業なんだよ。いろいろやることがあるんだ」と、一瞬間を開けてから彼が言った。
「それって私が毎日やってることなんだけどね」
ダンが何かを言い返そうとして、ぐっとこらえたのがわかった。「わかってるよ」と彼は言った。「それで、どうした?」
「今日ね、あるものを見つけちゃって。あなたにそれを伝えたかったの」
「え? やばいものじゃないよな?」と言ってから、「価値あるものか?」と、彼が期待のこもった声音(こわね)で付け加えた。
「ううん。箱よ」
「箱? いいか、ジェシ、俺は今、本当にいっぱいいっぱいなんだ。そういう話は―」
「ダン。これは重要なことなのよ」
しばしの間、沈黙だけが耳に流れてきて、それからダンが言った。「わかった、ちょっと待ってくれ。2分だけ」
彼が「マックス、エルスペス、ご飯できたよ~」と声を張り上げるのが、テーブルに置いたらしい受話器越しに聞こえてきた。それから、フォークやナイフが入ってる引き出しをガチャガチャあさる音が聞こえてきて、1分ほどしてから、再び彼が電話に出た。
「それで、その箱は、どんな箱なんだ?」
「金属製の赤い箱だったわ。工具箱か、そんな感じの。だけど、彼はそれに鍵をかけてたのよ」
「そして、鍵がなくて開けられないってわけか?」
「カースティが鍵を持ってる。葬儀が終わるまで開けるなってメモが貼ってあったのよ」
「それはあれだ、ジェシ。彼の個人的なものが入っていて、君たちに持っていてほしいんだろ。どうせ価値のないガラクタだよ」
「ガラクタ?」
「わかるだろ、一般的にはって意味だよ」
「たぶんね」と彼女はゆっくりと言った。「でも、なんか変よね。パパらしくないわ」
「なんていうか...ジェシ、人は変にもなるんだよ」と彼は言って、言葉を止めた。「変っていうか、なんていえばいいんだろ? あれだ、センチメンタルになるんだよ。その時が来る...自分はもうすぐってわかるとね」
「たぶんね」と彼女はまたその言葉を口にした。「あの中に何が入ってるのか、気になっちゃうのよ」
「じゃあ、なおさら開けちゃだめだ。お前は誕生日の時もそんな感じだからな。いつも先に見ちゃって、待てばよかったって後悔してるじゃないか」
「誕生日プレゼントとは違う気がするの。きっとそれ以上の何かよ」と彼女は、彼が正しいことを言ってるのは百も承知で、そんなの認めない、と反駁(はんばく)するような語気で言った。
「あ~もう」とダンが言った。「もう切らなくちゃ。子供たちが...」と彼は言って、思わせぶりなところで言葉を切った。子供たちがどうしたの? 家具を壊しだした? ラウンジに火をつけた? 口の中を食べものでいっぱいにしたまま、けんかを始めた?
「私のことは心配しないで。今ディナーが目の前にあるの」と彼女は嘘をついた。
「それはよかった。何を食べるんだい?」
「シーザーサラダ」と、彼女はまた嘘をついた。なぜわざわざそんな嘘をつくのか、自分でもよくわからない。
二人はグッバイを言い合って、電話を切った。ジェシカはベッドの端に座り込んだ。2時間も車を走らせれば、夫と子供たちに会いに行けるのに、同じ町には妹がいるのに、彼女はどうしようもなく孤独だった。―自分が空洞化して、ぽっかりと開いた穴になったような気分だった。そして、その空虚な穴に、後悔とか、失望といった、よろしくない感情がどっと流れ込んできた。
スマホが震えて、ピザが到着したことを知らせるメールが届いた。彼女は鏡の前に立ち、目の端をティッシュでぬぐってから、表情をキリッとさせて、ロビーへ向かった。
パトリック
マギーが飛行機になったつもりで両手を広げ、出発ロビーを走り回っている。9時半になろうとしていた。彼らが乗る予定の飛行機はすでに1時間10分ほど遅れている。さっきまで疲れきって彼の腕の中でぐったりしていたのが、充電が完了したかのように元気に走り回っている娘を見て、きっとまたすぐに疲れた~とか言い出して、ぐずり出すのだろう、とパトリックは思った。
彼はスマホを取り出すと、スチュアートへメールを打ち始めた。
パトリック:すまない、相棒。まだ空港のロビーで待たされてる。もし大変なら、ウーバータクシーでも使おうか?
「おい」と彼はマギーに声をかけた。若くて、子供がいないことが幸せでならない感じのカップルが、明らかに近くで騒いでいるマギーに苛立っている。「おい、おい、おい」
3回目の呼びかけで、マギーは振り返り、とぼとぼと父親の方へ歩いてきた。すかさず彼は娘をひょいと持ち上げて、膝の上に乗せた。
スチュ:全然大丈夫さ。搭乗できそうになったらまたメールしてくれ。スタンステッド空港で会おう。
パトリック:ルートン空港の方。
スチュ:ああ、じゃあそこで。
「いいかい、みんなちょっとばかり疲れててね」と彼は娘に言った。「迷惑をかけないようにしてなさい」
「ポテトチップスある?」と娘は、彼の注意をなんでもない様子で無視して聞いた。
「いや、果物しかないよ。ブルーベリー食べる?」と彼は言って、リュックサックからタッパーを取り出し、彼女に差し出した。
彼は、ポテトチップスを持ってくるべきだったな、と思った。そして、ポテトチップスを持ってこなかったのは、自分の準備不足の表れだったかもしれない、と振り返った。マギーと二人だけで遠出するのは初めてだった。いつもならスザンヌも一緒で、二人のうちのどちらかが、機内でマギーを楽しませるものを用意し、目的地に着いてからも、おやつや衣服に事欠かないよう、必要なものは大体持参していた。
今回、彼は重要な衣類を少なくとも3つ、彼女を慰めるために必須のおもちゃを2つ、それから、それでしか彼女は飲み物を飲まない唯一のコップまで忘れたことに思い至った。
パトリックは、自分が出来損ないの父親なのか、それとも今回ばかりは状況のせいにしていいのかわからなかった。この旅の目的、かつての故郷であるホーブに戻った時、何が起こるのか、そういったことが、カースティから父の訃報(ふほう)を知らされて以来、ずっと気にかかっていて、娘のおやつやおもちゃのことまで気が回らなかったのだ。
あの電話で、記憶をかなりたどらなければ思い出せないほど、久しぶりに妹と話したのだが、二人の会話はひどくぎこちなく、しらじらしさに満ちたものだった。何年も前に仲が悪くなって以来、どんなコミュニケーションもビジネスライクで堅苦しいものに変わり、感情や共感といった昔はあったはずのものが欠如していた。翌日、彼女からもう一度電話があった時も同様だった。ギャントン地区はホーブの一等地で、白いしっくい塗りの3階建てのタウンハウスが立ち並ぶ高級住宅地なのだが、その中の父親が住んでいた邸宅をさっそく片付けるという話だった。
最初、カースティがあまりにも早く父親が暮らしていた痕跡(こんせき)を消そうとしていることに彼は驚いた。しかし、カドガン家が近年どんな状況だったのかを知っている人なら、彼女が一刻も早くあの家を空っぽにして、すっきりしたい気持ちもわかるな、と納得した。
「ジェシカが片付けを手伝いに来てくれたのよ、頼んでもいないのに」と彼女は電話で言っていた。「まあ、いいんだけど」
「ああ...いいじゃないか。じゃあ、俺は金で埋め合わせるよ」
「お金で?」
「ああ。家具とか私物を撤去するのに業者を呼ばないとだろ。安くやってくれそうな知り合いがいるんだ」
「パトリック」彼女は苛立ちとショックが入り混じったような声をもらした。初めて聞いたというわけではなく、彼女は時折そのような声を発するのだ。おそらく彼女は、姉と兄が作業を手伝ってくれることを望みつつも、亡き父の家で兄妹三人、息が詰まるような時間を延々と過ごすのは避けたい、という切実な思いに苛(さいな)まれているのだろう。
「何?」
「それって、あなた自身は来ないってことを遠回しに言ってるわけ?」
正直言えば、彼は即座に電話を切りたかった。もちろんその場は逃げきれても、短期的な解決にしかならない。ただ、短期的な解決策を何度も繰り返すことで、結果的に長期的な解決になり得るはずだ...
「まあ」
「ちょっと、パトリック」
一瞬、彼は本当の理由を言いそうになってしまった。最近、妻と別居し、シングルファーザー的な暮らしをしていることを。
「要はあれだ—」
「能なし」とカースティが吐き捨てたことで、彼は踏ん切りがつき、電話を切った。
言わなくてよかったんだよな。
ようやく客室乗務員が出発ロビーにやって来て、遅れていた飛行機の到着を告げた。間もなく搭乗できるらしい。それでもパトリックの頭の中は、数ヶ月前に妻が出て行ったことを姉と妹にどうやって伝えようか、ということでいっぱいだった。おかしなことになるのは必至(ひっし)だ。なぜもっと早く言わなかったのかと責められるだろうし、今までずるずると言わずにきたという事実が、カドガン家の三人兄妹の関係を如実(にょじつ)に物語ることになる。それから、次々と質問の矢が飛んでくることが目に見えている。どれも答えにくいものばかりで、一つ答えるごとに傷がえぐられるように、痛みが増幅していくだろう。
とはいえ、いつまでも黙っているわけにはいかない。いずれ真実が明らかになるのだから。それに、彼はイングランドに戻りたいと思っていた。まずスチュアートの家に泊めてもらって様子を見つつ、できればロンドンで暮らしたい。何があっても、ブライトンにだけは戻りたくない。
飛行機はあっという間にグレートブリテン島に渡った。マギーは彼の腕に頭を預け、両手で彼のスマホを握ったまま眠っている。彼は本を読みたい気分ではなかったし、最近、音楽を聴くのもためらわれていた。どの曲を聞いてもスザンヌのことを思い出しそうだったからだ。悲恋(ひれん)の曲しかこの世にはないのではないか、と思ってしまうくらい、どの歌詞にも胸が締め付けられる。それで彼は、冷たいプラスチックの窓に頭を押し付けて、アイリッシュ海の上に広がる星空を夢想しながら、真っ暗な夜空を眺めていた。ルートン空港が近づくと、眼下に、光の触手で縁取られた町や都市が広がるように見えてきた。
俺は何者にでもなって生きていける、と彼は自分に言い聞かせながら、誰でもない人として新たな生活を始めることに思いを馳(は)せていた。けれど、新しい人生に移行することは、すなわち、元の人生に置いてきた人々に多大な迷惑をかけることになるな、と思い至る。海を渡ったパトリックは、そのことを誰よりも身に染みて知っていた。
飛行機はルートン空港にそっと降り立った。まるでパイロットが大幅な遅れの埋め合わせに、誰も起こさないようにと配慮しているかのような、静かな着地だった。それでも、はみ出すように聞こえてきたブレーキ音と、完全には抑えられなかったらしい機体の揺れに、マギーが目をこすりながら起き出した。額にかかった茶色の巻き毛を手で横に流している。
「パパ~」と彼女はめそめそと泣き言を言うように声を発した。あたしが眠るまでこのまま寝室にいて、と懇願(こんがん)する時と同じ口調だ。最近は二人でよくそんな夜を過ごしていた。
「ああ、パパはここにいる。もう着いたよ」
「スチュの家?」と彼女は言った。
「いや、まだ空港に着いたところだよ。スチュが空港で待ってるんだ」と彼は、待ってるはず、と期待を込めて言った。スチュはパトリックにお金だけ渡して、これでタクシーを呼べ、と言ってくるような男だった。
しかし、今回は待っていてくれたようだ。パトリックがスマホの電源を入れると、真っ先に彼からのメッセージが目に飛び込んできた。
スチュ:もういるぞ。クソおせーな。
パトリック:わりい。今着いた。
旅行カバンを預けている乗客が少なかったようで、すんなり流れてきた旅行カバンを受け取り、到着ゲートを出るまで、ほとんど時間はかからなかった。また待たされるのかとうんざりしていたパトリックは、そのスムーズさに頬がほころぶ。人々でごった返すロビーに出ると、すぐに「マギー・カドガン」と書かれたプラカードが目に入った。スチュがそれを掲げて、出口の近くに立っていた。手をつないだマギーを見下ろすと、寝ぼけまなこで薄目を開けるようにして歩いている。寝起きじゃなければ、自分の名前が書かれたプラカードを見て、彼女の笑顔がはじけただろうな、と思った。
彼は古くからの友人とひとしきり抱き合い、一緒に冷たい夜の空気の中を歩き出した。久しぶりにイングランドの地を歩きながら、パトリックは不思議な感覚な包まれていた。いつまでここにいるのかまだ決めていないことも相まって、足が宙に浮いている感じだ。
「よく戻ってきたな」とスチュが言い、キャスター付きの旅行カバンを代わりに押してくれた。手が空いたパトリックはマギーを抱える。
「久しぶりの空気だ」
「まあ元気出せよ...お前の―」
「ああ」とパトリックが発言をさえぎった。
「それでお前の―」
「ああ」
1秒か2秒立ち止まり、その話題には触れてほしくないんだなと理解したスチュは、あからさまに明るい声に転調して、「うちまでお送りしましょうか?」と、執事(しつじ)を真似て左手を右胸に当てた。
「頼む」とパトリックは言い、夜気(やき)を深く吸い込むと、先を急ぐように歩き出した。
〔チャプター 1の(実況中継的な)感想〕
さっそく泣けてきた...涙←はえーよ!!笑
WhatsApp(ワッツアップ)というのは、日本で言うとLINEみたいな、メッセージアプリです。ヨーロッパではWhatsAppが主流なんです。ここから謎の自慢タイムに入りますが、笑
藍はスカイプで国際電話をかけたり、WhatsAppでやり取りしたりという、交渉や連絡の仕事を、おととしから去年までしていたので(まあ、通訳みたいな仕事ですね)、藍もWhatsAppを使っていました。なので、WhatsAppに関しては日本で3位に入るくらい詳しいです!!笑←独身男はすべてをアピールに使わないとだから大変だね!爆笑
藍はジェシカに考え方が近いかもしれない。←いや、ジェシカはちゃんと考えがあってのことだから、君とは違うと思う。笑
また泣けてきた。藍は幸運なことに(体は)まだ健康なんだけど、ジェリーの晩年の過ごし方と、今の藍の日々が似通っている。しかし残念ながら、藍のところには出張ナースは来てくれないらしい。藍はナース服のコスプレが好きなのに...泣
「私はあの時あれをやったんだから、今回はあなたが...」とか、「あん時は俺がやっただろ。今度はお前が...」とかって、日本でもありますよね?(あれ、藍の周りだけかな?)
イギリスも日本も同じなんだな、と安心するような、なんだよ、どこも同じかよ、とうんざりするような気分です。
不謹慎かもですが、訳しながら笑いっぱなしです。爆笑
カースティは教員ですが、一応藍も教員だったんですよ。(まあ、信じなくてもいいですけど...笑)←「なんとかして信じさせたい」から「まあ、信じなくてもいいですけど」なんて、ずいぶんとマインド(心の持ちよう)が変わったね^^
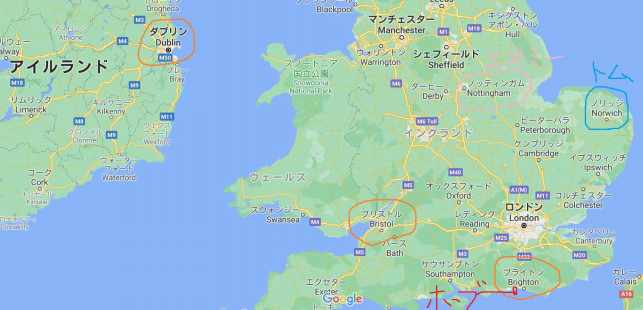
そろそろ「どこ?」と、地図が欲しくなってきたと思うので、載せます!笑
・ダブリン(パトリックが住んでいるアイルランドの首都)
・ブライトン(カースティが住んでいる町)
・ホーブ(ジェリーが住んでいた実家のある町。ブライトンから西へ5キロほど海外沿いを走るとある。←いや、走らなくてもあるだろ!笑)
最近、日本のニュースでも「イギリス」と「イングランド」を区別して報道するようになって、説明が楽...笑←お前にはもう説明する機会がないだろ!(っていうか、教壇で説明してた頃も、「楽...笑」とか以前に誰も聞いてなかったくせに!!爆笑)
あぶなかった~。レナちゃんと出会えなかったら、藍の人生は全く花がない無味乾燥な砂漠になってたところだった。レナちゃんは記憶の中のオアシスのように、藍を死ぬまで、もしかしたら死んでからも、シコシコ癒してくれる。
それにしても、父と娘の関係とか、藍には全く関係ない話で、まるで月か木星で起きていることのように遠く、記憶から感情を引っ張り出すわけにはいかないのですが、一応「父親」になりきって、訳してます。
チャプター 2
ブライトン、サセックス
カースティ
カースティ、ジェシカ、パトリック、三人揃って乗り込んだメルセデスのリムジン型霊柩車(れいきゅうしゃ)は、つややかな車体を黒光りさせながら、ルイス・ロードをゆるやかに滑走(かっそう)していた。カースティがジェリーのお別れ会の会場として予約した〈鐘の音〉というパブに向かっている。霊柩車が路上に現れると、周りの車が一斉に神妙(しんみょう)な運転に切り替わり、交通の流れが大人しくなることが、カースティには不思議でならない。―普段は見られない周りへの気遣いが感じられるのだ。A地点からB地点に素早く移動すること以上の大きな力が、この路上を支配しているらしい。
普段からこうあってほしい、と自転車愛好家のカースティは思う。政府が率先(そっせん)して霊柩車をそこら中に走らせればいい、とも思う。このルイス・ロードでも自転車に乗りながら、何度ヒヤッとしたことか。彼女は窓の外を眺めながら、安全で思いやりに満ちた道路を望んでいた。
隣では、ジェシカが人差し指の関節を噛みしめながら、窓の外を見つめている。実家の前までリムジンが迎えに来た時、彼女は泣いていた。それから火葬場でも、彼女は泣いていた。そのどちらでも周りの視線を気にしてか、節度をわきまえた、おしとやかな泣き方だった。時折、彼女のシュッとした頬に涙がつたった。―彼女の顔は、ぜい肉がそぎ落とされ、頬骨が浮き上がっている。―それを見て、カースティがハンドバッグの中に入れていた2つのポケットティッシュのうち、1つをジェシカに手渡すと、彼女はそのティッシュで上品に涙をぬぐった。
パトリックは感情をむき出しにするタイプだった。ほとんど暴力的といえるほどに感情を爆発させ、2、3度大きくしゃくり上げるように泣きじゃくってから、ようやく落ち着いたと言わんばかりに顔を上げ、その時の相手が誰であっても、ジェリーの思い出を話しているその人を、うるうるとした目で見つめるのだ。
彼は悲しみをアピールし過ぎね、彼の生き方全般にいえることだけど、と彼女は思った。
その後、パトリックの手元を見ると、彼は葬儀のパンフレットをくしゃくしゃになるまで握りしめていた。―表紙には父親の写真と、父が生まれて亡くなるまでの年月日が書かれているのだが、しわくちゃに歪(ゆが)んでしまっている。まるで父の悔しさ、悲しみ、怒りが、パンフレットのしわに凝縮されているように見える。そんなこともあろうかと、とカースティは思った。パンフレットを余分に印刷しておいてよかった。きれいなパンフレットを彼に差し出してみよう。どんな顔で受け取るかしら。
「なかなかいい葬儀だったんじゃない?」とカースティが沈黙を破った。信号待ちでリムジンが止まり、景色の流れも止まった時だった。
ジェシカが「うーんまあそうね」となんとか声をしぼり出すと、パトリックもうなずいた。
カースティは礼拝中、しっとりと涙を流しながら、〈バルサム・ティッシュ〉で時折涙をぬぐいつつ、うまく立ち振る舞えたと自負していた。そして、朗読もうまくできた。ジェリー・カドガンは詩を好んで読んだり書いたりする人ではなかったけれど、フィリップ・ラーキンの『高窓』が葬儀に合っている気がして、彼女はそれを朗読した。それによって場が引き締まり、おごそかな雰囲気になったのは確かだ。彼女自身はラーキンの世界観に心底共感したわけではなかったけれど。
「不思議よね?」とカースティは続けた。「礼拝を取り仕切っていたあの司祭は、彼に一度も会ったことがないのよ。でも、まるで生前よく会っていたみたいな、親しさをうまく醸し出してたわよね。マイクおじさんの葬儀の時も、あの司祭だったでしょ」と言いながら、よぼよぼの司祭を思い出していた。彼はマイクおじさんの葬儀の間ずっと、サリーおばさんのことを、なぜかシルビアと親しげに呼んでいた。
彼女はジェシカにティッシュを一枚差し出したが、手のひらを突き出されて拒否されてしまった。
「ダンは―?」
また手のひらを突き出された。どうやら姉は、お互いの気遣いを交換するようなやり取りをしている気分ではないようだ。
「お好きなように」カースティはふんと鼻を鳴らした。
パトリックは二人の反対側で、黒いカーペットが敷かれた車内の床に両足を伸ばして座っていた。彼の隣には、ガラス張りの小さな冷蔵庫があり、〈エビアン〉のペットボトルがいっぱいに入っている。それを見て、カースティは、このリムジンが葬儀だけでなく、高校の華やかなプロムや、独身最後のバチェロレッテ・パーティーにも使われているのではないかと思った。―彼女がリムジンに乗った機会はその二回だったから。もしかしたらこの運転手は、今頭に載せているシュッとしたシルクハットを、夜には運転手用の平べったい帽子に変えて、誰かの40歳の誕生日会や、離婚パーティーに参加する人たちをこのリムジンに乗せて、ブライトンの会場まで運んでくるのかもしれない。
彼女は、ジェシカが片手で払いのけたティッシュをパトリックに差し出した。「俺は平気だよ。ありがとう」と彼は言った。
「よかった。スーズが来れなかったのは残念だけど」と彼女は言った。葬儀で義理の姉を見かけなかったことは驚きだった。パトリックはブライトンに着いてからずっと、彼女の出席について、なんだかはっきりしない返事をしていたのだ。
「ああ」と彼が言った。「彼女は仕事を休むことができなかったんだ」
「そう」
「あの職場のやつらはろくでもないな。思いやりの欠片もない連中だよ」と彼は言った。
「旅行をキャンセルできなかったの?」
「できないよ。アメリカで年次総会があるんだ。彼女も出席しなければならない。どういうことかわかるだろ」
「もちろん」とカースティが言った時、リムジンがパブ〈鐘の音〉の前で停車した。もちろん、彼女にはどういうことかわからなかったけれど、今はそこを深く追及している場合ではない。
店の外には喪服(もふく)を着て、煙草を吸っている人たちが集まっていた。実家で父と一緒にディナーを食べているところを見かけた覚えがある人たちだ。かなり昔のことなので、かすかな記憶しかないけれど、父の仕事関係の人たちだろう。父の建築士事務所は自営業だから、実際に建物を建てる段になると、建築業者へ発注しなければならない。彼らのうちの何人かは、父からその代金を受け取っていたと思う。彼らが店の前で、談笑するように軽口を叩き合っている姿を見ると、父の友人とは言えないな、と思った。続々と、葬儀の二次会ともいうべきお別れ会の会場に参列者が集まってきた。
何はともあれ、葬儀が満員になったことは、会場の手配をしたカースティにとって救いだった。それにしても、この数年間、彼らはどこで何をやっていたのだろう。父が重い病(やまい)と闘っていることは当然知っていたはずだから、まだ彼がかろうじて立てるうちに、彼に顔を見せに来るべきだと思わなかったのだろうか。数十年来の付き合いで、父が取ってきた多くの仕事を彼らに回していたんだろうし、父が生きているうちに、お別れの挨拶くらいあってもよさそうなものよね。
「着きましたよ?」と運転手が言った。
「ちょっと待ってもらえますか?」とジェシカが言った。「目の周りを整えないといけないので」
「いやいや」と運転手は呆れたように言った。「心配しなくても、みなさんダンスに夢中で、人の目の周りなんて見ませんよ」
ジェシカはあからさまに片眉を上げ、怪訝(けげん)な表情をしたが、誰も何も言わなかった。カースティは、それが霊柩車の中のやり取りだとは思えなくて、つい笑いそうになってしまった。
パトリック
彼は自分が何を考えているのか、本当にわからなかった。全部スーズの会社のせいにして、義理の親が亡くなったというのに彼女を無理やりアメリカに行かせた、なんて馬鹿げた話を口走ってしまった。真実を隠すことに必死すぎて、その過程で自分が馬鹿だと思われても構わないというのか? どう口先でごまかしても、いずれは明らかになることなのに。
一方で彼は、スザンヌの元上司であるエオイフェの印象を、そんな風にねじ曲げて伝えてしまったことに、ひどく罪悪感を抱いていた。彼女は、部下が身内の葬儀に行くといえば、仕事なんかほっぽり出していいから早く行ってあげなさい、と言うような人なのだ。
少なくとも、妻がアメリカに行ってしまったのは本当だった。
パトリックはパイントグラスで3杯目のビールを飲みながら、娘のマギーを探してパブを歩き回った。彼女はダン、マックス、エルスペス、それからリヴィと一緒に、店内を巡(めぐ)っていたようだ。彼はリムジンの中でずっと、今ごろマギーが自分たちの秘密をバラしているのではないかとひやひやしていた。
しかし、それは杞憂(きゆう)だった。マギーは真実を心のうちに秘めながら、こう言っていたのだ。ママはね、どうしても休めない仕事があって来れなかったの。
スーズ自身について悪く言うより、彼女が働いていたIT企業を悪者にする方が、気分的にずっと楽だった。彼女はまだあの会社で働いていると、みんな思っているようだし。実際は一ヶ月半前に、彼女は億万長者の起業家と一緒に、夫と娘を残したまま、サンフランシスコに引っ越してしまったのだ。相手は、新興企業を立ち上げ、巨万の富を築いた成り上がり男で、去年の半ば頃から不倫関係にあったらしい。それを認めたくない、という気持ちもあって、周りに真実を打ち明けるのがためらわれるのだ。
スチュ以外にもう一人だけ、パトリックの方から自発的に相談を持ち掛ける人がいた。彼は建築業を営んでいて、彼を通して多くの仕事を得(え)ていた。最近、時間の管理がうまくいってないんです、と、その理由を含めて彼に愚痴っぽく言いたかった。マギーを幼稚園に連れて行き、その足で自分も、その日の現場がどこであれ、仕事場に向かうという生活を続けていると、時間のやりくりが大変なのだ。その二人以外に、夫婦のいざこざまで打ち明けられる人はいなかった。アイルランドで暮らしているとはいえ、アイルランドに知り合いはほとんどおらず、一応知っている人といえば、スーズのかつての仕事仲間くらいだった。スーズがアイルランドでIT関係の事務所を構えた時に、仕事を回してもらっていた大手企業の人たちだ。ただ、当然のことながら、妻が一緒に仕事をしていた、というだけの薄い関係の人たちとは、瞬(またた)く間に疎遠(そえん)になってしまった。彼のようなイングランド人のペンキ職人兼内装業者と、ダブリンの一等地にオフィスを構えるIT企業のおしゃれ担当では、共通の話題なんてそうそう見つかるわけがないのだ。彼はそのことを重々承知していた。
「彼女はスカイプを使って連絡してくるんだろ?」とナイルは言った。―彼はスーズの元アシスタントの、気のいい夫だった。彼女がアメリカに行ってしまった1週間後、彼は残されたパトリックを心配してか、ビールを飲みに連れ出してくれたのだ。(そんなことはその時が初めてで、それ以降は一度もないところを見ると、興味本位だったのかもしれない。)
「そうなんです。彼女が言うには、映像技術はますます進歩してるから、あと1年もすれば、彼女とマギーが同じ部屋にいるような感覚を味わえるそうです。厄介なことに、彼女は本気でそういうことを言ってるんですよ」
スーズはテクノロジー関連の話に弱いというか、毒物が混じった粉末ジュース〈クールエイド〉を飲み干した、あの狂信的な信者たちのように、胡散(うさん)臭さなど気にせず鵜吞み(うのみ)にしてしまうのだ。まさに昨年の半ば頃から、そのうち自動車がなくなるとか、人工知能が発達して人間は物を作る必要がなくなるとか、彼女はそんな絵空事を口にするようになった。不倫の事実を知って、なるほど、こいつの入れ知恵か、と思ったものだ。恋人のジョンがピロートークで彼女に語った話を、彼女は盲信的に丸呑みにしてしまったのだ。ジョン自身はアメリカで、あまり華やかとはいえないプログラミングの分野で働いていた。パトリックには詳しいことはわからないが、クラウド関連の仕事をしていたようだ。ジョンがダブリンに来たのは、彼の会社のヨーロッパ支社を作るのに、ロンドンよりも安価で会社を設立できるかららしい。そして、テクノロジー関係の成り金たちが集(つど)う、いわゆる合コンでスーズと出会い、数ヶ月のうちにパトリックの結婚生活を破綻(はたん)させ、アイルランドに支社も作って、彼女を引き連れてアメリカに戻ってしまった。
パトリックは沈んだ表情でパイントグラスをカウンターに置くと、何か食べようとビュッフェに向かった。そこには喪主のカースティが発注した食べ物がずらっと並んでいた。
ジェシカが「パパの好きなものも出してよね」とカースティにリクエストしていたのを思い出す。そのリクエスト通りに、フライドポテト、ピーナッツ、生地の柔らかいソーセージロール(ソーセージとパン生地の間にすき間ができている、すかすかな安いやつ)もちゃんと並んでいる。それから、四角いチェダーチーズ。こうして見ると、父は茶色っぽいものばかりが好きだったんだな、と思った。ひときわ異彩を放っていたのは、ボウルいっぱいに盛られたスナック菓子〈ウォッツ〉で、パトリックはそれを一掴みして口に放り込むと、オレンジ色の粉にまみれた指をぺろりと舐めた。
カースティがビュッフェのところにやって来て、彼の横に立った。テーブルの奥、ほとんど手をつけられていないチェダーチーズの後ろには、父親の写真が一枚立て掛けてある。髪の毛がなく、ポロシャツのお腹の部分がぽっこり突き出ていることから察するに、5、6年前に撮られたものだろう。ジェリーは川岸に座り、片手に釣り竿、片手に鯉の尻尾を掴んで、満面の笑みを浮かべている。彼は幸せそうで、優しそうだな、とパトリックは思った。彼の父親はもういないのだ。
「楽しんでる?」とパトリックが聞いた。
「ええ、そりゃもう。カラオケは何時から始まるのかな?」
彼女がクスッと笑った。
「君たちが見つけた釣り具箱のことを考えていたんだ」
「あれを開けるのはまだ早いわ」
「ていうか中には普通に、彼が使ってた釣りの道具がそのまま入ってるんじゃないか?」とパトリックは彼女を無視して続けた。彼は少し酔っ払っていた。
「そうは思えないけど」
「つまり、そういう可能性もあるんじゃないかってこと。もしかしたら、俺ら3人の中の誰かに彼の趣味を継(つ)いで、釣りをさせたいのかもしれない。エルトン・ジョンの歌でそんなのがあっただろ?『親父の銃』っていう歌」
「その歌は聴いたことないわね」
「『今日から~、俺は親父の銃を腰に差すよ~』」とパトリックが大声で歌い出した。父親のお別れ会なんだし、歌ったって不謹慎でも何でもないはずだ。
「やめて」とカースティがきっぱりと言った。「とにかく。中に入ってるのは、彼の手垢にまみれた釣りの道具ではないわ。そういうのは全部ガレージにあったから」
「あったのか?」
「うん、あった。整理してたらいっぱい出てきたから、青少年センターに寄付しちゃった」
「もうないのか? 俺が欲しいって言ったらどうするつもりだったんだよ? 子供たちの誰かが釣りをやりたがるかもしれないだろ」
「あなたが片付けを手伝いに来てくれれば、あなたのものになったでしょうね」
「わかるだろ、行けなかったんだよ―」
「それに」と彼女が割って入るように言った。「あなたはダブリンに住んでるじゃない。ダブリンにもリフィー川だっけ、川はあるみたいだけど、あなたは釣りをしないんだから、道具なんて持ってても仕方ないでしょ」
「そうだな」パトリックは、ダブリンに住んでる云々(うんぬん)という話をこれ以上進めるわけにはいかないと思い、話を切り上げた。実は今、ロンドンの北部、クラウチ・エンドにある旧友のスチュの家に住まわせてもらっている、なんて言えるわけがない。マギーは空いていた客間で寝て、俺はリビングのソファで身を縮めて寝ている、なんて言えっこない。
「とにかく、中身はあとでわかるわ。家に帰ったら開けましょ」
「君の家?」
「いいえ、実家」とカースティが言った。「ママとパパの家よ」
彼女はフライドポテトをつまむと、ポテトの端をケチャップにひたしてから、口に詰め込んだが、美味しさも喜びも、肯定的な感情は何も感じていないようだった。
「すっかり冷めちゃって美味しくないよな?」
彼女はうなずいた。
「まったくだ」と彼も同じようにうなずきながら、ポテトを口に放り込んだ。「でも、おかしいよな? 俺たちはまだあの家をホームだと思ってるんだぜ。もう3人のうちの誰も...わかるだろ?」
「その話は今はよしましょ」とカースティが言った。「ここがお開きになったら、ゆっくり話せるわ」
パトリックはカウンターに戻り、次は何を飲もうか考えながら、カウンターの向こう側の、従業員の制服を着ている若い男に目配せした。ところが彼はうつむいたまま、iPhoneの画面に夢中になっていて、パトリックが半分丁寧に、半分イラつきながら彼の注意を引こうとしていることに気づかない。すると、どことなく見覚えのある女性店員が奥から出てきて、パトリックを見て微笑んだ。彼女は若い従業員の頭を叩いて、彼の額をiPhoneの画面にぶつけてから、こちらに近づいてきた。誰だったかな? パトリックは彼女の名前を思い出そうとした。
メアリー、マーラ、メイジー、メレディス。
頭の中で色々な名前がぐるぐる回っていた。たしかMで始まる名前だったはず...
モイラ、マーサ、マディー、マリアンヌ、メリッサ。
あ、きっとそうだ、と思った。メリッサだ。
「ごきげんよう」と彼女が言った。「久しぶりね」
「やあ!」とパトリックはなるべく陽気に言った。久しぶりだということだけはたしかだ、と彼は思った。彼は今38歳なので、彼女と最後に会ったのは、おそらく18年ほど前になるだろう。ブライトンのナイトクラブで会った可能性が高い。彼女は彼と大学が同じで、彼の一つ下の学年だったことを思い出す。スチュが彼女の友達の一人(タマラだったか、タムシンだったか)と付き合っていて、彼女のグループと彼のグループが一緒にブライトンの街に繰り出すことが時々あったのだ。
長い年月が経過したにもかかわらず、彼女の外見はそれほど変わっていなかった。相変わらず美人で、引き上がった頬が魅力的だった。いつでも冗談を言おうとしている感じの茶目っ気のある笑顔を常に浮かべている。
あとは、彼女の名前さえ思い出せれば。
「あれからもう、18年くらい経つかな...?」と彼は思い切って言ってみた。
「そのくらい経つわね」と彼女が笑顔で言った。「私の名前を思い出せなくて困ってるんでしょ? パトリック・カドガン」
「バレてた?」
「バレバレよ。だって唇の端を噛んでるんだもん...」
「なるほど。あ、思い出したかも、メル?」
「メルルゥ―」と彼女は、Lの音を引き延ばして、その先をつなげさせようとする。
「メル、イッサ。メリッサ?」
「それはどこの子?」
「じゃあ、メル、アニー。メラニー?」
「残念。諦める?」
「うん」
「クロエよ」と言って、彼女は笑った。
「は? さっきのメルルゥ―はなんだったんだよ?」
「ちょっとからかったの」
「ていうか、俺の親父の葬式だってわかってて言ってるのか? 葬式はもう終わって、今はお別れ会だけど」
「わかってるわ。あなたが少しでも元気になってくれればと思って」と言って、彼女は肩をすくめた。「それはともかく。ご注文は何になさいますか?」
「ギネス・ビールを頼む。それと、ウイスキーも飲みたいな。何があるの?」
クロエは棚の一番上の段を見上げながら、ボトルのラベルをすらすらと読み上げていった。言い慣れている感じだったが、パトリックはほとんど聞いていなかった。彼女が他のお客さんのところへ行ってしまわないように、何か話を続ける話題はないかと必死に頭を巡らせていた。
「じゃあ、オーバンで」と彼は、ラベルの文字が真っ先に目に入ってきたから、という理由だけで適当にそのウイスキーを選んだ。
「あ、それはいいお酒よね?」
「おそらく」と彼は言った。彼女がビールサーバーの蛇口をひねり、パイントグラスにギネスが注がれ始めた。ビールはすでに4杯目だ。その上、ウイスキーにまで手を出したら、きっとまずいことになる、と頭ではわかっていた。この後、あの釣り具箱を開けるという一大イベントが控えているというのに。
「ご愁傷様」とクロエは言いながら、彼の前のカウンターにウイスキーの入ったグラスを置いた。ギネス・ビールはまだ泡が落ち着くまでに時間がかかりそうだ。そこがギネスのいいところだ、と彼は思った。話す時間をかせいでくれる。「あなたのお父さんのこと、少し知ってるの。いい人だったわ。彼はこのお店を修繕しに何度か来てくれて、その時に知り合ったの。彼は全然お金を請求しない人だった。ただ同然で仕事を引き受けてたわ」
「ありがとう。彼はそういう人なんだよ。いつからこの店で働いてるんだ?」
「また働き始めてからは、2年ね。でも大学時代に、夏休みはここで働いてたから」
「そうなんだ。なんでまた...」と彼は、バーの仕事に戻った理由を聞こうとして、途中で質問を尻すぼみにした。そこまで聞くのは個人的なことに踏み込みすぎだと思われ、彼女に引かれてしまうかもしれない。
「あの筋肉バカ」とクロエは、チャーミングな笑みを浮かべて言った。「私はマティ・ハイドと結婚したのよ。あのバカ覚えてる?」パトリックはうなずいた。
マティ・ハイドも同じ大学で、彼より2つ上の学年だったから、彼女より3つ上ということになる。マティ・ハイドは学内でモテ男として名を馳せていた。言い換えると、マティ・ハイドといえば、やりチンで有名だった。
「あいつ、私と結婚してからも、サラ・バーンズとやりまくってたのよ。彼女を覚えてる?」
「クソだな」
「まったくね。それで離婚して、今はここで週に3、4日夜に働いてるの。昼間は大学でも働いてるんだけど、それだけじゃお金がね」
「え、大学? じゃあ、君は...?」
「天体物理学の上級講師よ。まだ教授にはなれてないけどね」
「マジ?」
クロエは口を大きな「ハ」の字に開いて笑った。
「なわけないでしょ。広報の仕事よ。高校生向けに大学紹介のパンフレットを作ったりとか、そういう仕事」
彼女は、とっくに泡が落ち着いていたギネス・ビールをパトリックの前に置いた。彼女をここに引き止めて、もっと話を続けるには、もう一杯注文しなければならないのは明らかだ。彼はグラスを傾け、オーバンをぐっと飲み干すと、もう一杯、と言った。
「このウイスキーは、一杯9ポンド(約1,300円)だってわかってる?」
「マジかよ? ふざけんなよ」
「次の一杯だけ無料でいいわ」とクロエが言った。「悲しみに暮れる息子への、はなむけ的なね」
「君ってすごく親切なんだね」
「どういたしまして。じゃあ、今飲んだ一杯分はレジに通すから。それから、私がもう一杯グラスに注いでいる間に、次に何を話すか考えておいて。あなた自身のことよ」
「わかった」
「そのギネス・ビールも全部飲んじゃって。ビールのおかわりは有料になるけどね」
パトリックはパイントグラスを見つめながら、これ以上飲むのはやめておくか、と思案した。すべては、数十年ぶりに再会した(数十年も経ったとは思えないほど魅力的な)バーテンダーを口説き落とし、いちゃつくためだ。
「俺はダブリンに住んでたんだけど」と彼は早口で言った。「最近こっちに来て、4歳の娘がいて、実は住むところもないし、妻は出て行っちゃったし、今のところ仕事もないんだ」
「あらまあ、それはご愁傷様」クロエはウイスキーを彼の前に置いて言った。「それはこの1年くらいの話?」
「そう。あ、それと、この話は俺の妹たちにはいっさい言わないでほしい。あそこにいる二人」と彼は言って、顎(あご)で指し示すように顔をもう一つのフロアへ向けた。カースティとジェシカが小さなテーブルを挟んで座っている。彼女たちのすぐそばではダーツの試合が行われているが、それには興味なさそうに何やらこそこそ話している。
「彼女たちはあなたに娘がいることを知らないの?」
「あ、いっさい、は言い過ぎた。それだけは知ってる。それ以外は何も知らない。―そんなことが起きてるなんて、つゆほども思ってないよ」
「そっか」とクロエは言った。「まあ、積もる話もあるわよね。とりあえず、何か別のお酒を飲むのが一番よ。有料になるけどね」
彼女は微笑んで背を向けた。ダーツをしていたお客の一人が、カウンターの彼女に向かって手を挙げたのだ。彼女はカウンターを出る際、まだスマホの画面に釘付けになっている店員のスマホを下から叩いて、再び彼の額にぶつけた。
彼女の歩く姿を目で追いつつ、妹たちの方に目をやると、二人と目が合った。いぶかるように、こっちをにらみつけている。どうやら俺のことを話していたらしい。ジェシカがあきれたように、かすかに首を横に振るのが見えた気がした。
ジェシカ
ダンと子供たちは早い時間に帰った。そこまではよかった。腹立たしいのは、パトリックとジェリーの昔の友人3人が、そろそろお別れ会をお開きにしてもいい頃合いになっても、昔話を掘り返しながら、ぐだぐだと深酒をしているのを見ていなければならないことだった。それ以上に腹立たしいのは、パトリックがあのバーテンダーの女性といちゃつくためだけに、いつまでもあの老いぼれたちとお酒を酌(く)み交わしていることだ。
パトリックは酔っ払っていた。ただ、ジェシカには彼がどの程度酔っ払っているのかはわからなかった。この数時間、彼はカウンターの椅子に腰掛けたままだったので、彼が立ち上がって歩き出さない限り、そのダメージの大きさを計り知ることはできない。
夜の7時近くになると、パトリックたちは3本目のウイスキーに取り掛かっていた。彼らは、「極上のウイスキーをこよなく愛した男に」と、ジェリーのウイスキー好きを引き合いに出して、乾杯の音頭を取っていた。ジェリーは高価なシングルモルト・スコッチを膨大にコレクションしていたほどのウイスキー好きだった。そのコレクションは、彼の仕事部屋の鍵のかかったキャビネットに、2つの〈エディンバラ・クリスタル・グラス〉と一緒に保管されていた。毎年クリスマスになると、そのアザミの花模様の入ったクリスタル・グラスを引っ張り出し、グラスが違うと味も違ってくると言わんばかりのうっとりした表情で、彼はウイスキーを体内に流し込んでいた。
「いつになったら帰れるの?」とジェシカがカースティに聞いた。彼女たちはカウンターから離れたテーブル席に座っていた。彼女たちの頭上にはスクリーンがあって、一日中〈スカイ・スポーツ〉が映し出されている。「うちらの関係で残ってるのは、もう彼らだけみたいだし、ここの店主もそろそろ私たちを追い出したいでしょうね」
そのパブでは7時半からクイズのイベントが始まるらしく、それが目当ての常連客で賑わい始めてきた。スタッフがうちらのビュッフェの残り物を片付けながら、「他に何か必要なものはございませんか?」と4回も聞いてきた。「ていうか、なんなのあれ? 見てらんないわ。ちょいちょいあのバーテンダーにちょっかい出してるじゃない」
「彼らは大学で知り合ったんだよ、ジェシ。彼から聞いたわ」とカースティが言った。
「なるほど、そういうことね。だからスザンヌは来なかったわけか。話が見えてきたわ。ほんとに、何やってんだか」
「私たちはもう行きましょ」とカースティがコーヒーを一口すすりながら言った。「これを飲んじゃったらね」
「それよりほら。早く実家に行きたいわ。あの箱を開けたくて仕方ない。そしたら、私はホテルに戻りたい。今日はなんだか―」
「よしなよ、ジェシ」
「よしなって何を?」
「ベッドであえぐようなこと」
「あえぐようなことなんてしないわ」
「じゃあ、そうやって文句ばっかり言うのはやめなよ」
「文句なんか言おうとしてないわ。今日はなんだか疲れちゃったって言おうとしたのよ。あなたはどうなの?」
「そうね」と、カースティはコーヒーをもう一口飲みながら言った。「たしかに」
二人が何分か彼を待ちながら黙り込んでいると、頭のはげた太った男がバーの端の席に腰掛けた。ブライトンを拠点とするサッカーチームのアウェイ用のユニフォームを着ている彼は、パイントグラスに入ったコーラを一口喉に流し込むと、マイクを3回叩いた。
「若き紳士、ならびに若き淑女の皆さん、こんばんは」彼が野太い声をとどろかせた。「毎週恒例のひらめきクイズ〈鐘の音〉がまもなく始まります。ラストオーダーの鐘が鳴るまで、時を忘れて、心ゆくまでお楽しみください...」
パブの反対側の人だかりから、やかましいほどの歓声が上がり、ジェシカが立ち上がった。
「ほんとにもう、行きましょ」
彼女はパトリックのところにつかつかと歩いていった。彼はウイスキーが入ったグラスをぼんやりと見つめている。
「準備はいい?」と彼女が彼に威圧的な言い方をした。「ウーバータクシーがもう、あと2分もすれば来るわ」
厳密な時間は定かではなかった。実際はまだ車を呼んでもいなかったが、パトリックには知りようもないでしょう。彼が「もう一杯だけ飲んでいこうかな」などとつぶやいている横で、彼女はスマホのアプリを開いて、近くを走っている車を探した。4分後には来てくれることがわかり、大して時間差がなかったことにほっとする。
「ダメ。もう行くよ、パトリック、ほら今すぐ」と彼女は、つい息子のマックスに言っているような気分になり、お友達にバイバイしなさい、と付け加えそうになった。
「あと一杯だけだからさ。ちょうど今、親父の古い車の話をしてたんだ」
「絶対にダメ。家に帰ってあの箱を開けるのよ。そしたら、私はホテルに戻るんだから」
「じゃあ、俺はあとから―」
「ダメよ」と彼女はピシャリと言い残し、ドアに向かって大股で、上着の裾をなびかせるように歩いていった。ドアの手前で振り返ってみると、パトリックがまた、あのバーテンダーの女性と話そうと、カウンターに覆いかぶさるように身を乗り出していた。
彼の行動を正すために、何かもう一言しかりつけてやりたい気持ちもあったが、それ以上に、どうでもよくなっていた。私はすぐに帰るんだし、彼もダブリンに帰るだろうし、そうしたらもう二度と、こんなことにわずらわされることはないわ。
「あー、バカバカしい」と彼女は目を一周させると、寒い夜の中へ足を踏み出し、カールという名のドライバーが黒のアウディ・A2に乗ってやって来るのを待った。
パトリック
「いい加減にして」と、カースティが彼のスーツの上着を引っ張りながら言った。「ジェシカがカンカンだったのわからないの」
「あと2分だけだよ。外で待っててくれ」
パトリックは半分空になったグラスを掲げ、これを飲んでしまうためだと言わんばかりにアピールしたが…お目当てはバーテンダーの女性だと誰の目にも明らかだった。
「わかったわ。くれぐれもお礼を言っておいてね、みなさんに」
「当然さ」
パトリックはカウンターに向き直ると、さっそくクロエを探した。彼女は反対側の隅の方で、クイズの司会をしている太った男の隣に座っていた。高いスツールに腰掛けて、スカンピ(エビ味)のポテトチップスを食べながら、片手でiPhoneをいじっている。
「招集がかかったか?」とジャックが横からぼそぼそと聞いてきた。彼は父親の仕事仲間のしっくい塗り職人で、さっきから〈サンミゲール〉のビールをちびちびと飲んでいる。
「みたいですね。もう行かないと」パトリックはスツールから降り、ふらふらする足取りで歩き出した。「その前に、お礼を言いに行った方がいいな」
彼はクロエの方へすり足で歩み寄った。彼女がスマホから顔を上げて彼を認めると、微笑んだ。
「もう帰るの?」
「そうなんだけど、その前にお礼を言いに来たんだ。その…この会場」
「素晴らしい会場だったってデニスに伝えておく。彼はきっと喜ぶわ」
「よかった。あぁぁそれと…」彼はその場でもじもじするように体を左右に揺らした。
「あぁぁそれと」とクロエが繰り返した。
「ちくしょう。こういう時、どうしたらいいんだろう。俺の名刺を渡してもいいかな? その、もしもだけど、君が連絡したくなった場合のため…念のためというか」
「あなたが渡したいのなら、どうぞ。止めるものは何もないわ」と言って、彼女が笑った。「なんか、ほとんど詩ね」
「ほんとだ、面白い。なんていうかほら、君はそんなことしなくてもいいんだけど…俺はただ、また―」
「名刺をちょうだい」
パトリックは、スーツの内ポケットをまさぐり、財布を引っ張り出すと、ボロボロの白い名刺を一枚抜き出した。パトリック・カドガン、ペンキ塗り、内装装飾、インテリアのリノベーション、お見積もりはお電話で。その下には電話番号とメールアドレスが書かれ、絵筆で描かれたアート模様が添えられている。
「インテリアのリノベーション」と彼女がその部分を読み上げた。
「他に何を書いたらいいか迷ってたら、スザンヌが」と彼は途中まで言いかけたが、後半はうやむやに言いよどんだ。
「あら、彼女があなたを呼んでるわ。もう行った方がいいんじゃない」彼女は彼の肩越しに店の入り口付近を見て、彼を促した。振り返ると、扉のところからカースティが激しく手招きして、彼を呼んでいる。
「みたいだね。じゃあ行くよ」と彼は言った。「それで、さっき言ったように。もしもだけど―」
「連絡したくなったら、でしょ」と彼女が言った。パトリックは赤面したが、彼女が「そうするかもしれない」と付け加えるのを聞くと、赤い顔を隠すように振り返り、その場を立ち去った。
20分後、3人はホーブに戻り、ギャントンの一等地にそびえ立つ邸宅の前にいた。もうすっかり暗くなっていたが、3階建てのタウンハウスの白く塗られた壁は、ほのかに明るく浮き上がって見える。ジェシカが運転免許試験に合格した翌日、車で突っ込んだ壁の凹みが、街灯の黄色い光に照らし出されていた。
「大丈夫よ。さあ早く」と、先に敷地内に入ったジェシカが門の向こうから手招きする。
家の中は、パトリックの子供の頃の記憶とはズレが生じていた。空気は冷たくて、どことなく居心地が悪い。ここ数日、家の中には誰もいなかったからか。その上、不気味といえるほどに奇妙に思えたのは、その何も無さだった。むき出しの壁、ただの長方形の輪郭、絵や写真が掛けられていた名残りのフック。家具類は、キッチンのダイニングテーブルと椅子、リビングルームのソファを除いては何も無い。カーテンはまだかかったままだったが、もうカーテンを引く意味も無い。
「こっちよ」とジェシカが言って、パトリックをキッチンへと導く。一方、カースティは釣り具箱を取りにジェリーの書斎へ向かった。「紅茶でいい?」
「もっと刺激のある飲み物は?」とパトリックは、キッチンをせわしなく歩き回っている彼女に聞いた。子供の頃、数え切れないほど家族で夕食を共にしてきた場所だ。当時のキッチンは、オーク材を使ったラミネートの食器棚でほぼ統一されていて、赤レンガ風のビニールの床というカントリー風のキッチンだった。2005年に、料理研究家のナイジェラ・ローソンの影響で、モダンな内装へとアレンジを加えたものが今のキッチンだが、流行りは廃(すた)れるものだ。
「あなたはもう十分飲んだでしょ」
「俺の親父の葬式なんだよ、ジェシ」と彼は言った。
「私たちの父親のね。それ以上ウイスキーを飲んだって、何もいいことないわ。具合が悪くなって、明日はひどい二日酔いよ。あなたは36歳でしょ。もう歳なんだから、二日酔いはこたえるわよ」
「俺は38だよ」
「同じようなものでしょ」と彼女が言った。「それにね、いい歳して、あのパブでのあなたの振る舞いは何? 年寄りたちの隣に座って昔話でもしてるのかと思って見てたら、あのバーメイドと喋ってばかりだったじゃない」
「いや、そういうつもりじゃ―」
「気色悪い」彼女はマグカップにミルクを注ぎながら、顔をしかめた。「スザンヌがここに来られなかった理由は知らないけど…それがどんな理由であれ、言い訳にはならないわ。ナイトクラブでナンパしてる20歳の男みたいにガツガツしちゃって」
彼は思わず、それは違う、と言いそうになった。スザンヌは遠く離れた地に行ってしまったのだ。彼女が葬式に来られなかったのは、葬式が行われていることさえ知らなかったからだと。しかし声が出るより先に、キッチンの扉が開き、視線をそちらに持って行かれた。
「そのミルク、まだ大丈夫だといいんだけど」とカースティが言った。彼女は大きな赤い金属製の釣り箱を両手で抱えている。
「これしかないのよ。大丈夫でしょ」
「俺のは、ブランデーを少し足してくれると嬉しいな」とパトリックがにやけ気味に言うと、ジェシカがじろっと睨みつけて彼を黙らせた。彼はダイニングチェアの背もたれにもたれかかっていたが、背もたれを構成する5本の棒のうち、1本が取れて無くなっていた。いつの間に無くなったのか、記憶をたどっても定かではなかった。彼の白いシャツは首元のボタンが外れていて、汚く黄ばんだ襟の裏が見えていた。最近Yシャツを着て外出していない証拠だ。
「さて、これがそうよ」とカースティが言った。彼女はその箱をテーブルの上に置いた。ホットティーのカップが3つと、カスタードクリームを挟んだクッキーもテーブルの上に置かれていた。彼女とジェシカが大掃除の間に食べた残り物らしい。「準備はいい?」
カースティ
彼女は少し擦り切れたハンドバッグのポケットを開けると、鍵を探した。〈Boots〉のリップクリーム、タンポンが3個、1ユーロ38セントの硬貨をかき分けて、その底から鍵をつまみ上げる。厳重にしまい込みすぎのような気もした。―この鍵がなくても、ちょっとした技術とヘアピンさえあれば、誰でも簡単に開けられそうな箱だったから。
「じゃあ、いくよ」と彼女は言って、鍵を南京錠に差し込む。みんな緊張していた。誰も認めようとはしなかったが、自分たちの知らないことが明らかになるのではないか、亡き父がカドガン家の最後の秘密を暴こうとしているのではないか、と内心ドキドキしていた。長い間、それぞれがうまく順応して、幸せな家族を構成してきたつもりだった。しかし、その幸せな家族のイメージは、10年前にあまりにも唐突な形で、あまりにも無惨に終わってしまった…
彼女は鍵を回し、蓋を開けると、首を伸ばすように前のめりになり、中を覗き込んだ。ジェシカも同じようにする。
「なんだ、これは?」とパトリックが言った。
「ウイスキーのボトルみたいね」とジェシカが言った。
「おお、いいね。さっそく栓(せん)を抜いちゃおう」
「黙って、パトリック」とジェシカが彼を睨む。
「他にも入ってるわ」とカースティが言った。「ママとパパの昔のアルバムかしら」
彼女はずっしりと厚みのある革製のアルバムを3冊、箱から取り出してテーブルの上に置いた。それらのアルバムは以前にも見たことがあったが、しばらく見ていなかった。赤、青、黒の3色に色分けされたアルバムは、3冊とも剥がれかけた金箔で縁取られている。ジェシカが生まれた1978年から始まり、写真を印刷することが少なくなった2000年代の前半まで続いている。たしかこのようなアルバムは10冊ほどあったはずだが、そのうちの3冊ということでしょう。
ジェシカが取り出したウイスキーは、「ポート・エレン」と書かれた箱に収められていた。
ポート・エレン
アイラ島・シングルモルト・スコッチ・ウイスキー
1984年ボトリング。10年間熟成。
その箱には、ジェリーの手書きで「私の子供たちへ」と書かれた封筒が貼り付けてあった。
「マジかよ!」とパトリックがウイスキーを手にして言った。
「何が?」
「ポート・エレンだよ」
「それが?」
「親父が2012年に買ったものだ。たしか、2,000ドル(約22万円)くらいしたはず」
「2千!?」とジェシカが叫んだ。「ウイスキーがそんなにするの?」
「アイラ島の蒸溜所(じょうりゅうじょ)は1980年代に閉鎖されちゃったんだ。これは貴重なコレクターズ・アイテムだよ。彼は70歳になったらこれを開けるつもりだって言ってたんだけど…」
パトリックは言葉を濁(にご)した。ジェリーは70歳まで生きられなかったのだ。あと4年、66歳で逝(い)ってしまった彼は、自慢のウイスキーの栓を開けることなく、味わえずじまいだった。
「ていうか、もう腐ってるんじゃない?」とジェシカが言った。「私と同い年くらいよ、このウイスキー」
「ウイスキーは腐ったりしないよ。ボトリングされた瞬間から何も変わらないんだ」とパトリックが説明した。彼が唯一、スコットランドの高級ウイスキー好きという父親の趣味を少しでも受け継いだ人物だった。ジェリーは妻のスーと二人で、色々な蒸溜所を巡る旅にキャンピングカーを走らせ出かけることがあった。ジェリーが蒸溜所を見学したり、試飲会に参加している間、スーはキャンピングカーの椅子を倒して足を伸ばし、心ゆくまで読書にふけっていた。パトリックはその北への旅に同行するほどスコッチ・ウイスキーに思い入れがあったわけではないが、それでも好きなことには変わりなかった。
「まあいいわ。とりあえずウイスキーのことは気にしないで」とカースティが割って入った。「それより、この封筒を開けてみて」
彼女に促(うなが)され、パトリックが封を開いた。中には手紙が入っていた。一目で、ジェリーが書いたものだとわかった。バースデーカードや、家のあちこちに貼られた〈やるべきことリスト〉で、長年見てきた彼の字だ。その便箋は、家族のみんなが馬鹿にしていた自社名入りのメモ用紙だった。パトリックが読み始めようとすると、ジェシカがそれを横からさっと奪い取り、代わりに読み始めた。
『ジェリーからの手紙』
9月28日
親愛なるジェシカ、パトリック、カースティへ
お前たちがこれを読んでいるということは、俺の葬式が終わったばかりってことだな。まあ、そんなにくよくよすんな。葬式では俺の好きなチャス&デイヴの曲をちゃんと流してくれたか?
俺がこれを書いているのは、お前たちにお願いしたいことがあるからなんだ。
お前たちはおそらく、俺の遺灰を母さんの時と同じように、すぐそこの浜辺から撒きたいって思っているよな。でも、俺は違うことを望んでいる。
この箱の中には、俺の古いキャンピングカーの鍵が入っている。3人でこの車に乗って、アイラ島まで行ってほしい。ポート・エレン蒸溜所のある浜辺から、俺の遺灰を撒いてほしいんだ。旅のお供に、3人分のアルバムとウイスキーを1本(いいやつだぞ!)も用意した。
お前たちはまた、3人それぞれ違った意見を言い出すんだろうな。ただ、今回だけは俺のためにこれをやってくれ。俺の最後の願いだ。ひょっとしたら、お前たちにとっても、楽しい旅になるかもしれんしな。
それでは、よい旅を。
俺はお前たちみんなが心から大好きだ。
お前たちの父親、ジェリーより
ジェシカ
しばらくの間、誰も口を開かなかった。それぞれが自分以外の誰かの反応を待っていた。
ジェリーの古いキャンピングカーに乗って、もう何年もただの同国人以上の何者でもなかった人たちと一台の車に詰め込まれ、国を南から北まで縦断する旅。ただ父の遺灰を撒(ま)くためだけに。
ジェシカには、交渉の余地なく放っておけないことがあった。仕事、子供たち、ダン。みんな彼女の存在を必要としている。他の2人は、行こうと思えば行けるでしょうね。私も飛行機なら、葬儀の一環として彼の遺灰を、北の最果ての地であっても届けてあげるわ。―きっとその蒸溜所の近くの浜辺に遺灰を撒くことが、彼にとって何か大きな意味があるんでしょうから。だけど、何日も車の中で過ごすのはどうだろう? カースティとパトリックと一緒に? 絶対に無理だ。
彼女は窓の外に目をやった。父が数年前に設置したスポットライトが中庭を照らし出している。ジェリーが亡くなってから火葬されるまでまだそんなに日にちが経っていないのに、もう庭は荒れ果ててしまった。アジサイの花は茶色く萎(しお)れ、芝生は刈り込みが必要なほど伸び、秋には綺麗な花を咲かせるはずの植物は枯れていた。花好きのジェシカは手入れを怠(おこた)ったことを後悔していた。そうだ! ブライトンにいるうちに、カースティと一緒に庭の手入れをしよう! だけど、何のために? どうせすぐにこの家は売ることになる。だいぶ前、カドガン・ファミリー・建築士事務所が金融危機に陥った時、両親は銀行に救済を求めた。その時にこの家を再び担保に入れたから、両親が背負った借金を返済するために、近々この実家を売ることになっているのだ。
彼女は中庭から窓ガラスへと視線の焦点を移した。椅子に腰掛ける自身の姿が映っている。お葬式とか、あとは銀行の支店長と会う時には、この黒の、体にぴったりフィットしたドレスを着ることにしている。黒のパンプスとマッチして、まだ新品同様に艶やかだ。以前は葬式にもヒールの高いものを履いていったけど、ヒールの低い靴に買い換えたばかりだった。髪は少し乱れ、整える必要はあったが、それは後回しでいいでしょう。
「ジェシ」とカースティが言った。「何を考えて―」
「ちょっと待って」
彼女は言葉を濁して時間を稼ごうとしている自分に気づいたが、実際は、すでに言い訳を思いついていた。仕事があると言おう。それがうまくいかなければ、健康上の理由で無理だということにしよう。キャンピングカーの狭苦しくて、寝心地の悪いベッドで何日も寝るなんて、耐えられるわけがないし、寝袋で寝るなんてもってのほかよ!
やっぱり自身の快適さが大事。
パトリックは紅茶を一口飲むと、何か言おうと口を開きかけたが、すぐに口をすぼめてしまった。サッカー選手がパスを出すと見せかけて出さない、フェイントみたいな。(ダンとマックスが裏庭でボールを蹴り合っている時に、その言葉を耳にしたことがある。)カースティが手紙を折りたたんで、封筒に戻した。
「どうすべきか、私に言わせようとしてるってわけね?」とジェシカが言った。「いつもそうやって年長者に任せっきりで」
「偉ぶるなよ」とパトリックが言った。
「そうじゃないけど」とカースティが言った。
「はっきり言って、答えはノー。そうでしょ? 絶対にありえないわ」
「でも、彼の最後の―」
「彼の最後の...なんであれ、私は気にしないわ、カースティ」と彼女はぴしゃりと言った。「なんだかよくわからない...遠足のために、長い期間仕事から離れるなんて」と彼女は続けた。「そんなの馬鹿げてるわ。無理に決まってるでしょ」
「私は学校が休みに入ってからなら」とカースティは言った。「もうすでに休みすぎちゃってるから」
「私はいつだってダメよ」
「ってことは、カースティはイエスなんだ?」とパトリックが、ジェシカの威勢のいい発言を無視して、カースティに聞いた。
「もちろん」と言って、彼女はクッキーを手に取った。そのまま、それを口に持っていくことなく、まるでクッキー型のストレス解消ボールのように掴んでいた。「だってそれが、彼が私たちに最後にしてほしいことなのよ」
「私がしたいリストの最後のことね」
「上手いこと言うな、ジェシ」
「ごめん、つい。でも、私には子供や夫がいるってわかってたはずでしょ。彼が私たちの生活に支障が出ることも顧(かえり)みず、こんな願いを思い付くなんて、私には信じられない」
「素敵なアイデアだと私は思うけどな」とカースティが言った。
「素敵? あんな古臭いキャンピングカーで何日も過ごすことのどこが素敵なのよ?」
「彼は新しい車を買ったのよ。数年前にね。あの汚らしい旧式とは違うの」
「それでもキャンピングカーには変わりないでしょ、カースティ。どっちにしても汚らしいわ」
「遠出にはもってこいだよ。世界を見て回るには、ああいう車がうってつけだ。というか、君の夫はあれか、子供の面倒を見てくれないのか?」とパトリックが聞いた。
「彼には仕事があるのよ、パトリック。とても重要な仕事なんだから」
「彼だって休暇ぐらい取れるさ、ジェシ。あのクソな首相でさえ休暇を取るんだからな」
「じゃあ、私のお店は?」
「君は店主だろ。花屋のことは君に決定権があるんだ。いつでも好きな時に休んでいいんだよ」
ジェシカはそれには答えず、健康上の理由という手札を切らないとかな、と考えていた。そうすれば、そう簡単には反論できないでしょ。しかし、キッチンがどんどん冷え込んできて、彼女は一刻も早くホテルに戻りたかった。葬儀の後、ダンは子供たちを連れて海に面した商業施設〈ブライトン・パレス・ピア〉に行き、子供たちにハンバーガーを食べさせていた。わずか数年の間に2回も、身内の葬式に子供たちを連れ出したことを、少しは楽しい思い出に変えようという試みらしく、ダンから写真付きのメッセージが届いていた。夫と二人の子供が、大きなステンレス製のカップに入ったアイスクリーム・ミルクセーキを美味しそうに頬張っている自撮り写真だった。数時間前に火葬場で父親を荼毘(だび)に付したばかりの私に、そんな写真を送り付けてくるなんて不謹慎なんだけど、私も早く彼らのいる明るい世界へ帰りたい。
「あなたはどうなの?」と、カースティがパトリックを見て言った。
「まあ」と彼は、テストで赤点を取ったことをごまかすみたいに言葉を濁した。「まあ、あれだな、懸案(けんあん)の子育てには俺は参加する派かな」
「『懸案の子育て』ってどういう意味?」とカースティが聞いた。「マギーはスーズが待ってるアイルランドに帰るんでしょ。私が考えてたのは、あなたがもう少しイングランドに残るのか、一旦アイルランドに帰ってから、もう一度この旅行のために戻ってくるのか」
「そうそう...そうだったな」とパトリックは誰のことも見ずにつぶやいた。「まああれだ、仕事はなんとかなるんじゃないかな」と彼は言った。「例外的な事情とか、そんな規定があったはずだから。俺はスチュとサラの家に押しかけて、しばらく泊めてもらうよ。マギーは...そうだな...彼女はアイルランドに帰ることになるかな?」
「4歳の子供を一人で飛行機に乗せるなんてあり得ないわ、パトリック」
「いや...それもそうだな」と彼はまた口ごもった。「まあ、俺たちのことは俺たちでなんとかするさ」
彼は紅茶を一口飲むと、天井を見上げた。
「しっかりしてちょうだい、パトリック」とジェシカが言った。「まだ酔っ払ってるの? ほんと、あなたとは会話が成立しないのよね。あのバーメイドのこともそう―」
「じゃあ、私とパトリックはOKね」とカースティが、彼女の言葉を遮(さえぎ)った。「あとは―」
「無理よ、カースティ。私は絶対にノー。行きたければ二人で行けばいいじゃない。私は行かないわ。こんなの、パパの勝手な横暴よ。そんな言い方、パパに向かってひどい? っていうか、私はあまりにも―」
「自分勝手?」とカースティが口を挟んだ。
ジェシカは立ち上がって、スマホとバッグをつかむと、キッチンを出た。
「ちょっと、ねえ、ジェシ。どこへ―」
「トイレよ」とジェシカは言い残し、すたすたと階段を降りると、トイレに駆け込み、きしむドアをバタンと閉めた。
便座は閉じたままでその上に座り込むと、彼女はスマホを操作し、今度はホテルまで送ってくれるウーバータクシーが近くを走っていないか探した。
車はすぐに見つかりリクエストボタンを押すと、彼女は父にリクエストされた旅がどのようなものになるかを考えた。キャンピングカーの中に詰め込まれ、初めはそれぞれが対立しないようにとお行儀よく座っているけれど、数時間もすれば、否が応でも口論が始まる。もちろん、それはほんの些細(ささい)なことから始まる。たとえば、パトリックがティーバッグを水切り台に置いたとか、カースティの運転が下手だとか、そんなことから緊張の糸がプツンと切れてしまうのだ。
自分が他の二人の気に障(さわ)るようなことをするとは、なかなか想像できなかったが、その時になれば、私もきっと何かしら文句を言われるんでしょうね。昔からそうだった。
さらに1分ほど、(自宅のトイレでよくそうするように)ぼんやりと空間を見つめていると、手に持ったままだったスマホがヴーッと震えた。
ドライバーのメラルと申します。あなたの家の前に着きました。
音を立てないように彼女はトイレから出ると、こっそり玄関から抜け出した。
門の前で待っていた車に乗り込むと、窓越しに実家の邸宅を見た。ラウンジの窓からキッチンの光がほのかにこぼれているが、それ以外の窓は真っ暗だ。家全体が息をひそめて、次にここで暮らすことになる新しい家族の到来を待ち構えているようだった。どんな人たちが、どんな政治性を持ち込み、どんな性癖を見せてくれるのかと、興奮を押し隠しているようでもある。
ジェシカはもう二度と見ることはないかもしれない、と思った。この家はすぐに売却され、このギャントン通りで過ごした記憶は、私の抜け殻と化すのでしょう。弟や妹とのいさかいを避けるために、私はここを巣立ったのだ。
「シートベルトをしてください」と、運転席のドイツ人女性が無愛想に言った。
言われた通りにすると、車が動き出した。それでもジェシカは感傷に浸(ひた)るように、ギャントン通りの家々を眺めていた。
~~~
〔チャプター 2の(実況中継的な)感想〕
ジェリーとスー(スーザン)が結婚して、3人の子供がこの世に生を受けました。
①ジェシカ:花屋の店長
ダン(ダニエル):夫
マックス(12歳):息子
エルスペス(6歳):娘
クリス・ファーブレイス:大学時代の友人で、不倫の一歩手前まで行った。
サディ・ダーリントン:ライフスタイルを提案するコラムニスト
②パトリック:(元)内装業者、シングルファーザー(的な)
スーズ(スザンヌ):妻、別居中
マギー(4歳):娘
スチュ(スチュアート):旧友
サラ:スチュの妻
クロエ:大学時代の友達、バーの店員
③カースティ:中学校の教師、シングルマザー
リヴィ:娘
クララ:友人、リヴィの面倒を見てくれている。
ネーラ:インド人女性のセラピスト、カースティは彼女に惹かれている。
・親戚
デレクおじさん(故人)
クレア:デレクの娘、3人のいとこ、ピュア
マイクおじさん(故人)
サリーおばさん:マイクの妻、司祭になぜかシルビアと呼ばれる(よぼよぼの司祭がボケてるのか、個人的な関係があるのか…笑)
藍も身内の葬式を何度か経験したことがあり、(お坊さんと司祭は違うといえば違うけど、)イギリスも日本も同じ感じだな、という印象です。
違いといえば、日本の場合、パブで立食(ビュッフェ)形式ではなく、日本料理屋の広いお座敷に親戚一同、何列かに並んで座って飲み食いするんですよね。そして、カラオケとか始まっちゃって、親戚のおじさんとかが演歌とかを歌うのはいいとしても、その日本料理屋の店主みたいな(親戚ではない)おっさんが、自慢のこぶし(ビブラート)を効かせた演歌を聞かせたいのか知らないけど、しゃしゃり出てきて歌い出すから、藍も対抗して、ノリノリのロックンロールを拳(こぶし)を突き上げながら飛び跳ねるようにして歌ったら、親戚一同ドン引き…(-_-;)汗←君って実は度胸あるよね!笑←チキンは基本的に度胸あるんだよ!!笑笑←ん?
つまり、チキン(臆病者)は、チキンであるがゆえに必然的に、恋人やパートナーがいないから、いざとなったら捨て身になれる。←ただ、「いざ」という時は待てど暮らせど来ないけどね!笑←とっくに「感想」ですらない…
相手の名前がわからなくなることは藍にもあって、ベッドで虹のコンキスタドールの歌詞カードをめくりながら、あれ、この子が「つるみもえちゃん」だったよな? ん、こっちの子か? この子はたしか「あーおちゃん」だったはず…←名前書いてあるんじゃないの?←歌詞カードには書いてないんだよ!←てか、きもっ!!爆笑
やっぱり藍はパトリックに一番近いな。←娘はいないけどね。笑
藍も、何か話題を、って頭をフル回転させながら話すから、熱くなりすぎて機能を停止したシュレッダーみたいに、役立たずになっちゃう…号泣
それぞれが内面に負の要素を抱えているというか、いらやしい面を持っているところがいいよね。この人は悪者で、この人はいい人、みたいな区分けがないところがいい。←そもそも区分けのある小説なんてあるの?笑
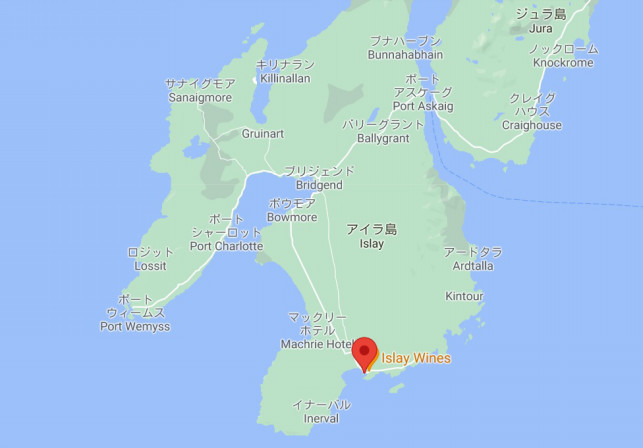
アイラ島👆

日本でいうと、北海道の函館辺りかな?🗾
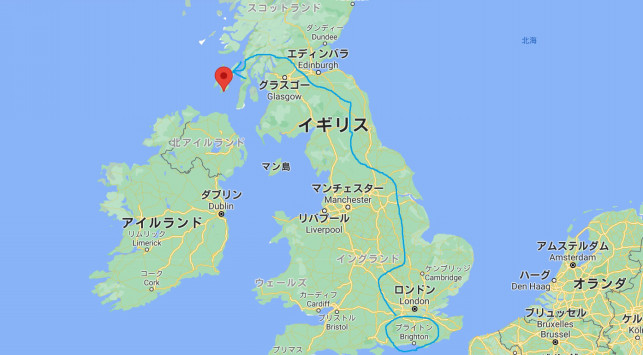
そして、北への旅が始まった...🚙
~~~
チャプター 3
ホーブ・キャラバンパーク
パトリック
キャラバンパークは、まるでキャンピングカーの墓地のようだった。見渡す限りずらっと、白い抜け殻のような車が区画(くかく)ごとに止まっている。その多くは何ヶ月も放置された状態で、風雨(ふうう)にさらされ、埃(ほこり)に埋もれていた。タイヤがパンクしているものもあるし、苔(こけ)が生え始めているものさえあった。―どの車もこのパークに放って置かれたまま、少なくともひと夏は独りぼっちで、所有者が乗りに来るのを待ちわびていたことが見て取れた。当の所有者は、キャンピングカーの存在など忘れ、他の手段で休暇を満喫していたのだろう。
「親父のはどこだっけ―」
「6列目の12番よ」カースティは、いつになったら覚えるの? と言外に込めて言った。今日の彼女はなんだか素気(すげ)ない。(学校が1週間の中間休みに入り、)おそらく今年最後くらいのさわやかな気候だというのに、ビーチにも行かず、こんなことをして土曜日を過ごさなければならないことに苛立っているようだ。
今日はキャンピングカーを引き取って洗車した後、ホーブの火葬場に行って父親の遺灰を回収することになっていた。そして来週の水曜日、彼の遺灰を彼の車に乗せて、いよいよスコットランドへの旅に出発する。
彼らは、法外とも思える大金を支払って、前もって金と黒の立派な骨つぼを購入した。母親が亡くなった時、何も用意せずに行ったら、安物のビニール袋に入った遺灰を渡されたからだ。パトリックは、数年前の、その時に感じたことを思い出していた。人の死も、物流同様、事務的で簡易的なものになってしまったんだな、と思った。葬儀屋が悲しみに暮れる家族に対し、故人のためにも、と、より高額な商品を売りつける機会に成り下がってしまったようだった。
「いまだに信じられないよ、こんなことするなんて」とパトリックは言った。
「正しいことをするのよ」
「わかってるけど、まったく、無茶な頼みごとするよな」
「よしな、パトリック」
「ていうか、二人でほんとにするつもりか? 彼の最後の願いは三人で、ってことだろ。彼女なしじゃダメだろ」と彼は言った。
二人ともジェシカとは連絡を取っていなかった。8日前の火曜日、葬儀の後の夜にジェシカが実家をこっそり抜け出して以来、彼女から連絡はない。彼女がキッチンに戻ってこないので、彼らは「ジェシカ」、「ジェシ」、そして何度か「ジェシー」とも呼びながら家中を探し回った。「ジェシー」と呼ばれることを彼女は嫌がっていて、それを聞いたら怒るかもしれないとはわかっていた。5回ほど電話もかけたが、返ってきたメッセージは1通だけだった。
ジェシカ:ホテルに戻ってる。電話はやめて。そんな馬鹿げたこと私はしない。
実家に残されたパトリックとカースティは、二人で簡単に話をした。二人の間には明確な意見の一致があった。パトリックは、これをやり遂げなければ、自分の内なる良心が許さないことを自覚していた。ジェリーの最後の頼みまで断ってしまったら、罪悪感でがんじがらめになって生きていけない。父が病床に伏していた時、そばにいてあげられなかったことへの罪悪感がすでにあった。マギーが彼を、赤の他人のように感じていること。祖父として、それはつらかっただろうと思う。ジェシカがいないと、半分しか達成したことにならないかもしれない。たとえそうだとしても、やってやる、と彼は意気込んでいた。
その上、クラウチ・エンドに居続けることが耐えられなくなっていた。スチュと彼の妻は親切だし、いろいろ気にかけてくれて、マギーを温かく受け入れてくれた。しかし、招かれざる片親の客は、彼らのロンドン流のライフスタイルにはそぐわないことをひしひしと痛感していた。ソファに座って娘と一緒に『モアナと伝説の海』を見ていると、彼らは彼をディナーパーティーに誘ってくるといったことが重なった。彼らは夜にヨガのレッスンを受けたり、ジムでがっつり体を鍛えたりしていたが、彼はごくたまに公園の周りを5キロほどジョギングする程度だったから、その差が恥ずかしくて、いたたまれなくなっていたのだ。
最近、彼はお昼時にぶらぶらと街を歩き、建ち並ぶ共同住宅を見上げながら、自分が初めてこの街に来た時のことを懐かしく思い出していた。―2006年から2011年まで、彼とスチュはチョーク・ファームの辺りでルームシェアをしていて、夜になると〈ザ・ロック・タバーン〉に飲みに繰り出したり、スポーツなら何でもいいから、テレビでその日やっている試合を見ながら二人で楽しく過ごしていた。数年後、スチュはサラと出会い、彼はスーズと出会い、人生が好転しだした。あの頃からマギーが生まれた直後までが、彼の人生で最も幸せな時期だったと言えるだろう。娘の誕生をピークに、後は下がる一方だった。
「ここよ」と、カースティが立ち止まった。彼女が指さす先には、芝生から小さな石碑(せきひ)のような平らな杭(くい)が突き出ていて、「12」とペンキで手書きされていた。
父の車は周りに停まっている他の車よりも明らかに古く、かなり汚れていた。車種はフォードの〈トランジット〉で、後部にこじんまりとした荷物入れが付いていて、運転席の上にはキャビンが乗っかっている(この部分を見るとパトリックはいつも、額の上でがっつり固めた「リーゼントヘアー」を思い出す)。フロントガラスは蓄積された砂ぼこりで濁(にご)っているし、片方のドアミラーはガムテープで固定されているし、助手席の下のタイヤはぺしゃんこにパンクしていて、全体的に沈みゆく船のようだった。
車体の横にでかでかと貼られた〈THE ADVENTURER(冒険家)〉という鮮やかなブルーのステッカーとは裏腹に、その佇(たたず)まいは、めそめそとしょぼくれているみたいだった。
「最後にいつ―」
「3年くらい前」とカースティが、パトリックの質問を先回りして答えた。「ママが亡くなってから1年後に、パパはノーフォークまで釣りに行ったのよ。キングス・リンの近くの川に行ったみたいね」
「それ以来、ここに置きっぱなし?」
「まあね」
「しょうがねえな。俺たちできれいにするか?」彼は鍵を手の中で転がしながら、キャンピングカーに向かって歩いていった。ドアを開けると中から何が出てくるのか、と内心ドキドキしていた。ネズミ? 人間の死体? 家をなくした家族が秋雨(あきさめ)を避けるように暮らしてたりして?
パトリックは薄っぺらいドアに鍵を差し込み、ひねった(というか鍵がなくても、こんなぺらいドアなら、簡単に突き破れそうだと前から思っていた)。ドアを開けたとたん、むわっとカビ臭い湿った空気が二人の顔を襲い、二人とも顔をしかめる。天井の電灯のスイッチを入れてみたが、バッテリー切れらしく、つかなかった。スマホの明かりを頼りに、二人は3段の小さな階段を登り、松の木をビニール加工した床をおそるおそる覗き込んだ。
「マジか」と彼は言った。「快適な空間ってこういうことか」
〈冒険家〉は子供の頃に乗った記憶よりも狭かった。最後尾に2段ベッドが2つと、バスルームがあり、そこから細い通路を3歩も歩くと前方の運転席に着いてしまう。真ん中の小さなテーブルは4人も集まればキツキツで、食事も同時には取れないのではないか。―この車は6人用をうたっているが、広告とはそういうものだと割り切った方がいいらしい。通路の片側には一応ベンチがあるが、窮屈だし、背もたれが垂直すぎて腰が痛くなりそうだ。このベンチがダブルベッドになるのだが、実際どこをどうやって変形させればいいのか見当もつかなかった。通路の反対側にはキッチンがあり、小型の冷蔵庫、2口のクッキングヒーター、ガス式のオーブングリルが設置されていた。
「思ってたよりきれいじゃない」とカースティが努めて明るい声で言った。彼女は鍵のついた食器棚を開けると、中の食器を手に取って眺めている。どの食器も昔家で使っていたもので、ある時この車に移されたものばかりだった。大昔のチョコレートバーのロゴが入ったマグカップや、親父が昔からひいきにしているサッカーチームの紋章が記(しる)されたマグカップが並んでいる。そのワトフォードFCのロゴマークは、現在の鹿(しか)をモチーフにしたものではなく、数十年前の蜂(はち)の紋章だったが、パトリックは一目でそれとわかった。その横に重ねられたプラスチック製のお皿は、90年代の前半に家族で行ったキャンプで使ったものだと彼は思い出す。
「まだ走るかな?」と聞きながら、彼は運転席に体を滑り込ませた。一方、彼女は小さなバスルームを見に行って、バスルームのドアにぶら下がっていた「ユーザーズガイド」に目を落とした。
彼は鍵穴にキーを差し込むと、勢い良くひねった。ダッシュボードが点灯し、ディーゼルエンジンの燃料タンクが4分の1であることを示した。もう一度キーを思いっきりひねると、エンジンが何度かゴホゴホと咳払いをした後、息を吹き返した。テーブルの真上の照明がすぐに点灯し、と思ったらすぐに消えた。キッチンに設置された時計が、雄鶏(おんどり)のように2回鳴いた。
「なんてこった」
「動くの?」と、彼の真後ろまで来ていたカースティが聞いた。
「動いちゃった」と彼は言った。
二人とも少しがっかりした口調だった。もしも、このキャンピングカーが故障していて使い物にならなかったり、あるいは大きな修理が必要だったりしたら、父親の指令とはいえ仕方ないな、と諦めるつもりだったのだ。代わりに飛行機で行くことを二人は考えていたのだが、その逃げ道は父親が予め塞(ふさ)いでいた。彼らの父親は、車のメンテナンスに関しては凝り性で、たとえ実際に運転してどこかへ行くことはなかったとしても、年に一度はちゃんと整備していたようだ。
あらゆる予想を覆して、〈冒険家〉は生きていた。
バーカムステッド、ハートフォードシャー
ジェシカ
彼女はスマホをチェックした。
カースティ:私たちのことを無視してるのはわかってるけど、キャンピングカーが動いたって一応知らせておこうと思って。水曜日の午前中、パットと私は出発する。あなたも気が変わったら来てね😘
それから再びスマホにロックをかけ、そのメッセージのことは忘れることにした。
ジェシカはガスコンロの前に戻ると、ぐつぐつと煮立っているミートソースの鍋をコンロからいったん外した。彼女はミートソースにもっとワインを加えようかと思案している。友人を家に招いたり、子供たちが出かけていて、いない時にはワインを追加するのだけれど、今日は馴染みのない声が頭の中でチクチクと嫌味っぽく、子供が食べる料理にお酒を加えるなんてもっての外(ほか)だと鳴り響いている。〈ママネット〉に寄せられた道徳的な正しさを押し付ける投稿みたいだ。
代わりに、彼女は大きな球状のグラスに赤ワインをなみなみと注(つ)いだ。このグラスは、ダンが買ったワイングラスセットの一つだ。元々は結婚式の記念品で似たようなものがあったのだけど、ダンが事あるごとにグラスを一つずつ割ってしまい、彼はその埋め合わせとしてこれを買ったのだ。
彼女はさっきのメッセージから気をそらそうと、キッチンを見渡した。去年、キッチンを改装したばかりだった。新しく石造りの床にしたアイルランド風のキッチンには、フライパンが芸術的に吊り下がり、すべてがシルバー系かダークブルーで統一されている。改装工事の後、ダンが「そのうちやる」と言って、そのままになっているものもある。茶色がかった灰色のブラインドを木目調のものに変えるはずがそのままだし、換気扇のところの黄色い電球を白いものに変えると言っていたのに、まだ黄色いままだ。しかし彼らは、少なくとも彼は、今ではその不完全さと共に生活していくことを選んだようだった。
ジェシカが降参したようにスマホを手に取り、再びカースティのメッセージを読むまでに、5分もかからなかった。
「誰からだ?」と、キッチンのドアを開けて入ってきたダンが聞いた。彼はまだ仕事用のズボンを履いたままだったが、シャツは脱ぎかけでズボンの外に出ていて、グレーのスリッパを履いていた。
「べつに、誰ってこともないけど」
「そうか」
「なぜ聞いたの? どうでもいいくせに」
「ただ聞いただけだよ...なぜって聞かれても」
「誰ってこともないけど...」と彼女は繰り返し、再び鍋の前に戻って、付け足した。「カースティからよ」
「そうか、わかった」とダンは明るい口調で言った。「彼女からなんて?」
「なんでもないわ」とジェシカは答えた直後、「降りなさい! ブーツィー、ダウン!」と猫に向かって怒鳴った。ブーツィーは、息子のマックスがまだ3歳だった頃に飼い始めた猫で、マックスが名前を付けたいと言ったからそうさせたのだけど、こうして「ブーツィー!」と呼ぶたびに、名前は私が付けるべきだったと後悔している。
「そうか」とダンが言って、キッチンから出て行こうとしたから、ジェシカはしびれを切らして言った。「なんか、馬鹿げた旅に出るみたいよ」
彼は怪訝(けげん)な顔で振り向き、一瞬間を開けてから、「旅ってどんな?」と聞いた。
「二人で行くみたいね。パパの遺灰を撒く旅だって」
「おお」と、彼が驚いたように声を上げた。彼に話すのは初めてだったから、驚くのも無理ないわね。「ごめん。それって俺に言ってたか?」
「いいえ...言う必要がないと思ってたから」
「君は行くのか?」
「いいえ」と彼女は言って、ワインをぐいっと喉に流し込んだ。
「どうして? 彼らは君を誘わなかったのか? 俺は誓って言えるけど、もしあの二人が―」
「誘われたわ。それに、三人でっていうのが彼の望みでもあるし。彼ってパパのことね」と彼女は言って、彼と目を合わせないように鍋の中のミートソースをかき混ぜた。「私は行かないって言ったの」
ダンがドア付近から戻ってきて、キッチンテーブルの席に座った。
「すまない、ジェシ。俺には全然話が見えない。ちゃんと説明してくれないか?」
彼女は一(いち)から説明した。カースティがジェリーの手紙を写真に撮って送り付けてきたので、それを読み上げさえした。―カースティのこういうやり口はずるい、とジェシカは思った。私は行きたくないって言ってるのに、感情に訴える脅迫めいたメールをバンバン送ってくるなんて。
話し終わるまで、ダンはあまり表情を変えなかった。その話から彼が何を感じ取ったのか、いまいち伝わってこない。とはいえ、彼は話の途中で2度笑った。パトリックがバーメイドを口説こうと必死になってたくだりと、ジェシカがその夜、二人に黙ってこっそり実家を抜け出した場面で、ふっと息を吹き出すように笑った。しかし、彼女の父親がこのような旅を提案したことには、彼も驚いている様子だった。ここ数年、ジェリーは家族のために外食を提案したことさえ一度もなかったからだ。
「どう思う?」と彼女は聞いた。
「君は行くべきだと思うよ。明らかにね」
「本当に?」
「ジェシ。5年後の自分を想像してみろ。行かなかったことを後悔してないって言い切れるか?」
「さあね」と、彼女はワインを口に含み、しばらく飲み込まずにワインの舌触りを味わいながら言った。「でも、かなりかかるでしょうね。行きに2日。帰りに2日」
「かなりって4日だろ?」
「それに現地で1日。島で過ごすことになるわ。たぶんね」
「それでも5日じゃないか」
「私たちは休暇を利用して家族旅行に行く予定だったじゃない」と彼女は言った。子供たちが中間休みに入ったら家族4人で行こうと、マヨルカ島への旅行を計画していたのだ。
「俺も今そのことを言おうと思ったんだ。もしかして、君が急にマヨルカ島に行こうとか言い出したのは、パトリックとカースティと一緒にその旅行に行くのが嫌で、その口実作りだったのか?」
「それは...」
「それは口実にはならないよ。マヨルカ島へは俺と子供たちだけでも行けるし。ママにも来てもらえるかもしれないし」
「ダン」と彼女は、今はママの話はやめて、と半分頼み込むように言った。
「行った方がいいって」
「お店が」
「マヨルカ島に行こうとしてたんだろ!」
ジェシカは空になったワイングラスに再びワインを注ぐと、冷蔵庫からビールを取り出し、ダンのグラスに注いだ。二人はしばらく見つめ合っていた。マックスとエルスペスを厳しく𠮟(しか)ろうと決めたどちらかを、もう一方が今回は大目に見てやろう、と説き伏せている時のようだった。それから彼女はおもむろに立ち上がり、流し台の横のディスペンサーを2、3回押し、手のひらにハンドクリームを出すと、指全体をマッサージするように塗り込んだ。
「それは何の香り?」
「カルダモンとベルガモットよ」
「カレーっぽい匂いがするな」と彼は言った。彼女はそれを無視して、電気ケトルでお湯を沸かした。沸騰中、ボコボコと大きな音を立てるので、少しの間会話ができなくなった。ダンはケトルがカチッと音を立て、お湯が沸き上がるのを待ってから、コンロの前に立つ彼女に忍び寄り、大きな鍋でスパゲッティを茹でている彼女を後ろから抱きしめた。
「あなたの家族とは違うのよ」とジェシカが言った。「あなたは家族と仲がいいじゃない」
「君も昔は彼らと仲良くやってたじゃないか」
「はるか昔のことでしょ、ダン。最後に普通の会話をしたのがいつかも覚えてないわ」
「カースティとは仲良くしてたんだろ? 実家の片付けも一緒にしたんだろ?」
「義務感からよ。友達というより、一緒に仕事をしてる同僚って感じだった」
「まあ、そんなもんだろ。むしろ仲いい方なんじゃないか」
「そうかもしれないけど、 昔からそうだし、この先もずっとこんな感じが続きそうじゃない? 私たち夫婦がパパをあの家から追い出そうとしてたって、彼女はこれからも思い続けるでしょうね。逆に私は、彼女がすべてのことに対して世間知らずだってこれからも思い続けるわ」
「パトリックは?」
「彼は何も言わないわ。彼も昔からそう。いつだって手遅れになるまで、何も言わない」
「黙ってるのが一番だよ。そう思わないか? 結局黙っていれば、いろんないざこざを避けられる」
「でも、そもそも私たちは仲良くやっていくつもりなんてないのよ、そうでしょ? そうじゃない人もいるでしょうけど、私たちがいがみ合ってるのは、理由があって」
「ジェシ」とダンが真剣な口調で言った。「みんな知ってるよ、そのことが原因で君たち姉弟の仲が悪くなったわけじゃない。君は―」
「やめて」と彼女は言って、ダンを振り払うように押しのけた。「今はだめ、ダン。その話はしないで。ほら、食事もできたし―」
「しないけど、君はちゃんと認めないといけない。思い出したくもないほどショックだったんだろうけど」と彼は続けたが、ジェシカは彼から離れて廊下に向かって歩いていった。
「ご飯よ」と彼女は階段の上に向かって声を上げた。「今すぐ下りてらっしゃい」
「ジェシ」と彼は、キッチンに戻ってきた彼女に向かって優しく言った。
「黙って」と彼女は言うと、ガチャガチャと音を立ててフォークやナイフをキッチンテーブルに置いた。それから、すでに焼き上がっていたガーリック・パイをオーブンから取り出した。
「その旅に行ってこいよ」と彼は言った。
ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス
カースティ
カースティは一輪のマリーゴールドをポキッと折ると、流し台に放り込んだ。当然のことのように、このひどい有り様のキャンピングカーを掃除するのは彼女の役目になった。彼女は娘のリヴィを連れてきて、運転席に散らばっている〈テスコ・グレイシャーミント・ガム〉の包み紙を拾うといった比較的軽い仕事をやらせつつ、彼女は床掃除、食器洗い、キッチンやバスルームやベッドの掃除を続けた。
パトリックの名誉のためにも言っておくと、車の外側の掃除は彼が引き受けてくれた。外見はそれほど重要視していないんだけど、彼も私も、一応外側もきれいにしておく必要があると感じていた(帰ってきたらほぼ間違いなく、この車を売りに出すことを見据えての伏線でもあった)。彼は骨つぼをプチプチのビニールで厳重に包んでいた。きっとそれは子供の頃、キャンピングカーで湖水地方に行った時、急なカーブを曲がった衝撃で、ビール瓶が3本も割れてしまったことを思い出してのことでしょう。
「ママ、37個も拾ったよ」とリヴィが言って、お菓子の包み紙でいっぱいの両手を開いてみせた。
「すごいじゃない、よくやったわ。さあ、それをそのゴミ袋に捨てて」と彼女は言って、助手席に置いてあるビニールのゴミ袋を指差した。
「どれがママのベッドになるの?」
「どこにしようかしらね。パトリックおじさんがどこで寝るかを見てから決めようかな」
「私はここがいい」と彼女は言いながら梯子(はしご)を登り、運転席の上に付いているリーゼント・ヘアーみたいな寝台に入っていく。カースティはそこが寝心地良さそうだと思った。
娘を見ていたら、罪悪感の波がどっと押し寄せてきた。学期と学期の間の1週間の休みくらいは、たっぷりと娘と過ごす、という暗黙の取り決めが二人の間にはあったのだけど、明日からは一緒に過ごせなくなる。残りの休暇は、水族館や動物園に行ったり、お家で一緒にお絵かきや工作をしたり、お友達を家に招待したりして過ごすはずだった。
しかし、リヴィを置いて旅に出ることになり、その計画はなくなった。リヴィは残りの休暇を、2人のお友達の家でお泊まりすることになった(どちらかに偏って負担をかけたくない、というカースティの配慮で、2人のお友達の家に預けることにした)。
「なかなかいい感じでしょ? あなたも一緒に来ればいいのに」と彼女は言って、言わなきゃよかった、とすぐに後悔した。
リヴィは悲しそうな顔で「私も行く」と言うと、慎重に後ろ向きで梯子を下りてきた。
「あの人たち、おじいちゃんの家から出て来たよ」とリヴィが窓の外を見て、指差した。スーツを着ているが、まだ学生感が漂う若い不動産仲介人が、同じような年頃の若いカップルを連れて、玄関先の踏み段を下りてくる。家の中の案内が終わったようだ。3日前から、この家は売りに出されていて、これまでに5件の内見希望があったが、まだ購入希望は1件もない。
カースティが窓の外を見ると、不動産仲介人と目が合った。彼は彼女に親指を立てて、「今回はいい感触でした!」と伝えようとしたが、横の夫婦は彼女たちを見て、怪訝そうに顔をしかめた。私の姿は彼らの目にどのように映っているのだろう、と思った。亡くなった父親の家の前に止めたキャンピングカーの中で生活している、気の狂った老婆にでも見えたのかしら? 彼女は、今すぐ車から出て、彼らにつかつかと大股で歩み寄り、「私はここには住んでいません。ブライトンにちゃんと部屋を持っています」と宣言したかったが、余計に頭がおかしい人だと思われそうでやめておいた。
「さあ、リヴィちゃん、こっち」とカースティは言って、リヴィに窓から離れるように促(うなが)した。「もう大体終わったから。それを持って」と彼女は、ゴミでいっぱいになったスーパーマーケット〈セインズベリー〉のビニール袋を指差しながら言った。「今夜はピザにしようかしらね。お掃除したからご褒美よ」
リヴィが歓声を上げると、カースティの携帯がヴー、ヴーと震え、メッセージの受信を知らせた。
ジェシカ:明日は何時に出発するの?😘
彼女はそのメッセージを一度読むと、その画面をスクショして、「まったくもう!」という意味を込めて、怒った絵文字と肩をすくめた絵文字をその写真に添えて、パトリックに送信し、携帯をバッグに戻した。姉の気まぐれに振り回されるのはいつものことだけど、今回ばかりは怒っても仕方ないわね。
ノース・レーヌ、ブライトン
パトリック
彼はカースティからのメッセージを見て、スマホの画面を伏せてテーブルに置いた。
「大事なメッセージなら、返信するなり電話するなりしたら?」とクロエが言った。「さっきあなたが言ってた旅のことじゃない?」
「いや、いいんだ」とパトリックは言って、「もっと聞かせて」と、彼女に続きを促した。クロエは大学時代の友人たちの『その後』をよく知っていた。まるでゴシップ誌をめくるように次々と、二人と同じ大学に通っていた連中の、スキャンダラスな顛末(てんまつ)を聞かせてくれた。誰々は刑務所に入ったとか、誰々は離婚したとか、他言無用のやばい話や、本人は誰にも知られたくないはずの笑っちゃう話に特化した情報網を、彼女は持っているらしい。
二人は30分ほど前から、カースティが立ち寄りそうもない地区のお店で落ち合い、手羽先の唐揚げを食べながらクラフトビールを飲んでいた。葬儀の2日後、クロエからメールが来て、元気? と聞かれた。それから頻繫にメッセージのやり取りをするようになり、ついに彼女を飲みに誘ったのだ。女の子を口説くには、飲みに誘うのが一番手っ取り早いことを、彼は経験から知っていた。結婚して、子供ができて、別居まで経験した今となっては、飲みに行こう、というメッセージを送るくらい、どうってことないのだ。昔はそんなメールを送るだけで、指が震えるほどパニックになったり、相手の心理を過剰に分析したりとドキドキものだったが、ハードルはいつの間にかだいぶ下がっていた。
それでも彼の心の大部分を占めているのは、まだスザンヌだった。彼女と離れて数ヶ月が経った。彼女とはもう終わったのか? と彼は自問した。彼女はすでに過去の人なのか?
いや、明らかに違う。乗り越えるにはもっと長い月日が必要になるだろう。しかし、彼の心の中の何かが、前に進んでもいい、と言っていた。もし自分が不倫をした側だったら、妻と子供を置いて出て行った側だったら、違う感じ方をしていただろう。自分は捨てられた側だから、と彼は自分を正当化して、久しぶりに幸せを感じていた。
「今度はあなたが話す番よ」とクロエが言った。「ドナ・カーターがどんな人生を歩んできたかよりも、もっと面白い話があるんじゃないの?」
「いや、ないと思うけど。だって彼女は、いろんなお店がある中で、よりによって賭け事のノミ屋から、お金を盗んだんだろ?」
「パトリック」と彼女が、からかうような口調で彼をたしなめた。
先日のお別れ会の時と同様に、クロエは常ににこやかな笑みを浮かべながら、冗談を言ったり、彼をからかったり、声を上げて笑ったりと、もてなし上手で、ずっとこうして一緒にいたいと思える相手だった。彼女は濃紺のタイトなジーンズに、赤いハイヒールを履き、胸元を覗き込めそうなくらいゆったりとした黒いシャツを着ていた。彼よりオシャレに気を遣ってきたのは明らかで、彼は軽い罪悪感を覚えた。彼女の髪はストレートで、可愛らしい顔の両脇をまっすぐに滑り降りている。ハッピーオーラに包まれたような彼女に対して、彼はレザーブーツにジーンズ、そして襟元に毛皮の裏地が付いた、厚手のフランネル生地のチェックシャツという地味な格好だった。さすがに彼女が来る前に、ニット帽は脱ぎ、トイレの鏡で一応髪を整えたけれど。
「さっきの旅についてもっと知りたいわ。そういうのってなんか...」
「狂ってる?」と彼が先に言った。彼女が適切な言葉を探しているようだったので、助け舟を出したつもりだった。
「そういうことじゃないんだけど、私が聞いた話だと、そういう風に亡き人の遺灰を撒く場合、ゴルフ場とか、ビーチとか、そういう場所で」
「俺たちもビーチに撒くんだよ。ただ、地元のビーチではないけど」
「なんで地元じゃないの? ホーブにも海はあるじゃない」
「どうやら思い出の地らしいね。何年か前にウイスキー・フェスティバルがそこであって、父は母と一緒に車でそこに行ったんだ」
「なんだかスリリングな旅ね」
「父にとってはそうだったんだろうけど、母にとってはそうでもなかったんだ。というか、彼が目的地としてヘブリディーズ諸島を選んだ本当の理由は、俺たち三人を一台のキャンピングカーに、何日もぶっ通しで閉じ込めることなんだよ。そんな狭いところで体を押し付け合うようにして一緒に過ごせば、何かしらの修復が生まれるんじゃないかって。家族の絆とかさ、そういうのを取り戻せってことだろ。ただ、ジェシカのおかげで、この計画は今のところ白紙状態なんだけど」と彼は言って、再びスマホの画面を見た。
「お姉さんと妹さんが同じ車で過ごせば、関係は修復すると思う?」
「まあ、どっちに転ぶかは微妙だな。仲直りするか、逆に首を絞め合っちゃったりして」と彼は言った。「彼女たちも昔は仲良かったんだよ。最近はピリピリした関係が続いてるけど。母親が死んだことで、二人の間で何かが一気に弾けちゃったんだろうな」
「あなたは? あなたは彼女たちと仲良くやってるの?」
パトリックは、そのことについて話すのをためらった。カドガン家の三人兄妹の仲が険悪だということは、周りから見ても明らかだったが、彼の立ち位置に関しては、単なる傍観者だと見なす人もいれば、共犯者というか、二人の姉妹よりも、むしろ彼が諸悪の根源だと見なす人もいた。
「上辺はね」と彼は言った。「腹を割って話すことはもうないな。一応礼儀として、話は合わせるけどさ。姉は俺が妹の味方だと思ってるし、逆に妹は俺が姉の味方だと思ってる。ということで俺は、間に立って双方から攻撃をくらってる感じだよ。まあ、俺自身がはっきりした態度を取らないせいなんだけど。俺はいつも手遅れになるまで、何も言わないから」
「あなたはどっちの味方なの? どっちかというと、どっちに肩入れしてる?」
「さあ、どうなんだろ。ジェシの言い分もわかることはわかる。あんな大きな家に親父一人で、どうせゴロゴロしてるだけなんだから、さっさと売っちゃった方が銀行にお金も返せるしって。親父は銀行からかなり借金してたんだよ。けど、それについてカースティが怒った時、俺はもっともだと思った。なにせ俺たちが育った実家だしね。俺も親父が生きてるうちは売るべきじゃないって思ったよ」
クロエはしばらく考え込むように黙っていた。気まずい空気になってしまった、と思った。彼女は俺との関係を始めることを考え直しているのかもしれない。しょっぱなから、やっちまった感がいなめない。もう少し良識や正直さがあれば、このような事態は避けることができたのではないか、と考えていた。
「その時が来たのよ、パトリック」と彼女がついに口を開いた。「私の父が亡くなった時、私たちは自分たちが育った家を売らなければならなかったわ。母はもう、一人で庭の手入れをすることができなかったし」
「わかるよ」と彼は言った。「俺たちも今、家を売りに出してて、今週すでに内見者がいたみたいだね」
「でも、お姉さんの方だっけ? 行かないって言ってるんでしょ? それは悲しいことね。たとえ車の中で首を絞め合うことになったとしても、お父さんの最後の願いなんだし」
「ちょっと悪巧みが過ぎると思わないか? そんなこと誰もやりたがらないだろ。けど、亡き父に対して、ノーとも言えない。ずるいよな?」
「そうね。でも、彼はそれに値する人なんでしょ? あなたが自分で言ってたじゃない。あんなことがあった後でも彼は偉かったって―」
「それはそうだ」とパトリックはきっぱりと言った。今夜はあの箱を開けないでおこう、と心に決めた。せっかくの夜が台無しになりかねない。間違いなく、数日以内にはカースティとそのことについて話し合うことになるだろう。けどそれまでは、そっと蓋(ふた)をしておこうと決めた。「おかわりは?」と彼は言って、空になった彼女のグラスに視線を送った。
「いただくわ」と彼女は笑顔で答えた。
「同じもの?」
「うん、お願い」
パトリックは二人のグラスを手に取ると、テーブル席から立ち上がった。
「綺麗だね」と彼は言った。「おかわりを持って戻ってきたら、もう家族の話はよそう。いい?」
「そうね、よしましょ」とクロエが言った。
パトリックはカウンターに向かいながら、あのことを話さずに済んでよかった、と、ほっとしていた。カドガン家といえば、あんなことがあった家として有名で、近隣の人たちにはそういう家として認識されていた。彼がブライトンやホーブで暮らしたくない理由でもあり、今までここを離れて過ごせていたことに満足していた。一方で、今回の旅が終わり、この町に戻ってくることになったら、と不安が胸中(きょうちゅう)に湧き起こりつつあった。
~~~
〔チャプター 3の感想〕
これは本当の話なんだけど、藍の最長ドライブは、長崎県から埼玉県までで、丸2日くらいかかった。たしか名古屋辺りのパーキングエリアで、運転席の椅子を倒して3、4時間は寝たけれど、最後の方はハンドルを握っている腕が震えてくるほど、心身ともに疲労困憊でした...💦当時乗っていた車はホンダのHR-Vというシルバーの車でした🚙まあ、若かったので成せたことですね!←何を書いたって、もう噓にしか思えない!笑
藍が懐かしく思い出すのは札幌の街で、オリンピックのマラソンに合わせて札幌に行きたかったんだけど、それは叶わなかったから、そのうち(?)、行きたいな~と思っている。ただ、おっさんがぶらぶらと建物を見上げていたら、あやしさ満点だけど...💦笑←ホリー・ゴライトリーを探しに来たとか?(伝われ~~!笑)
家族に何かあったっぽい!←キーワードはドイツ?
あと、ジェリーは年に1度、キャンピングカーのメンテナンスをしながら、運転してどこへも動かしてやれない自分がふがいないというか、車が不憫(ふびん)に思えて、俺の車に乗って行け、と言ったのかもしれませんね。←いや、3人を強制的にくっつけるためだろ!←いや、車が可哀想だと思ったからだよ!←どっちでもいい。というか、どうでもいい!⇐っていうか、お前誰だよ!!爆笑
~~~
チャプター 4
ブライトン、サセックス
パトリック
朝の6時前、ドアがバンバン叩かれる音で目が覚めた。まるで誰かが火事を住人たちに知らせようと各部屋のドアを叩いて回っているかのような、切迫した激しい叩き方だった。彼はスマホをチェックしながら、それが誰であっても、すぐにカースティがドアを開けて対応してくれるだろうと思った。
あと1、2時間は寝たいところだった。今日の午前中に出発することになっていて、最初の運転者はパトリックだった。計画通りにいけば、3時間ほどでノッティンガムに着き、そこのサービスエリアで昼食を取ってから、運転を交代するという手はずだった。
昨夜は1時過ぎまでなかなか寝付けなかった。カースティの部屋のソファは寝心地が悪かったというのもあるが、スチュとサラの家に預けてきたマギーのことが気掛かりで仕方がなかったのである。マギーが家でぐっすり眠れるようになったのはごく最近のことで、いくら「ママ」と呼んでも、パパしか来てくれないという事実を受け入れたばかりだったのだ。パトリックは、また元に戻って、マギーが夜中にぐずり出さないか心配だった。
その上、夜中の12時頃までクロエとバーで飲んでいたので、少しとはいえないほど、二日酔い気味だった。
まだドアはバンバン叩かれているが、カースティが受け答えをする気配はない。
「ふざけんなよ」と、彼はもうろうとした意識の中でつぶやいた。マギーが赤ん坊だった頃、夜泣きで30分ごとに起こされていた時を思い出す。
彼は重い頭を起こし、体を引きずるようにして、冷たいフローリングの床に平たい素足(すあし)をペタペタと打ち付けながら、玄関へ向かった。ボクサーパンツの前が閉まっていることを確認し、彼のお気に入りのバンド〈ガスライト・アンセム〉のTシャツを下まで引っ張り、お腹を隠した。
ドアを開けようと手を伸ばすと、再びドアがバンバンと叩かれた。
「今開けるよ」と彼は言った。
「なら早くしてよ」と、ドアの向こう側から声がした。
「ジェシ?」
「そうよ」と彼女は、さも当たり前のように言った。「早くこのいまいましいドアを開けてちょうだい」
パトリックはチェーンロックを外し、さらに、かんぬき錠も横に引き抜いた。1階のロビーで侵入騒ぎがあった後、カースティがドアの内側に取り付けたものだ。そしてようやくドアを開けると、姉が姿を現した。彼女は、大きな旅行カバンとハンドバッグを両手に持ち、立っていた。ニット帽を被り、ダウンコートを着て、ブルーのスキニージーンズを穿き、靴はいつものコンバースの〈オールスター〉を履いている。まだそこまで寒い季節じゃないだろ、と思った。
「とうとう来ちゃった」
ジェシカは急いで中に入ると、さっきまで彼が寝ていたソファに荷物をドサッと置いた。
「何しに来たんだ?」
「あなたを見送りに来たのよ、パトリック。って言ったらどう思う?」
「知らねえよ。あの夜からまだトイレに入ってるのかと思ってたよ。『ちょっとトイレに行ってくる』じゃなかったか?」
「婉曲(えんきょく)表現のつもりだったんだけど、わかりにくかったかしら?」と彼女は言った。「気が変わったのよ」
パトリックは、レジがバーコードに反応するようには、瞬時に理解できなかった。「お前も行くってことか?」
「不本意だけどね」
「は?」
「ダンに行ってこいって言われたのよ。そうしないと後悔するって。それから、その考えが頭から離れなくなっちゃって、それで」と彼女は言って、コートを脱ぎ、カースティがリサイクルショップで買った、使い込まれた木製のキッチンチェアの一つにそれを投げかけた。「来ちゃった」
「そうか」
「言っときますけど、このために家族旅行をキャンセルしたんだからね。エルスペスはもうカンカン。だから、余計なことはせずにさっさと済ませるわよ」
その時、ベッドルームのドアが開き、顔を出したリヴィが、「ジェシおばさん!」と叫びながら、だだっ広いリビングを駆け抜けてきた。
パトリックは、ジェシカの高慢ちきな表情が柔和(にゅうわ)にほころぶ瞬間を目撃した。両手を開いて姪っ子を待ち受ける彼女の眼中に、パトリックはもういない。二人の間で勃発しそうだった口論の火種を、リヴィが踏み消した形だ。
「そうすると、あなた、気が変わったってこと?」カースティがそう言いながら、大きなふわふわのバスローブに身を包んでリビングに入ってきた。
「今パトリックに話したばかりだけど―」
「私たちはね、この日のために頑張ったのよ。あのひどい状態のキャンピングカーをきれいにして、この馬鹿げた旅行のためにいろいろ準備したんだから。あなたはなに、出発の30分前になって登場って、ロックスター気取りもいい加減にしてよね」
「聞いて。私は―」
「私は何?」カースティが嚙みつくように言った。「リヴ、ちょっと自分の部屋に戻ってて。5分だけでいいから」
娘が言われた通り寝室に入っていくのを見届けて、彼女の母親はジェシカに詰め寄った。
「ほんとあなたっていっつもそうね、ジェシカ。ほんとに呆れるわ」
「どういうこと? 私に来て欲しかったんでしょ? 言わせてもらいますけど、あのキャンピングカーを『ひどい状態』とか言ったって無駄よ。どうせ大したことしてないんでしょ」
「したわよ」とカースティは言った。キャンピングカーが本当にひどい状態だったかどうかについては言及しないことにしたらしい。「前も言ったけど」
「今の話をして」
「今は...」と彼女は言った。パトリックは、次に彼女の口から何が飛び出すのか瞬時に予想した。あなたはとっとと家に帰って、あなたはこのことは忘れてちょうだい、あるいは、あなたにはずっと運転してもらうから、かな?
「今はそうね、あなたはそうするしかないでしょうね」
「カースティ、申し訳ないんだけど、あなたが何を言いたいのか、私にはさっぱり」
「あなたはいつもそんな感じじゃない?」カースティはそう言うと、マグツリーから陶磁器のティーカップを手に取り、ティーバッグを勢い良くカップに放り込んだ。「ちょっとは変わろうっていう気にはならないの? 少しは自分の芯みたいなものを持ちなさいよ」
「だから行くことにしたんでしょ」
「最後の最後でね。それに、どうせあなたが行きたいって思ったわけじゃないんでしょ。私にはお見通しよ。罪悪感を感じたくないからでしょ?」
「さっきも言ったけど、ダンが行けって言ったのよ。っていうか、もしそうだとしたら、なんなの?」
「まさにそれ! あなたはいっつもその言い草。それがあなたの生き方なんでしょうね」
「そうよ」ジェシカがバッグを手に取った。「あなたはそんなことばかり言って、私をどうしたいのかわかったわ。これから3日間、こんな口論がずうっと続くのなら、私はさっさと家に帰るわ」
「お好きにどうぞ」とカースティは言った。
ジェシカが玄関に向かって歩き始めるのを見て、パトリックが「待て!」と叫んだ。「頼むよ。べつに理由はなんだっていいじゃないか。彼女が今、ここにいることの方が重要なんだよ」
数秒間、沈黙が続いた。ハムスターが車輪を回すカラカラという音だけが不気味に鳴っていた。
「パトリック、なんだかあなたらしくないじゃない―」
「その先は言うな」と、パトリックがカースティを制した。「それからジェシ、バカにするな。君も行くんだ」
三人はお互いに顔を見合わせた。パトリックは、そろそろ母親の死後に起こったことについて話し合わなければならないな、と思った。いや、話し合う、では生ぬるい。言い争わなければならない。俺たちはそういう段階に近づいていることを感じていた。そして、旅はまだ始まってもいなかった。葬儀の前後は、親戚たちへの手前もあって、三人はそれなりに仲睦まじい姿を見せていたが、そのメッキもだいぶ剥がれ落ちてきて、ここ数年の間についた傷やへこみが、再び透けて見えるようになっていた。
しかし、そのことを正面から語り合う必要があるのは確かだが、今はまだその時ではなかった。そしてパトリックは、それが重層的に絡み合った長い議論になるだろう、と予見できた。
父親が未亡人となって一人取り残された時、実家をどうすべきかという問題が湧き上がった。そこには一筋縄ではいかない、家族の中での役割分担の問題があったのだ。それは一般的に広く知られていることではあるが、当事者にならないと見えてこない問題も内在している。
そして、その下には、もう一つ大きな問題があった。カドガン家の三人姉弟ならではの関係性が、その底流を成していた。
「聞いてくれ。そのうちみんなで話し合うことになる。でも、今はやめておいた方がいい。でないと、いつまで経っても旅に出られない」と彼は、これ以上波風を立てないよう慎重に言葉を選びつつ、意識的に温和な声を発した。「抱き合って仲直りしろなんて言うつもりはないよ。そうだな、少なくともこれからの3時間は、穏やかに過ごすか、まったく話さないかのどちらかにしよう」
ジェシカとカースティが同時にうなずいた。すかさずカースティはその場を離れ、お湯を沸かしに行った。
カースティの準備が整うまでに、そこから2時間かかった。旅行に必要な荷物は大方すでにまとめてあったが、いくつかまだ入れていなかった物をカバンに詰めなければならなかったし、泣きじゃくるリヴィに何度も連れては行けないと言い聞かせなければならなかった。彼女は、一緒に行きたい、と繰り返し訴え続けていたのだ。
そんな中、パトリックはキャンピングカーをチェックして来る、と言ってその場を抜け出し、階下に降りて行ったが、本当の目的はマギーとFaceTimeでビデオ通話をするためだった。スマホの画面を通してマギーの顔を見るのは、不思議な感覚だった。スチュのiPadから、娘がこちらに手を振っている。子供のいない夫婦ならではの、完璧なまでに清潔感溢れるデザイナーズキッチンが背後に映り込み、サラがせわしなく動き回っていた。旅の途中、娘とビデオ通話をしている時に、姉妹のうちのどちらかが、背景に映り込むピカピカのキッチンに気づいてしまったら、スザンヌの要望でキッチンを改装した、と言わなければならないな、と心にメモ書きしておいた。
それから、彼はクロエにメッセージを送った。
パトリック:昨夜はありがとう。最高に楽しかったよ😘
上の階に上がり、カースティの部屋に戻ると、二人の姉妹が一つの小さなソファに座って、それぞれにスマホをいじっていた。それを見て、彼はほっと胸を撫で下ろした。見えない火花は散っているのかもしれないが、少なくとも表面上は、口論は巻き起こっていない。
「そう、それでいいんだよ」とパトリックは明るく言って、バッグを手に取り、二人をソファから立つように促した。まるで離婚したシングルファーザーが、せっかくの週末なんだからスマホばかりいじってないで外へ行こう、と二人の子供から熱意を引き出そうとしているような気分だった。そして、それは気が滅入るほど、現実の状況に近かった。
最初に立ち上がったのはカースティだった。彼女はキャスター付きのスーツケースのハンドルを引き上げると、リヴィに最後にもう一度ハグをして、チュッと頭の天辺にキスをした。ジェシカも、何やらスマホに入力中だったものが終わったようで、同じように立ち上がると、コートを羽織りながら、「仕事よ」と言った。まるで、あなたたちとは違うのよ、と言い捨てるような言い方だった。私は小さいながらも、れっきとした企業経営者であり、あなたたち二人みたいに仕事を同僚に任せとけばいい、という気軽な身分じゃないのよ、とマウントを取りたいらしい。
彼は、二人の姉妹も自分と同じように、これから始まる旅に関して不安を抱いているのだろうか、と考えた。これから何日も一緒に過ごすんだと思うと少しうんざりして、いったい道中、どんな過去がほじくり返されるのだろうか、と心配にはならないのだろうか。
しかし、それは自分の胸にしまっておくことにして、三人でカースティの部屋を後にした。直前になってやって来たトリーナという彼女の友人がリヴィの相手をしている隙に、部屋を抜け出した形だ。三人はブライトンの、郊外ながらも交通量の多い通りに出て、〈冒険家〉が停まっているところまで道を渡った。
「彼女はここに停めておいたんだ」と彼は言って、バッグを地面に落とし、ドアを開けた。
「彼女?」とジェシカが聞いた。
「そう。頑丈な船はいつだって女性名詞だ。だろ? ボートとかさ」
「キャンピングカーは例外じゃないかしら、パトリック。だってこれはもう、見た目からして男性でしょ。ママがこんな...ものにときめくとは思えないわ」
「彼らはこれを一緒に買ったんだよ」
「本当にそう思ってるの?」ジェシカはそう言うと、彼を押しのけるようにして車内へ入り、後方の二段ベッドの下の段にバッグを投げ込んだ。カースティは上の段を取り、パトリックはエルヴィス・プレスリーのリーゼントのごときロフトに、自分の荷物を持ち上げつつ押し入れると、運転席に座った。
「道案内の手助けは誰が―?」
「私がするわ」とカースティが助手席に座りながら言った。「それじゃ、私たち、本当に旅に出るんだね」と彼女は続けた。
「みたいだな」とパトリックが言った。後ろにいるジェシカに目をやると、少し涙ぐんでいるように見える。
鍵を差し込み、エンジンをかけようとした時、パトリックの携帯が鳴った。彼は慌てて胸ポケットからそれを取り出した。
クロエ:私もよ。安全運転でね。着いたら電話してくれる? どこに着いたとしてもよ😘
「スザンヌ?」とカースティが、彼の顔がほころんでいるのを見て聞いた。
「いや」と彼は答えてしまってから、うなずいとけばよかった、と悔やんだ。「スチュ」と彼は嘘をつきながら、キーを回してエンジンをブルンと吹かした。三人を乗せた性別不明の〈冒険家〉が、巨体を揺らし動き出した。
クローリー
カースティ
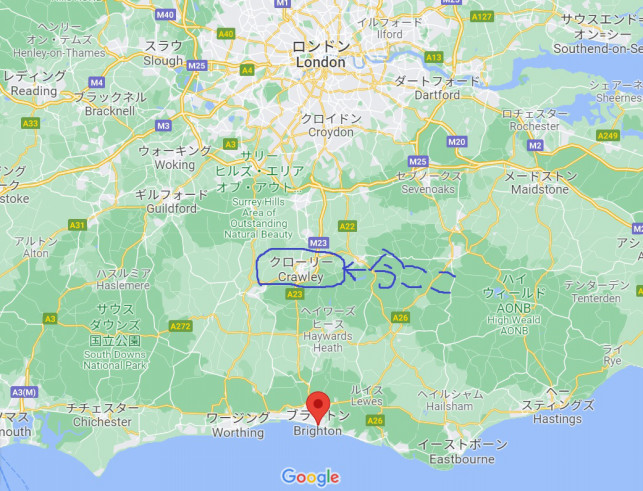
2時間後、彼らはようやくクローリーに差し掛かった。パトリックはブライトンを出るまでの道順ですでに手こずってしまった。道に迷いながらも、自分の生まれ育った街で迷っていることを頑として認めようとはしなかった。
カースティが助手席から「そっちじゃない」と言うと、「こっちの道の方が早いんだよ」と、彼はやけになって怒鳴った。
「近道なんてないのよ。ディッチリング通りを真っ直ぐ進むと、中央分離帯のある幹線道路に入るから、左側を走ってればいいの。忘れないで、私は今もここに住んでるんだからね」と、彼女はぼやくように言った。二人がめったに親に会いに来ないことを、あるいは、自分だけが故郷に残っていることを愚痴る時と同じ口調だ。しかし、パトリックは彼女を無視して、狭い通りをよくわからないまま、車輪の付いた重い車体をごろごろと引っ張るように進んだ。狭い通りの両脇には、キャンドルや、インテリア用品や、コーヒーを売る魅惑的な小売店が、肩を寄せ合うようにして並んでいる。
「しっかり方向は定めてよね」とジェシカが後ろから声をかけてきた。「乗り物酔いしたくないのよ。キャンピングカー酔いっていうのか、なんていうのか知らないけど」
カースティが振り返ると、彼女は携帯の画面を見つめながら、特大サイズのカップを片手に、ミルクたっぷりのコーヒーをすすっていた。出発して5分もしないうちに、彼女がどうしても飲みたくなって買ったコーヒーだ。そういう飲み方が車酔いの引き金になるんじゃないかしら、と思いながらも、それは胸に秘めたまま、あえて助言しないことにした。
それから30分ほどして、ブライトンからここまで渋滞に巻き込まれずに進んできたのだが、ついに高速道路上で車の流れは止まってしまった。
道路の両側には、秋色に染まった木々が生い茂っていた。しかし、この灰色の気が滅入るような舗装道路から眺めている限り、気休めにもならなかった。なかなか進んでくれない道路から抜け出せるわけでもないし、境界線を織り成す紅葉の向こうには、気持ちの良い草原が広がっていることを、紅葉の隙間から、ほんのわずかに感じ入るだけだ。
「しょっぱなから縁起のいいこと」と、後ろからジェシカが皮肉った。「この調子だと、ちょうど夕食時に私の家の近くを通ることになりそうね。私んちに立ち寄って夕食を食べていってもいいわよ」
カースティはパトリックの反応をうかがったが、彼は乗り気ではないようだった。1分ほどして、〈冒険家〉は再び動き出した。
「パパはこういう感じをイメージして、この旅を用意したのかな? 自分の三人の子供が、クローリーの郊外で渋滞につかまることを想定して。食器棚の一番下には自分の遺灰が置いてある状況で」
「彼はたぶん、もっと楽しい旅になると思ったんだろうな」とパトリックが言った。「あの釣り具箱の中を調べてみてくれ。〈カー・ビンゴ〉か何か入ってないか?」
「ああ、そういえば」とカースティが言った。「フランスに車で行った時も、コーンウォールに行った時も、いつだって車の中でゲームをしてたじゃない、覚えてる? 渋滞に巻き込まれると、ママが私たちにゲームを振ってくるの」
「〈エディ・ストバート〉のトラックを見つけて」とパトリックが母を真似て言った。
「それ!」と言って、ジェシカが声を上げて笑った。「もう一つは何だったかしら?」
「カー・クイズね」とカースティは言いながら、子供の頃の夏休みを思い出していた。どこへ行く時も、父親が運転する車の中で、私たちは抜き打ち的なトリビア・クイズをやっていた。
「後部座席にテレビが付いてる車が、窓から見えたのを覚えてるわ」とジェシカが言った。
「それは夢だったな」とパトリックが言った。「あと、夏休みに飛行機でどこかへ行くやつ。親父はそういうのを邪道(じゃどう)だと考えていたんだと思う。道中、苦労は必要だってことだよ。途中の苦しみがあってこそ、どこかへたどり着いた時の達成感は格別なんだ」
「カー・ゲームの問題点はね」と、カースティが言った。「あの頃は、みんな15歳とかだったでしょ。だから、私たちが探すべきものは、もう今は道路上には走ってないってこと」
「毎年クリスマスになると戸棚から引っ張り出してきて、みんなでやったじゃない。ほら、〈トリビアル・パスート〉。あれもそんな感じだったわ。ユーゴスラビアについての記述が古くて今とは違うし、アメリカの州の数も今とは違ってたり」
「彼は答えを全部暗記してたんだよ」とパトリックが言うと、三人は、ふふっと満足そうに笑った。懐かしさだけがもたらすことのできる満ち足りた笑いだった。
カースティは、子供の頃、長期休みに入るとみんなで行った家族旅行を思い出して微笑んだ。夕方になると、これからがお楽しみと言わんばかりに、ジェリーはバッグからトランプやドミノを取り出すのだった。(彼のバッグには、それらと数枚のCDが入っているだけで、あとの荷物は妻に任せていた。)山小屋や、テントや、キャンピングカーの中で、小さなテーブルを囲んだ家族は、心ゆくまで七並べやババ抜きに興じていた。それから〈ナンセンス〉というゲームもよくやった。母親がそう呼んでいたからその名前で記憶しているが、一般的には〈シットヘッド〉と呼ばれるゲームだとのちに知った。下品な名前を母親がオブラートに包んでくれたんでしょう。
「昔みたいにカードゲームをやろうよ」と彼女は提案した。「家族旅行の時によくやったじゃない。私もパパみたいに、トランプを一式持ってきたのよ」
「もうルールを覚えてないわ」とジェシカが言った。「ダンは休日にトランプなんてしないし、子供たちはいつもiPadに夢中だし。あれがあると他のことを一切しなくなるから、考えものよね」
「私はしてたわ」と彼女は言った。「たまにだけど、パパの家で七並べとか、クリベッジもやってた。でも父は上手すぎて、私が相手では物足りない感じだった。それで彼は毎週のように、『ブルドッグ・ビル』っていうよくわからない男を呼んで、二人でカードの腕前を競い合ってたわ」
「ブルドッグ・ビル?」とジェシカが聞き返した。
「パブで知り合った飲み仲間の一人みたいね。彼はブルドッグを飼っていて、何年も前にブルドッグは死んじゃったらしいけど、今でも彼はそう呼ばれてるのよ。葬式にも来てたわ。ほら、NHSから支給されたみたいな黒縁メガネの太った男よ」
「さあ、そんな人いたかしら? 前から思ってたんだけど、パパには...まともなっていうか...わかるでしょ? 友達がいなかったのかしらね」
「親しかったのは一人か二人ね。パブに行って、その人がいれば話すくらいの知り合いなら結構いたみたいだけど、大体みんな、妻に先立たれたか、妻に逃げられた男たちで、その中の一人はたしか、『マリード(結婚してる)・ピート』って呼ばれてたわ。彼だけはまだ結婚してたから、特別な存在だったんじゃない?」
「どれも、あだ名のセンスが抜群だな」
パトリックが割り込むようにそう言って、笑った。三人の中では、彼が一番パブの文化に詳しかったんだ、とカースティは思った。ジェリーがよく言っていたジョークや、あだ名や、カードゲームは、どれもパブで慣れ親しんだものなんでしょう。
「私はそれを聞いて嬉しいけどね、って、一応言っておく」とジェシカが言った。
「何が嬉しいの? ブルドッグ・ビルのこと?」とカースティが言った。「でも、そんなに、まともな友達でもなかったけど―」
「そうじゃなくて、あなたがまだパパとカードゲームをしてたことよ。感謝してる、って言った方がいいかしら?」
その言葉に苛立ちを覚えた。私と父の関係が、幸せなものではなく、情けや慈善からくる行為だと思ってるんだわ。とげのある言い方しちゃって。
「べつに感謝しなくてもいいのよ」と彼女は言いつつ、口論が勃発するのはなんとか避けようと、トーンを抑えた。「実際に私は楽しんでやってたんだから」
「ああ、わかってるわ。ごめんなさい。でも、私が何を言いたかったかわかるでしょ?」
実際はわからなかったが、カースティはうなずいた。今はまだ、言い争いは避けた方がいい、そう思った。車は渋滞の中をゆっくりと少しずつ進んでいた。長い旅路はまだ始まったばかりなのだ。
カースティは早く渋滞が解消され、もっと先までぐんぐん進んでほしいと強く願った。たとえそれが見当違いで絶望的な旅であっても、私たちはちゃんと前へ進んでいるという実感がほしかった。まだここは、私の家にも彼女の家にも、近いのだ。ささいな言い合いが、ののしり合いに変わり、やっぱりこんな旅行くのやめる、なんてことになりかねない。彼女は、二人の間をつなぎとめている、なかば強制的な友好関係と、キャンピングカーのどちらが先に壊れるか心配だった。
そういえばこの辺りにあいつが住んでたよな、と、パトリックがジェシカの元カレの一人を思い出した。私たちが渋滞で立ち往生しているクローリーという地名が、彼のあだ名には含まれていたからだ。
「あいつはオカルトにはまってたんだよな? それを聞いた親父が、あいつのことを『クリーピー(不気味な)・クローリー』って呼び出したんだ」
「ああ、そんな時期もあったわね!」とジェシカが言った。「マットっていうんだけど、なぜかクリーピー・クローリーで定着しちゃったのよ! 〈ザ・キュアー〉のギタリスト、ロバート・スミスにちょっと似てて、いいかなって思ったんだけど、今思えば、ロバート・スミスを10キロ太らせて、顔に湿疹ができれば、似てないこともないわね」
三人は声を合わせたように、笑った。カースティはほっと安堵した。今のところ、この雰囲気が無難よね、と思った。
さらに30分ほど、〈冒険家〉はえっちらおっちら車体を左右にゆさぶりながら、時折20メートルほどグンッと進んでは、ほとんど停止するということを繰り返し、ついに渋滞の原因となった場所を通過した。私たちの車と似たようなキャンピングカーが高速道路の真ん中に停まっていて、フロントバンパーのところが黒ずんでいた。おそらくエンジンに負荷がかかり過ぎて、悲鳴を上げるように火を噴いたんでしょう。
ウォーリック・パーキングエリア
パトリック
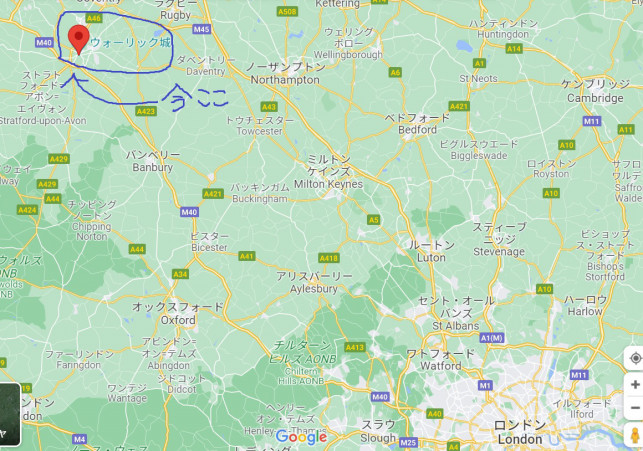
「よし、ピットインだ」とパトリックが運転席から声を発した。ループ状にぐるりと円を描くようなスリップロードに入ると、遠心力を体に感じながら、車体が横転しないかと心配になった。開(ひら)けた駐車場に入り、一番奥の方に車を停めたが、〈冒険家〉はほとんど3台分の駐車スペースを陣取ってしまった。
パトリックは4時間ほど運転席でハンドルを握っていたが、そのほとんどの時間、助手席でカースティが案内役を務めていて、うんざりさせられた。彼は忘れていたのだが、カースティには潜在的なリスクを気にしすぎる、という厄介な癖があったのだ。「そこ気をつけて」、「彼を気遣って」、「彼がどうなるかは神のみぞ知るね」いちいちうるせえな、と思いながら、『彼』とは誰のことを言っているのか、よくわからなかった。運転してる俺か、それとも、この車を『彼』と呼び出したのか?
そんな横やりを右から左に受け流しながら、彼はこの45分間ほど、サービスエリアで何を食べようかと悩んでいた。どういうわけか長旅になると、きっちり食事をとるという意識が窓の外へすっ飛んでしまい、間食用のスナック菓子をお腹いっぱいになるまで食べてしまうのだ。今回もすでに、〈フラッスル・チップス〉を2袋、〈パーシーピッグ・チョコ〉を半袋、カースティが作ってきた〈フラップジャック・クッキー〉を1つ食べてしまった。というか、〈フラップジャック・クッキー〉は普通ゴールデンシロップで甘くするだろ! なんで代わりに蜂蜜なんだよ!
「休憩はどれくらい取る? 15分でいい?」と彼は聞いた。こわばった脚を伸ばすように車を降りると、ガラス張りのサービスステーションに向かって歩いていった。屋外にはピクニック用のベンチが4つ置かれているが、誰も座っていない。一息つこうとサービスステーションに立ち寄って、屋外のテラス席でがっつりキャンプを始める人などいないだろ、と彼は思った。喫煙者が使うくらいか。
「コーヒーを飲んで、トイレに行くだけだからそれくらいで十分じゃない」とカースティが答えた。
「そうね。私はダンに電話してみるわ。みんなが無事か確認しなくちゃ」
「君抜きでどこへ行ったんだっけ?」
「スペインのマヨルカ島よ」
「いいね」とパトリックは言った。
「やめて」と彼女は言いながら立ち止まると、ストレッチをするように脚を伸ばした。「私も今頃、プールサイドで寝そべっていただろうな。まったく、いまだに私はここにいることが信じられないわ。ここがどこだか知らないけど」
「ウォーリックだよ」
「どこだっていいけど」と彼女は興味なさそうに言って、三人は中に入っていった。
ブライトン付近の渋滞を抜けてからは、順調な旅路が続いていた。パトリックは、子供の頃を思い出して、高速道路から見えるはずのサッカースタジアムを見つけようとしていた。カースティは、父親が車に導入していた最新のブルートゥース・ラジオを使って、彼女だけが興味のあるジャンルのポッドキャストを流していた。ジェシカは、寝たり、文句を言ったり、ハンドクリームを塗ったり、花屋の従業員にメールを送ったり、そしてまた寝たり、と一連の行動を繰り返していた。
彼はここまでの道中、明るいムードを保とうとしてきた。〈M6高速〉の通行料は「俺がおごってやるよ」と冗談めかして言ったり、午前中のラジオでやっているクイズ番組を聞いて点数を競い合おうと提案したりと、血は争えないのか、いつしか昔の親父の役割を担(にな)っている自分に気づいた。子供の頃の家族旅行でもそうだった。数百キロも走るとみんなドライブに飽きてしまい、しょんぼりムードの家族から旅への熱狂を引き出そうと、ジェリー・カドガンが必死になっていたのを思い出す。
ここまでの旅路で、2回休憩を取った。1回目はロンドンの南西に位置するサリー州で、最初の中継地点としては残念なほど実家に近く、全然進んでいないことを実感する休憩となった。2回目の今回はコヴェントリーという都市の近郊で、予定ではこの時間には、もっと先まで進んでいるはずだった。
「今日はあとどれくらい走る?」と彼が聞いた。三人はそれぞれコーヒーや、バカ高いお菓子の袋を持って車に戻った。パトリックは好物の海老入りサンドイッチを買ったのだが、駐車場の隣に〈グレッグス〉の売店が設置されているのが目に入り、ソーセージロールも追加で買いたくなった。が、それはぐっとこらえる。
「ボウランドの森で高速道路を降りれば、近くにキャンプ場があるわ」とカースティが言った。「たぶん、あと3時間も走れば着くんじゃない」
「ボウランドの森なんて、記憶をたどっても聞いたことないわね」とジェシカが言った。
「素敵なところよ。デイヴィッドと一緒にハイキングに行ったのよ」とカースティが答えた。リヴィが生まれてから今までで、最も真剣に付き合ったボーイフレンドだったが、その真剣さは彼女の心の中だけのものだったのかもしれない。彼女が同棲を提案したとたん、彼は南米を旅行すると言い残し、彼女の元を去っていったのだから。
「どこかのサービスステーションに車を停めて、車内で寝ればよくないか?」と、パトリックが提案すると、ジェシカが顔面を平手打ちされたように顔をしかめた。「何だよ?」と彼は言った。
「もう車内で十分に寝たわ、パトリック。夜もサービスステーションで寝るなんてごめんよ。あなたがホテル代をおごってくれるなら、ホテルの部屋で寝るっていうのもありね」
「ちょっとした思い付きで言っただけだよ」と言って、彼は助手席に乗り込み、カースティに運転を代わってもらった。
「最悪の思い付きね」とジェシカが言った。
「じゃあ、出発するよ。準備はいい?」とカースティは言って、この旅で初めて握ったハンドルを回し、〈冒険家〉を発進させた。
ストーク近郊を走行中
カースティ
〈M6高速〉を1時間ほど走っただけで、やっぱり高速道路は嫌いだとカースティは改めて思い知った。何もかもが殺風景で退屈なのだ。両脇に広がる低木や草原さえ、奇妙な灰色を帯びているように見え、気分がどんよりしてくる。
夕方になると、澄んだ水にポタッと落とした黒いインクが広がるみたいに、白い曇り空がじんわりと暗くなってきた。高速道路の頭上にはいくつもの電光掲示板が掛かっていて、閉鎖中のジャンクションや、距離と交通量を考慮した目的地までの所要推定時間が表示されている。車の中、後ろの席では、眠くなくなったらしいジェシカが、自分の仕事、家族、生活について延々と語っている。話題が変わっても、中心にはいつでも彼女がいて、彼女の経験や意見に周りが引っ張られ、振り回されている感じだ。
「ニューヨークに住むことの大きな問題点はね...」と、彼女がパトリックに話し出した。彼は助手席で体をやや斜めにして、実際は知らないが、熱心に耳を傾けている姿勢だ。さっきまで二人は、パトリックのダブリンでの生活について話していたはずだが、彼女の友人のサンドラが最近ニューヨークに引っ越したとかで、いつの間にか話題がニューヨークでの生活に移っていた。「やっぱりスペースの問題よね。要するに、1人目の子供までならなんとかなるけど、2人目となると、もう無理ね。あそこで子育てなんて不可能よ。アンドレアっていう友達も、1年前からニューヨークに住んでるんだけど、あ、彼女は広告業界で働いていて、海外に出向中なのよ。それで、彼女は2人目を妊娠した時、もううんざりってニューヨークを去ったわ。また1年、乳母車を共同住宅のエレベーターに乗せて、昇り降りする生活なんて耐えられないって」
パトリックは、彼女の話にうなずいて見せはするが、自分の意見は一切言わないようにしていた。一方通行の会話はすぐに失速すると思いきや、なぜか会話はひとりでに踊り出したかのように、ぴょんぴょんとあちこちを飛び跳ね、むしろ活発になるばかりだ。まるで美容師やタクシー運転手に向かって、やっかいなお客さんがとりとめもなく話しているかのようで、二人の間には、親しみも相互理解も感じられない。今日初めて会った二人みたいに、彼らを結びつけてきた長い歴史があることなど、最近になって仲たがいするまでは、仲たがいできるほどの絆がかつてあったことなど、微塵も感じられない。
車の流れがゆっくりになり、高速道路にかかる電光掲示板に、40という数字が赤い丸で囲まれた表示が点灯した。制限速度40マイル(65キロ)を示す標識を見て、カースティはブレーキに足をかけつつ、上っ面だけ装った見せかけの態度を崩そう、と決心した。
「そろそろ、なぜ私たちがここに集まっているのか、話し合った方がいいと思わない?」と彼女は後部座席まで届くように呼びかけた。
「ん?」と、パトリックはスマホの画面に目をやりつつ、上の空で聞き返す。
「私が言ったのは、話をした方がいいんじゃないかってことよ。なぜ私たちがこんなことをしているのか」と、今度はエンジン音に負けじと、さらに声を張って言った。「パパが何を望んでいたのかについて」
車内が一瞬静まり返った。その沈黙は、なぜ私たちがここに集まっているのかということよりも、そもそも子供たちを置き去りにしてまで、こんな路上の旅に出ようと提案したのはあなたでしょ? というカースティへの非難のように感じた。
「どうなの?」と彼女は反応を求めた。「いつかはしなくちゃいけないでしょ。ずっと先延ばしにはできないわ」
「どうして?」とジェシカが返した。「そんなの話し合わなくても、明らかじゃない? 彼はあの手紙の中で、私たちにもう一度仲良くなってほしいって言ってたじゃない。そして、私の立場から見ると、私たちは仲良くやってるわ。みんな礼儀正しくしてるし」
「それはそうだけど、それだけでしょ。礼儀正しいだけで、実際には何も話してないわ。雑談ばっかり。彼が死んでからずーっと雑談」
「じゃあ、どうして欲しいの? 正直になったらいいのね、なら正直になってあげる」
「ジェシ」と彼女は言ったが、手遅れだった。
「父の家で一緒に後片付けをしているとき、あなたはいろいろ私に指図してきたけど、余計なお世話でうっとうしかったわ。それから、あなた」と、彼女はパトリックを指さして、続けた。「実家の後片付けにも来なかったくせに、父のお別れ会でバーメイドといちゃついてるなんて、父は笑って許すかもしれないけど、私からすると、あなたって最低ね。あなたの奥さんが、なんだか知らないけど、来れなかったからって―」
「ジェシ!」と、カースティが叫んだ。「この一週間半くらいのことを、そんなに馬鹿正直に振り返ったって仕方ないでしょ。もっと前のことよ、私たちに起こったことをちゃんと話し合いたいの」
「もっと前がどうしたっていうの? ママが死んだ時からのことを逐一(ちくいち)全部振り返らないといけないわけ?」ジェシカがそう言うのを聞きつつ、カースティはブレーキをぐっと踏み込み、キャンピングカーを渋滞の最後尾に停止させた。視界の先には赤いブレーキランプが、蛇のようにどこまでも伸びている。「今さらそんなことを話し合っても、なんにもならないと思うんだよね。あの時だって意見が合わなかったんだから、今もそうでしょ」
「今も、あれは正しいことだったって思ってるの? パパの家を売ろうとしたのは」と、カースティが言った。「ママが亡くなってからも、パパはあの家でとても幸せに過ごしていたのよ」
「あの時は正しいことだと思ったし、ええ、今もそう思ってるわ。いずれにしても、彼が幸せだったっていうのは、ちょっと言い過ぎね」
「言い過ぎじゃないわ。私は彼のことをずっと見てきたのよ、忘れちゃった?」
「そうね、カースティ。そんなこと言わなくても、あなたがパパを一番よく見てきたことはみんな知ってる。ただ、私は実家から2時間離れたところに住んでいて、パトリックなんて別の国に住んでるんだから、そんなの当たり前でしょ。って、そこまで言わないとわからない?」
「ジェシ!」と、カースティが毅然(きぜん)とした口調で言った。
「何? ところで、前の車が動き出したわよ」
カースティは体勢を元に戻し正面を向くと、100メートルほど車を前に進めてから、再び停車した。
「さすがに前の車は追い越せないけど、家族の問題はちゃんと乗り越えたいの。それがパパの望んだことだから」
「どうぞ、私は止めないわよ」とジェシカが言った。「ただ、昔みたいな関係に戻れる、なんて考えがどこから来るのかわからないわね。人生って変わっていくものでしょ?」彼女は反応をうかがうように少し間を開けてから、続けた。「べつにまったくの疎遠になったわけじゃないんだし、何がそんなに不満なのかわからないわ。昔は仲が良かったけど、今はそうでもない、ただそれだけのことでしょ? 人生にはそういうことだって起こるわよ。今ではもう、ほとんど会わなくなった友達だっているし」
カースティはこれに対しては何も言えなかった。彼女自身も、一部の友人を除けば、同じことを感じていた。自分が生まれ育った町に住み続けるということは、通りを歩けば、かなりの頻度で知り合いに出くわすということだ。―もちろん、会いたくない人にも。
それでも彼女は、ジェリーのリクエストには応えるべきだと思っていた。少なくとも、応えようとしてみるのは当然のことだと思っていた。失くした絆を取り戻し、再び結(むす)んでみる。やってみなくちゃわからないじゃない!
「私はただ、私たちがこんな感じになってしまって残念なのよ。何よりも、パパに申し訳ない。彼には私たちのこの状態が理解できなかったでしょうね」
「彼は認めようとしなかったのよ。私たちがああいう経験をしたことで、もう前みたいな関係でいるのが難しくなったってことを、彼は受け入れなかったの。昔みたいに、小さく一つにまとまった家族なんて」
「あなたもごめんなさいって言えばいいのよ」
ジェシカはしばしの間、黙っていた。彼女に非があったことは周知の事実だけど、自分の非を認めるのは誰だってつらい。カースティもそれくらい心得ていた。けれども、ようやくジェシカは静かに「いいわ、そうね」とつぶやいた。「わかってる。あなたたちもわかってるように、私が悪かったわ」
「ありがとう」
「でも、だからといって、すべてが元に戻るわけでもないでしょ? いろんなことが昔とは違う。あなたにはあなたの人生がある。さっきも言ったように、私だって実家から離れた場所で自分の人生を築いてきたわけだし、パトリックは―」
「俺は違うよ」と彼が言った。車の列がまた少し進んだが、カースティは最後尾に距離を詰めようとはせずに、彼の方を見たままだった。彼はこれまでほとんど口を開かず、窓の外を見つめたり、ジェシカの話にうなずいたりしていた。昔からそうだ。彼は家族のもめ事から一歩距離を置くことに徹し、干渉しないことで気楽な人生を歩んできた。「俺はもうそこには住んでないんだ」
パトリック
彼はなぜそれを言ってしまったのか自分でもわからなかった。魔が差したというか、二人の会話の方向性が見えてしまったからだろう。母の死とその後のこと。逃げ場のないキャンピングカーの中で、予想通りの口論を聞き続けることに嫌気が差したのだ。本当のことを言えば、自分の私生活の話はするつもりじゃなかった。何食わぬ顔で、スコットランドの島まで行って帰って来るつもりだった。
「どういうこと? あなた引っ越したの?」とジェシカがすかさず言った。「ってことは、今まで黙ってたってことね? パトリック、どうして言わなかったの?」
「今言ったじゃないか、俺はもうそこには住んでないんだって」
彼は姉の顔に影が差すを見た。「まったく、パトリックって人は。あなた家を出て来たのね? どうせそんなことだろうと思ってたのよ。やっぱりって感じ。あなたはやっぱり最低―」
「俺が家を出たんじゃないよ、ジェシ。そうじゃなくて、彼女が俺を置いて出て行ったんだ」
ジェシカの表情が変わった。かすかに、だが確かに、彼女の顔に光が差したのを彼は見逃さなかった。家族を捨てた弟に感じていた失望感がすっと消え、怒る必要がなくなった代わりに、芸能人のゴシップ記事の詳細を求めるような、にやけた探求心が芽生えたらしい。これほどまでに、他の誰かの残念な人生の成り行きを知りたがっている人を、これまで間近で見たことがないかもしれない。
「いつ私たちに話すつもりだったの?」
「さあね。そろそろ話そうとは思ってたよ」
「それでどうなったの? 別居? もう離婚しちゃった?」
「ジェシ」と、カースティが仲裁に入った。「そんなにせかさないであげて」
「いや、俺は大丈夫だよ」とパトリックは言ってみたが、内心は大丈夫ではなかった。結婚生活が破綻(はたん)したいきさつを説明するのは、スチュとサラに話した後で、これが2回目だったが、1分ほどでうまくまとめて話せるか自信がなかった。
「その前にちょっと...」と彼は言って、シートベルトを外すと、後ろの小さな冷蔵庫へ向かい、ビールを取り出した。「他に誰かいる人?」
ジェシカは首を横に振った。カースティは返事すらしなかった。
「俺たち夫婦は終わったんだ。スザンヌと俺はもう」と彼は言い、〈フラーズ〉の瓶(びん)の栓を抜き、泡立つビールをごくごくと喉に流し込んだ。「親父が亡くなる1ヶ月くらい前だったかな、彼女は家を出て行った。もちろん言おうと思ったさ。でも、すぐに戻ってくるかもしれなかったし、わかるだろ? なんて言えばいいのかわからなかったんだ」
「なんなのよ」とジェシカが憤慨して言った。
「ジェシ」とカースティがそれを制するように声を上げた。
「俺は大丈夫だよ」
「全然大丈夫じゃないでしょ」
「ジェシカ!」
パトリックはもう一口ビールをぐっと飲んで、前方に目を向けた。ゆっくりと前の車が動き出す。外はだいぶ暗くなってきて、フロントガラスに小雨がぽたぽたと落ちてきた。その水滴に、前方のテールランプの光が赤くにじむようだった。
「彼女は新しい男と出会ったんだよ。出会ったというか、なんというか」
「あなたも知ってる人?」
「あまり知らないけど、彼女が働いてた会社に、奴(やつ)がデジタル部門のコンサルタントとして入ってきたらしい。インターネットとかウェブサイトとか、そういう関係の族(やから)だよ」と彼は、スザンヌが言っていた『デジタル・アーキテクチャー』という、それっぽい言葉を使わずに説明した。「奴は自分のことをデジタルをさまよう流浪人(るろうにん)とか呼んでるらしいな。本名はジョンだけど、ネット上ではパークと名乗ってるとか、わけのわからない野郎だよ」
「ちょっと待って、冗談でしょ?」と、ジェシカが小ばかにするように嘲笑した。予想通りの反応だった。彼女は自分ではリベラルを気取って、どんなライフスタイルでも受け入れる器の広い女性を自任しているが、自分が未経験のことを提示されたり、彼女が住む場所ではめったに起こらない出来事を目の当たりにすると、往々にして拒絶反応を示すのだ。「っていうか、彼はどうやってお金を稼いでるわけ?」
「その点ではそいつはかなり優秀みたいだな。彼女によると、そいつは億万長者だそうだ。なんだか知らないが、何かのアプリを開発したとかで、彼女はクラウドなんちゃらとか言ってたな。それを誰かが買い取って、彼は一生安泰(あんたい)なんだとよ」
「現実にそんな仕事あるの? っていうかそれって仕事なのかしら」
「私は聞いたことがあるわ」とカースティが言った。妹の方は、姉に比べるとずっと温和で、喧嘩を吹っ掛けてくる感じがない。「友達のメイベルが付き合ってた恋人が、そんな感じだったわ。現代の流浪人ね」
「じゃあ何? 彼は世界中をさまよい歩いてるとか言うわけ?」
「メイベルの恋人は彼じゃなくて、彼女よ。彼女はリバプール辺りに引っ越したとか言ってたわね」
「で、それだけ?」と、ジェシカはカースティを無視して、彼に聞いた。「あなたの奥さんも現代の流浪人になるってこと?」
パトリックはうなずいたが、いまだにスザンヌが家族を捨てて、そんな生活を選んだことが腑に落ちなかった。短期契約の賃貸住宅を転々として、アメリカ中を、あるいは世界中を住み歩く生活がそんなに魅力的か? 彼は歯がゆい思いだった。それを可能にする資金は、パトリックには理解できない方法で、奴が生み出しているのだ。
「マギーちゃんが可哀想。なんて人生なの。あなたは彼女の親権を争って戦うつもりなんでしょ?」
「まあ、それは別問題だけど」と、彼はビールを一口飲んで言った。「マギーは彼女のところには行かないよ。これからも俺のところにいる。俺が世話をする」そう言うと、彼はジェシカから視線を横にずらし、キャンピングカーの前方、蛇のように連なるテールランプを見つめた。「これからもずっと、四六時中俺が世話する」
一瞬、ジェシカが車内で飛び上がって、「よく言ったわ!」と彼に抱きついてくる気配を感じた。妻が娘の親権を放棄したことを祝福するかのような姉の表情に、彼は水をかけることにした。そんなに良いニュースじゃない、と。
「俺は無職のシングルファーザーになったんだよ。友人のスチュの家のソファで寝てる浮浪者だな。俺は不要と見なされて、ごみの山に捨てられちまったのさ」と彼は言った。「これから残処理(ざんしょり)が大変だ」
「あまり褒められたものじゃないわね」とカースティが言った。
「まあな」
パトリックは再びビールを口にした。ジェシカも今では、彼の窮状(きゅうじょう)を心配しているような表情だった。彼女は身を乗り出すようにして、冷蔵庫へ向かうと、ビールを1本取り出した。あるいは彼に同情して、1杯付き合おうということかもしれない。
「いつまでもソファで寝起きなんてできないでしょ、パトリック。毎朝背中が痛くてたまらないんじゃない? 寝ている間にグサッて刺されたみたいに」
「そこまで寝心地は悪くないよ」と彼は言いながら、なぜジェシカが真っ先に背中の心配をしたのか不思議だった。もっと他に気に掛けるべきことはあるだろうに。そして気づいた。きっと彼女自身の人生で今起きている何かに関連しているんだ。だから最重要事項として、真っ先にそれが浮かんだんだ。「大きなソファなんだよ。スチュの家は結構広くて、リビングの角にゆったりと寝れる長いソファがあるんだ」
「ああ、そうなの。それはいいわね。うちもそういうのを買おうと思ってたのよ」と彼女は言った。「それはともかく、マギーちゃんを連れてうちに来なさいよ。一緒に住みましょ。ロフトの部屋が空いてるから。うちの子供たちも喜ぶわ」
パトリックは思わずビールを吹き出しそうになった。
「何よ?」
「ジェシカ、まさか本気じゃないだろうな? お前の家に住む?」
「ほんの少しの間だけよ。あなたが前みたいにちゃんとするまで」
「あり得ないよ、ジェシカ。悪気はないけど、それは無理な相談だ。今回の旅だってギリギリのところで我慢して一緒にいる感じだし、1週間が限度だろ。それ以上一緒にいたら、3人のうちの誰かが、誰かを殺しかねない」
「まあ、考えといて」
「ちょっといい?」と、カースティが運転席から後ろの二人に言った。「マギーはどうしてるの? お母さんには会えるの? スザンヌはどこだか知らないけど...どこか遠いところにいるんでしょ。あなたはここにいるし」
「彼女は母親に会えるよ」とパトリックは言った。
彼は、スザンヌが提案したことをここで明け透けにするのをためらった。それを口にした途端(とたん)、二人の姉妹が笑い出したり、スザンヌの頭がおかしくなったと思われたりするのではないか、と心配だったのだ。彼女は不倫をしたし、人生を全面的に見直したい、と言って出て行った。にもかかわらず、自分は彼女に捨てられた分際(ぶんざい)でありながら、なおも彼女を守りたい、という気持ちがどこかに残っていた。樽(たる)の底に溜まった愛の残りかすが、微々たるものだけど、まだそこにあったのだ。
関係が終わっても、愛は残ることを身に染みて実感していた。もしも愛が、関係が終了した時点ですぐさま消え去るものならば、と彼は考えた。彼女が同棲しているその天才技術者は、なぜ愛の代わりになるものをテクノロジーで発明できないのか?
「でもどうやって? マギーを一人で飛行機に乗せたって、無事にスザンヌのいるところにたどり着けるなんて思わないでよ」
「彼女には考えがあるんだよ」と彼は静かに言った。「彼女はビデオリンクで連絡を取り合おうとしてるんだ。そうすれば今後も娘に会うことができるって考えてる」
「勘弁してちょうだい」とジェシカは、高音域のつまみをひねったみたいに、信じられなさのレベルをちょっと上げて言った。
「パークだかジョンだか、名前はどうでもいいけど、そいつが言うには、ビデオリンクでの子育てが次の流行になるんだとよ。そのテクノロジーはとても優れていて、対話相手が実際に部屋にいるみたいな感覚を味わえるらしいな」
「ちょっといい?」とカースティが言った。「ということは、彼女は週に1回とか、娘とビデオ通話して、それだけで済まそうとしてるわけ?」
パトリックは一瞬ためらった。再び、元妻の名誉を守ろうとする気持ちが瞬時に胸のうちに湧き出たのだ。彼女にも母性はちゃんとある、と言いたかった。そして、スザンヌが言っていた売り文句を、そのまま彼女たちに言いたくなった。つまり、立体的な3次元映像、いわゆるホログラムの凄さをアピールしたい気持ちになっていた。―パークが研究しているのはまさにその技術で、それを使えば、スザンヌは娘と同じ空間にいる感覚で対話できるし、シリコンバレーの連中は、そのうち子供を託児所に預けるのをやめ、オフィスで働きながら子育てするようになるのだ、と。
しかし実際のところ、それは現実からは程遠いものだった。ボールズブリッジの自宅で、キッチンテーブル越しに彼がスザンヌに言い放ったことが、まさに真実だったのだ。「君は娘を捨てて、渡り鳥だかなんだか知らないが、そいつとあちこちの宿泊施設でセックスするんだ。直接面と向かってな! 綺麗事を並べたってごまかせないぞ、スザンヌ。今だってそうだろ、こうして面と向かわなきゃだめなんだよ」
「それだけで済まそうとしてるな」と彼は、カースティの言葉を繰り返しながら、スザンヌが家を出たいと言い出したあの日を思い出していた。それを聞いて、彼は珍しく怒りをあらわにした。それは彼の人生で、まだ3、4回しか経験したことのない、自制の利かない瞬間だった。彼は常日頃から対立の芽を摘みつつ生きてきたつもりだったが、その日は自分が思っていることを洗いざらいぶちまけてしまったのだ。
最初、彼は彼女に「ゆっくりして来い」と言って、彼女を送り出そうとした。一時の気の迷いだろうと、帰ってきたら彼女の浮気を許すつもりだった。また、パトリックは彼自身にも非がなかったか、自らの行いを省(かえり)みた。彼の父親の病気、仕事、サッカー観戦など、気を取られることが多くて、彼女とマギーに十分な気配りができていなかったのではないか。あるいは、まだマギーが生まれる前、彼女と二人でロンドンからアイルランドのダブリンに引っ越したのが、そもそもの間違いだったのかもしれない。スザンヌがダブリンのIT企業からオファーを受け、彼女はとても張り切っていた。「今のうちにアイルランドのパスポートを取得しておきましょ」とさえ言っていた。イギリスだけEUを離脱したら、EU圏内ならどこでも使えるパスポートを求めて、イギリスのあちこちで長蛇(ちょうだ)の列ができるから、なんて会話さえ思い出される。
「俺が何かしたか?」と彼は彼女に聞いた。彼の顔は怒りで赤みを帯び、伸ばしっぱなしの髭(ひげ)は汗と涙で湿っていた。「もし俺が何かしたのなら、はっきり言ってくれ」
「あなたが何かしたとかじゃないの」とスザンヌは繰り返し彼に言い聞かせた。彼が彼女の浮気の全容を知った時から、悲嘆(ひたん)に暮れている彼に対し、彼女は半分理解したような、半分苛立ったような口調で接していた。「パトリック、落ち度なんて探す必要ないのよ。私たちの旅が終わったってだけなんだから」
彼女が言おうとしていたのは、疑似哲学とか、聞こえがいい流行り文句の類(たぐい)だった。パークが彼女に見るように言った動画やブログで、IT長者の波に乗り、調子に乗ってる連中が喚(わめ)き散らしているような与太話だ。彼らは中世の福音(ふくいん)伝道師やキリストの使徒に自分たちをなぞらえて、デジタル世界で生き抜く術を啓蒙(けいもう)していた。パトリック自身も、飲み会や食事会で何度かパークに会ったことがある。彼は彼女の会社にコンサルタントとして雇われていて、月に2、3回、ランチタイムに顔を出しては、デジタル関係の講演を行っていた。彼自身は、未来を見通し、経営の指針を示す先導者だとかほざいていたが、パトリックからすると、蛇の皮から取った万能のエキスだと言って怪しげな薬を売る、いんちきセールスマンと何ら変わらなかった。彼は他にも3、4社を回って同じ講演をしているらしく、彼がダブリンで巻き起こったITブームにうまく乗っかって、新興市場をフル活用しているのは確かだった。
「ふざけんなよ」とパトリックは、これまでの「旅」がいかにくだらないものだったかに呆(あき)れつつ言った。「っていうか、バレてほっとしたみたいな言い方だな」
「そうかもね」と言ってスザンヌは、謝っているというよりは恩を着せているといった風に、彼の手の上に彼女の手を乗せた。「これでよかったのよ。これで二人とも、それぞれの人生を歩んで行けるんだし」
「もし俺が気づかなかったら、どうしてたんだ? あのうすのろとこっそり、やり続けてたのか?」
「どの道あと1ヶ月くらいしたら、あなたに話すつもりだったの。私たちには計画があるからね」
「計画?」
「私たちはカリフォルニアに行くの。その後はニューメキシコに行って、その後はまだわからないわ。あまり先のことまで予定を立てたくないのよ。それに、パークは世界中から引っ張りだこなんだから、どこからお呼びがかかるかわからないわ」
「くそったれ」と彼はまだ信じられない様子で吐き捨てた。
「パトリック」と彼女が、彼の顔を覗き込むように目を合わせた。彼の瞳に映る女性は、もう彼の知っている彼女ではなかった。「私は私だけじゃなくて、あなたにも幸せになってほしいのよ」
「俺は十分幸せだよ、スザンヌ」
「そうね」と彼女は言って目を逸らした。「それは残念ね」
いたたまれなくなったパトリックは、キッチンテーブルの席を立ち、家を出ると、最初に見つけたパブに入った。〈リアリーズ〉という、これまで一度も行ったことのない店だったが、その名前からティモシー・リアリーを思い浮かべ、スザンヌもまたサイバー空間の魔力に囚われたんだな、とやけ酒した。2日後、パークがタクシーで迎えに来て、スザンヌを乗せて空港へ向かった。
「呆れてものも言えないわ、パトリック」とジェシカが言った。「いったいどうなってるのよ。彼女は母親でしょ、娘への愛情とかないわけ?」
「ないことはないんじゃないかな」とカースティがなだめるように言った。彼女は明らかに、母親バッシングが加熱して罵詈雑言(ばりぞうごん)に変わる前に鎮(しず)めようとしていた。
「そこが問題なのよ。彼女は本気でそんな絵空事を信じてるわけ? その手の話を一度聞いてみるといいわ。本気にする人なんているわけないって思うから」
パトリックはビールをもう1本開けた。彼は元々こんなに早くにこのことを打ち明けるつもりではなかった。まず、どうやって話せばいいのかわからなかったし、同情されるのが嫌だったからだ。
スチュとサラの家に居候し始めてからというもの、特にサラからたっぷりと同情をかけられ、ふがいない自分に嫌気が差していたのだ。結婚生活の破綻、それに追い打ちをかけるような父親の死、いわばダブルパンチをくらってノックアウト寸前の彼の姿が、サラの琴線に触れたようで、ソースのたっぷりかかった料理で手厚くもてなしてくれるのだ。夕食の席では、セラピーやカウンセリングを受けるようにしつこく言われ、せっかくのご馳走がなかなか喉を通らなかった。人生に関するコーチングを頼めば、悲しみを受け入れる、あるいは逆に吐き出すのか知らないが、何かしらの助けになるとサラは言うのだ。しかし実際のところ、パトリックが圧倒的に感じていたのは、悲しみではなく、「虚無感」であることを言い出せずに、ただ頷きながら、口をもごもごと咀嚼(そしゃく)するのみだった。スザンヌがタクシーで去った後も泣いたし、父親の訃報を聞いた時も泣いた。だけど今は、自分の人生を襲った災害が去った跡地で、涙も出ず、ただ呆然と虚無感に包まれ、突っ立っている状態だったのだ。これからどうやって前へ進めばいいのか、来年、自分の人生がどんな形になっているのか、周りには何の手がかりもなかった。
「それであなたは全く気づかなかったの?」とカースティが言った。「彼女から言い出すまで、彼女が浮気してる気配とか感じなかったわけ?」
嫌な質問が飛んできた。変に聞こえるかもしれないが、この部分に触(ふ)れられることを、彼は最も恐れていたのだ。その話をすると、登場人物全員が馬鹿か阿呆だと思われそうだったから。
「まあね」
「手がかりを見つけられなかったのね?」ジェシカは、彼が言い出すかもしれない何かに興味をそそられつつ、反面、怖くて聞きたくないといった二律背反の気持ちを抱えているようだった。「私からしたら、気づかないなんてあり得ないんだけど」
「そういうことじゃないんだ。奇妙なことがあって、本当に。あんな風にバレるなんて。あり得ないくらい愚かというか」
「べつに話さなくてもいいのよ」とカースティが、戦略的にへりくだった態度を取る外交官のように言った。
「私たちじゃ相談相手として頼りない?」とジェシカが言った。
「話すよ」とパトリックは言った。「でも...絶対笑わないって約束してくれ」
「約束する」とジェシカが言った。
「よし」とパトリックは言って、2ヶ月ほど前のことに思いをめぐらす。あの時、イングランドのクライアントにメールを送ろうと思って、スザンヌのノートパソコンを借りたんだ。「前から俺は彼女のノートパソコンを使って、メールを送ったりしていた。彼女もそれは知っていた。その時彼女はいなくて―」
「メール?」とジェシカが口を挟んだ。「大体そういう話ってメール絡(がら)みなのよね。私の友達のメアリーも―」
「ジェシカ」とカースティが言って、シーッと口を慎むように促した。車の流れが再びゆっくりになり、前の車が止まってしまったので、彼女は振り返って二人の顔を見た。
「いや、メールじゃない」とパトリックは言った。そして、まるで絆創膏(ばんそうこう)を傷口から剥がす直前の耐え難い瞬間のように、苦痛に耐(た)えつつ言った。「彼女の〈フィットビット〉だよ」
二人は一瞬、ん? という顔をして、ああ! と万能の腕時計を思い浮かべ、ジェシカは常にゴム製のリストバンドをしている自分の手首に目を落とした。
「噓でしょ」と彼女は言い、ゴシップ的洗礼を受けたように、にんまりした。まるで気に食わない友人の夫が、妻に隠れてデリヘルを呼んでいたのがバレたみたいに、嬉しそうだ。
パトリックはうなずいた。「彼女は〈フィットビット〉のすべてのデータを開いた状態にしていたんだ。それを見て不思議というか、不自然だったのは、毎週火曜と木曜の夜6時頃になると、彼女の心拍数が激しく上昇していることだった。彼女がジョギングしたり、ジムに行ったりしていないことは知っていた。それで―」
「何? これはどういうことだって、彼女に説明を迫ったの?」
「いや」と彼は首を振った。ここからが、彼の結婚生活を破綻させた不条理極まりない部分だと言わんばかりに、もったいぶって少し間を開けた。「彼女の話によると、火木は遅い時間に会議があるんだそうだ。アメリカの会社との合同会議で、時差の関係で夜にやってるとかね。それで、俺は5時半に彼女のオフィスに行ったんだよ。そしたら彼女が出てきて、彼の車に乗り込むところを目撃した」
「それで彼らの後をつけたの?」
「その必要はなかった。彼女と目が合ったんだ」と彼は、その瞬間の彼女の表情を思い浮かべながら言った。俺も間抜けな顔をしてたんだろうな、と、彼女のオフィスの向かいのビルの、中庭の植え込みの陰に隠れて、ひょっこり顔を出していた自分の姿を思い浮かべた。「彼女はすぐに浮気を認めたよ」
「全く言い訳とかしなかったの?」
パトリックは首を横に振った。「正直言って、彼女はちょっとほっとしたような顔をしてたよ。早くバレることを望んでたんだろうな。彼女の口から俺に言い出すのが嫌だったんだろう。それで終わったんだよ、俺たちの旅は」
彼は細かな状況説明を割愛(かつあい)した。例えば、ロビーの外で彼女と激しく口論していると、会社から出てきた彼女の同僚が挨拶してきた場面は省(はぶ)いた。その同僚はパトリックのことを知っているようで、そういえばパトリックにも見覚えがあった。スザンヌに対して熱(いき)り立っていた表情を取り繕うように、引きつった笑顔を浮かべつつ挨拶を返していると、パークが「その辺のカフェにでも入りませんか? みんなにとって一番良い解決法を探しましょう」と言ってきて、パトリックはその余裕ぶった顔を、拳で思いっきり殴りつけたくなった。
しかし、そこまでする必要はないだろうと、ぐっとこらえた。その気になれば、新聞社にパークのスキャンダルを売ることだってできる、と思った。一番の愚か者はパトリック自身だったのだ。まさか健康的な人生を送るためのスマートウォッチが、結婚生活を終わらせる最終兵器になろうとは。幸いなことに、自身の不名誉を新聞社に売るほどは、まだお金に困っていなかった。
「あらあら、パトリック」とジェシカが言った時、後ろから長いクラクションが鳴り響いた。カースティが慌てて前を向き、ハンドルに手をかける。前の車はとっくに発進していて、かなりの車間距離が開いていた。「大変な目に遭(あ)ったのね」
彼はジェシカの表情に葛藤を見て取った。同情と笑いが混在し、どちらが優勢を占めるか、接戦を繰り広げている。
「笑いたければ笑えよ」と彼は言った。「つまり、本当にバカバカしいことなんだから」
それなら、と言わんばかりに、彼女がクスクスと笑い出した。最初は遠慮がちに笑っていたが、パトリック自身も笑い出すと、二人はそれから数分間、お互いに顔を見合わせて、爆笑の渦に包まれていた。まるで10年前と何も変わっていないような、仲の良い姉と弟の姿だった。
~~~
〔チャプター 4(の前半)の感想〕
最近の藍が目覚めて真っ先に思うことは、「あそこの表現はこうした方がもっと良くなる」というような翻訳に関することで、顔を洗うより先にパソコンを立ち上げ、部分的に直すのです。そして朝日の中で、メンタルがすこぶるヘルシーになったなーと、翻訳はささやかどころか、大いなる自己セラピーだなーと、しみじみ感じ入るのです。←この欄って近況報告の場だっけ? っていうか、それが感想だとしたら、朝方恐怖感に襲われるかもしれないって怯えてるのは、パトリック(俺)じゃなくて、トム(僕)の方だよ! ごっちゃになって来ただろ?笑
名言来た! 「途中の苦しみがあってこそ、どこかへたどり着いた時の達成感は格別なんだ。」
まあ、翻訳は、渋滞ほど苦しくないので、喩えには使えないんだけど、(←渋滞も助手席に誰かいれば、苦しくないどころか、むしろ楽しいよ!笑)
そうだな、恋愛に喩えると、簡単に手に入る相手は、付き合ってもあんまり嬉しくないんですよ!←それは君には想像でしょ!!爆笑
恋愛は苦しい。IはAさんが好き。AさんはBくんが好き。BくんはCさんが好き。CさんはDくんが好き。という風に全員が「上」を見てしまうから、誰にとっても恋愛は苦しい。←やっぱり君は底辺なんだね!笑
イギリスの小説でも、好きな人が去ってゆく場所は、やっぱり「南米」なんだね! ホリー・ゴライトリーも南米に行っちゃったんだよね...😢(思い出し泣き)
静かな生活と、言い争いのある騒がしい生活、どちらがいいかってたまに考える。ベストは両方なんだろうな。年がら年中にぎやかなのも、うんざりしそうだし、静かすぎるのも、寂しくなる...😢(現状泣き)
衝撃の告白って、一旦秘密にしておくから「衝撃」が生まれるわけで、藍の場合、どうにも「かたわらいたし」ですぐ言っちゃうから(笑)、「衝撃」の総量がちっともたまらない...f^_^;💦←君ってすぐいっちゃうよね!笑
*藍の愛読書『徒然草』によると、「傍ら痛し」は「きまりが悪い、落ち着かない」という意味らしいです。
藍も娘を持った気になって、泣いてしまった。←きもっ!笑
最近の藍は平安時代を想っている。
エジソンだかオスカー・ワイルドだか、名前はいちいち挙げないけど、蓄音機とか、レコードとか、カセットテープとか、レーザーディスクとか、コンパクトディスクとか、ビデオとか、DVDとか、ブルーレイとか、バーチャル・リアリティーとか、ホログラムとかが一切無かった時代、月明かりの下で、恋文や短歌を交わし合い、逢引きをしていた雅(みやび)の人たちと、現代人の幸福の度合いや質は違ったのだろうか? (きっと同じだね💙チュッ)
いよいよ衆議院選挙です!←えーーーーーーー!!!! それ書く~~~~~~??????? (場が暖まってきた頃合いで水をかけるのが大好き💙ブチュー)
~~~
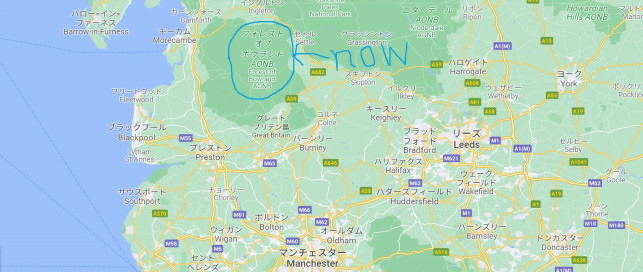
日本でいうと、長野と新潟の県境辺りかな?←日本でいう必要ある?笑←じゃあ、生きる必要ある?←ある!!!(笑)
ボウランドの森
ジェシカ
3時間半後、彼らはボウランドの森にあるキャンプ場に近づいていた。高速道路を降りると、1車線の道路が続いた。コンクリートを使っていない石垣と、緑の生け垣が両脇に散見された。その向こうには野原が広がっていて、たくさんの羊が風雨を避けるように身を寄せ合っている。カースティは何度もブレーキを踏んだ。ウサギやキジ、シカなどが車輪の下に飛び出してくるのではないかと思ったからだ。この3人の中で唯一のベジタリアンが、キャンピングカーで動物を轢(ひ)き殺したなんて、シャレにならない、というか、いかにも起こりそうなオチに思えたからだ。
ジェシカは遠くに、ヨークシャーの方へ向かってなだらかに伸びる丘のシルエットをぼんやりと眺めていた。その向こうには濃い紫と群青色が混じった空が広がっていて、夜が丘を越えてこちら側へやって来ようとしていた。ここは、彼女が住んでいる家の近くの〈ナショナル・トラスト・パークランド〉よりも、さらに田舎の田園地帯だった。ここには道案内板が随所(ずいしょ)にあるような散歩道はない。〈ナショナル・トラスト・パークランド〉のように、散歩を楽しむ人たちに美味しいホットチョコレートやケーキを売るカフェもない。それでも、ちらほらと農家はあって、大体どの家も、丸くて大きな衛星放送受信用アンテナを壁に取り付け、家の前にはプラスチック製の大きなゴミ箱を置いている。
カースティがまた急ブレーキをかけ、ジェシカは前のめりにつんのめった。
「一体どうしたっていうのよ?」と彼女は言った。
「そこを曲がるんだったわ」とカースティが言った。「ちょっと通り過ぎちゃった」
「この場所はなんていう名前だっけ? ティーアンドビスケットの森だっけ?」
「今ケーキっていう看板があったでしょ、ボウランドのケーキよ!」とカースティは、今日はもうこれ以上車には乗りたくないと思いながらも、ジェシカのボケに乗ってあげた。
彼女はギアをリバースに入れ、バックで狭い上り坂を登って行った。道の真ん中に苔(こけ)が生えているところを見ると、めったに車は通らないようだ。カースティはアクセルを踏み込み、苔で滑るタイヤをやや空回りさせながらも、細道が水平になるまで登り切った。ジェシカは窓の外に目をやって、わきを流れる小川を眺めていた。岩間を流れ落ちる透明な水が、夕闇の中でキラキラと光っていた。
「やっと休めるな」とパトリックが言って、車が大きな木製の門の前で停まった。風化してさびれた看板には「ケーキとお酒:ファミリーキャンプ場」と、まるで何かの教訓のように書かれている。ケーキとお酒があれば人生は楽しいと言ったのは、シェイクスピアだったか、サマセット・モームだったか。カースティは車の窓から身を乗り出すようにして、門のブザーを押した。〈バブアー〉の黒ジャケットを着て、〈ウェリントン〉のゴム長靴を履いた老人が、牧羊犬を連れて現れた。その犬も、彼とほぼ同年代に見える老犬だった。
それで羊を追い立てているのか、彼は木の棒を手に持っていて、なぜかそれで車のボンネットをコンコンと叩いた。傷やへこみができるかもしれないというのに、全く意に介していない様子だ。ジェシカは、これまでに何台の車が同じようにその棒で叩かれてきたのかしら、と思った。運転手の困惑した表情を窓越しに見て、毎回楽しんでいるのかとも思ったが、そうも見えない。続いて彼は、その棒で指し示すようにして、生け垣に囲まれた野原まで車を誘導した。
カースティがキャンピングカーを駐車したところで、彼は運転席の窓越しに「この時期に来る人はあんまりいないんだがね」と言った。
「そうでしょうね」
「君らと、あの人たちだけだよ」と彼は言って、棒を振り上げ、野原の真ん中にある3つの大きなテントを指差した。「田舎をめぐってるんだろうな、散策者たちだ」
キャンプ場といっても、ほぼ原っぱのままだった。一応数本、木製の電柱は立っていて、そこからキャンピングカーに電気を取り込めるらしい。あとは、その老人が住んでいる庭付きのコテージがあるだけだった。そのコテージとキャンプ場は、高さ50センチほどの緑の生け垣(モクセイ科イボタノキ属の落葉低木)で仕切られていて、その隣には小さな売店と、薄気味悪いシャワー室があった。
「とてもいいところですね」
「それはともかく、電気はここだ」と彼は言って、電柱の一つを木の棒で叩いた。「無料だが、ここに小便はするなよ。そこに売店もあるが、大したものは売ってない。温かい食事は出ますか? なんて野暮なことは聞くんじゃないぞ」
カースティは丁寧にお礼を言ったが、その男は彼女を無視するように、ぷいっと振り向くと、行ってしまった。噛まれてボロボロになったテニスボールを前方に投げて、それを犬に追いかけさせながら、歩き去って行く。ジェシカは、自分と全く共通点のない男と会話する羽目に陥ることを避け、彼と犬がだいぶ遠くまて行ったことを確認してから、キャンピングカーの踏み段を降りて外に出た。
「素敵なところでしょ?」とカースティが言った。
「さあ、どうなんだろ。暗くてよくわからないわ」
「匂いのことよ。ほら、田舎の空気って感じじゃない?」
「べつに珍しくもないけど」とジェシカは言った。「私の家の辺りも、とても緑が多いし」
カースティはキャンピングカーの後ろのドアから再び車内に入って、中にいるパトリックに合流した。彼女がシンクの上の戸棚から片手鍋を出す音や、やかんでお湯を沸かす音が、外にいるジェシカの耳に届いてくる。さっき高速道路のサービスエリアで買っていた、チキンやニンニクやバジルをパスタで包(くる)んだ詰め物に火を通すのだろう。ジェシカは、今日は水曜日か、と思った。ラクラン家では水曜日は炭水化物を摂(と)らない日と決めていて、パスタなどは食卓に出さないようにしているのだが、今日は例外でしょ、この状況だし、と思い、話としてもそのことには触(ふ)れないことにした。
ジェシカは草原の真ん中を歩きながら、スマホの画面を見た。左上の表示が「圏外」になっていないことを期待したのだが、不運にも「圏外」だった。彼女が契約している携帯電話会社は、イギリス全土の99%をカバーしていると謳(うた)っていたのだが、ちょうどこの場所は、残りの1パーセントの範囲に入っているらしい。彼女はそれを後ろのポケットにしまうと、夜空を見上げた。ボードゲームでもしているのだろう、テントの中から、散策者たちの陽気なおしゃべりが、夜風に乗って流れてきた。
今日はまずまずね、と声に出して言ってみると、自然と顔が綻(ほころ)んだ。
ここまでの道のり、懐かしさや思い出に浸っていた時間もあった。それから、パトリックの大きな告白があって、それ以来、彼はまた物静かでよそよそしい態度に戻ってしまった。―ほんのひと時、素の自分をさらけ出したかと思ったら、また昔の「何もしない、何も言わない、大騒ぎしない」少年の姿に舞い戻ってしまったのだ。
ジェシカは内心、この旅に付いて来て良かった、と喜びを感じていた。ダンは正しかった。この旅のどこかの時点で、私たち三人は、ここ数年の間に生まれたわだかまりをすべて吐き出すことになる、と彼女は思った。結局のところ、私たちは和解し、関係を修復するためにここにいるのだから。しかし、ジェシカはその時、どのような態度を取るべきか決めかねていた。母親の死が家族にもたらした傷の大きさを考えれば、修復も一筋縄ではいきそうもない。ただ、今振り返ってみても、自分が何か別の行動に出ていたとも思えない。
ジェシカは、カースティから送られてきたメールをまだ保存していた。ダンと私が実家を売ろうとしていることが彼女に知れて、送られてきたメールだった。彼女の怒りが文字を通して、スマホの画面から溢れ出ていた。
ダンと私は、これは良いことなのよ、とジェリーを説得し、彼が入居するための素敵なアパートまで見つけてあげた。ギャントン通りの邸宅は年寄りが1人で住むには大きすぎるし、あんなに嫌な思い出ばかりが詰まっている家で、余生を過ごすのは気の毒に思えたというのもある。それに、銀行が彼のビジネスを救済した2009年以来、あの家は抵当に入っていたから、借金を返済しなければ、どの道銀行のものになってしまうのだ。
あの時の言い争いは、彼女の頭の中で鮮明に繰り返し再現されてきた。家族会議が開かれたのは3年前のことだが、まるで先週起こったことのように、台詞の一つ一つを思い出せる。何年経っても色褪(あ)せない記憶というのは、良い思い出だけとは限らない。
カースティから召集令状のようなメールを受け取った私とダンは、ギャントン通りの邸宅まで赴(おもむ)いた。普段から家族会議なんて開いたことがなかった私たちは、ぎこちなさに包まれつつ、キッチンテーブルを挟んで向き合っていた。緊急事態が発生してからすでに5日が経っていたというのに、ようやく集まったのだ。
「よくもまぁ、ジェシカ、なんてことをしてくれたの!」とカースティが叫んだ。「心理的に彼を操ろうなんて。彼はまだ悲しんでるっていうのに」
「ここには思いっきり抵当権が設定されてるのよ!」
「そんなことはわかってるけど、あなたの目的はそうじゃないでしょ、ジェシカ。その話を持ち出して、ごまかさないで」
「私たちは保証人なのよ」と彼女は言った。〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉が破産寸前まで行った時、彼女とダンが保証人になることで、実家の2度目の抵当権設定を銀行が認めたのだ。銀行曰(いわ)く、今後少なくとも20年は仕事をする見込みがある人の後ろ盾がなければ、彼女の両親のような高齢夫婦に多額の融資をすることはできない、ということだった。「私たちには、この家を今後どうすべきかについて、ある程度の発言権があるってことでしょ」
「私よりも発言権があるっていうの? パトリックよりも?」とカースティが、ほとんどヒステリーを起こしそうになりながら言った。「パパよりもあるっていうわけ?」
ジェシカは一瞬黙り込み、ダンの顔を見てから、言い放った。「あるわ。はっきり言わないとわからないみたいね」
その瞬間が決定的な決別の瞬間だったのかもしれない。カースティの腕が動き、一瞬、彼女が熱い紅茶の入ったマグカップを投げつけてくるのではないかと思った。
そこからは非難の応酬となった。彼女とダンが家の売却を強行して、そのお金の一部を自分たちの住宅ローンの返済に充てようとしている、とカースティは言うのだ。厳密にはそういう気持ちもなかったとは言えないが、私たちの真の意図がねじ曲げられ、取り違えられていた。
緊急会議にスカイプで海の向こうから参加していたパトリックは、いつものようにほとんど口出ししなかった。しかし、彼がジェシカの計画をすでに知っていて、それを「まあ、売ってもいいんじゃない?」と暗に認めていたことがカースティの知るところとなり、彼女の怒りの矛先を向けられてしまった。(彼はその後、ジェシカとも仲違いし、「どうせ俺は二人の間のスケープゴートだよ」と、ぼやくようになっていた。)
「なぜそんなに計算高いとか思うの?」とジェシカは言った。「常識的に考えて言ってるだけよ。この古くて広い家にポツンとひとりで暮らすなんて、彼だって望んでないでしょ」
「この古くて広い、お金になる家でしょ?」とカースティが口を挟んだ。
「重要なのはそこじゃないわ」
「ジェシカ、ここは私たち家族の家なのよ。それをどうするかは家族みんなで決めなきゃね」
「だから、なぜ彼はまだここに住みたいのか、その理由を聞いてるのよ」
「ここは俺の家だからだ」とジェリーが口を開いた。それまで隅の席で、ほとんど上の空といった様子で座っていたのだが、ここぞとばかりに目を見開いた。「この家は半分俺が建てたようなものだ。母さんと俺がここに来た時は、ボロボロで到底住めるような家じゃなかった」と彼は言った。「俺はお前たちを、そんな風に財産や金のことばかり考えるように育てたつもりはないぞ。勤勉さを重んじるように、一生懸命働くように育てたんだ」
彼は立ち上がったが、先月の大半をテレビの前でダラダラと過ごしていたせいで、足元がふらついた。
「今のところ、自分でもどうしたいのか決めかねてる。ただ、もしこんな風に嘆かわしい言い争いの種になってるのならば、もうこのことは忘れてくれ。お前たち全員に言ってるんだぞ」
そう言って、ジェリーはパブに向かった。パトリックは、赤ん坊の世話を手伝うように妻に言われたとか言い訳をしながら通話を切った。ジェシカとダンは、別れの挨拶もそこそこに実家を出て行った。カースティは一人でそこに残って、キッチンの片付けを始めた。
その口論の後、少なくとも1週間は、カドガン家の面々はお互いに口をきかなかった。それぞれがそれぞれの形で裏切られたと感じていたのだ。カースティは、大きな決断から自分だけ除け者にされたことに。パトリックは、ジェシカがカースティよりも優位に立とうと彼を利用していたのだと気づいたために。ジェシカは、外のみんなが現実的な理由ではなく、感傷的な理由であの家に固執(こしゅう)していることがわかったために。彼女にとって、無用な感傷ほど嫌いなものはなかったから。
その夜が、今日ここに三人が集まることになったそもそもの原因だった。あの夜から今日まで、ぎくしゃくした関係が修復されることはなかった。しかし元はと言えば、それは何の説明もなく、忽然(こつぜん)と姿を消した一人の家族がもたらしたものに他ならなかった。長年に渡って、それぞれの心に深く積もった痛切な想いのゆえだったのだ。
ちょうどその時、ジェシカはお尻のポケットで携帯が震えるのを感じた。電波が届いたらしい。携帯を引き抜き、ダンか子供たちからのメッセージを期待しつつ画面を見ると、それは単に、花屋のインスタグラムに新たなフォロワーが増えたという通知だった。
キャンピングカーに戻ると、カースティがテーブルに座って、プラスチックのコップで赤ワインを飲んでいた。フリースの上着を着て、脚には毛布をかけている。パトリックはさっき見かけたシャワー室に行っているとのことだった。明日は凍(こご)えるような寒い朝になることが目に見えているから、今のうちに体を温めているんでしょう。
「私にも1杯ちょうだい」とジェシカが言った。
しばらくの間、二人は黙ってワインを飲み、窓の外の夜空を眺めていた。家で見るよりもずっとたくさんの星がまたたいていた。自分の家では、近くの都市の光がぼんやりと届き、完全な田舎ではないことを常に思い知らせていた。美味しいレストランやカフェ、〈ウェイトローズ〉の支店などが立ち並ぶ、快適なマーケットタウンがすぐそこにあることが常に意識のうちにあった。しかし、ここではそれが全く違っていた。夜空はあまりにも多くの白いビーズで覆われていて、彼女が家でたまにマックスとエルスペスに説明して見せるように、星座を解読し指でなぞることは、ここでは不可能だった。
「かわいそうなパトリック」とカースティがついに口を開いた。
「そうね。私も同じことを考えてたわ」とジェシカは言ったが、それは嘘だった。彼女が考えていたのは、家のこと、子供のこと、仕事のこと、夫のこと、キャンセルした休暇旅行のこと、電波の状態が不安定で彼らに電話をかけられなかったことだった。「パトリックったら、今までずっと黙ってたなんて、私たちが彼を裁く裁判官みたいじゃない? ようやく白状したけど」
「裁けるの?」とカースティが、驚いたような表情で言った。「ジェシ、だからこそ私たちはここに集まってるのよ。10年前だったら、彼は真っ先に私たちにそのことを話していたでしょうね。でも今は違う。私たちがこうやって狭い場所に閉じ込められるまで、彼は文字通り何も言う気にはなれなかった。その事実がすべてを物語ってるわ」
ジェシカは納得がいかないような表情をして、ため息をついた。
「何?」
「10年前はああだったこうだったって言うのは勝手だけど、ただ、何か変ね。彼は昔から物事を溜め込んでしまう質(たち)なのよ」
「だから言ってるじゃない。パパがこの旅をリクエストしたのは、そういうことなのよ。私たちに昔みたいに戻れって言ってるの...何もかもを」
「待って。わかってて言ってる? つまり、彼のメモにははっきりとそういう風には書かれてなかったでしょ」
「そうね。私はただ推測してるだけよ」とカースティが、むっとして言った。「でも、そう考えるのが妥当じゃない?」
ジェシカは言い返す前に、自分の言いたいことがもっと鮮明になるのではないかと、少し間を開けた。
「それで、それは実際に可能だと思う?」
カースティがそれに答える前にドアが開き、パトリックがキャンピングカーに戻ってきた。下はジョギング用のジャージにアディダスのサンダル、上は〈ワトフォード・フットボール・クラブ〉の黄色いシャツを着ていた。髪は濡れて乱れ、顔は青ざめている。
「あのシャワー室、クッソ寒みぃぞ」彼は犬が体を乾かそうとするように、ぶるぶると全身を揺さぶった。そして、二人が自分を見つめていることに気づき、「何だよ?」と言った。
「なんでもない」とカースティが言った。「飲む?」
「飲むけど、腹減ったな。俺が料理すっか?」と言って、彼は冷蔵庫からパスタの詰め物を2パックと、瓶入りのペスト・ジェノヴェーゼを取り出した。
「ごめん。今やろうと思ってたんだけど」
「いいよ、俺に任せろ」と彼は言った。
「考えてたんだけど」とカースティがワインを手渡しながら言った。「夕食を食べたら、あの箱を開けてみようよ。最初のアルバムをめくってみるの。パパの指図通りの順番で」
「ウイスキーもね」とパトリックが付け加えた。
「もちろん」とジェシカは静かに言った。彼女はさっきカースティが言っていたことを思い返していた。すべてを昔みたいに戻す。昔の三人の関係が自然に出来上がった秩序だとしたら、今は無理にゆがめた異常な状態で、それが長く続きすぎている。いびつなまま固まってしまう前に、ほぐさないといけないのかもしれない。
「何か問題でも?」とカースティが、ぼんやりした様子の彼女を見て聞いた。
「子供たちのことが心配なだけ。電波がほとんど届かないから、電話もメールもできないし。もし彼らが私に何かメッセージを送ってたとしても」
「きっと送ってるわね」とカースティが、なだめるような口調で言った。
ジェシカは立ち上がると、キャンピングカーの中をそわそわと歩き回った。
「ねえ、この車ってちゃんと暖房はあるの?」と彼女が焦ったように聞いた。
「一応はね」とパトリックが言った。
「一応って何? ちゃんと暖かくならないの?」
「まあ、ラジエーターがないからな。あそこから一応熱風は出るよ」と彼は言って、ドアのそばにある小さな円形の通気口を指差した。「ただ、それで一酸化炭素中毒にならないとは保証できないけどな」
「リスクを冒して眠るわけね」と彼女は言った。
パトリックは温めたパスタの詰め物を大きなボウルに移し、それをテーブルの上に置いた。それから、お皿を3枚、フォークを3本、ワインのボトルをもう1本並べ、テーブルの下から赤い金属製の釣り具箱を取り出した。
「これは食後だな」と言って、2人の間に腰を下ろす。
カースティ
カースティは、今回もまた自分が司会役を務めなければならないのか、と感じた。何でもいっつも私にばっかり押しつけて、と言ってやりたい気持ちになったが、私は分別のある大人よ、と自分に言い聞かせ、ぐっと言葉を押し込めた。
赤ワインを2本飲み干し、昔の家族旅行のこととかを思い出すままに話したりしながら、食事が終わり、誰も言い出さないので仕方なくカースティは、パトリックがさっき横に置いた赤い箱を手に取って、テーブルの上に載せた。小さな南京錠に鍵を差し込み、父の葬儀の日の夜以来ずっと鍵をかけたままだった釣り具箱の蓋を開けた。
そこにはすべてがそろっていた。2週間誰の手にも触られないまま、手紙、ウイスキー、アルバムが入っていた。
「どうぞ」彼女は、ジェリー・カドガンの古い釣り具箱の中から、イエス・キリストの聖杯を取り出すかのような厳(おごそ)かな表情で、ウイスキーのボトルを両手で取り出すと、それをパトリックに手渡した。彼はそれを開封すると、一人で笑い出した。
「何?」とカースティが言った。「何も問題ないでしょ?」
「いや、まったくないよ。ただ、親父のやつ、ちょっと飲んだな」コルク栓を引っこ抜きながら、彼は言った。「シールが破れてる」
「飲んではいけないって言われてたのよ」と、カースティは信じられないといった表情で言った。
「どっちにしろ余命宣告を受けてたんだから、少しくらい飲んだってどうってことないだろ」と彼は言って、大きめのグラスにウイスキーを等分に注いでいった。
「それにしたって―」
「ほんのちょっとしか飲んでないよ」彼はジェシカの反論を遮って、3つのグラスにウイスキーを注ぎ終えると、親父がよく言っていた美味しいウイスキーの飲み方を思い出し、それぞれのグラスに1滴か2滴の水を加えた。
「じゃあ」とカースティが言った。「きっとこれが最初の1冊ね」
彼女は箱からアルバムを取り出した。それは縦横が昔のレコード盤くらいの大きさで、青い革製のアルバムだった。四方には金色のふち飾りが施されているが、ところどころはがれている。彼女はそれをテーブルの真ん中に置いた。―パトリックとジェシカが向かい合って座り、カースティの向かいにはプラスチックの窓があった。そこに映った自分の顔は、思いのほか緊張気味だった。
「さあ、始めましょう」彼女はそう言うと、表紙に指をかけ、時の扉を開くように最初のページをめくった。
そこには、左上に日付と場所が、母の筆跡とわかる丸みを帯びた文字で書かれていた。
1990年7月、コベラック、コーンウォール。
その下には写真が3枚収まっている。
1枚目には、ピンクのウインドブレーカーを着たジェシカが、紫の〈ラレー〉のマウンテンバイクにまたがっている。ハンドルから葉っぱが伸びるように、紫にきらめくミラーがついた子供用の自転車だ。
2枚目には、パブの外のベンチテーブルに座った両親が、ビールとワインのグラスをカメラに向かって掲(かか)げ、酔った赤い目をして、にっこりと微笑んでいる。
そして最後の写真は、カドガン家の4人の子供たちが並んで海辺の防波堤に座っているものだった。
ジェシカ、パトリック、カースティ、そして最後に隙っ歯を見せて笑っているのが、アンドリューだ。
カースティは息を吸って、まだ自分が1歳を過ぎたばかりの頃に家族で出かけた旅行に飛び込んだ。彼女は何も覚えていなかった。しかし他の二人は覚えているかもしれない、と思って周りを見た。そして、三人は一緒に記憶の中に潜っていった。


フィッシュ・アンド・チップス
1990年7月 ― コベラック、コーンウォール
「3、2、1」スーがそう叫ぶと、4人はカメラに向かって笑顔を見せた。「ハイ、チーズ」
全員が彼女に向かって叫び返す。甲高い二人の声が響き、赤ちゃんのキャキャッという興奮した声が弾(はじ)け、パトリックはいつものように「ソーセージー!」と叫んだ。
彼らはコーンウォールの小さな漁村にいた。フィッシュ・アンド・チップス専門店の向かいの壁に子供たちが腰掛け写真を撮っている間、ジェリーは6人の家族が食べきれないほどの料理を注文していた。カウンターの男性店員は、今年もやって来たこの家族を覚えていた。観光地であるコベラックでは、町全体の収益アップにつなげる取り組みとして、観光客には親切に対応するという合意が、ほとんどの店で取り交わされていた。ただ、一軒の釣具店だけは例外で、そこの店主は7月と8月の間、子供向けの網(あみ)やバケツ、鋤(すき)などを売ってはいたが、お客がそれらを買おうと手を伸ばすと、そんなものを使うなんて図々しいとでもいうように、ギロッと睨(にら)み付けるのだった。
コベラックはカドガン家にとっての別荘地といえる場所だった。スペインの特定のリゾート地で毎年夏を過ごす人がいるように、東海岸に居心地の良い夏用の別荘を持っている人がいるように、フランスのキャンプ場に毎年行く人がいるように、カドガン家は毎年ここにやって来るのだった。毎年7月の第2週は、海岸沿いの道路からすぐのところにあるコテージで過ごすことにしていた。後方にはどこまでも続くような草原が広がり、前方には岩だらけの小さな砂浜が広がっていた。毎晩、潮が満ちるとともに、その砂浜は海面に沈み、朝になると濡れた岩場が再び姿を現すのだった。岩にはり付いた海藻が朝の光に照らされ、鮮やかな緑色にキラキラと輝いていた。
このコテージは、〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉の顧客であるジェインという老婦人が所有しているものだった。―彼女はイギリスをぐるっと巡れるようにと、あちこちの海岸沿いに6つの土地を所有していた。1979年に初めてこのコテージを訪れた時には、まだジェリー、スー、ジェシカの3人だけだった。酔っ払いが運転する車がコテージ前のレンガ壁に突っ込んできて、新しい壁を作る必要があったジェインが、ジェリーにそれを頼んだのがきっかけだった。ジェリーには幼い娘がいて、お金もないことを知っていた彼女は、その工事を引き受ける代わりに、コテージを貸してくれたのだ。それ以来、毎年夏にはここに訪れるようになった。―最初の数回は補修や雑用を行うことで賃貸料の代わりとし、その後、ジェリー・カドガンが独立し、少しずつ収入が増えていったことで、現金で支払うようになった。
1990年、彼らが滞在した1週間は雨の日が多かった。カドガン一家は、黄色いポンチョのようなレインコートをかぶって、農地や起伏(きふく)の激しい海岸沿いの道を歩き回っていた。
その日、彼らはティンタジェル城に出向いた。そこでジェシカはアーサー王伝説に夢中になって、休日に使っていいことになっている20ポンドをすべて、アーサー王のグッズに使ってしまった。黒い紐で首にかけることができるルーン文字が刻まれた青い石碑や、この地方の作家兼詐欺師が「真実の歴史」という文字を石に刻んだ剣(つるぎ)などを買い込んだのだ。
「よし」とジェリーが5つの箱を抱えて、フィッシュ・アンド・チップス専門店から出てきた。「あそこのベンチにしよう」
「カモメはどうするの?」とジェシカが、思春期に近づくにつれ、少しすねてきた声で言った。
「カモメなんかほっとけ」
「ジェリー、やめて」と彼の妻が言った。
「下品な意味じゃないよ、スーザン」と彼は、しわがれ声を含み笑いで和らげつつ言った。「オカマを掘るという意味で使うやつもいるかもしれんが、れっきとしたアングロサクソン語だ」
子供たちはベンチに座り、スーが一人一人に食べ物の入った箱と木製のフォークを手渡した。パトリックはすかさずアンドリューの腕にフォークを突き刺し、お返しに熱々のフライドポテトを顔面にくらった。
「やめなさい」とジェシカが言った。
「お前はママじゃないだろ」
「ママはここにいるわ」とスーが割って入った。「弟を刺すんじゃありません。あなたも食べ物を投げたりしないの」
ジェリーとスーはベンチの両端に腰掛け、フライドポテトをつまんだり、なかなか切れない木製のナイフで魚を切り分けたりしていた。
「あと二日だな」とジェリーは言って、家族で飼っているラブラドール・レトリーバーにフライドポテトを一つ投げ与えた。犬の名前はグレイで、彼のひいきのサッカーチーム、ワトフォードFCの監督グレアム・テイラーから取った名前だ。「明日は何をしようか?」
「ビーチがいい」とアンドリューが、ポテトで口をいっぱいにしながら言った。
「今日みたいな名所は他にもある?」とジェシカが聞いた。
「お城はもういいでしょ」とスーが言った。また一日中、4人の子供を統率しながらお城を巡るのはうんざりだった。どうせ15分後にはジェシカ以外の3人は飽きてしまうんだから。「晴れてたらビーチに行きましょ。晴れてなければ、ボードゲームをして、その辺を散歩しましょ」
この提案は家族全員を満足させるものだった。少なくとも、誰からも不満は出なかった。
食事が終わると、スーとジェリーはリュックサックに予備の服や食べきれなかったお菓子、カメラなどを詰め込んだ。スーは最後に、ティンタジェル城で男の子たちに買ってあげた木製の剣(つるぎ)をリュックサックの一番上に突き刺した。手で握る柄(つか)の部分がリュックから飛び出ている。そして、濡れた犬の匂いが常に充満している家族用のワンボックスカーへ歩いて戻った。
翌朝はコテージの窓から太陽が顔を出し、ぽかぽかと暖かかった。まるで夏が満を持して登場することを決意したかのような青空が、窓の外に広がっていた。アンドリューはこれで今日はビーチに行くことが決定したと勢い勇んで、すぐにスーパーマンの水泳用トランクスを穿き、先月イタリアで行われたばかりのワールドカップの記念Tシャツを着た。イングランドが勝ち進むにつれ、ジェリーが興奮のあまり購入していったグッズの一つだ。(ジェリー自身はイングランドが準決勝で負けた時、イングランドのTシャツをクローゼットの一番奥に突っ込んでしまい、それからそのTシャツは何年も日の目を見ることはなかった。)
アンドリューは、キッチンの配膳カウンターに置いてあったカメラを手に取った。それはコダックの〈ホビー〉という黒くて分厚いカメラで、カセットテープとほぼ同じ大きさと形状だった。ボタンを押して起動すると、上部からフラッシュの点灯部分がポンと飛び出す仕組みだ。
彼は一人で庭に出て、写真を撮り始めた。羊が点在する草原の風景、コテージの向かいの小さなビーチ、それから、2匹のミツバチが花弁の間でそわそわと舞っている様子をクローズアップで撮った。
「1枚。2枚。3枚」と彼は口ずさみながら、シャッターを押していった。無駄な写真をたくさん撮ったことで、追加でフィルムを買い足さなければならなくなったパパの憤(いきどお)る顔が、今から目に浮かぶようだ。「4枚。5枚」
コテージの中に戻り、子供用の寝室に入ると、まだ眠っているパトリックの写真を撮った。彼は寝相が悪く、まるで6メートル上空からマットレスの上に落とされたかのような体勢でだらしなく寝ていて、前の晩、両親が丁寧に布団を掛けてあげた形跡(けいせき)は微塵も残っていない。彼はジェシカの寝姿も写真に収めると、カメラの巻き上げ可能数が昨夜よりも大幅に少なくなっていることにママが気付かないことを願いながら、カメラを元々置かれていた場所に戻した。
1時間半後、彼らはみんなで持ち物をかき集めて、海水浴客でごった返しているだろうビーチへ向かった。
「ママ」とアンドリューは、スーの少し後ろを歩きながら言った。「今日はいっぱい写真をしてもいい?」
「あら、『写真をしてもいい?』ってどういうこと?」
「撮ってもいい?」
「1枚か2枚ならね。ママがお手本を見せて、カメラの使い方を教えてあげるわ」
「うん」とアンドリューは言った。あやうく彼は、使い方ならすでに、かなり詳しく知っていることを言ってしまうところだった。
ビーチに到着すると、他の家族からなるべく距離を取って自分たちの荷物を設置した。ただ、あまり距離を広げすぎると、別の家族が間に割り込んでくる可能性があるので、そのギリギリのラインを見極めつつ自分たちの場所を確保した。カースティは母親の腕に抱かれ波打ち際までやって来ると、砂浜の上にそっと下ろされた。娘がよちよちと海水に手足を沈め、その冷たさに泣きそうになって後ずさるのを、母親はいつでも抱き上げられるように両手を伸ばしつつ間近で見守っていた。ホーブの海岸でも毎週末のように娘を海水で遊ばせているので、息の合ったダンスのように手慣れたものだった。一方、ジェシカは砂浜で、学園ものの恋愛小説『スイート・ヴァレー・ハイ』を読んでいた。仲のいい友達同士で回し読みしているものだ。彼女はコテージから持ってきたガーデンチェアーの1つに腰を下ろし、優雅にくつろいでいたが、その椅子の白いペンキは剝げかけていて、金属の部分は錆びつき、花模様も色あせていた。その近くで、パトリックとジェリーは、ゴム製の軽いサッカーボールを互いに蹴り合い、父親が息子のヘディングとボレーシュートの能力をテストしていた。いまだに自分の息子から将来のスター選手が出ることを夢見ているようだ。
「お前の頭を狙うぞ、アンディ」とパトリックは叫び、弟の頭を目がけてボールを蹴った。しかし、彼の思い描いていた軌道を大きく外れたボールは、眠っているのか死んでいるのかわからない老夫婦の方へ一直線に飛んでいった。彼は決してサッカーの才能があるわけではなく、時々弟と庭でボールを蹴って遊ぶくらいがちょうどよかった。だから、父親が入るように勧めた地元のサンデーリーグのチームにも参加しなかった。
学校では、ほとんどの男子は人生でただ一つの目標を持っていた。それはサッカー選手になることだった。けれどアンドリューは違った。彼はゆくゆくは軍隊に入隊したいと思っていて、祖父がたまにしてくれるイギリス空軍にいた頃の話に、熱心に耳を傾けていた。その道への最初の一歩は、8歳になったらカブ・スカウトに入ることだった。そして11歳からはボーイ・スカウトへ移行するのだ。そこで待ち受けている冒険や友情を思い描くだけで、彼の心はわくわくと高鳴り、武者震いがするのだった。パパがその計画にどれほど賛成してくれるのか、それだけが不安の種だった。
アンドリューは老夫婦の近くまでボールを取りに行くと、パトリックに蹴り返し、「ママ! カメラ!」と叫んだ。
「バッグの中」とジェリーが叫び返した。「サンドイッチの横。おい、フィルムがもったいないから、ガシガシ撮って無駄使いするなよ」
パトリックはひざでボールを2回空中に浮き上げ、そのままボレーシュートを決める要領で、海に向かって蹴り上げた。ボールは風の壁にぶつかったように、波打ち際で宙返りすると、砂浜に落下した。ジェリーがボールを取りに、のっそのっそと走っていく。黄色いポロシャツの下で、たるんだお腹がぷるぷると揺れる。薄くなった細い髪が、そよ風に捕らえられ、なびく。
その時、アンドリューは再び写真を撮り始めた。―海辺でボールと戯(たわむ)れる兄と父を撮り、小さな妹と母の仲睦まじい姿を撮り、読書に耽(ふけ)るジェシカを撮った。彼は誰に対しても公平でありたかった。誰かが除け者になったり、誰かが一人だけ損をするのではないかと、いつも周りを気遣っていた。年齢的に真ん中の存在として、自分より年上の姉と兄が持っているものが見えたし、年下の妹がまだ持っていないものも見えた。
カースティは彼がカメラを構えて、自分に向けているのに気づいたのか、にっこりと微笑んだ。
「よく見えない」とアンドリューは叫んだ。
「ズームを使えばいいんだよ」とジェリーはジョギングをするような足取りで、アンドリューの元へ向かった。一人残されたパトリックは片足でボールを踏んだまま、サッカー漫画『ロイ・オブ・ザ・ローヴァーズ』の表紙みたいに、ニヒルに佇んでいた。
「ズームってどれ?」
「ここ。この小さなボタンを押すと、自分が近寄らなくてもグッと距離が縮まる。逆に押すと、また視界が広がる。これで、遠くから妹の写真を撮ることができるぞ」
アンドリューは言われた通りにズームボタンを押し、母親の腕の中でもじもじと動くカースティにズームインした。
「お前はまさに、小さなデイヴィッド・ベイリーだ」とジェリーが言った。
「サッカー選手?」
「いや、そうじゃない。著名な写真家だ」
「あと何枚撮れる?」とスーが、カースティを海辺から連れ戻し、タオルの上に座るように指示しながら聞いた。
「4枚」と、アンドリューは小さな数字盤に視線を落として言った。
「じゃあ、あと1枚にしなさい」と彼女は言って、ジェリーの顔を一瞥した。彼は、もうそんなに撮ったのか、フィルム代がいくらかかると思ってるんだ、と今にもグチグチ言い出しそうな雲行きだ。「家族全員の写真を1枚撮りましょ。アンディ、撮ってくれる?」
スーは子供たちを集合させて、ピクニック用のシートの上に並ばせた。そして彼女とジェリーはその後ろに立った。
「まだ撮るのか?」とジェリーが耳元で囁いた。
「彼は趣味が必要なのよ。せっかく写真が好きになりそうなんだから、余計なことは言わないで」と彼女は小声で言ってから、声を張った。「アンディ、私たちがどこに立ったらいいか教えて。全員がフレームに入ってることを確認して」
アンドリューは、家族から距離を置いてカメラを構え、ズームインとズームアウトを繰り返した。構図を決めるためでもあるが、世界が伸縮するさまが新鮮だったから、というのも大きかった。
「パパとママはもっと低くかがんで」と彼が言い、両親は少ししゃがみ込んだ。「パトリックとジェシはもう少し近くに寄って」
彼の指示通りに彼らは立ち位置を調整した。
「私たちは準備いいわよ」とスーが言った。
「オッケー! 3、2、1」
みんながにっこりと笑顔になったところで、アンドリューはシャッターを押した。目の前に存在しているものが記憶に定着するような心地よい音が、カシャッと鳴った。
パトリック
彼はまだそれらの写真を見下ろしていた。そのアルバムはまるでボードゲームのように、3人の真ん中で開かれたまま、一身に視線を集めている。彼はそれぞれのカップに特別なウイスキーを、一晩で空にするわけにはいかないと注意しつつ、注(つ)ぎ足していった。
「あの夏休みを覚えてる?」とジェシカが言った。
「なんとなくな。コベラックは覚えてるよ。いつからあそこに行かなくなったんだ?」
「90年代の半ばね。パパがポルトガルに別荘を買ってからはそっちに行くようになったから」と彼女は言った。
パトリックはポルトガル最南端の海岸沿いにあった、アルガルヴェの別荘を思い出した。〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉の商売が繫盛していた時期が数年あり、その頃にジェリーが、ろくに物件を見もしないで即決して購入した別荘だった。普通、彼のような労働者階級で育った少年が立身出世した場合、派手なスポーツカーを真っ先に購入するのが相場だったが、ジェリーはそれよりも海外の別荘や、サッカースタジアムのVIPだけが入れるボックス席でサッカー観戦することに興味をそそられていた。地元のサッカーチーム〈ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC〉のスポンサーになり、ホームスタジアムのピッチサイドに〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉の広告を年間を通して掲(かか)げた時が絶頂期で、これでボックス席の夢も叶うかと期待したが、サッカーチームのオーナーとの会食止(ど)まりだった。家族で唯一、彼の趣向を受け継ぎ、サッカー観戦に興味を持ったのはパトリックで、彼は9月の冷えた夜に父と一緒に行ったその試合を覚えていた。1-0でワトフォードがブライトンを降(くだ)した一戦だった。
「私はほとんど覚えてないわ」とカースティが言った。「その時、私は何歳だった? 5歳? たしか、あなたなしでポルトガルの別荘に行った年があったわ」と彼女はジェシカに向かって言った。「あなたは学校の友達とどこかへ旅行に行っちゃったのよ。それから、あなたも」と今度はパトリックを指差して言った。「スティーブだったかしら? いつもつるんでた友達と、女の子をナンパしたり、たばこや発泡酒を買おうとしたりで忙しかったのよね。それで一週間、私とアンドリューの二人だけだったのよ」
とうとう彼の名前が発話された瞬間だった。この旅が始まって以来、彼の名前が誰かの口をついて出たのは初めてだった。父親が亡くなり、実家の片付けの時も、葬儀の計画を立てている時も、3人は彼の名前を口にしないようにと心掛けていた。彼の記憶を寄せ集めようとしても、めったにうまく思い描けなかった。失われた兄弟は、3人の中に答えよりも多くの疑問符を浮かべる存在だったのだ。アンドリューが火葬場や葬式に姿を現さないことを3人はほぼ確信していた。―彼は母親の葬儀の時も帰って来なかったのだから。
パトリックはアルバムのそれらの写真にもう一度視線を落とした。砂浜のカースティ。パトリック自身と父親が、90年代に持っていたゴム製のサッカーボールを蹴り合っている。最終日の雨の中、家族全員で写っている1枚。そして、太陽が降り注ぐビーチで家族並んで写っている1枚。そこには、アンドリューだけが写っていない。
「この中に彼がいないのは、なんか不思議だな」
「彼はこれを撮ってたのよ」とジェシカがすぐさま言った。当時の夏休みの思い出を、カラー映像のように一番鮮明に覚えているのは間違いなく彼女だった。「ママが彼に古くて四角いカメラを手渡して。ビデオテープみたいな形のカメラだったわ」
「俺もそれは覚えてるよ。フィルムを使い切ると、親父がもったいないって腹を立てるんだ」
3人は再び静かになった。パトリックは、あの頃のアンドリューのことを考えていた。彼がどれだけ、サッカーやクリケット、テニスなどの、その季節に合ったスポーツをやらせようとしても、なかなか良い返事は返って来なかった。彼の弟はそれよりも、写真や読書、ボードゲームなどに興味を持っていた。バカ騒ぎが好きな兄とは異なり、内省的で物静かな子供だったのだ。アンドリューは、祖父のイギリス空軍での体験話に特に魅了されていたようだったが、実際に彼が軍隊に入って、そこでの生活に溶け込み、やっていけるとは誰も思っていなかった。
17歳のアンドリューが空挺(くうてい)部隊の訓練生として入隊することを決めた時、あまり衝撃は走らなかった。それからパトリックが、海外遠征を2回ばかり経験し、4年余り経った頃、逆境に屈した形で早々(はやばや)と退役したことを知った時も、大して驚きはなかった。
必然的な思考の流れで、パトリックはあの日を思い出した。アンドリューがそこにいるものだと思っていた場所にいないことを知った日のことだ。―アフガニスタンの山奥に建てられた兵舎(へいしゃ)で暮らしていると思っていたのだが、ケヴという名の男からメールを受け取り、アンドリューの不在を知ったのだ。ケヴは、兵役中にできた数少ない友人の一人なのだろう。
彼はネットでパトリックの連絡先を見つけたらしい。腕のいい職人の一人としてリストに載っていたということだが、当時のサイトはもうないし、彼からのメールも保存していない。それでも彼は、そのメールをほとんど一字一句正確に記憶していた。
パトリック様
突然のメッセージに驚かれたらすみません。連絡を取ろうと思ってからしばらく放置していて、時間が経ってしまいました。
あなたの弟のアンディのことですが、彼は6ヶ月前に連隊を辞めました。それ以来、何の連絡もありません。あなたには連絡ありましたか? あるいはご家族には? 仲間が少し心配しています。ロンドンに行くとか、そんなことを言っていましたが、実際にはわかりません。あなたにも知らせておくべきだと思い、こうしてメールしました。彼が去った理由は誰も知りません。もし彼から連絡があったら教えてください。
ケヴ
その時、パトリックはそのメールのことを誰にも言わず、自分の胸にしまっておいた。
混乱したまま彼はすぐさまロンドンへ向かい、カムデンに直行した。カムデンは、ロンドンの中でも地図や観光案内なしで歩き回れる数少ない地区の一つだったからだが、ほどなくして、よく知っている地区だからといって、行方不明の退役軍人をあてもなく探し回ったところで、徒労(とろう)にもほどがあると気づいたのだった。
彼はロンドン市内のシェルターや避難施設に電話をかけ、弟の特徴を説明し、そういう人がいないかと聞いて回ることにした。ソーシャルワーカーやボランティア、看護師たちが、毎晩寝床を求めてやって来る何千人ものさまよい人や、あらゆる熱にうなされた人たちの中から、黒髪でシュッと細長い顔をした魅力的な青年を見つけ出してくれるかもしれないという漠然とした期待を胸に、彼の特徴を熱く説明した。といっても、アンドリューの唯一の特徴は、彼の鼻の真ん中辺りにへこみがあることくらいだったのだが。―彼が嫌々ながらも参加せざるを得なかった学校の体育のラグビーで、タイミング悪く顔面にタックルをくらった時にできたくぼみだった。
アンドリューを見つけられないまま、もどかしい日々が続いた。それでも彼は予約が入っていた仕事をキャンセルしてまで、捜索を続けることにした。リビングの壁紙を張り替えに、あるいはペンキを塗りに彼がやって来るのを待っていた顧客たちは困惑の色を隠さなかったが、一旦地元に戻った彼は、シェルターや避難所で奉仕活動をする人たちに見せる写真を携(たずさ)えて、ロンドンに戻った。
ある日、〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉経由で受けた仕事を延期したところ、父親から電話が来た。「何やってんだ?」と父は受話器越しに憤っていた。「今朝、シムキンスの婆さんがやって来て、お前が来ないって文句をたらたら垂れ流していったよ」
「彼女には電話したんだけどな。具合が悪くて、ベッドから出られないんだよ。一晩中吐いたりなんだりで眠れなかったんだ」
「いいかげんにしろ。明日は必ず行けよ。こっちは『ホーブで最も信頼されている建築士事務所』を謳(うた)ってるんだ。忘れたか? 俺がそろそろ引退しようかと考えてる時に、お前がそれをぶち壊すなんて承知しないぞ」
実際はベッドの中ではなく、再びロンドンへ向かう途中の高速道路のサービスステーションにいた。彼は車の中で地図を開き、一人で捜索するにはとてつもなく広いロンドンの街を、いくつかのエリアに区切り、重点的に捜索していく順番を考えていた。
カースティやジェシカ、あるいは父か母のどちらか一人にでも手伝ってもらえば、もっと手際よく探せるだろうと思った。しかし、先が見えない不確実性と不安の中に、彼らを巻き込みたくはなかった。軍隊にいると思っていた弟、あるいは息子が、ATMの近くに座って、お金を下ろしに来た人たちに小銭をめぐんでもらっているところを発見する可能性もあった。あるいは、ドラッグとか、その種の依存症に陥っている可能性の方が高そうだとパトリックは思った。軍隊での生活に憧れ、キャッタリックのキャンプ場へ向けて家を出た10代の青年が、今では汚い地下道で、腕に針を刺しているかもしれないのだ。
突破口が開かれたのは、5回目の上京の時だった。
パトリックが写真を見せると、ランベス区にある避難所の職員が、「彼なら知ってるよ」と言ったのだ。30分かけてこの施設に電話がつながり、さらに15分間、受話器の向こうの相手を説得し、直接会う段取りを取り付けた結果だった。「ポールじゃないかな?」
「彼の名前はアンドリューだよ。本名はそうなんだ」
「なるほど。彼はここに来る時はポールと名乗ってますよ」
「どのくらいの頻度で? つまり、彼はいつここに来るんですか?」
「ほぼ毎日来てますよ。いつも泊まっていくわけじゃないけど、雨が降ってたり、寒かったりすると泊まっていきますね。そういう人が多いんですよ。泊まるにはお金がかかるので、節約のためにも外で寝るんです。最近は季節がら外のことが多いですよ」
「彼がどこに行くか知ってますか? ここにいない時はどこへ?」
「残念ながら、さっぱりわかりませんね。お友達ですか?」
「彼の兄なんだ」と、パトリックが真剣な眼差しを向けると、その男の心はいくぶん和らいだようだった。
「まあ、ここに来るカウンセラーの誰かが知ってる可能性はありますね。でも、教えないでしょうね。中には借金を抱えてる人もいるし。売人とかも多いし。あなたはそういうタイプには見えませんが、もし私たちが彼の居場所を教えたら...彼がどうなるか、わかりますよね?」
パトリックはイライラしつつも、理解はした。
「ここで待っていてもいいですか?」と彼は尋ねた。「彼が来たらわかるように」
「この中は駄目です。ですが、外をうろついてる分には止めようはありませんが」
「わかりました」と彼は、少しがっかりしたように言った。
「紅茶でもいかがですか?」
「え?」
「紅茶の友っていうのかな? 手に持ってるだけでも、ほっとしますよ」と、その男は優しい笑顔で言った。
「ありがとう」と彼は言った。
パトリックはプラスチック製のカップに入った薄い紅茶を受け取ると、外の通りに出た。そして避難所の反対側の縁石に腰を下ろした。彼はその時読んでいた犯罪小説で時間をつぶそうとしたが、1段落読むごとに通り過ぎる人々に気を取られ、顔を上げてしまう。その中の誰かが弟かもしれないのだ。
時間の経過とともに、さっきの男性が、さらに2杯の紅茶と1枚のビスケットを持ってきてくれた。そんな細(こま)やかな気遣いに、パトリックは目頭が熱くなり、このような施設で働く人々の心意気を知った。
夕方6時頃になると、避難所のドアの前に人だかりができてきた。貧窮(ひんきゅう)した、汚い身なりの、一見して不幸とわかる男たちだ。中にはアルコール度の高いりんご酒の缶をすすっている者や、マクドナルドのチーズバーガーを大事そうに両手で守っている者もいた。もしかしたらアンドリューかもしれないと思いながら、一人一人の顔を一心に観察した。しかし、誰一人として彼の横顔に合致する者はいなかった。
さらに30分ほど過ぎた頃、パトリックは一人の男が通りの端の角を曲がって来るのに気づいた。彼は迷彩柄の軍隊ズボンを穿き、黒くて大きなダウンジャケットを着ていた。無精ひげを生やし、野球帽の下からボサボサの黒髪が突き出ている。寝袋を詰め込んだスーパーマーケット〈セインズベリーズ〉の袋を肌身離さず手に持ち、同じくパンパンに膨れたバックパックを背負っていた。
21歳とは思えないほど老けていたが、紛れもなくアンドリューだった。彼は他の男たちに近づきつつも、うつむいたまま顔を上げようとしない。―どうやら友達や仲間を作ることには興味がないようだ。
彼の手には缶ビールは握られていなかったが、金属製の水筒がバックパックからぶら下がっていて、軍隊での生活が垣間見えるようだった。彼はパトリックが道の向こうから自分を見ていることには気づかず、壁の方を向き、他の人たちとともに避難所が開くのを待っている。
どうやって近づけばいいのか、何を話せばいいのかわからないまま、パトリックは立ち上がり、ためらいがちに道路を渡っていった。
「おい!」と彼が呼びかけると、何人かの男たちがこちらに顔を向けた。しかしアンドリューはうつむいたままだ。パトリックはもう一度声を上げ、今度は「アンドリュー・カドガン」と付け加えた。
パトリックは、弟の肩がガクンと落ちたのに気づいた。見つかったことで落胆したのか? いや、そうではないだろうと思った。パトリックの声は親しみに溢れ、親切で、ふるさとや救いを連想させただろうから。
いや、そうでもなかったか。
ゆっくりと、アンドリューは兄の方を振り向いた。
パトリックは、アンドリューが今にも走り出すのではないかと心配しながら道路を渡り、慎重に彼に近づいていった。彼が軍隊で体をきたえている間、パトリックはビールで腹をふくらまし続けていたのだ。―追いかけっこをしても、勝てるわけがない。
「アンドリュー」と彼はもう一度言った。「どうして―」
「なぜ来たの?」と彼は言った。「なんだってこんなところまで来たんだよ?」
唾(つば)のしぶきがパトリックの顔面にかかる。彼の吐く息は、腐ったコーヒーの臭いがした。―何時間も前に飲んだコーヒーが胃の中で発酵したかのような臭いだった。
「なぜって―」
「僕は逃げ出したかったんだ」
「ずいぶんと荒れた生活をしてるみたいじゃないか」と彼は言って、訴えかけるように弟を見つめた。
「僕が選んだ生活だからね」
「アンドリュー、しっかりしろ。何があったんだ?」
「あんたにはまったく関係ないだろ」と彼は怒鳴った。「僕が家を出た時はちっとも気にしなかったくせに、今になってなんで気にするんだよ?」
他の何人かが周りから様子を窺っていた。喧嘩が始まるんじゃないかと期待しているのだろう。
「そうだな、10分だけくれないか。どこかその辺でお茶でも飲もう」とパトリックは言った。アンドリューは拒否したそうに渋い顔をしている。彼が今にも逃げ出すのではないかとパトリックは再び思った。しかし、アンドリューは心のどこかで、「もう万事休すだ」と諦めていた。見つかってしまった以上、ちゃんと自分の言葉で説明しなければならない。
「いったい何だってんだよ」と彼は言った。
「頼むよ」
アンドリューはうなずきはしなかったが、同意してくれたようだった。二人は角を曲がったところにあった〈プレタ・マンジェ〉に入り、温かい紅茶を飲むことにした。パトリックは自分の時間をこれだけ割(さ)いて彼を探し出し、温かい飲み物を振る舞っている自分が、なんだか聖書に出てくる善きサマリア人のように思え、ひっそりとほくそ笑んだ。そして弟がいなくならないようにちらちらと視線を送りつつ、レジでお金を払った。
パトリックは罪悪感を感じていた。確かに、アンドリューが軍隊に入ることを決めた時、彼はあまり関心を寄せなかった。彼が家を出てキャンプ場へ行ってからは、ほとんど連絡も取らなかった。パトリックには自分の生活があり、自分の友人たちがいて、そちらに気を取られていたのだ。―家族は家族であり、それは誰にとってもそうであるように、特に努力をしなくても当たり前に自分の周りにあるものだと思っていたから。
積極的に関与しなかったとはいえ、俺が何かしたか? とパトリックは思った。アンドリューがひねくれ、人生の道を外してしまうほど悪いことを俺はしたか? 彼がこんな生活を選ばなければならなかったほど、俺たち家族が何をしたというのだろう?
パトリックが紅茶と砂糖の小袋を2つ手渡すと、アンドリューが「乾杯」と言った。
「何か必要なものはあるか...」と彼は言いかけたが、この種の質問をどう投げかければよいのかわからず、「つまり、何か食べたいものはあるか?」と言い換えた。
「大丈夫」
「そうか」
「さっきソーセージ・ロールを食べたばかりなんだ」と彼は言った。彼が昼間、温かい食べ物を買えるくらいの蓄えはあることをパトリックは理解した。
「それで」とパトリックは言った。「俺は...実は何を聞いていいのかわからないんだ」
「じゃあ、なんでここに来たんだよ?」
「うるせえ。推測してみろ、アンドリュー」
二人はしばし黙り込んでしまう。それぞれに紅茶を一口すすったが、まだ熱すぎて飲めたものではなかった。
「僕はドラッグはやってないよ。どうせ疑ってるんだろうから言っとくけど」とアンドリューが単刀直入に言った。「何度も誘われたよ。うんざりするほど何度もね。でもやらなかった」
「よかった...それはよかった」
「上から目線で言うなよ」
「わかった」とパトリックはその発言を遮るように食い気味に言った。「それで、何があったのか教えてくれ。軍隊に一時(いっとき)いたかと思えば、今度は野宿同然の生活をしてるなんて、いったいどういうわけだ? まだ誰にも言ってないんだろ? お金が全くないわけでもなさそうじゃないか? 寝る部屋だって」
アンドリューは今にも身を乗り出し、反撃したそうな顔をしている。パトリックは、カフェにいる他のお客たちが自分たちを見ていることに気づいた。おそらく、この浮浪者が暴れ出すのではないかと心配しているのだろう。
「僕は出て行った」と彼がようやく口を開いた。落ち着きはらった口調だった。「もううんざりだと思ったから出て行ったんだ」
「自分から空挺部隊を去ったわけじゃないんだろ、アンドリュー」
「まあ、自分からだよ」
パトリックはそれが事実ではないとわかった。部分的に見ればそうかもしれないが、それが話の全体像ではないことは知れたが、彼は追及しないことにした。
弟が任務を外されたことを知るまでには、それからさらに1週間を要した。直近の遠征から戻ってきて、主に精神面の評価が下された結果、長期休暇を取るように促されたらしい。アンドリューは、そう告げてきた将校の執務室をめちゃくちゃに荒らし、さらに自分の部屋もめちゃめちゃにして、兵舎を後にした。任務を完遂する半年前に、彼は除隊されたのだ。
「ていうか、なんで家に帰ってこなかったんだよ?」
「心の準備ができてなかったから。軍隊に入って、ランクを一つも上げられずに、何の称号も得られずに脱落したなんて、恥ずかしくて伝えたくなかったし。それに軍隊は僕の人生計画そのものだったから、それをポシャったなんて」
「それがどうした?」とパトリックは言った。「そんなどうでもいいことで、ちょっと外で寝てみようかなんて思ったのか? そしたら他に新たな道が開けるかもしれないってか?」
「外で寝たことはないよ」と彼はピシャリと言い返した。「ユースホステルや避難所を利用してるんだ。大抵ベッドはある」
「それがない時は?」
「いつもあるよ」と彼は言った。パトリックはこれも嘘だとわかったが、やはり無理に追及しないことにした。
それから二人は数分の間じっと黙っていた。窓の外に目をやると、絶え間なく人々が行き交っている。
沈黙を破ったのはパトリックだった。
「それで、どうしてほしいんだ?」
「まあ、理想を言えば、僕を2、3ヶ月放っておいてほしい。もう少し準備ができるまで」と彼は言った。
パトリックはそれを聞いて、不当に重い判決を受けたような気分になった。何も悪いことをしていないのに、出禁をくらった気分だった。「しかし、そうそう理想通りにはいかないだろ」
「キャンピングカーがあるんだ」と彼は、逆に頼み込むように言った。「俺が南海岸まで送ってやる。少しの間、俺のところに泊まってもいい。それか、どこかに部屋を見つける。誰にもわからないようにするから」
「どうやって―」
「健康診断で不合格になったとか、そういうことにしよう。それでお前が俺に、迎えに来てくれと電話した。そうして俺はここに来て、お前を車に乗せて帰る。そうすれば、お前が話したくないことは話さなくて済むし、みんなもお前が軍隊を辞めたと知れば、安心するさ」
「そうかな」
「アンドリュー、わかってると思うけど、息子が軍隊に入ってあちこち飛び回ってるっていうのは、親としては気が気ではないんだ。それはともかく、もっと重要なのは、お前が話したいことだけ話して、言いたくないことは言わなくていいってことだ。お金が必要なら、俺と一緒に仕事をすればいい。実は仕事が次々に回ってきて、一人では全部こなせない状態なんだ」
パトリックはアンドリューをひと睨みして、それはお前のせいだからな、と無言の圧力をかけた。弟を探し回るために仕事をキャンセルしたつけが回っているんだぞ、と。
アンドリューはしばらく思案するように窓の外の上空を眺めていたが、「いいよ」と言った。「でも、すぐに君の家は出て、自分の部屋を見つけるから。それでいい? そうしたら、みんなに僕が戻ってきたことを伝えよう」
「好きにすればいいさ」とパトリックは言った。アンドリューの顔に微笑みが浮かんだような気がした。パトリックはそれを自分への感謝の印として捉えたが、再び、気のせいかもしれないな、と思い直した。「角を曲がったところに駐車してあるんだ」と彼は言って、二人は一緒にカフェを出ると、昔のように並んで車まで歩き、ブライトンまで戻っていった。
「彼のことを考えてるの?」とカースティが言った。
パトリックはキャンピングカーの窓から外を見た。漆黒の闇が視界を遮り、遠くまで見えない。一組の散策者のテントだけが、ぼんやりと光を発している。彼は今どこにいるのだろう? とパトリックは考えていた。2度目の失踪は何の手掛かりも残してくれなかった。アンドリュー・カドガンを知っている者は皆、彼が残していった謎と疑問符の中で、首をかしげながら途方に暮れるしかなかったのだ。
「彼には時々会うわ」とジェシカが言った。「ロンドンにいるとね、あ、って思うことがあるのよ。彼にちょっとでも似てる人が目の前を横切ったりするとね、髪の色とか、歩き方とかを見て、もしかしたらって思う瞬間がしょっちゅうあるんだけど、でもそれってあれよね、他人の空似っていうか、脳のいたずらっていうか」
「あなたの言いたいことはわかるわ」とカースティも言った。「彼がいなくなって数年間は、ホームレスの人たちの中に彼と同じくらいの年齢の人はいないかって見て回ってたもの。念のためにね」
「そういう人たちに聞いてみたことはある? 彼を知ってるかどうか」
「一度か二度ね」
「もしかしてそのために、クリスマスに避難所でボランティアをしてたの?」
カースティはうなずきつつも、照れたように、はにかんだ。周りの人が思っているよりも、自分は利他的ではないことを少し恥じているようだった。一方、パトリックは、胸に秘めたまま打ち明けられずにいる秘密に身震いした。
家族のみんなは、アンドリューが軍隊を辞めた時に起こったことを半分も知らなかった。パトリック以外の家族が知っていることは、アンドリューは喘息(ぜんそく)のために健康診断で不適格となり、子供の頃からの夢だった仕事を続けることができなくなった、それだけだった。彼が兵舎を去る時、感情を爆発させ暴れたことも、ホームレスになったことも、パトリックがロンドン中を探し回ってようやく彼を見つけたことも、何も知らなかった。
パトリックは、いつになったら彼女たちに本当のことを話せるのだろうかと考えた。話せば少しは、彼女たちが今でも愛している弟について考える上で、何らかの手助けになるかもしれない。もっとも、彼が今どこにいるのか、誰といるのか、生きているのかどうかさえわからない状態は変わらないだろうけど。
「あなたはどうなの?」とジェシカに聞かれて、物思いに沈んでいたパトリックは、ハッと我に返った。
「毎日考えてるよ」と彼は言って、ドアのそばに置いてあったバックパックから財布を取り出した。「これを常に持ってるんだ」彼はくしゃくしゃになった写真を財布から引き抜くと、それをテーブルの上に置いた。
写真には、20代前半の若い男が写っていた。ライトブラウンの髪はスタイリングされ、無造作風に整えられていた。彼はロックバンド〈リバティーンズ〉のTシャツを着て、分厚い腕時計を革製のストラップで手首に巻き、ダークブルーのジーンズを穿いている。無精ひげを生やした顔には、満面の笑みが浮かんでいる。片手には半分ほど残っているビールのジョッキを持ち、ジョッキの縁にはライムがひと切れ刺さっている。パトリックはそれがどこで撮られたものかを覚えていた。―ブライトンの〈ホープ・アンド・ルーイン〉だ。ある新進気鋭のバンドを見るために、彼らはそのパブ兼ライブハウスに行ったのだ。ちなみに、そのバンドは「新進気鋭」の域を抜けることなく沈んでいったのだが、そこで、メルという名の、アンドリューのガールフレンドが撮った写真だった。
「これっていつ?」
「2009年の3月だよ」
「彼がいなくなる2ヶ月前ね」とジェシカが言うと、パトリックはうなずいた。
三人はもうしばらくの間、その写真を眺めていた。パトリックにとって、この写真は弟との思い出を呼び覚ますものだった。さらに、今では30代になっている彼の顔をこの写真をもとに推測し、道端で絶望を背負って座っている30代らしき男を見るたびに照らし合わせるのだった。
とはいえ、何週間も、時には何ヶ月も、この写真を見ることなく過ごすこともあった。その間、パトリックの頭の中のアンドリューは、昔の少年に戻るのだった。世界に明確な居場所を見つけられない寡黙(かもく)な少年、健康志向が強く、体力づくりには余念がないのに、スポーツには全く興味のない10代の少年、ジェリー・カドガンの息子であろうと頑張ったが、失敗した少年。そして2009年のある日、彼は、もう二度と戻らない、と宣言し、家族のもとを去っていった。
「彼が来なかったことに驚いてるの? つまりパパの葬式に」とカースティが言った。
「ママの時にも来なかったじゃない」とジェシカが言った。「自分が死んじゃったことにも気づいてないんじゃない? そうじゃなかったら...」
「よせよ」とパトリックが言った。
「時々思うのよ」と彼女は続けた。「彼は今でも、私たちのことを考えたりするのかな?」
「やめろって言っただろ。そんなこと、誰のためにもならないよ。こうやって憶測を話してたって、なんにもならない」
ジェシカはコップに残っていたウイスキーを飲み干すと、「そうね、あなたの言う通り。それにもう遅いし、明日すっきりした頭で、もっと話し合いましょ」
そう言うと、彼女はテーブルに両手をつき、席を立った。それから、キャンピングカーの後部にある小さなバスルームへと向かった。
今は凍えるような寒さが身に染みていた。骨がきしむような寒さに、昔の家族旅行でもこんな経験をしたことがあるな、とパトリックは思い出していた。家族みんなでキャンピングカーの中で眠った夜、じめじめと湿気を含んだ空気に包まれ、痛みをともなう寒さに耐(た)えていた。キャンピングカーの中の空気はいつまで経ってもカラッと乾くことなく、快適さとは無縁だった。
彼はウイスキーを一口飲んだ。この寒さの中では、体内に流れ込んだその熱さが、異様に際立っていた。
「そんなにいいものなの?」とカースティが聞いた。「私はウイスキーのことは、よく知らないっていうか、パパが教えてくれたことしか知らないし。私には、なんかヒリヒリ胸焼けするような味しかしないんだけど」
「ああ、うまいよ。あまりのめり込みすぎると、親父みたいにろくなことにはならないけどな」
シャワーの音が止まり、ジェシカが唾を吐いた音がして、バスルームのドアが開いた。そして、再びバタンと閉まる音が聞こえてから、パトリックは振り返ってそちらを見た。彼女が二段ベッドの下段に入り込み、カーテンを閉めているところだった。
彼とカースティはお互いに顔を見合わせた。お互いが、ジェシカが寝ちゃった今こそ、彼女について話しましょう、と言っているかのようだった。
「私もシャワーを浴びようかしら」と彼女は笑顔で言った。「おやすみ」
「おやすみ」と彼も言った。
彼女がシャワーを浴びている間、パトリックはウイスキーをケースに戻し、それをアルバムと一緒に再び釣り具箱に入れた。そして、アンドリューの写真を手に取ると、最後にもう一度彼の顔を見つめてから、財布の中に滑り込ませた。
~~~
〔チャプター 4(の後半)の感想〕
一人キャンプが流行っているらしい!←情報が2周くらい遅っ!! 山の中に住んでるの?!爆笑
テレビを見なくなってから(寝る間際にYouTubeは見てるけど)、情報の荷が下りたというか、心なしか翻訳ペースも速くなった(1日で進む量も多くなった)気がする。←今の若者は思春期からすでにテレビは見てないから!←だから今の若者は凄いのか!!←謎の解釈!笑
それにしても、キャンプしてる人が焼いたり炊(た)いたりして食べてるものって、お店とかより美味しそうに思えるのはなぜだろう?←ジャック・ロンドンの『荒野の叫び』でも読んで、それについて論文を書け!
ウッドストックっていう、スヌーピーの相棒の黄色い鳥じゃなくて、野外の音楽イベントがあって(今もあるのかもしれないけど)、←行ったことあるの??←いや(笑)、昔CNNか何かで見て、3日くらいキャンプしながら音楽を聴くんだー! と思って、行きたいなー! と思っただけ...f^_^;←じゃあ、書くなよ!!笑←キャンプと音楽の組み合わせが絶妙だなー! と思って🐤ピヨピヨ♬
「圏外」だと諦めがつくというか、どうあがいても自分にはどうしようもないから、逆にほっとするというか、解き放たれた感が半端ないのかもしれませんね。ひと時の解放感こそ必要🐤チュンチュン♬
藍の人生にもリア充への兆しが、ようやく遥か彼方に、
オアシスのように、あるいは蜃気楼(逃げ水)のように、
キラッと見えてきて、
リアルが若干忙しくなってきたので、
現在超~スローペースで進行中です。笑
数週間ぶりに翻訳して、なまりつつあった頭が、油を注がれたぜんまい仕掛けみたいに、すこぶる気持ちいい。
楽器でも将棋でもなんでもそうだと思うけど、毎日やることが一番の秘訣なんだね!
クローズアップとズームインは何が違うかというと、クローズアップは実際に歩いて対象に近づいていって接写すること。対して、ズームインは立ち位置はそのままで、カメラのズーム機能を使って被写体を撮影すること。藍が好きなのはクローズアップで、藍は昔から、河野英喜さんとか、会田なんとかさんとかのカメラマンに、「いいな~♡」と目をハートにしながら憧れていて、←全部グラビアのカメラマンじゃねーかよ!!爆笑
若い頃、翻訳の勉強をしている時、(←今もだろ?笑←僕って今も若いよね!笑←そこじゃねーよ!笑)がっつり参考にしていた小説が、弟か幼馴染を探し求める話だったので、なんだか懐かしさに包まれている。やっぱり(人生という)暇をつぶすには、片手に小説、片手にコーヒーだね☕←そこは紅茶じゃねーのかよ!笑
~~~
パート 2
チャプター 5
ボウランドの森
ジェシカ
雨が降っていた。そのせいか、思ったよりも早く目覚めてしまった。ジェシカの戦略は、この旅をできるだけ長く寝て過ごせば、体感的にあっという間に旅が終わってくれる、というものだった。しかし朝の6時、彼女は寝袋の中で丸くなりながら、キャンピングカーの屋根を小刻みに叩く雨音を聞いていた。
彼女は眠りの浅い人だった。普段から階段のきしむ音や、夫の咳、フクロウのホーホーという鳴き声などでも、すぐに目が覚めてしまうのだ。数年前に診てもらったセラピストによると、それは彼女の頭の中で常に物事がぐるぐると回っているからだという。
「花屋の経営、家族。子供の学校のことまで、ありとあらゆることを考えているんでしょうから、そうなっても全然不思議ではありませんよ」
彼女としては、自分が重要な存在で毎日が忙しいと言われているようで、悪い気はしなかったのだが、自分が実はどんな状況にあっても自ら心配事を作り出してしまうタイプだというセラピストの指摘だけは信じなかった。信じたくない部分は信じない、それが彼女の流儀なのだ。
ジェシカは自分のスマホをチェックした。メッセージは届いていない。というか、電波自体が届いていない。彼女はタイマーアプリを開き、6時43分、6時48分、6時56分、7時8分に設定してあるアラームをスクロールして飛ばし、7時12分に設定しておいたアラームをオフにした。
二日酔いで少し頭がくらくらしていた。普通の赤ワイン4杯と高級なウイスキーを2杯、これは彼女が1週間で飲むお酒の量を超えていたし、ましてや1晩で飲む量ではなかった。特にウイスキーに関しては、カクテルを作るときにやむを得ず使う場合を除いて、彼女は手を出してこなかったのだ。夫のダンはウイスキーが好きだった。―彼女の父親とダンが、絆を深めることができる数少ない共通の趣味がウイスキーだった。それ以外は、あまり話が合わないようだった。ジェリーはサッカーが好きで、対してダンはラグビー好きだったし、ダンはジェリーの仕事、建築業のことを全く理解していなかった。そもそもダンには自営業者に対して偏見があり、彼らは自分のようなエリートをねたみ、嫌っているんだと思い込んでいた。―ジェシカはウイスキーよりも、上等な冷えたウォッカにトニックを少し加えたものを好んで飲んだ。
寝袋の内側の毛が口の中に入ったような嫌な味がして、それを消そうと彼女は水筒に手を伸ばした。その時、車内の前方、リビングエリアで梯子(はしご)のきしむ音がした。パトリックが起きてきて、梯子を降りたのだとわかったが、彼女はまだ、カーテンを開けて彼に話しかけたいとは思わなかった。昨晩は、話が奇妙な方向へ逸(そ)れ、そのままお開きになってしまった。アンドリューの話が持ち上がるたびに、いつもそうなってしまうのだ。解けない謎をそのまま放置したみたいに。
あまり弟や妹と比較したくはないのだが、ジェシカとしては、アンドリューが失踪したことで、一番苦労したのは自分だと思っていた。その時、彼女にはすでに子供がいた。―当時3歳だったマックスは、自分を取り巻く世界をなんとなく認識してきた頃だった。誰が自分にとって重要な役割を果たしているのかを理解し、その中の一人がいなくなったことにも気づくことができた。
それからの1年間は、家族の行事などで親戚が集まると、「アンドリューおじさんは来るの?」「アンドリューおじさんは次は来るの?」「アンドリューおじさんはどこにいるの?」といった質問が、マックスの口からぽんぽん飛び出す有り様だった。母親のスーがその場にいた場合、彼女は頽(くずお)れるように顔を覆い、奥へ引っ込んでしまった。その後、「おばあちゃんはどこか悪いの?」とマックスが聞くのだった。
マックスがアンドリューと交流したことはほとんどなかったのだが、家族の集まりになると、彼は周囲の大人たちの顔を見回し、いつもの叔父や叔母の集まりとは違うことをすぐに見抜いた。もう少し年長になっていれば、これは言わない方がいいな、と自制も働くのだろうが、そのフィルターすらない年頃だったのだ。
結局、ジェシカが説明を余儀なくされた。
「アンドリューおじさんはもう来ないのよ。おじさんは家を出て行くことにしたの」と彼女は言った。少しの間だけね、と付け加えようかとも悩んだが、付け加えないことにした。マックスの期待を高めないためであると同時に、自分の期待を高めないためでもあった。
「どこに行ったの? パパみたいにロンドン?」
「それがわからないのよ。でも彼は行ってしまったの。私たちは彼が元気でいることを祈るしかないのよ」
というのが、何度も繰り返された会話だった。当時を振り返ると、20回以上はこれに類するやり取りを経験し、数年後には、マックスの口からさらに鋭い質問が飛び出した。
「アンドリューおじさんは死んだの?」と彼が聞いてきたのだ。その頃、友達の祖母が亡くなったことで、彼は死について学んだばかりだった。その友達はクラスのみんなに、死と死後の世界について、両親からの受け売りらしいが、宗教めいた話を聞かせていたそうだ。空に昇った祖母が、去年死んだモルモットと一緒に僕たちを見下ろしている、という昔からよくある話だった。生きている間モルモットが常に震えていたのは、死におびえていたからだ、とも言ったらしい。
「そうじゃないわ」と、ジェシカはショックで涙を浮かべながら言った。
「どこかに行っちゃっただけ?」
「そうよ」と彼女は言った。彼女は弟が生きていることを確信していたが、もし弟が死んでしまっても、それを知る術はないだろうとも感じていた。
「でも、ロンドンじゃないんだよね」
「違うわ、マックス」
「じゃあ、どこか違う場所なんだね」
「そうよ」
それを聞いて、マックスはにこやかな表情になり、その会話に興味を失ったらしく、床にぺたりと座ると、木製の車を押して、木製の道路の上を走らせ始めた。
「じゃあ、もうすぐ彼に会えるね」
ジェシカは、彼の発言を正さなかった。そこで何か言ってしまったら、また会話の出発地点に戻り、初めから同じやり取りを繰り返さなければならないとわかったからだ。彼女は2階のトイレへ急いで向かうと、閉まったままの便座の上に座って、泣いた。
そのうちに、息子は何も聞いてこなくなった。あるいは、どうでもよくなったのかもしれない。とはいえ、家族の一員が自分たちのもとを去った、という一大事を、わかりやすい言葉で何度も説明しなければならなかったことは後を引き、ジェシカの精神を弱らせた。「私はどうすればよかったのか?」「どうすれば彼の失踪を防ぐことができたのか?」という内なる声が、それ以来絶え間なく聞こえ続けている。
他の二人はこのようなことを経験していない。経験していない以上、それがどのようなものなのかを知ることはできない。
ジェシカは顔のすぐ隣にある小さなカーテンを開けて外を眺めようとした。プラスチック製の窓ガラスには雨のしずくがつき、内側には結露ができていて、白くぼやけている。彼女はそれを手でこすって視界を良くした。
外は明るくなり始めていたが、空はどんよりと灰色の雲に覆われていた。管理されたキャンプ場というよりは、野原を一応囲っただけの敷地には、何人か早起きの人たちがいて、小さなテントの前で輪になり、ブリキのマグカップで温かそうな飲み物を飲んでいた。彼らは皆、目立つ色合いの登山用ウェアを着込んでいる。朝食を済ませたら、さっそく山歩きを始める構えだ。敷地を取り囲む生垣には鳥が飛び交い、その向こうには、緑が色あせて茶色っぽくなった草原がどこまでも広がっていた。
彼女は家での日常を考えた。朝、太陽光を模(も)してだんだんと光が増す目覚まし時計で目覚め、形状記憶マットレスから起き上がる。階段を下りると、まずは美味しいコーヒーを飲み、子供たちにお粥(かゆ)などの朝食を作る。子供たちを学校まで送り届けたのち、彼女は花屋の仕事を開始する。奥のオフィスで事務処理をしながらラジオを聴き、その間、表では店員の女の子たちがお客さんの注文に合わせて、花を選(え)り抜き、花束を作って売っている。この花屋は曜日に関係なく安定した売り上げを誇っているようで、いつでも活気づいていた。彼女は仕事が終わったら急いで家に帰り、ワインを飲みながら夕食を作って、ダンを待つ。そんな日々に思いを馳せていた。
彼女は自分の生活を気に入っていた。それを邪魔したこの旅が、いまだに癪(しゃく)に障る。
「正しいことをするのは、必ずしも簡単ではないよ」というダンの言葉が思い出される。もし彼が私と別れることになったら、まさにこういうことを言われるのではないか、といつも思う。
「わかってる。けど、気まずさに耐えられなくなるのよ。みんなが私に遠慮してさぐりさぐりで、まるで腫れ物に触るような扱いなんだもの」
「じゃあ、気まずさなんて感じてないで、思ってることを言えばいい」
彼女は再びスマホをチェックした。まだ何も届いてない。電波は近くの町までは来てるんだろうけど、ここまでは届かない。昨夜みたいに一瞬風向きが良くなって、電波が風に乗ってやって来てくれればいいのに。
ジェシカは素早く寝袋のジッパーを開け、カーテンも開けてベッドから出た。すでにパトリックと、カースティも起きていた。パトリックは自分の紅茶を飲みながら、片手で私にも紅茶の入ったマグカップを差し出してきた。
この人たちは私のことを何にもわかってないんだわ、と彼女は思った。
パトリック
「よく眠れた?」と彼は、髪をかきあげているジェシカに聞いた。昼間の彼女は念入りに髪型に手を入れているのだが、彼には、わざとぼさぼさ風に崩したヘアスタイルと、寝起きのぼさぼさの違いがわからなかった。
「まあまあね」と彼女は言いながら、彼から受け取った紅茶をテーブルに置き、コーヒードリッパーでコーヒーを入れ始めた。コーヒードリッパーが、キャンプの不自由さにどっぷり浸かれない彼女の妥協点なのだろう、と彼は想像した。もし彼女に判断をゆだねていたら、エスプレッソマシンごと持ってきた可能性すらある。4種類のコーヒー豆を選択できる豪華なやつだ。「雨音で目が覚めたのよ」
「私はそれが逆に落ち着かせてくれたわ。ホワイトノイズか何かみたいで、心地よかったじゃない」とカースティが言った。
「うぇ、私は大っ嫌い」
「それじゃ、どのくらい前から起きてたの?」
「30分前くらいかな」と彼女は言いながら、コーヒーの粉が入った小さな三角形の紙の中にお湯を注いだ。
「あなたも出てくるべきだったわね。外でちょっとしたヨガをやってたのよ」とカースティが言った。
「アウトドアでヨガをするにはちょっと寒くない?」
「ピリッと寒かったけど、かえって身が引き締まったし、屋外でするとすっきりするのよ。とっても静かだし、鳥の鳴き声を聞きながら、草の香りをかいで、新鮮な空気を吸い込む。あそこのコテージから、まきを燃やした煙のいい匂いがしてくるのよ」と、彼女は昨日会った管理人が住んでいる場所を指差した。
「ああ、忘れてたわ」とジェシカが言った。「あなたは秋人(あきびと)タイプだったわね?」
「秋人タイプって?」
「わかるでしょ。葉っぱの色とか、マフラーとか、そういうのが大好きなんでしょ。そういえば、あなたは昔からそうだった。10月になった途端、待ってましたと言わんばかりに、あなたは頭のてっぺんにボンボンが付いた毛糸の帽子をかぶって、スターバックスの赤いカップを片手に外を歩き回ってたわ。まだどんなに暖かくてもね」
「それの何がいけないの?」とカースティが言った。朝っぱらから人格を攻撃されて、ちょっと面食らっているようだった。
「とにかく、私はヨガなんてできない」とジェシカはきっぱりと言った。生き方の選択というよりは、物理的に不可能であるかのような言い方だった。
「どういうこと? ただのストレッチとリラクゼーションよ」
「タムと一緒に一度やってみたんだけど、私には、なんにも集中できなかった。はい、意識を集中させて、深呼吸~! とかって言われても、私は一週間の食事の献立(こんだて)をどうしようかって考えてたわ」彼女はコーヒーを一口飲んでから、続けた。「私には考えなくちゃいけないことが色々ありすぎて、今を生きるとか、今この瞬間に集中、なんてできないのよ」
「それはまあ―」
「ちょっと思ったんだけど」とパトリックが口を挟んだ。二人の間に、沸騰前のぐつぐつと煮え出した、不穏な空気を読み取ったのだ。ジェシカとカースティが、お互いのライフスタイルや様々な選択を批判し出した。いつものパターンだ。ジェシカは自分がいかに忙しく、重要な人物であるかをそれとなく、あるいはあからさまに伝えようとし、一方カースティは、ベジタリアン、ヨガ、マインドフルネス、体型が太ってたって綺麗という肯定主義、潜在能力の開花、などの「聞こえが良い」ライフスタイルを強調し、自分は全体として健全な生活を送っていると主張する。結局、どちらかがキレる。それから、パトリックがどちらかの肩を持つようなことを言って、三方向に入り乱れた言い争いが勃発するのだ。これらすべてが、わずか15分ほどで起こってしまう。
「何?」とジェシカが言った。
「なぜアイラ島なんだろう?」とパトリックは言った。「それに、俺たちが実際にこの旅に出かけるって、どうして彼はわかったんだろう?」
「サディズムね」とジェシカが言った。「愛する娘たちをこんな寒い、イワシの缶詰みたいな中に押し込んで、来る日も来る日も昔の写真、昔の自分たちの姿を見させるなんて、どんな男なのよ?」
「ジェシ」とカースティが言った。
パトリックはハハッと、無理に笑い声を発した。ジェシカの言い草を聞いて、この話を持ち出すことに不安を覚えた。しかし彼は昨夜、眠りにつくまでの1時間、もやもやと煮え切らない頭で、このことを考え続けていたのだ。
最初、アイラ島は、この旅の目的地として奇妙な場所に思えた。ジェリー・カドガンとヘブリディーズ諸島のその島を結びつけるものは、休暇に数回訪れた場所だということ、それから彼がウイスキー好きだという理由しかないはずだ。それなのになぜ、彼はカーディガン湾やダーウェント湖などではなく、アイラ島に遺灰を撒いてくれ、と言ったのだろうか? 他にも、彼と彼の妻が好んで訪れていた場所はあったはずだし、そもそも、実家から800メートルも歩けば、何十年もの間、毎日のように散歩していた、小さな丸石が敷き詰められた海岸があるではないか。
もしかしたら、その島がアンドリューと関係しているのではないか、という考えがぬぐいきれなかった。
ジェリーが時々、私立探偵について検索していたことは家族の誰もが知っていた。私立探偵の多くは、元警察官とか元軍人で、疑り深い男からの依頼で、妻の浮気の確証をつかんだり、あるいは逆に、孤独や不安に駆られた妻からの依頼で、結婚したことを後悔しているクソ夫について調べたりして、小銭を稼いでいるのだった。基本的に、不安は杞憂でしたよ、という結果よりも、やっぱりあいつ浮気してましたよ、という報告の方がはるかに喜ばれるらしい。そしてカドガン家では、そんなジェリーを妻のスーが、やめておきなさい、と説得するのが常だった。ジェシカ、カースティ、パトリックは、母親から、父親がしようとしていたことを、まったく呆れちゃうわ、という前置きとともに聞かされていた。
「もしお父さんがあなたたちにそんな話をしてきたら、それは良くない考えだって言ってちょうだいね」と彼女はいつも言っていた。彼女は確信していたのだ。そんな裏から手を回すみたいな手段でアンドリューを見つけたとしても、彼をさらに遠ざけるだけだと。もし彼が、いつか家族のもとに戻るとしたら、それは彼自身の側に何らかの変化があった時であり、それはおそらく、何十年もかかってやっと起こる変化なのだろう。
けれども、妻を失い、自分自身の時間も残り少なくなってきたジェリーが、意を決してそれを実行したのだろうか? 彼はついに、しかめっ面した私立探偵にお金を払って、自分を捨てた息子捜しに乗り出したのかもしれない。息子が失踪した時、ジェリーはつゆほども想像しなかった形で心を壊されたのだ。それくらいしてもおかしくはない。
「君はどう思う?」と、パトリックはカースティに聞いた。「この数年、親父の一番近くにいたのは君だ。アイラ島のこととか、何も言ってなかったか?」
「いいえ、でも彼の考えを理解するのは難しくないわ。アイラ島はすごく遠いじゃない、そうすると、道中こうしてたくさん話をしないといけない。きっとそれが理由よ。彼は私たちの関係がぎくしゃくしていたことを、いつも気にしていたわ。時々、あなたたちのどちらかと話をしたか?って聞いてきて、私が話してないって答えると、残念そうな顔で、いいかって、仲たがいの解決策を教えてくれた。『いいか、人生は一周しかない。会う人会う人に親切にしておかないと、後からじゃ遅いんだ』彼女は声を1オクターブ下げて、親父の真似をした。「会うたびに同じことを言ってたわ」
「私たちはお互いに親切にしてるじゃない」とジェシカが言った。
「一口に親切と言っても、そこに真心がこもってないとダメなのよ。真心は家族である証だけど、単に親切っていうのは、コールセンターにかかってきた電話で、お客さんと話す時の態度でしょ」
「それはそうだ。かなり納得」とパトリックは言った。「でも、なんでよりによってアイラ島なんだ?」
「彼はそこが好きだったのよ。あのウイスキーだってそこで作られたんでしょ? よく知らないけど」
「さっき言ったように、彼はサディストなの」とジェシカが言った。今度はちょっとにやけている。
「あるいは、何か隠された動機があるのか」と、パトリックは顎に人差し指と親指を当てて言った。
カースティ
「やめて」と彼女はきっぱり言った。「何が言いたいのかわかるわ。実はね、私たちがこの旅に出発する前、私もそう思って自分で調べてみたのよ。でも、何の手掛かりも見つからなかった。あなたも期待しない方がいいわ」
パトリックが意気消沈するように、うなだれてしまった。彼には珍しい表情だった。彼はいつでも楽観主義で、明るい面を見なさい、親切にしなさい、幸せでいなさい、という父親のアドバイスに最も忠実に従ってきた。彼は昔から、どんなに救いようのない暗い状況に陥っても、その良い面を探し求めることで、そんな状況を明るく笑い飛ばしてきたのだ。パトリックが財布に弟の写真を入れていても不思議ではなかったし、弟の写真を見ては、弟を思い出すとともに、自分自身の存在も確かめているんでしょう、と彼女は思った。彼は弟が帰ってくるという希望を、3人の中で一番捨てていない人だった。
カースティにはアイラ島の謎はわからなかった。そして、パトリックの希望をいきなり打ち砕いたことを、少し残酷だったかもしれないと感じた。けど、その方がよかったのだ。
釣り具箱を開けて、父からの手紙を読んだ日の翌日、カースティは自分でもそのことを考えていた。彼女はしばらく試していなかった言葉を、Google検索に入力した。「アンドリュー・カドガン」、「アンドリュー・カドガン 名前変更」、「アンドリュー・カドガン 行方不明者」久しぶりに彼のFacebookも開いてみた。数年前に見た時と同じページが、少し古びた印象を纏(まと)い、そのまま残っていた。更新が続いている他の人たちのページと比べると、彼のページだけ時が止まっているようだった。最後の投稿は失踪の6週間前のもので、2009年の日付もそのままだ。
カドガン・ファミリー・建築士事務所ではご依頼を募集中です。
増築、修理、建築、造園、どんな小さな仕事でも引き受けます。
お見積もりはお電話でどうぞ。
その下には電話番号と、アンドリューが会社の経営を引き継いだ時に、高すぎるデザイン料を支払って作った会社のロゴマークが貼られていた。
その後、カースティは「アンドリュー・カドガン アイラ島」、「写真家 アンドリュー・カドガン」という検索ワードも、(彼が、趣味だった写真を仕事にして、新たな人生を歩み始めたことを願いつつ)試してみた。さらに、「アイラ島 新参者」とも打ってみた。小さい島だろうから、島のコミュニティはかなり緊密で、新しい人が入ってくれば、地元紙の見出しを飾るほどの大ごとかもしれないと期待したのだ。―が、何もヒットしなかった。
次第に、希望が現実に取って代わられ、彼女は立ち往生した。どうやらパトリックは思っただけで、同じことはやらなかったようだ。
「わかってるよ」と、1分ほどの沈黙の後、彼は言った。「わかってるけど、ただ、あの頃親父は、探偵を雇うとか、そんなことを言ってたじゃないか―」
「彼は実行には移さなかったのよ、パトリック。私を信じて。彼は決してそうしなかった。パパはアンドリューの居場所を知らないまま死んだの。そして私達もそうなるんでしょうね」
「でも、どうしてわかるの?」とジェシカが聞いた。
カースティはパトリックを熱心に観察していたので、姉もそこにいることをほとんど忘れかけていた。
「だって、彼がそんなことをしていれば、絶対私に話してくれたわ、ジェシ。私は何年もずっと、一日おきに彼に会いに行っていたのよ。彼が誰かを雇ったりしたら、そんなのわかるに決まってるじゃない。もし彼がアンドリューを見つけのなら、私が知らないはずがないわ。彼が誰かと連絡を取っていたとしても、私は気づくでしょうね。こんな...的外れな議論をしていても仕方ないわ」と言って、彼女は適切な言葉を探した。自分たちが感じている、弟に対する自責の念や罪悪感、羞恥心などの感情を束ねて一つにして、投げ捨てられるような言葉を。すなわち、それらすべての中心を成す本質を探していた。
「じゃあ、私たちはどうすればいいのよ?」
「わからないわ、ジェシ。正直、私はお手上げ状態。彼がヘブリディーズ諸島のどこかのビーチに劇的に立っていて、私たちを待っていてくれる、なんて期待したって無駄だし、そもそも、私たちは彼が出て行った理由と折り合いをつけなきゃいけないのよ。そんなこと考えたって意味ないでしょ」
カースティはマグカップをシンクに投げ入れた。硬い金属製のたらいに当たった衝撃で、取っ手の部分が割れてしまった。
「いけない」と彼女は言って、それを拾い上げると、ゴミ箱に捨てた。「ほら、そろそろ出発しなくちゃでしょ。ジェシ、今度はあなたが運転する番よ。さあ、もう出るわよ、いい?」
~~~
〔チャプター 5の感想〕
パトリックはトムと違って、結構健全なんだよね。
藍はこのストーリーの中では、ジェシカに近いかなと思う。藍も周りから腫れ物に触るような扱いを受けるし、誰も自分のことをわかってくれない感にも、しょっちゅう苛まれている...😿
あと、藍もコーヒー好きだし☕←君は好きを通り越して「中毒」だよ!笑←「コーヒーくれ~~!!」って? まあ、コーヒーならそれでもいいじゃない!笑
出た。朝からヨガパターン! ジョン・アップダイクの『キリスト教徒のルームメイトたち』を訳して以来、幾度となく登場したヨガ好きキャラ! 実は、インドア派の藍の淡い夢でもあって、朝起きたら何よりも真っ先に、恋人と並んで朝陽を浴びながらヨガしたい!! ストレッチでもいいよ🐱(それが叶わないから、ツイキャスでヨガしてる人を見ながら、インドアで毎日ヨガってる...😻)←それは書くな!!!笑笑
それは冗談だけど、カースティは海辺を走って帰ってたこともあったし、アウトドア派なんだよね。そしてパトリックの立ち位置が微妙で、二人の姉妹の間で、どっちつかずにふらふらしながら、火消し役に徹してる感じかな...🌼🦋🌻
生き方の選択(a life choice)とか、ライフスタイルや選択(lifestyle and choices)という言葉が出てきたんだけど、藍の場合(In the case of Ai)、生き方を自分で選択していると言えるのかどうか微妙...🙀
というのも、藍も(おっさんのくせに、笑)音楽のサブスクリプションに入って、定額でいろんな音楽を聴いているんだけど、「あなたへのおすすめ曲」とか、謎の判断で勝手におすすめされた曲を聴いているわけで、自分で選んでいるのかどうか、微妙...🙀💦
(こいつにはこれをあてがっとけばいいってか? と思ったら、僕好みのいい曲じゃねーかよ♪爆笑)
今もそうかもしれないけど、藍が10代の後半の頃は、「英文速読」ということが、(予備校講師などによって)さかんに叫ばれた時代だったんですよ。速く読むことが最善、という主義なんだけど、そのマインドにどっぷりと浸かっていたから、いまだにその志向がぬぐいきれなくて、ふと気づくと、無意識で目を高速に走らせ、ダーーッてかなり先まで読み進めている自分がいるから、いつも「ゆっくり、ゆっくり、味わって」って、自分に言い聞かせながら訳しています。
いつしかそれが口癖になっちゃって、「ゆっくり、ゆっくり」って、会う人会う人につい言ってしまい、怪訝な顔をされます。笑
季節は合わせたわけではないんだけど、ちょうど年末のこの時期の数年前に、三人はキャンピングカーの旅をしていたのかと思うと、朝のピリッと肌を刺すような寒さだけでなく、キャンプ場というよりは草原の、寒々とした景色さえも目に見えるようで、シンクロ率がぐっと高まる🎅
本当に寒い季節に「寒い」と書くのと、夏の暑いさなかに「寒い」と書くのとでは、伝わり方が若干異なる、と藍は信じている。たとえば、10年後とかに読み返した時に、目に見えて違ってくると...🕵
~~~
チャプター 6
スコティッシュ・ボーダーズ
パトリック
もうすぐ正午になる頃、ジェシカが運転する車は、英語とゲール語で〈スコットランドへようこそ〉というメッセージが書かれた巨大な看板の前を通り過ぎた。青地に白の十字架が描かれた国旗も大きく掲げられている。パトリックは、他の二人のどちらかがそれについて何か言うのを待っていた。もし自分が運転していたら、ちょうど国境を越える時に『スコットランドの花』でも流すところだ。
しかし誰も何も言わなかった。看板に気づいてさえいないようだ。それなりに感慨深い瞬間ではあるはずなのに、とパトリックは思った。父親の遺骨をまくことになる国へ入ろうとしているのだから。たとえその遺骨は、カモメか何かの海鳥につままれる運命だとしても。
まだ何時間も車を走らせなければならないことを考えると気が滅入って、それどころではないのかもしれない。目的の島へ渡る船に乗る波止場までには、トロサックスやローモンド湖などを越えて、まだまだ深い田園地帯を抜けて進まなければならない。
彼らは着実に北へ進んで行った。湖水地方の丘が広がる美しい景観を片側に眺めつつ、反対側には国立公園の外縁部を横目に、それぞれが黙り込んでいた。時折、車が坂道を登り切ると、そこには、イギリスが誇る素晴らしい絶景が広がっていて、自然と目が広がった。ジェシの負担を軽減しようと、代わりにパトリックが運転していた時、一度彼はヒヤッとした。下り坂でややスピードを出しすぎてしまい、あやうくキャンピングカーが横転し、中央分離帯に突っ込むところだったのだ。しかしその時でさえ、誰も何も言わなかった。沈黙を破ったのはパトリックの一言で、「〈テバイ〉のサービスエリアだ」と彼は窓の外を指さして、つい口走っていた。独自のシェフがいて、店内で調理していることで有名なサービスエリアだった。カフェもチェーン店ではなく、独自のものが入っている。
もちろん、彼女たちが黙っている理由はわかっていた。彼女たちに少しでも、彼のような気質があるとすれば、彼女たちも弟のことを考え、弟の思い出に浸っているのだろう。ちょうど10年前、弟は家族の一員ではなくなることを選び、カドガン家の形を永遠に変えてしまった。そのことについて、あれこれ思いを馳せているのだろう。
カースティとジェシカはおそらく、彼が失踪する前に、それを食い止めるために自分たちができたかもしれないことを考え、彼がいなくなった後、どうやって気持ちを整理し、彼の不在を受け入れてきたかを振り返り、その後、弟捜しに迷走した日々を思い返しているのだ、とパトリックは思った。まさに自分がそうしていたように。
アンドリューの失踪後、家族は一丸となって、弱体化してゆるくなった絆を束ねようと、がむしゃらに突っ走ってきた。まるで、家族の一人が天寿を全うすることなく夭折(ようせつ)したことで、残りの家族が自分たちの持っているもの、すなわち生の価値に気づいたかのようだった。
しかし、実際は、何かが根本のところで変わってしまった。アンドリューはカドガン家の中で、それほど目立って発言するタイプではなかったし、積極的に行動するタイプでもなかったのだが、彼の存在は家族という共同体にとって、なくてはならないほど重要だったのだ。彼がいなくなってからそのことに気づくなんて、悲しすぎるじゃないか、とパトリックは思いながら、スマホを取り出した。メールアプリを開くと、検索バーにandrew.cadogan33@gmail.comと入力する。
パトリックはそのメールを「A」というフォルダに保存していた。また、そのメールをプリントアウトした紙を、ナイキの〈エア マックス 1〉のシューズボックスにも入れて保管してある。その箱には他にも、見れば当時を思い出すライブのチケットや、お土産の類、個人的に意味のあるグリーティングカードなども保管していた。
アンドリューのメールは、短く、形式的に書かれたもので、返信を求めず、何か質問があれば、などという言葉もなかった。その硬い文体は全くアンドリューらしくないもので、誰かの助けを借りて書いたのではないか、と疑うほどだった。しかし、とパトリックは思い直す。アンドリュー・カドガンは、このメールを送信するまでの数ヶ月という日々を送る中で、弁護士や銀行からの形式ばった手紙を何度も読む機会があったに違いない。それで、このような形式的すぎる書き方を真似することができたのだろう。
差出人: andrew.cadogan33@gmail.com
送信: 2009年5月18日 10:20
宛先: patrick@patrickcadoganhomeimprovements.co.uk
件名: 私について
パトリックへ
この度、私は我が家を離れることにしましたので、そのことをお伝えしたいと思います。
あなたがこれを読む頃には、私はもういなくなっていることでしょう。どこへ行くかは教えるつもりはありませんし、私を捜さないでほしいと願います。私はこのことについて長い間、真剣に考えてきました。要するに、私はカドガン家にふさわしくない、ということです。一度も家族の一員であるという実感を抱いたことはないかもしれません。いずれにせよ、これは一時の気の迷いではありませんし、もう二度とお目にかかることはないでしょう。私のこの思いを尊重してほしいと切に願います。
アンドリューより
パトリックは、初めてこれを読んだ時、ある種の深い衝撃を受けたことを覚えている。神経が内側からピリピリしてくるような、初めて抱く感覚だった。そのメールを受け取った時、彼はブライトンから西へ15キロほど行った海岸沿いの町、ワーシングで、リフォームの仕事をしていた。数ヶ月前に知り合って意気投合した同業者と一緒に働いていた。彼は休憩中に飲んでいた紅茶を置くと、作業員たちの誰かがスイッチを入れた大音量のラジオから離れるために、別の部屋へ行った。
彼はもう2回ほど、その文面に目を通してから、返信を打ち込んだ。
差出人: patrick@patrickcadoganhomeimprovements.co.uk
送信: 2009年5月18日 10:26
宛先: andrew.cadogan33@gmail.com
件名 Re: 私について
相棒。直接話せるか? こんなことやめてくれ。5分後にまた連絡する。
すると、すぐに自動返信が返って来た。
差出人: andrew.cadogan33@gmail.com
送信: 2009年5月18日 10:26
宛先: patrick@patrickcadoganhomeimprovements.co.uk
件名: Re: 私について
このメールアドレスは現在使われておらず、確認が取れません。
これをもって完全に姿をくらまそうと、すでに決めていたらしい。
「大丈夫か?」と知らない声がした。この部屋には誰もいないものと思っていたのだが、部屋の隅っこでラジエーターを取り付けている作業員がいたのだ。
「ああ、まあ」
「ほんとに? なんだかおびえてるようだけど」
「大丈夫。ちょっと用事で、すぐ戻る」
パトリックは半分壊れかけた家の中を突っ切り、周りで作業している人たちを無視し、バケツにつまずくのをかろうじて避けながら、外へ出た。それから海岸沿いの道に出ると、海を見ながら歩いていた。誰かに電話した方がいいかな、と彼は迷っていた。腕時計を見るとまだ10時半で、アンドリューからメールが届いてから10分しか経っていない。彼が家族のみんなにメールを送ったのなら、両親ともまだ読んでいない可能性が高い。カースティは、授業中にこっそりパソコンをチェックするという芸当をしていない限り、間違いなく読んでいないはずだ。ジェシカだけは、彼と同じようにスマートフォンを持ち歩いていたので、指でタッチするだけでメールを見ることができただろう。
彼は家族のみんなに知らせることをためらった。しかし前回のことを考えると、何もしないわけにはいかない。前にアンドリューが軍隊を勝手に抜け出し、ロンドンをさまよっていた時、俺が家族のみんなに真実を伝えていれば、こんなことにはならなかったかもしれないのだ。
その答えはともかく、アンドリューはすでに新しい人生の計画を立て、出発してしまった後なんだ、とパトリックは気がついた。その計画に、カドガン家は含まれていないんだ。
ビクトリア朝様式を今に伝える〈バーリントン・ホテル〉や、同じくビクトリア朝時代から海岸沿いの道路に建ち並んでいる古民家を横目に、パトリックはどうしたらいいのか考えていた。何の決断もできないまま、ただ歩くペースだけが速くなる。その時、彼の手の中で携帯が鳴った。
母さん。
「もしもし」と彼は言った。
「アンドリューから連絡あった?」彼女は挨拶もせずに開口一番そう言った。彼女の声はパニックで震えていた。
「ああ。まあ、メールがね」
「ジェシカにも届いたそうよ。今彼女から電話があって」それを聞いてパトリックは、ぐじぐじと考え込んでいたことを悔やんだ。やっぱりメールを見たらすぐに、両親に連絡すべきだったんだ。ジェシカは昔から彼よりもずっと、自分に自信を持っていて、どんな状況でも自分のすべきことを的確に判断していた。
「じゃあ、母さんにも届いてたんだ? メール?」
「私たちには手紙。ズンバ・エクササイズから帰ってきたら、テーブルの上に置いてあったのよ。郵便じゃなくて」
「そうすると彼は家まで―」
「わかってる、彼はまだ遠くへは行ってないわ。お父さんは仕事中だったけど、今捜しに行った。私は、彼がまた家に立ち寄るかもしれないから、ここにいるようにって。でも、パトリック」と彼女は、かすれぎみの声で言った。「何もしないでいると、いたたまれなくなって、無力感に押しつぶされそうで」
パトリックは何も答えなかった。かけるべき言葉が見つからなかった。母さんの気持ちはよくわかったが、父さんもまた、正しいことを言っている。いずれにしても、アンドリューが最後にもう一度実家を見に戻るとはとても思えなかった。ただの引っ越しならそれもわかるが、彼は、もう二度とお目にかかることはない、と書いてきたのだ。
「手紙にはなんて?」しばしの沈黙の後、彼は聞いた。アンドリューが両親に書いた手紙には、メールの内容よりも、もっと深刻な事態が書かれているのではないか、と彼はたじろぎそうになる。「もしかして―」
「これを読む頃には、私はもういないって」と彼女は言った。それを聞いてパトリックは、全員が全く同じ形式の文章を受け取ったのだと悟った。「彼がこんなことをするなんて、私には信じられないわ。彼が動揺してたのは知ってたけど、どうして話してくれなかったのかしら?」
「わからない」とパトリックは言いながら、家族全員でキッチンテーブルを囲んだ時のことを思い返していた。アンドリューが最後の望みをかけて家族に助けを求めていたというのに、みんなは要するに、それを無視したんだ。
電話は再び、しばしの沈黙に包まれた。母親もおそらく同じ時のことを思い出して、後悔の念にさいなまれているのだろう。
「もう切らないと。彼から電話がかかってくるかもしれないから」と彼女は言った。携帯電話は話し中でも、新たな電話を受信できることを理解していないらしい。「あなたに彼から連絡があったら、電話くれるんでしょ?」と彼女は言った。パトリックは同意し、二人は電話を切った。
その日、彼は残業して働いた。他に何ができるのか、もっと役に立てることはないのか、もっと他に気が紛れるようなことはないのか、わからないままに、彼は現場で一人きりになるまで働いていた。その間、カースティ、ジェシカ、そして母親から、ひっきりなしに電話がかかってきた。みんな実家のあるホーブに集まって、彼を捜し回っているらしい。そして、父親からもかかってきた。その声は、パトリックがこれまで聞いたこともないような、悲しく、諦めに満ちた、怯(おび)え切った声だった。
ようやくちゃんと話せたのは、全員が彼の捜索をやめた夜の9時だった。誰も口には出さなかったが、彼がもう近くにはいないことに気づいていた。
「じゃあ、これからどうするんだ?」とパトリックは、携帯電話を耳に当てて、ジェシカに聞いた。カースティは今、意気消沈してしまった両親に何か食べさせようと必死で説得を試みているという。
「どうしたらいいのかわからないけど、当分の間は、何の知らせもないことを良い知らせだと思うのがいいかもしれないわね...」彼女は語尾を曖昧に濁(にご)らせた。アンドリューの手紙が字面(じづら)よりも、はるかに恐ろしいことをほのめかしているのではないか、そう言ってしまいたいのをぐっと堪(こら)えているようだった。
「行方不明者として届け出るんだろ? 待ってても仕方ないし、わかるだろ?」
「ママもそう言ってたけど、私にはわからないのよ、パトリック。本当にどうしたらいいのかわからない。もし彼が遠くへ行きたいのなら、捜索願を出せばもっと彼を追い詰めることになるんじゃないかしら? 私たちが彼の決断を尊重してないって感じさせてしまうわ」
「おいおい、ジェシカ。ちゃんと捜索願は出さなきゃダメだぞ」
「そうかもしれないわね」と彼女は冷静に答えた。「でも、今言ったように、それがいい考えかどうか、私にはわからない」
その週を皮切りに、何ヶ月にも及ぶ捜索活動が始まった。若者の死について、みんなで探せるだけ探して、あらゆる記事をチェックした。ホームレスの避難所に電話して、アンドリュー・カドガンの特徴に合う人物が最近やって来なかったかどうか確認した。公に行方不明者として届け出ることまではしなかったが、特にスーが泣き崩れる場面が多々あった。
しかし、月日が経つにつれ、家族は徐々に彼の決断を受け入れるようになっていった。そして、いつか彼が戻ることを決断する日が来るかもしれないという希望を胸に、生きていくことを学んだ。家族のほとんど全員がその時を待っていた。
当時を振り返ると、アンドリューが家族の屋台骨(やたいぼね)だったことがよくわかる。彼がいなくなったことで、まさに礎石(そせき)を抜かれた家のように、みるみるうちに家族は崩壊の一途(いっと)をたどった。完全に壊れつくすのは時間の問題だった。何もかもが、もう二度と元には戻れないところまで崩れていった。
最後の一撃は、4年近く前に起こった。ブライトンでスー・カドガンが暴走した盗難車にひかれ、即死したのだ。残された面々の反応は様々だった。―ジェシカはジェリーに実家を売らせようとし、カースティは、二人のうちどちらか一人でも、故郷であるこの町に戻ってくるよう働きかけ、パトリックは、その時もやはり黙り込んでいた。その一撃がきっかけとなり、三人の仲はその後、修復しようという気力も湧いて来ないほど、バラバラに引き裂かれてしまった。
避けられたはずの家族の失踪に追い討ちをかけるように、避ける間もない形で、もう一人の家族が失われた。その時パトリックは、立て続けに盗難に遭ったようだ、と思った。その感覚に一番近い記憶を呼び起こすと、彼が11歳の時に遡(さかのぼ)る。ギャントン通りの邸宅に泥棒が入り、学校から帰ってみると、家の中がぐちゃぐちゃに荒らされていたのだ。何者かがずかずかと侵入してきて、尊厳を踏みにじるように、家族のものを奪っていた感覚。
残された者は皆、戦地からの帰還兵のように、人生を不条理なものとして否応なく定義づけられてしまった。
パトリックは、まだ解決されていないそういった議論に触れずに、この旅を終えるわけにはいかないと思った。俺の遺灰を撒いてくれ、なんていうのは表向きの口実に過ぎない。親父からの本当の依頼は、三人でとことん話し合い、関係性に折り合いをつけることに違いないのだ。親父は生前からそれを望んでいたが、叶わなかったから手紙に託した。それが、パトリックの手紙の読み方だった。
「聞きたいことがあるんだ」と彼は言った。ジェシカは運転中だったが、助手席のカースティが後ろを振り向いた。彼女は軽いショックを受けたような表情をしていた。まるで30年の沈黙の誓いを破って、酒でも飲むか? と声を発した僧侶を見るように、目を点にしていた。
「どう思う?」と彼は続けた。「俺たちはこんな風に、なんていうか、疎遠(そえん)になってしまった。もし母さんがああならなかったら...」
その問題提起はしばしの間、車内にふわふわと浮かんだまま、着地点を見失っていた。ジェシカはパッと風船をつかむように声を発した。「疎遠っていうのは、ちょっと強い言葉じゃないかな」
「だとしても、言いたいことはわかるだろ。俺たちはバラバラの人生を歩んでいる。あの夜以来...俺たちは基本的に、1年間お互いに一言も口をきかなかったじゃないか」
「そんなに長くはなかったわ。数ヶ月くらいのものでしょ」
「ジェシ、そういうことを言ってるんじゃない、わかるだろ。俺たちは、そうだな、疎遠じゃないにしても、仲違(なかたが)いしてるじゃないか」
「まあ、ちょっとは難しい状況だったのはわかるけどさ、なんか少しあなた、メロドラマチックになりすぎじゃない?」
「そんなことない。メロドラマなんか気取ってない。俺たちはこの4年近く、まともな、意味のある会話を一度もしてこなかった。手紙も書かないし、会話もしない。何かよっぽどのことがない限り、メールすら送らない」と彼は言った。「俺たちは、お互いに口をきかない家族になってしまったんだ。俺がアイルランドに住んでた頃、二人とも一度も俺を訪ねて来なかったじゃないか」
「招待されたこともないわ!」
「まさにそれだよ。それこそ俺の言いたいことだ。他人行儀というか...前は違っただろ、数週間に一度は顔を合わせてた。それが今は、義理でクリスマスカードを送り合うのがやっとみたいな間柄になっちまった。招待されなきゃ来ないような仲なのかって聞いてるんだ」
「実はアイルランドに行っことはあるのよ」とジェシカが言った。「聞きたいなら聞かせてあげるわ。ダンが商用旅行というか、仕事の取引でね、私もついて行ったの」
「そうか。なら、余計にひどいんじゃないか? 俺が住んでる国まで来ておいて、俺に連絡を取ろうという考えが一度も浮かばないとはな」
「とっても忙しかったのよ、パトリック。ビジネスだったんだから―」
「ならいいよ」と彼はぶっきらぼうに言った。「わかった。もういい。俺が質問したのが間違いだった。今のはなかったことにしてくれ。何も変わってない、昔のままだ。すべては順調、それでいい」
「いったい何なの? あなたが何を望んでるのかわからないわ、パトリック。週に一度のランチ? 家族で集まって語らいましょうってこと? 最近流行りのWhatsAppグループでも作って、家族で退屈を紛らわしたいとか?」と彼女は言った。「私たちが集まったのは、パパの遺灰を撒きに行くためよ」
「でも、真の目的はそうじゃないだろ? 俺たちは絆(きずな)を取り戻すために集まった。親父の手紙にそう書いてあった」
「そんなこと書いてなかったわ」
「そういう意味だったんだよ」
「私たちが旅を楽しむことを望んでるとは書いてあったけど、家族の絆を取り戻せ、なんて解釈するのは無理があるわね」
「じゃあ、なぜ彼はこれを計画したんだ?」
「そんなの知らないわ、パトリック。彼はもういないの。彼の気持ちなんて今さらわかるわけないでしょ? 『絆を取り戻せ』でも何でもいいけど、おままごとなら、あなたたち二人でやっててちょうだい。私は彼に頼まれたことを文面通り、そのままするためにここにいるの。それだけよ」
「ああ、もういい加減にして! 二人とも黙ってて」とカースティが怒鳴った。「もううんざり。とことんまでうんざりしたわ。二人とも自分自身のことしか考えてないじゃない。4年も経ってから、あの時俺はこう思ってたんだ、とか、今さらぐじぐじ言い出すのはやめて」と、彼女はパトリックに向かって言った。「気づいてないといけないから言うけどね、あの後、パパのそばにいたのは私なの。パパは息子を失った後、妻まで失ったのよ。そんなパパの目の前で、あなたたち二人は平気な顔して、あの家を売ろうとした」
「俺はしてない」とパトリックは言い放った。彼は爆発寸前の高鳴りを感じた。昨日と今日の会話や、これまでのささいな口論で溜まりに溜まった、三人の鬱屈した感情が、今にも暴れ狂い、噴き出しそうだった。
「ふざけたこと言わないで、パトリック」
「あなたは私に賛成してくれたわ」とジェシカが言った。
「あなたたち二人とも、どっちもどっちね。あなたたちは、この4年間に実家で何があったかなんて、なんにも知らないでしょ。年に一度クリスマスの時期になると、別々の日にちょこっと顔を出すだけ。それから月に一度のペースで、後ろめたさを感じてきた頃合いで電話だけしてきて、罪悪感を解消して勝手にいい気になって」
「はい、始まった。お得意の『可哀想な私を見て』の上演開幕ね。っていうか、ブライトンに残ることを選んだのはあなたでしょ」とジェシカが言った。「そのことで私たちを責めたってなんにもならないわ。私には私の人生があるんだから」
「うぬぼれるのもいい加減にして、ジェシカ」とカースティが一段と声を荒げた。「あなたのどうでもいい、無意味な人生なんて誰も注目してないわ」
その瞬間、バンッという大きな衝撃音がして、キャンピングカーが高速道路を左によろめき、たなびいた。後ろからクラクションが鳴り響く中、ジェシカの運転する車は、ふらふらと蛇行を続け、彼女は唖然としたまま、ハンドルから一瞬手を離してしまう。パトリックは、これは間違いなく横転する、と思った。彼はパニックに陥りながらも、自分だけシートベルトをしていないことに気づき、さらにパニックに陥った。カースティが悲鳴を上げた時、車は急に右に折れ、路肩に乗り上げたところで、ふーっと息を吐くように停まった。ジェシカは深く息を吸い込みながら、ゆっくりとすすり泣きを始めた。
~~~
〔チャプター 6の感想〕
「このメールアドレスは現在使われておらず、確認が取れません。」
これは響く! ほんとに響く!! 藍の骨の髄まで響いたね!!! 藍の人生最大の衝撃と言っても過言ではない。まさに死ぬまで覚えている、生命がゆらぐ感覚...
あの日の昼間、藍と上原レナちゃんは数ヶ月後に迫ったクリスマスの話をしていた。(←何回同じこと書くんだよ!笑←何回でも書くよ! 藍の人生最大の一大事なんだから!)
それなのに、「またね」って笑顔で手を振って、家に帰って、夜になったら、「もう会うこともメールすることもない」というメールが藍の携帯に届いて、目が点状態の藍はもちろん返信したけれど、すぐに自動返信が返ってきた。
このメールアドレスは現在使われておらず、確認が取れません。
藍も10代の頃、一度家出を試みたことがある。ただ、それはアンドリューとは違って、ただ単に思春期でこじらせていたってだけで...都会に出てみたくて、同じ県の、より都会に近い町に住んでいた、一人暮らしの親戚の家に行ったってだけで...😅笑
でも、その時に見た一人暮らしの部屋が、藍の中でデフォルトというか、プロトタイプになっていて、大学時代に一人暮らしをした時、その時のことを思い返しては参考にしていた。←何の話だよ??笑
~~~
チャプター 7
グレットナ
カースティ
「あのさ」とジェシカがようやく言葉を発した。キャンピングカーが止まってから数分後のことだった。カースティの指導による深呼吸と、カースティがミントの葉っぱを入れてくれた水を何口かすすったことで、なんとか話しができるほどには落ち着いてきた。「他に何か言うことはないわけ? これで私が死んだら、死にゆく私にかけた最後の言葉が、ヨガの呼吸法だったなんて、あなたは生涯そのことを悔やみ続けるわよ」
カースティは怒りとともに、感心する気持ちも入り混じった表情で彼女を見つめた。どんな状況でも自分のストーリーに組み込んでしまう姉の天性の能力に、改めて感嘆してしまう。カースティは何か言い返そうとしたが、何も言葉が見つからず、やるせなくパトリックの方に目をやると、彼が額を押さえていた。
「大丈夫?」
「ああ」と彼は歯を食いしばりながら言った。
「どうしたの?」
「クソッ、頭をぶつけた。車がぐらっと揺れたとき、窓にぶつけたんだ」
彼はまるで、つま先をドアにぶつけて、なんでこんなところにドアがあるんだよ、と見当違いの文句を言っているような口ぶりだった。
「あらまあ。血は出てないんでしょ? 真っ直ぐこっちを見て、私が何人に見える?」
「大丈夫。ただ痛いだけ」
「パトリック」ジェシカが運転席から後ろを振り向いて、彼の名を呼んだ。「あなたの名前は? あなたは誰だか言ってみて」
彼はカースティに鋭い視線を送った。
「脳震盪(のうしんとう)を起こしているかもしれないわ」ジェシカが一段と声の音量を上げた。
「脳震盪じゃない、ただ痛いだけ。っていうか、いったい何が起こったんだ?」
「わからないわ」とジェシカが言った。「制御不能っていうか、私には為す術もなく、車体が跳ね上がったと思ったら、左右に揺れ出して」
カースティは車から降りた。〈グレットナ・サービスエリア〉を過ぎて、1.5キロほど進んだところの路肩に車は停まっていた。路肩の向こう側は急な斜面になっていて、木がまばらに立っているが、それよりも車から投げ捨てられたゴミが目立つ。路肩のこちら側は、北へ向かう片側2車線の高速道路で、車が次々と通り過ぎていく。小雨が降っていて、肌寒い。カースティはグレーのカーディガンの前を締めるように両手をクロスさせながら、車の前に回り込んで故障箇所を確認した。
「パンクね」彼女は窓の外から、運転席のジェシカに言った。「左前のタイヤ。ぺしゃんこにつぶれてる」
道路を振り返ると、タイヤのゴム跡がくっきりと残っていた。ジェシカがコントロールを失って、思いっきりブレーキを踏んだ時についた、黒くて長いタイヤ線がウェーブしながらこちらへ続いている。
「まあ、なんていうか、私のせいじゃないわ」とジェシカが開いた窓の中から言った。「ただ...まあ、そうね。ただパンクしちゃったってことでしょ?」
「誰もあなたのせいだなんて言ってないじゃない。誰のせいでもないわ。強いて言うなら、何年も誰にも乗られず、放っておかれた、この馬鹿でかい車のせいってことね」
「なに、これから先も、またパンクしちゃうかもってこと?」
「そうならないことを祈るしかないわね」
「まあ、私は車についてはよくわからないけど—」
「じゃあ、何も言わないで」とカースティは言って、その場を離れると、車内に戻ってきた。「後ろにスペアタイヤがあるわ」そう言って後方へ向かおうとした時、こちらを見ているパトリックの顔を見て、彼女は立ち止まった。
「何? 俺にやれってことか?」と彼はしかめっ面で言った。
「いや、そうじゃなくて...」
「何だよ?」
「あなたの」と彼女は言ったところで、何と言えばいいのかわからなくなった。彼の額(ひたい)の、右の眉のすぐ上に、大きな赤いこぶができていたのだ。「その...あなたの...ここ」
「ここが何?」彼はそう言って、スマホを手に取り、カメラを開いて自撮りモードにした。「おいおい、勘弁してくれよ」彼はそう言いながら、こぶを指で触って、たじろいだ。「これじゃ馬鹿みたいじゃねぇか。ゴルフボールくらいあるな」
カースティはクスッと笑ってしまった。
「ああ、そうかい。そんなにおかしいか?」彼が不機嫌そうに眉を動かした。「これじゃ、れっきとしたお馬鹿さんって感じだな」
「ごめんごめん」
「ああ、馬鹿馬鹿しい」と彼は言って、スマホをテーブルの上にポイッと投げ捨てた。
「まあ、あれよ、ヘブリディーズ諸島で誰かと待ち合わせして、デートするわけじゃないんだし、そうでしょ? ジェシカと私にしか見られないんだから」と言ってから、にっこりと笑みを浮かべて続けた。「そうだわ、あのセクシーバーテンダーに、名誉の負傷だって言って、その写真を送ったら?」
「ああ、そうかい。まだ傷は癒(い)えてないってのに、もう話のネタにしちゃえってことか?」
「パトリック」と彼女はなだめるような口調で言って、彼を落ち着かせようとした。「ただの頭のこぶなんだから、心配要らないわ」
「なんでもいいけど」と、彼は気分を切り替えようとした。「早くタイヤ交換した方がいいんじゃないか? ぐずぐずしてると、今日のフェリーの最終便に間に合わなくなるぞ」
パトリックは立ち上がると、レインコートを羽織って、雨の中へ出て行った。カースティは彼が座っていた座席に腰を下ろすと、スマホを取り出した。メッセージを3件受信していた。すべてトリーナからで、リヴィがタイプしたらしいメッセージが最初にあって、次に2人が一緒に写った自撮り写真。それから、トリーナ自身が打ったWhatsAppのメッセージだった。
トリーナ:どんな感じ? もう誰かを殺しちゃった?笑
カースティは返信した。
カースティ:今のところ、なんとか耐えてる。というか、パンクしちゃって、今はスコットランドの道端で立ち往生。ジェシはキレぎみ。パットは大丈夫。笑
トリーナ:あらあら大変ね! 何があったの?😘追伸、スコットランドのどこ? スコットランドって言っても広いからね😘
カースティ:ただタイヤがバンッて破裂したの。グレットナの近く😘
トリーナ:災難ね。まだかなり南の方じゃない。今日この後フェリーに乗るんじゃなかったの?😘
カースティ:思い出させてくれてありがとう
トリーナ:動揺させちゃったらごめんなさい。そんなつもりじゃなかったの。リヴィはあなたに会いたがってるわ😘
カースティ:こちらこそごめんなさい。ただこの状況に苛立ってるだけよ😘
トリーナは3つの絵文字を立て続けに返してきた。まず悲しい顔が来て、次に車。そして爆発を表す絵文字が画面にポッと現れた。カースティは椅子にもたれるように深く座ると、パトリックが頭をぶつけた窓に後頭部をつけて、のけぞった。
彼女たちはかなり気が滅入るような場所で立ち往生していた。順調に行けば、そろそろトロサックスに差し掛かっている頃で、スコットランドの湖や丘陵(きゅうりょう)地帯の絶景を眺めながら、気分良く車を走らせているはずだった。それがなぜか、こんな所で足止めを食っていた。グレットナといえば、結婚式場で有名だけど、ここで結婚式を挙げた新婚夫婦の離婚率が高いことでも有名だった。そんなことをぼんやりと考えながら、カースティは窓の外を見た。何もかもがどんよりとした灰色に見える。木々でさえも、夏の緑色から秋の赤々とした黄金(こがね)色に変わりつつあるというのに、灰色の靄(もや)が掛かって見えた。
「ていうか、謝らないわけ?」と、前の運転席から棘(とげ)のある、食って掛かるような声が飛んできた。
「なんで私が謝らないといけないの?」
「あなたの無意味な人生なんて誰も注目してないわ、だっけ?」と彼女が言った。「違った。あなたのどうでもいい、無意味な人生なんて誰も注目してないわ、だったわね」
カースティはため息をついた。母親が子供の親指に刺さったトゲを抜こうとするかのような執念(しゅうねん)で、妹から謝罪を引き出そうとしてくる姉を面倒に思うと同時に、ジェシカの言う通り、謝らなければいけないようなことを言ってしまったな、とも思った。
「言葉の綾(あや)よ」
「今まで一度も耳にしたことがない綾だけど、それしか言えないわけね―」
「わかったわ。ごめんなさい」と、カースティはきっぱりと謝った。その時、キャンピングカーの左前方が少し持ち上がり、グラスの水もその分傾いた。「さっきの私は、どうかしてた。あなたの人生は無意味なんかじゃない」
「人生の見方によるわね」とジェシカは言って、運転席から立ち上がると、後ろに来てテーブルを挟んで妹と向き合った。車から降りよう、という言葉が、カースティの喉元(のどもと)まで出かかった。そう提案すれば、二人で外に出ることになっただろう。しかし、雨は先ほどよりもさらに激しさを増していた。こんなどしゃ降りの中で、ビシャビシャと雨を跳ね返す路肩に立って、パトリックがタイヤを交換してるのを見守るなんて、耐え難いことに思えた。
「見方によるって何? あなたの人生だって無意味じゃないでしょ」
「私はそうは言いきれないわ。一部の人達には、私なんかの人生は無意味だって思われても仕方ないでしょうね。私は大金を動かしてるわけじゃないし、ただの郊外の花屋よ。ダンと子供たちと一緒に、ただ毎日を過ごしてるだけ。私は世界を変えてない」
「は? そんな人いるの?」
「少なくともあなたの仕事には、ある程度の影響力があるじゃない」
「私は中学で国語を教えてるのよ、ジェシカ。『いまを生きる』とかの映画みたいな感じを想像してるとしたら、大間違いよ、私はロビン・ウィリアムズでもないし。先週ね、『二十日鼠と人間』についてのエッセイを採点したんだけど、35人中、34人はほとんど同じ内容だったの」
「で、残りの一人は?」
「彼は間違った本を読んでたのよ」
ジェシカが笑った。外ではパトリックが、パンクしたタイヤを引っこ抜こうとして、唸り声を発していた。
「ダンがね、また政治の世界に戻ろうとか考えてるのよ」
「マジで! 今度は市会議員じゃなくて?」とカースティは言った。ダンが2年間、地元の小さな商業都市で保守党の議員を務めていたことを思い出した。市民の誰かが真夜中に、自宅の私道に停めていた彼の車に、『くそったれ』とか卑猥ないたずら書きをした後、彼は議員を辞めた。―いたずら書きをした人は学費の値上げに反対してたんだろうな、というのがダンの持論だった。
「それが、今度は1つランクを上げて、上の議会に出馬するとか言ってるの」
「あらあら...」
「だから私も憂鬱なのよ」とジェシカが言った。「あの頃は私も、しょっちゅう人と会ったり、食事をしたりで大変だったわ。もちろん、会う人会う人みんなひどい人たちなんだから。で、私は奥さん同士で仲良くしなきゃいけなくて、奥さんたちもうんざりするほどひどい人たち」
「いつも奥さん同士なんだ?」と、カースティは女性議員が少ないことを思い、少し決めつけるような口調で聞いた。
「大抵はそうね。あなたはブライトンから出たことないから、そこが基準になってるんでしょうけど、他の地域では少しは変わってきてるわね。たまにだけど、そういう場で女性議員の旦那さんの隣に座らされることもある。彼らはいつも居心地悪そうにしていて、ほとんど話すらしないわ。赤ちゃん連れの父親と同じよ。とにかく、私が言いたいのは、またそういう生活が始まるのかと思うと、うんざりっていうか、そういうのって少し不毛な時間の過ごし方だと思わない? 上辺だけの付き合いに何の意味があるの? 私は大学時代、本を書くつもりだったの。ブライトンでコラムニストになった友人に会うことになってたけど、キャンセルしたって言ったわよね。会う気になれなかったのよ」
「今からでもまだ書けるんじゃない―」
「そのことについてダンと話し合ったわ。お手伝いさんを雇おうかって。毎日じゃなくても、私が週3で家事をやってもいいから。お店の管理は他の人に任せて、とかって」
「じゃあ、そうすればいいじゃない?」
「いろいろと面倒なこともあるのよ。ダンが所属してる党の方針っていうか、党は支持者がどう思うかを気にするの。保守党の支持者は伝統的なものが好きなのよ。家庭も伝統的であるべきだって。ひどい話よね。でも、それが現実なの」
「失礼な言い方になっちゃうかもしれないけど、『くそったれ』はどっちだって話ね。彼に投票する人たちのことを言ってるのよ」
「ほんとそう。カーテンの隙間から見張ってるような人たちなのよ。ほんと嫌な人たち。人の人生を持ち上げたり落としたり、自分たちの思いのままだって思ってるんでしょうね。ダンが議員だった時、次の選挙では彼に投票しないでおこうかなって思ったことがあるくらい。誰も知らないでしょうけど。私以外は」
「そうすればよかったのに! ちょっとした反抗心があったっていいじゃない。それに、パパだったら何て言うか考えてみてよ」
「そうね。パパは、ダンが家族の一員であるという事実に最後まで慣れることができなかった。彼が当選した時、一応おめでとうって電話をくれたんだけど、なんだかいろんなことに対してパパが怒ってるのが伝わってきたわ」とジェシカは言った。「これはあなたには言ってなかったかしらね? 私が結婚する前、パパと二人きりで話したことがあるの。私たちを『正しい価値観』で育ててきたって言ってたわ。パパが子育てをしていた頃より、今のお前たちはお金を持っている。だけど、パパから教わったことを忘れてはいけないって。あの会話はたしか、ダンの父親が誰だかわかった時だったと思う」
カースティは笑った。その時の会話の様子を思い浮かべることができた。彼女の父親は、中産階級の中でも上層に位置する家庭で育った第1子が、必要以上のお金のせいで堕落するのではないかと心配していたのだ。勤勉さや誠実さよりも、自分の好みや血縁を重視するようになるかもしれない。そして、父が彼女に日々の中でしみ込ませるように植え付けてきた思いやりや共感、優しさといったものが、より自己中心的な世界観によって排除されてしまうかもしれない、と。
まず間違いなく、彼の心配は現実になってしまった。もしジェリー・カドガンの教えや格言に彼らがもっと忠実であったなら、もっと家族を大切にしていただろうし、こうして再び集まって、仲直り目的の旅になど出るまでもなかっただろう。
「ここで立ち往生するなんて、おかしいでしょ?」とジェシカが言った。
「どうして?」
「グレットナよ。よりによってこんなところで」
「私はここには来たことないけど、グレットナで何かあったの?」
ジェシカ
彼女は運転中、道路左側の地名表示を見た時から、それについて考えていた。その直後だった。突如、車が制御不能となり、恐ろしいほどの揺れを感じた。ぐらっと大きく傾いたキャンピングカーが、他の車との衝突をぎりぎりで避けたことだけは認識できた。車が緊急停止してからは口論が始まってしまい、カースティがひどく突っかかってきたため、今までそれについて言及できなかった。
「結婚式よ」とジェシカは言った。
「結婚式って何?」
「本気で言ってる? 知らないはずないでしょ」
「ジェシ」とカースティが真顔で言った。
その表情を見て、妹がグレットナと家族の関係を純粋に知らないことを初めて知り、彼女は驚いた。
「パパとママは、あなたにそのことを話さなかったの?」
「何のこと?」とカースティは聞いた。
「彼らの結婚式よ。昔、二人が結婚した場所。パパとママは駆け落ちして、ここまで来たんだって。親が結婚を許してくれない場合、当時の人たちは結構そういうことをしたそうよ」
「ママとパパが駆け落ち? 冗談でしょ? 私はずっと〈セント・フィリップ教会〉で結婚式を挙げたものとばかり思っていたわ」とカースティが言った。まるでそれこそが事実で、ジェシカの方が間違っていると言わんばかりの口調だった。「テレビの上に写真があったじゃない」彼女は金縁の写真立てに言及した。グレーのスーツを着たジェリー・カドガンと、白いドレスを着たスーが写っていた。家から10分ほどのところにある教会の前で、二人は微笑みながら立っていた。その写真はテレビ台の上にずっと立て掛けられていて、両脇には4人の子供たちの、それぞれ撮った時期の異なる写真も一緒に飾られていた。しかし数週間前の大掃除の時、それらの写真もすべて取り払ってしまった。
「あなたが知らなかったなんてびっくりね」とジェシカは言った。
「ジェシカ」カースティが再び真顔で、話を先に進めるよう促(うなが)した。
「あの写真は仕組まれたものだったのよ。ママの両親が、地元の牧師に結婚を祝福してもらいなさいって、改めてあの写真を撮ったんだけど、でも実際の結婚式はここで挙げたのよ」
「ほんとに? なんで駆け落ちなんてバカなことしたの?」
「おばあちゃんとおじいちゃんが認めなかったんだって。パパのことをよ。うちの家系には合わないって」
「嘘でしょ? おばあちゃんもおじいちゃんも、あんなにパパと仲良かったじゃない」
「だんだんと受け入れていったのよ。パパの建築士事務所がなんとか軌道に乗り始めた頃から、ようやく認められたみたいね。パパはワトフォードからブライトンに仕事でやって来た建築業者で、サッカー観戦の後、町で夜遊びしてた時、ママと知り合ったそうよ。だけど、ママの家系は兵隊さんばかりで、当然ママも大尉とか大佐とか、そういう軍人さんと結婚するという流れだったみたい」と彼女は言いながら、祖父の記憶を思い出していた。彼女が覚えているのは、現役を退いた後の他人行儀で不愛想な祖父の姿で、彼は一日中新聞をめくりながら、紙面に対してぶつぶつと文句を言っていた。「パパとは相容(あいい)れなかったのよ」
「だからって、駆け落ちまでするかな?」
「したのよ」
「それはいつのこと?」
「78年よ」とジェシカは言ってから、妹が話に付いてくるのを待つように間を開けた。
「そうすると、それって...」
「そう、私が生まれた年よ。ママはその時、妊娠5ヶ月だったの。だから急いで結婚式を挙げたんでしょうね。パパは妊娠を知るとすぐにプロポーズしたんだって。でも、両親には妊娠を隠してた。まだ若かったから。ママは19歳になったばかりだった。パパはおじいちゃんに、結婚させてくださいってお願いしたんだけど、カンカンに怒られちゃったみたい。それで二人で駆け落ちして、ここで式を挙げたの」
「あの写真は? ママはたしかお腹が出てなかったよね」
「テレビの上の?」ジェシカが尋ねると、カースティは頷いた。「あれは私が生後3ヶ月の時に撮ったものよ。おばあちゃんとおじいちゃんは、ママが結婚したのを知った時も、パパと会うのを拒否したそうだけど、私が生まれてからは、再び話をするようになったみたい。地元の牧師に改めて祝福してもらう、という条件付きでね。〈ボウルズ・クラブ〉の芝生の庭で、くだらない披露宴をやって、それでおしまい。だから、あの写真以外はないのよ」
「なんてこと」
カースティが処理しきれない情報をなんとか咀嚼している間、ジェシカは自分の中で最も古い記憶を思い起こしていた。
ブライトンのレインズ通り近くの共同住宅の記憶だった。今でこそ、あそこは家賃の高い物件になっているけど、当時は風通しが悪く、夏は湿気に、冬は寒さに悩まされる建物で、ジェリーの職人としての腕前があったからこそ、どうにか住めるくらいにはなっていった。ヘリンボーンの床は、彼の手によりカーペットが被せられ、壁紙が取り除かれ、壁はパイン材で覆われた。合成樹脂でできた茶色いキッチンを彼女は覚えている。消毒液の臭いがして、埃っぽかった。
あそこには3年間住んでいた。大家さんが所有する他の物件に関しても、ジェリーが同様の内装工事を請け負うことによって、家賃を安く、工事がかさんだ月は家賃をゼロにしてもらっていたそうだ。そうやって貯めたお金で、彼とスーは自分たちの家を買った。ジェリーは口癖のように、お金が貯まったらワトフォードに帰るぞ、と言っていた。スーの両親や友人たちの冷ややかな目から逃れるために、彼の地元で暮らす計画だったのだ。しかし、スーがパトリックを妊娠した頃には、彼らは南海岸の町に根を下ろしていた。ジェリーは、ワトフォード訛り(テムズ川の河口周辺の方言に、ロンドンの労働者階級の訛りを混ぜたようなアクセント)を、あえて直そうとはしなかったし、幼い頃から応援してきたサッカーチームへの熱烈な愛情も、頑なに抱き続けた。それでも彼の故郷は、その頃にはすっかり海岸の町になっていた。
カドガン夫妻は、パトリックが生まれる2ヶ月前にギャントン通りの邸宅に移り住み、そのままそこに住み続けることとなった。買った当時は、水道が使えるかどうかもわからないような、ボロボロの家だったそうで、その後数年かけて、ジェリーは手間暇かけてあの家を住めるように改築していった。そしてカースティが生まれる頃には、あの家は完成形に至り、子供たちがあちこちを壊し出すまでの少なくとも数年間は、完成形を保っていた。
「何も言ってくれなかったなんて信じられない」
「私はあなたが知ってるとばかり思ってたけどね」
「そういえばママはよく、結婚式のことはあまり覚えてないとか言ってた。あの頃は結婚式なんて大したイベントじゃなかったって」
「それはそうでしょうね。今だって結婚式なんて大したイベントじゃないわ。私は一応その時そこにいたから、私には知る権利があると思ったんじゃない? それで私にだけ話したのかもしれない」
その時、パトリックが車内に戻ってきた。全身ずぶ濡れで、手はタイヤの汚れと油にまみれ、真っ黒になっていた。ジェシカはカースティが動揺しているのがわかった。大人になってからのほとんどの時間を両親の一番近くで過ごし、ずっと心配し、世話をしてきたつもりだったのに、両親に裏切られたと感じているのかもしれない。
「じゃあ、もういいのね?」とジェシカが聞いた。
「もう無理だ」と彼は怒ったように言い捨て、蛇口をひねると、手についた落ちそうもない汚れを洗い出した。
「何が?」
「RACか、この辺りの修理工を呼んでくれ。完全に足止めだよ。この道路を横切って、パンクしたまま縁石に乗り上げた衝撃で、車輪がめちゃくちゃに曲がってるんだ。俺は素手で直そうとしちゃったものだから」と彼は言いながら、こちらに向き直り、所々赤くなって少し血もにじんでいる手のひらを見せてきた。
「ほんとだ」とカースティが穏やかな口調で言った。「じゃあ、誰かに電話して直してもらうしかないわね。タイヤを変えてもらわなきゃ」
「タイヤを変えるどころの話じゃないよ、カースティ。車輪が壊れてるんだ。ホイールがくにゃって曲がっちゃって、車軸から外れないんだよ」
パトリックの話を聞いて、ジェシカが慌て始めた。ここで過ごす時間が長くなればなるほど、今日中にフェリーに乗れる可能性はますます低くなる。家族や自分の人生から離れている日数が、もう1日延びることになってしまう。これ以上こんな馬鹿げた旅に、無駄に時間を費やしてはいられない。
「ダメ」と彼女は言った。パトリックが修理工を呼ぼうと、携帯を耳に当てたところだった。
「ダメってどうしたの? ジェシ。パトリックがやっても車輪を外せないんだったら、誰かを呼ぶしかないでしょ」
「無理ってこと。ここで何時間も待つのは嫌だっていう意味。絶対にもう嫌だ。もし今晩のフェリーに乗り遅れたら、私はもう降りるわ」
「明日の朝のフェリーに乗ればいいだけじゃない。理想的とは言えないけど、港で一晩過ごせるし、パブか何かのお店に入って、ゆっくりしましょうよ」
「いやよ!」と彼女がキレた。「カースティ、私は嫌だって言ってるの。もし今日中にフェリーに乗れなかったら、私を降ろしてちょうだい...エディンバラ空港かどこかで」
「エディンバラ空港は逆側だよ、東海岸。こっちは西海岸」とパトリックが言った。
「逆側だっていいじゃない。グラスゴーでもダンディーでも、何ならアバディーンまで行っちゃってもいいわ。どこだって構わない。この旅が予定より長くなることは絶対にないって言ってるの。じゃあ、こうしましょ。この近くの海岸で、海が見えたら遺灰を撒く。それで問題ないでしょ」
「ジェシ!」とカースティが言った。「パパがポートエレンの海岸って指定したのよ。どこでもいいから撒けばいいってわけじゃないでしょ。それとも、あなたにはどうでもいいのかしら? そして、ちゃんと使命は果たしたって言い張って、カドガン家の嘘の山に、また一つ嘘を積み重ねるんだ?」
「同じ海でしょ、カースティ。海は全部つながってるのよ」
「ああそうね。じゃあ、太平洋かインド洋にばら撒けばいいじゃない。それか、家族と一緒に地中海へ旅行に行ったついでに、撒いてくればよかったじゃない。全部同じ海なんでしょ?」
「ふざけたこと言わないで、カースティ」
「わがままばっかり言うな、バカジェシカ」
「もういい!」とパトリックが怒鳴った。
パトリック
彼はタイヤ交換を試みている最中、開いた助手席の窓から彼女たちの話を聞いていた。ホイールを車軸に固定しているボルトの1本をどうにか緩めようと、全身の力を指先に注ぎ込んでいる合間も、彼の意識は車内から聞こえてくる会話の断片に注がれていた。
彼女たちが両親の結婚の真相について話している時でさえ、もうすぐ沸点を超え、口論に発展するだろうな、と予期していた。
「バカな言い合いはやめろ」と、彼は二人に苛立ちをぶつけた。
「彼女に言ってよ」とカースティが言った。
「それはこっちの台詞よ」とジェシカが煽った。
「二人ともだよ! まったく、いつになったら終わるんだ? 2分くらいはまともに話してたと思ったら、もうこれだ」
「彼女が―」
「いいから黙れ。そして大人になれ」と彼は声を張った。
パトリックは現在の状況に対して声を張り上げた。でも本当は、これまでの20年間いつだって、そう言えたはずなんだ。
ジェシカとカースティの間には、常にピリピリとした緊張感が漂っていた。長女の知恵と、末っ子の特権がぶつかり合っていたのだが、ほとんどの場合、二人はそれを表面下に隠していた。しかしカースティがことさら、自分だけブライトンに残って親の世話をしていることや、故郷を離れ、それぞれの道を歩み出したあなたたちより、家族に対して忠誠心があることを強調した時には、緊張の糸がぷつりと切れ、口論が勃発するのだ。あるいは逆に、ジェシカが過度にわがままな態度をとった時や、過度に感傷モードに入った時も同様だった。
二人の間で些細なことから始まる口論や、どちらが上かという争いが、いつしか事実そのものよりも重要視されるようになったことに、パトリックは我慢がならなかった。本当に大切なものが何なのか、今ではもうぼやけてしまって見えにくい。
母親が亡くなった時、罪悪感にさいなまれたカースティは、悲嘆にくれ、卵を茹でたり、簡単な料理をすることもままならなくなってしまった父親の世話をすることに、多くの時間を割(さ)いた。そして父親が亡くなると、どちらがより多くの家事をこなせるか、二人は競うようになり、この旅自体も消耗戦になりつつあった。二人のうちどちらが父親のリクエストを成就(じょうじゅ)させるか、競(せ)り合っているのだ。
「馬鹿馬鹿しい」とジェシカが言った。誰かにというより、自分に向けて言ったようだった。彼女はテーブルに手をつけ、立ち上がると、自分の寝台へ向かった。
数年前から、二人は口論が起きそうになると、お互いにしばらく距離を置くようになった。それぞれのパートナーにうっぷんを発散することで、気を紛らすことを学んだのだ。パトリックにぶちまけてくることもあった。パトリックはどちらから相談を持ちかけられても、常に同意することにしていた。これ以上の衝突を避けるためには全てを肯定するしかない。その後、彼女たちは普段は友好的に振る舞うようになった。仲の良い友達同士の雰囲気すらあった。しかし今は、友達という仮面もはがれ、二人を結び付けられるのは、家族という絆だけだ。
カースティはテーブルの上でiPhoneに指を滑らせ、周りの世界に目もくれずにいる。彼は二人の親になった気分だった。自分の娘にも感じたことのない感覚で、ジェシカとカースティが10代の若者に見え、二人をたしなめた直後の親父に成り代わったようだった。彼の本当の娘はまだ小学校にも行っていない。対して、二人の姉妹はすっかり成人している。それなのに、彼女たちの間にできた溝を自分が埋めようとしていることに気づき、よりいっそう不思議な気持ちになった。
彼はテーブルに向かって座り、赤い釣り具箱を手に取った。彼が蓋を開けると、カースティは心配そうな顔をした。
「今は開けちゃだめよ」と彼女が言った。「足止めされてるからといって—」
彼女を無視し、彼は最初のアルバムを取り出した。昨夜三人で見ていたアルバムだ。海辺の防波堤に座る4人が写った写真のあるページを開く。
左端にカースティがいて、緑の花柄のスカートにトレーナー、中にはピンクのTシャツを着ている。その隣にはパトリックがいて、いつものように〈ワトフォード〉の黄色いユニフォーム型シャツに、デニムのショートパンツという格好だ。その隣のジェシカは、長い髪が風になびき、顔の大部分が隠れている。そして右端に、アンドリューがいた。
「俺たちは話さなければならない。彼について。この機会にちゃんと、正直に思っていることを言うんだ」
カーテンの向こうで聞いていたジェシカが、ここぞとばかりに寝台から顔を出した。
「今さら何言ってるの? 彼が出て行ってから何年経つのよ、もう話し合うことなんて残ってないでしょ」
「彼がどこにいるかについては話し合った。彼が何を考えているのか、についても話し合った。でも、なぜあんなことが起きたのかについては、一切話し合ってこなかったじゃないか。なぜ彼は俺たちのもとを去ったのかってことだよ。無意識のうちにであっても、俺たちはいったい何をしたのか、そして」そこでカースティが再び口を挟もうとしたが、彼は強引に続けた。「今、俺たちがそれについてどう思っているか、一度も話したことがないだろ」
「あなたは何様なの? カウンセラーか何か?」と、ジェシカが背後から苦々しげに言った。
「いいから聞け、ジェシカ。お前がこの旅を途中で離脱して帰るというのなら、せめて今、何かを得ようとすべきじゃないか?」
ジェシカがしぶしぶながらも寝台から降りてきて、テーブルに加わったのを見届けてから、彼はアルバムのページを覆っているセロファンをはがした。4人が揃って写っている写真を手に取り、テーブルの上に置く。
「なんだかあの時と同じ気持ち」とカースティが言った。
「それはどういう?」
「悲しい気持ち、かな。彼のことが心配で」
「罪悪感はないのか?」と彼は聞いた。「彼が出て行くのを止めるために、何かできたかもしれないって思ったことはないのか?」
「パトリック。彼はパパの事業資金の半分をギャンブルで溶かしたのよ。問題があったのは彼の方。そのことで私たちが罪悪感を感じたって仕方ないでしょ」
「彼は俺たちに助けを求めてきたじゃないか」
「パパは彼に仕事を与えたじゃない。事務所の経営を彼に任せて、そしたら、1年も経たないうちに彼は自己破産。事業をほとんどダメにしちゃって、ママとパパは慌ててあの家を抵当に入れて銀行からお金を借りて、なんとか廃業は免れたけど、あれからパパはまた、フルタイムで働かなくちゃならなくなって、きっとパパの病気もそのせい―」
「それ以上言うな、カースティ。それとこれとは関係ないだろ。親父は肝臓がんだったんだ」
「私が言いたいのは、ストレスが体に何かいい影響を与えるの? ってことよ」
「俺は、その2つに因果関係があるとは思えないって言ってるんだ。そりゃ、親父がまた事務所の経営を一手に担うことになったのは、不運が重なったのかもな...病気もひそかに進行中だったんだろうから。けど、俺たちだってもっと何かできたはずだろ」
彼女はそれについて少し考えているようだった。あるいは、ギャントン通りの実家での、あの時の家族会議を思い出しているのかもしれない。アンドリューは、失踪する数ヶ月前、俺たちを実家に集めた。ビジネスがまずい状況に陥っていることを打ち明け、家族に救いを求めたのだ。
彼女は「ギャンブル」という言葉を使ったが、アンドリューの場合、その言葉はぴったり当てはまらないかもしれない。彼にも少しは被害者という側面があったのだ。軍隊時代に知り合った友人からアドバイスを受けつつ、彼はさまざまな投資やファンドに資金を突っ込んでいった。アンドリューが退役して間もなく、そいつもアンドリューを追うようにして軍隊を辞めたそうで、今はロンドンの金融街で働いているという。そいつのアドバイスが全面的に悪かったと言いたいわけではなく、アンドリューにも不運が重なったということだろう。彼が資金を動かしている間に、なぜか金融危機がこの国を直撃し、この国の経済全体が停滞してしまったのだ。そんな時期にもかかわらず、彼は、こっちがダメならあっち、という風に、次々と投資先を変えていった。半分やけになっていたのだろう。まるでドッグレースで生計を立てようと意地になって賭けまくる、やばい男みたいに。
パトリックはあの日の会話を、まるで今朝の出来事のようにはっきりと覚えている。
「どうしてそんな?」と、ジェリー・カドガンが悲しそうな声でアンドリューに聞いた。「前回が最後じゃなかったのか?」
アンドリューは少しの間、逡巡(しゅんじゅん)しているようだった。ジェリーが言及したのは、2年前、アンドリューが悔恨(かいこん)の表情を浮かべ、両親の元へお金の工面を頼みに来た時のことだ。彼は軍隊を辞めた後、ある仕事に就いたのだが、3ヶ月も経たないうちに辞めてしまい、それからはニートのような暮らしをしていた。そんな彼を見るに見兼ねて、ジェリーとスーは彼に仕事を与えることにした。
パトリックと違って、彼は昔から家業にほとんど興味を示さなかった。そこで彼らの提案は、まず1年間、父親の付き人として〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉の経営面を学ぶ。それから数ヶ月、経理や給与計算といったマーケティングの面を母親から学ぶ、というものだった。そうして、彼は事務所の商業的な面を引き継ぐことになったのだ。引き継いだといっても、1年かそこらでポシャってしまったのだが。
「父さん、僕は稼げないんだ」と、彼はむせび泣き、しゃくり上げながら言った。ジェリーがアンドリューのために注いだウィスキーには、まったく手を付けていない。ジェリーは大きな失望と、それと同じくらい大きな愛情をもって息子を見つめていた。「商売がうまくいかないんだ。基本的なことはやってるつもりなんだけど、それ以外は、もう手が付けられない。だから―」
「なんてこった、アンドリュー」と、ジェリーは自嘲ぎみに言った。
「頑張ったんだ。本当に頑張ってはみたんだけど」
「あなたは会社のお金をギャンブルに使ったのよ」とスーが割って入った。「大金がすっかり消えたの、わかってる? アンドリュー。たくさんの人がうちの会社のために働いてるの。その人たちに給料を払わなければならないのに、あなたのせいで払えなくなりそうなんだからね」
「それは何とかなるさ」と、ジェリーが横から妻をなだめた。
「ギャンブルじゃないよ、ママ」とアンドリューが言った。「もちろんリスクはあるけど―」
「いい加減にしろ、アンドリュー。それをギャンブルっていうんだ」とパトリックが怒鳴った。カースティとジェシカもその場にいたが、二人とも口を開かなかった。「会社の資金をハイリスクな投資に突っ込むなんて、ふざけた真似を」
「みんなそうやって稼ごうとしてるんだよ」とアンドリューが懇願するように言った。「グラハムが言うには―」
「グラハムのことは忘れろ」とジェリーが言った。「今度あいつに会ったら、俺があいつの頭を引きちぎってやる」
「どれくらい必要なの?」とジェシカが、父親よりもだいぶ落ち着いた口調で聞いた。
少しの沈黙の後、アンドリューが再び口を開いた。
「2万」と、彼は伏し目がちにつぶやいた。「もうちょっと必要かな。今、ある仕事の見積もりをしていて...ちょうど2万ポンド(約323万円)くらいあれば」
重い沈黙がテーブルに降りてきた。パトリックには、その沈黙が何世代にも渡っていつまでも続くように思えた。窓から見える庭の温室で、これからはやばい薬草を育てて販売し、その売り上げを家業の財源に当てよう、とでもアンドリューが提案しているのではないか、そんな錯覚に陥りそうになる。沈黙を打ち破ったのはカースティだった。
「まさか本気じゃないでしょ? ねえ、アンドリュー。本気なわけないわよね?」
再び沈黙が舞い降りた。
「誰がそんな大金を持ち合わせてるっていうの? バカじゃないの、想像を絶するバカね」
「今持ち合わせてるとは思ってないけど...」
「なるほど。そうやって泣き崩しみたいに、みんながそれぞれせっせと貯めた貯金を引き出そうって魂胆(こんたん)ね。可哀想なあなたを救済するために」
「ビジネスだよ。僕のためじゃない。僕は自分で道を切りひらいていくよ。これは家業のために仕方ないことなんだ」
「アンドリュー、私はもうすぐ大学に行くの。学費で3万ポンドくらい必要になるんだから。パトリックは自分で仕事を始めて手一杯だし、ジェシには小さな子供が2人もいる。誰がそんな大金を出せるっていうの?」
「お前には期待してないよ」
「じゃあ、どうして私まで呼んだのよ?」
「家業のことだし、みんなで話し合った方がいいと思って。若いから発言権がない、ってことはないだろ」
「ずいぶん上から目線な言い草じゃない?」と彼女が半分立ち上がって、逆に上から目線でアンドリューを見下ろして言った。この発言をきっかけに、非難の応酬が始まった。四方八方から、「無責任」だの、「愚か」だの、「破産」がどうこうといった罵声が飛び交い、しっちゃかめっちゃかな喧騒(けんそう)が巻き起こった。パトリックはなんとか意味のある発言をとらえようと耳を澄ませたが、無理だった。アンドリューの声だけがまったく聞こえないことに気づき、彼の方を見ると、彼は喧騒の中で黙ったまま、兄をじっと見つめていた。その眼差しには、後悔とあきらめが滲んでいた。最終的に、ジェリーが「やめろ!」と叫んでその場を収め、全員をそれぞれの家に帰らせた。
あの時だったのだろうか? と、パトリックは当時のことを思い返していた。アンドリューがもうこの家族の一員ではないと腹を決め、出て行こうと決断したのは、まさにあの瞬間だったのだろうか。
案の定、ジェリーは彼にお金を渡そうと考えていた。数日後、息子に向かって彼は言った。「家を担保にして、その金でビジネスを立て直そう」と。そしてこう付け加えた。「もしこの金をお前自身の問題を解決するために使おうというのなら、お前はもう家族の一員ではない」とも。ただ、ジェリー・カドカンがその悪い知らせを伝えるよりも前に、アンドリューはすでに、出て行こう、と腹をくくっていたのかもしれない。
パトリックはこの10年、何度も繰り返し、あの時の彼を、あの瞬間の彼の表情を思い返していた。あまりにも繰り返し脳内再生していたゆえに、逆にその記憶がどこまで正確なものなのかがわからなくなってきた。あの時、アンドリューは微笑んでいただろうか? 涙を浮かべていただろうか? あるいは、もうこの家族は終わりだ、もうみんなが知ってる昔の家族ではない、と嘆くように首を振っていたのだろうか?
もしくは、ただ黙ってそこに座り、ごたごたの発信源は自分だというのに、周りで家族が言い争うのを彼は静観していた。そんな混乱の中にあっても、みんながそれぞれに家族の中の役割をしっかりと務めていた。ジェリーは家父長的な威厳を持って発言していたし、スーは家族の全員が平等に発言できるようにと配慮していたし、ジェシカは自分の人生のためになりそうなことは何でも取り入れようという心構えで振る舞っていたし、カースティは自己防衛にことさら躍起になり、理屈っぽく議論していた。
いったい何が起きていたのか、真実は一つしかない。それなのに、まるで俳優の〈過去の出演作ダイジェスト映像〉みたいに、いくつものバージョンがパトリックの脳内に去来するのだった。アンドリューが失踪してからというもの、何をしていても、罪悪感がつきまとった。あの時、何か悪いことが起こる、という予感はあった。こうなることはわかっていたのに、俺は何もしなかったのだ。結局のところ、アンドリューのことを、家族の誰よりも理解していたのは俺だった。そうだろう?
「じゃあ、どうしたらよかったの?」とカースティが言った。「私たちに何ができたっていうの? 私は19歳だったのよ」
「たぶん、お前じゃない」と彼は言った。「わからないけど、俺だ。俺が彼と話をするべきだったんだ。そうすれば、彼を救えたかもしれない」
「あなたにもそんな余裕なかったでしょ―」
「金のことだけを言ってるんじゃない、カースティ」とパトリックが、彼女の発言が終わらないうちに言った。「彼は俺たちの誰かから、思いやりを求めていたんだ。だけど誰も、それを差し出してやらなかった。みんなで彼を責めて、怒鳴って、彼のせいだとわめき散らした」
「それはそうだけど」と、ジェシカがゆっくりと熟考しながら言った。「でも彼のせいでしょ。彼が嘘をついたのよ。もしもっと前に彼が助けを求めてきていれば、私たちだって手を差し伸べていたでしょうね」
「『あんたの馬鹿な行いのせいでめちゃくちゃじゃない』」とパトリックが、ジェシカの言い方を真似て言った。「まさにあの時、君が言った台詞だ。覚えてるだろ? 君がアンドリューに言い放ったんだ」
「よしてよ、パトリック。今になってそんなこと言われても」
「君が言ったことだろ」
「私だって後悔してるわよ! これだけ時間が経てば...いろいろ状況だって違ってくる。っていうか、あなたはアンドリューを買いかぶり過ぎてるのよね。彼はとても壊滅的な人間なのよ。失踪したって、どこへ行ったって、彼がどういう人間かは変わらないでしょうね」
パトリックは反論しようとしたが、できないことはわかっていた。説得力もないし、正当性のある事例を持ち出すこともできない。軍を去った後、アンドリューは問題を次から次へと背負い込むようになった。彼の中で痛みはふくらむ一方で、彼は内側で誰にも届かない悲鳴を上げていた。21歳の時、彼は飲酒運転で捕まった。夜の街をほっつき歩いては喧嘩をし、また逮捕。朝方、パトリックが迎えに行くと、酔っ払い専用の監獄で彼はうずくまっていた。すべては彼の自傷行為のようだった。みんなが彼を曲解していた。どちらかといえば物静かで、根は優しい人間だと、家族はわかっていたはずなのに。
そして、もっと大きなこともあった。アンドリューがパトリックだけに打ち明けた、まだ誰にも言っていない秘密があったのだ。
「メルが妊娠したんだ」と彼は言った。ブライトンのパブ〈キングス・アームズ〉で、二人でギネス・ビールを飲んでいる時だった。「金曜日におろす。誰かに知ってほしくてね」
アンドリューはビールを一口飲んで、この話題を打ち切った。パトリックは、彼からもっと話を聞き出そうと、あれこれつついてみた。彼はそのことをどう思っているのか、その決断が下された時、彼はどういう態度をとったのか。しかし、「さあ」、「わからない」、「まあそうだね」といった返事ばかりで、アンドリューがこの件に関してこれ以上何も言うつもりはないことだけはわかった。メルは、アンドリューの人生を支えてきた唯一の存在だった。大学進学でブライトンにやって来て、街で彼と出会ったらしい。北部地方出身の素敵な女性だった。
堕胎手術から2ヶ月後、彼らは別れてしまった。
「わかってる」とパトリックは、ジェシカを見上げながら言った。彼はいっその事、すべてを話してしまおうかと思った。けれど、今がそのタイミングだろうか? こんな不安定な状況で話すべきことだろうか?
「俺たちの誰かが何かできたんじゃないかって今も思うんだ。彼が去ってしまう前に」
ジェシカ
やるせない表情の弟が椅子から立ち上がり、冷蔵庫を開けるのを彼女は見ていた。彼は缶ビールを取り出し、リングを勢い良く引くと、ごくごくと飲み始め、すぐに口の周りがビールの泡であふれた。
「このあと運転するんじゃないの?」とカースティが、いぶかしそうに聞いた。「スコットランドのトロサックス国立公園に着いたら飲むぞって、さっき言ってなかった?」
「もうトロサックスなんてどうでもいい」と彼は言った。「とにかく1杯飲まなきゃいられない」
ジェシカは舌の先まで出かかったことを口に出すべきかどうか悩んでいた。今こそ正直に胸のうちを明かす時だと思った。父親は娘と息子が償いをすることを望んでいる。その父親の思いに向けて、少なくとも何らかの反応は示すべきじゃないか。私たちは過去の清算を始めなければならない。このままでは、いつまで経っても過去からの湧き水はあふれ続ける。
「あの辺りを運転するには、シャキッとした頭じゃないとダメでしょ。地図によると、かなり曲がりくねった山道よ」
「じゃあ、お前が運転しろよ。シフトを入れ替えればいい」
「パトリック、そういう問題じゃないの」
アンドリューのことを話そうという彼の主張は、一応の成功をもたらし、それぞれが過去を顧みて、因果関係について思いを巡らせることにはつながった。けれど、誰も結論にはたどり着かなかった。彼がなぜ去ったのか、確かなことは誰にもわからなかったし、今彼がどこにいるのかについては見当もつかなかった。
ジェシカは釣り具箱の中に手を入れ、2冊目のアルバムを取り出した。少し埃をかぶって、へこんではいるが、パスポートのような赤色をしたアルバムだった。
「まだダメって言ったでしょ」とカースティが言った。
「そうだったわね。でも、誰かが来てくれるまでしばらくここにいることになりそうだし、それに、キャンプ場に着く頃にはもう疲れ切っちゃって、アルバムどころじゃないわ。朦朧(もうろう)としながら見てもしょうがないでしょ」
「ジェシ」
「彼女の言うとおりだ」とパトリックが言った。「業者の人がここに到着するまで2時間かかると言われた。もっとかもしれない。ここでアルバムを開いた方がよさそうだ。それとも他に話すことでもあるのか?」
「それじゃ、あなたはこの旅を続けるつもりなのね?」とカースティが聞いた。「遺灰をその辺のどぶ川に捨てるんじゃなかったの?」
「カースティ」と、パトリックがたしなめるように言った。
彼女は、わかったわよ、といった表情で折れた。ジェシカがアルバムを3人の中心に置き、再び電気ケトルのスイッチを入れた。表紙をめくると、最初のページに写真が2枚あった。低いレンガ壁を背に家族全員が並んでいる写真と、もう1枚は、パトリックとアンドリューが二人して釣り竿を持っている写真だった。
2000年6月 — フランス・ロワール渓谷、バズージュ・シュル・ル・ロワール
あの家族旅行は、ジェシカの大学卒業を祝って企画されたものだった。彼女は22歳で、ロンドン大学で3年間英文学を学び、さらに1年間、カナダのバンクーバー島にあるビクトリア大学で交換留学生として学んだ。
控えめに言っても、カナダとロンドンでの体験がジェシカを変えたのは間違いない。本好きでためらいがちだった少女は、ロンドンのホルボーン地区でルームシェアを経験し、カナダにも留学して、4年後、父親の運転する〈トランジット〉の荷台に荷物を詰め込んで、助手席に乗り込み、ブライトンに帰ってきたわけだが、なんとスタイリッシュで都会的なタイプに変身していたのだ。アメリカンなラップ調の表現をふんだんに使いこなし、出版社や音楽業界に就職した友人たちとも積極的に交流を続けることで、音楽や文学の最先端に身を置いていた。インターネットの創生期にあって、彼女はすでに電子メールを使って彼ら全員と連絡を取り合っていた。(「ビジネスに役立つから」と聞こえがいいことを言って両親を説得し、実家に導入したのだ。当時はダイアルアップモデムを使っての接続で、画像もじわじわと表示されるという辛抱強さを鍛えられる通信速度だった。)
フランス旅行では1週間コテージを借りて、そこで過ごしていた。その家は広い庭付きで、ジェシカはほとんどの時間を庭の椅子に座り、アレックス・ガーランドの、読み古して表紙の傷んだ『ザ・ビーチ』を読みふけっていた。その本を読んでいると、彼女は無性にタイへ旅行に行きたくなってきた。半年後、その年の暮れに友人の3人がタイ旅行を計画していることを思い出し、それに参加したくなったのだが、もしかしたらその時期、大手出版社の〈ペンギン・ブックス〉でインターンシップに参加できるかもしれなかった。給料はもらえないが、もう一度ロンドンに進出するチャンスでもある。本を読みながら、〈ディスクマン〉というポータブルCDプレーヤーのイヤホンを耳に突っ込み、彼女はジェフ・バックリィのアルバム『グレース』を聴いていた。以前は彼の曲を半分くらいは知っていて、まあまあ好きという程度だったのだが、ボーイフレンドのピーターに勧められ、さらに多くの曲を聴き込んでいた。彼は経済学部の学生で、シンガーソングライターとして成功することを決意しつつ、アメリカの政治にも並々ならぬ関心があるらしく、そういったことをジェシカに熱く語ってみせる男だった。
「10分後にランチが出来上がるわよ」スーが暗いキッチンに続く小さな木製のドアを開いて、外へ声をかけた。ジェシカはページの端を折りたたみ、顔を上げた。ちょうど妹が、水着から水をしたたらせながらプールから上がるところだった。ジェシカはその姿を見届けると、デッキチェアにあおむけに寝そべった。
そのコテージは今にも崩れ落ちそうな、おんぼろ小屋だった。周りにも同じような小屋がいくつか集まっていて、それらの中心に、同じくおんぼろのひときわ大きな邸宅がそびえ立っていた。所有者は一風変わった女性で、彼女自身の話によると、彼女は1970年代、『ヴォーグ』のモデルになろうと意を決して、ロサンゼルスからパリに渡ったが、結局はシェフとして成功したのだという。彼女は夏の数ヶ月間、この邸宅を貸し出すことで臨時収入を得ているそうだ。
ジェリーは様々な家の補修工事をしながら、「1週間ほど家族みんなで過ごせるくらい広々としていて、しかも格安な貸家はないか」と聞いて回っていたところ、クライアントの一人からこの邸宅の情報を得たのがきっかけだった。ここの最大の魅力は、カドガン一家それぞれのメンバーが別々のコテージで思い思いに過ごせることで、夕方には共有の庭やキッチンにみんなで集まれることだった。暖房がないこと、それからネズミが多いことは少し不満だったが、家賃の安さを照らし合わせて考えると、それらの欠点は目をつぶることにした。
ジェシカはジェフ・バックリィのアルバムを3曲飛ばして、中でも一番好きな『ハレルヤ』を聴き始めた。しかし彼女はそのことをピーターには決して言わないことにしていた。彼にしてみれば、『ハレルヤ』が一番好きとか、ありきたりすぎて鼻で笑われるのが目に見えていたし、『ハレルヤ』なら、レナード・コーエンのバージョンの方が断然いいから、と、またあの渋い歌声を聴くように強要されるだけだから。
「俺は噂で耳にした、ふふふーーん」と彼女はジェフ・バックリィの歌声に合わせて、口ずさんでいた。実際の彼女の歌声は、どんよりとくぐもっていたが、ジェシカの頭の中では、綺麗に澄んだ歌声が天に舞い昇っていった。
カースティがやってきて、隣のサンベッドに寝そべった。彼女はまだ11歳という多感な年頃で、姉みたいになりたい、とジェシカを尊敬していた。ジェシカはそんなカースティに、10代の楽しい世界をそれとなく吹き込んでいた。たまに夕食時にちょっとワインに口をつけるところを見せつけたり、ボーイフレンドの話や、セックスの危険性について話して聞かせたりしていた。妹を守りたい気持ちもあったが、同時に、カースティが13歳になった時、当時の自分よりも少し経験豊かで、いろんな知識もある女の子に仕立て上げることができるんだ、という自覚もあった。
ジェシカは微笑みながら目を閉じ、数分間リラックスしていたのだが、ガタガタとでこぼこの地面を、泥除けを揺らしながら走る自転車の音が近づいてきて、アルバムへの集中が途切れた。ちょうど『ハレルヤ』が終わったところで、一瞬の無音の後、ひずませたギターリフが勢いよく流れ出し、猫が威嚇(いかく)するような声で、ジェフが次の曲を歌い出した。この曲を好きなふりをしないといけないかも、と彼女は思いながら、自転車の音から音楽に意識を集中させた。彼女は『ハレルヤ』の方が断然好きだったのだが、今度ピーターに会った時、またこのアルバムの分析的すぎるうんちくを聞かされたあげく、この曲よかっただろ? と聞かれることがわかっていた。
自転車を押して、アンドリューが先に門をくぐってきた。カゴの中には、半分食べたらしいフランスパンと、使い古して傷んだエナメル生地の鞄、そしてTシャツが入っていた。ジェリーもすぐ後から敷地内に入ってきた。2本の釣り竿と、赤い釣り具箱を持っている。1年前、アンドリューが父にプレゼントした釣り具箱だった。アンドリューは最近では、土曜日に近くのパブまで父親についていくようになっていた。ジェリーの自転車のカゴには、空のビール瓶が入っていて、カチャカチャと音を立てていた。彼が3、4本、おそらくアンドリューも1本、飲んできたようだ。
「何かつかまえたか?」とパトリックが、新聞から顔を上げて言った。町の小さな店で買ってきた昨日の『デイリー・ミラー』を一丁前に読んでいたのだ。
「スズキが何匹か」とジェリーが言った。「鯉がかかったと思ったんだけどな、ビチャビチャと暴れて逃げられちまった。今度はお前も来るだろ?」
「たぶんね」
「1日前に起きたことを見てるより、ずっといいぞ。古いニュースだろ、そんなの」
「情報に追いつこうとしてるんだよ。っていうか、ロワール渓谷に行くのなら、俺も行くって言っただろ。ボートか何かを買ってさ」
「お前はどうする?」とジェリーは言って、ジェシカを見下ろした。彼女はデッキチェアに寝そべって、赤の〈Nokia 3210〉を指で叩いている。まだ画面が小さくて、液晶の文字しか表示されない携帯電話だったが、大方、ボーイフレンドとメールでもしているのだろう。
「釣り?」と彼女が言った。父親から急に、スカイダイビングでもするか? と誘われたかのような反応だった。
「そうだ、あそこはいいところだぞ。湖の静けさ、緑の木々に囲まれて、鳥のさえずりに耳を澄ます。大きな古いオランジュリーもあるんだ。昔はあの温室でオレンジを栽培してたんだろうけど、今はがらんどうだ。いい感じに改装すれば、何かの会場になるのにな」
「こうしている間も時間がもったいないから、何か仕事に自分を売り込もうとしてるのよ、パパ」と彼女は笑顔で言ったが、画面を見たまま、作成中のメッセージから目を上げなかった。
「俺は昔から働き詰めだ。お前らに愛情を注ぎすぎて、干からびそうだよ」
ジェリーは自転車を壁に立てかけ、その横に釣り竿を置いた。そして、パトリックが日光浴を楽しんでいる長椅子の端に腰を下ろした。「お前はそうやって、俺が稼いだ金を大西洋に流してるんだ。ロンドンに何度も何度もメールを送って」と、彼はジェシカに言った。彼女のボーイフレンドがロンドンではなく、英国のどこか別の場所に住んでいれば、通信料はもっと安くなるとでも言いたげな口調だった。「1通3ポンドだぞ」
「3ポンドもしないわ」
「そうか、じゃあ請求書が届いても、俺のところに持ってくるなよ。血まみれの大惨事になりかねない」
「パパの愛情で回避できるでしょ」
「いいや」と、ジェリーは冗談めかしつつも、きっぱり言うと、長椅子から立ち上がり、屋内へと入っていった。
ジェシカは昨日の口論を思い出していた。出発前に2回ほど、ピーターのことで両親ともめたのだ。彼女はこの旅行にピーターも連れて来ると言い張ったのだが、これはあくまでも家族旅行なんだ、と諭(さと)された。―家族全員で遠出するのは最後になるだろうから。カドガン家の年長組はもうすぐ、親と旅行なんて行かない、という年頃に達する。その前に、いわば最後の記念として、家族水入らずで過ごしたいんだ、と。
シュノンソー城の敷地内を散策している間、カースティはジェシカの携帯電話で延々と〈スネーク・ゲーム〉をしていた。中庭のカフェで飲み物でも飲もうということになった時、ジェシカの携帯電話は充電が切れてしまった。それがきっかけとなり、いつものいざこざが始まった。
「充電しておけばよかったのに」とスーが言った。ジェリーはカウンターで、6杯分の50ユーロほどを支払っているところだった。
「私が普通に使ってる分にはそんなにすぐ切れないわ。ていうか、なんであんたはこんなところまで来て、ゲームばっかしてんのよ?」
「退屈だったから」と、カースティは弁解するように言った。
「まったくもう。これでピーターからメールが来ても、私は気づかないままね」
「こんなところでやめなさい」と、スーが声を抑えつつ言った。そこへジェリーが、コーヒー3杯、コーラ2杯、アイスティー1杯を載せたトレーを持って戻ってきた。
「ここも紅茶はないんだとよ」と彼が言った。「またクソまずいアイスティーを買うはめになった」
「フランス人は紅茶を飲まないのよ」と、ジェシカがたしなめるように言った。「みんながみんな、あなたと同じようにするわけじゃないのよ」
「ったく、また喧嘩か。今度は何があった?」
「カースティが私の携帯を―」
「P-E-T-E-R(ピーイーティーイーアー)」と、スーがほとんど疲れ切ったような声で、ピーターの名前のスペルを一文字ずつ言い、遮った。
「おいおい、どうした。いったい何なんだ?」とジェリーが言った。
「私の携帯が死んだの。カースティが殺した。これで彼がメールを送ってきても、私は全く気づかない」
「そんなの1時間か2時間だろ。それくらい我慢できないのか?」とパトリックは言うと、新しく火をつけたタバコを一服吸って、煙を吐き出した。
「タバコなんかやめてほしいわ」とスーが彼に言った。
「なんなら俺も、タバコなんかやめたいんだけどね、ママ」と彼は言って、喫煙習慣についての議論を打ち切った。数ヶ月前のある晩、偶然にも両親が同じパブに来ていて、タバコを吸っているところを見られ、それからは開き直って隠すのをやめたのだ。
「まだ早いだろ。何をそんなに急ぐことがある?」
「もう私には、メールが来ても知る術がないのよ。それに、最初から彼も連れてくれば、こんなことにならずに―」
「ダメだ、ジェシカ。それはどうしてもダメなんだ。これは家族旅行なんだ。たぶん最後になるだろうな。こうして家族水入らずで。もしお前がそのバカと結婚しているのなら、そいつも家族ってことになるが、そうじゃない。お前はもう子供じゃないんだから、そんなわがままは言うな」ジェリーがそう言うと、ジェシカは怒って、すたすたとコテージの方へ戻っていった。ピーターに一度も会ったこともないというのに、ピーターをバカ呼ばわりしたことに対して、スーがジェリーを叱責した。
その夜、二人はコテージのリビングで一緒に過ごし、和解した様子だった。ジェリーは〈ペルノ〉の水割りをマグカップで飲んでいた。ジェシカはリビングの隅で本を読みながら、白ワインをすするように飲んでいた。実際のところ、ジェシカは心の底では気づいていた。もし仮に、ピーターをこの旅行に誘ったとしても、どうせ彼は断ってきただろう。フランスの田舎のコテージで、初めて会う家族と一週間を過ごすなんて、(一人だけ浮いてるようで気まずいだろうし、家族独特の風変わりな習慣に合わせるのも大変だろうし、)彼にとって最高の休日の過ごし方とは言えないはずだから。
その日、ピーターは一度もメールをしてこなかった。というか、その前日も、その翌日も、ホーブを出発してからというもの、一度も彼からメールはこなかった。ホーブでは、運転免許を取ったばかりのジェシカが、親の車を借りて出かけることが多くなり、ジェリーは思い切って、新しくキャンピングカーを購入したのだ。そのキャンピングカーで今回のフランス旅行にやってきたわけだが、休暇を1週間ほど延ばして、帰りはゆっくりと、海岸沿いのブルターニュ地方やノルマンディー地方を経由しつつ、車から視界に広がる海を横目に、家に帰ろうという予定だった。
実は、彼女が今、携帯の画面を見つめ、どう返信しようかと考えているメッセージは、ピーターからではなく、ダンという名の男の子から送られてきたものだった。3週間前、ジェシカはピーターと大喧嘩をした。きっかけは、一緒に映画館で見たブラジル映画が気に入らなかったとか、そんなことだったと思う。腹立たしい気持ちを抱えながら、その夜ブルームズベリーのカクテルバーに行って、一人で飲んでいたら、声をかけてきたのがダンだった。ジェシカは酔った勢いで、彼に聞かれるままに電話番号を教えた。彼女の大学時代の同居人だったアンドリーアと、彼が友達だったという偶然も後押しした。アンドリーアは怠け者のイタリア人で、四六時中タバコを吸っているような女の子だった。コーヒーも、そんなに飲んだら体に悪いよ、とジェシカが忠告しても、がぶがぶと体内に流し込んでいた。
ダンが彼女に好意を抱いていることは明らかだった。この最新のメッセージもまた、頻繫に届く一連のメッセージ同様、遠回しにさりげなくジェシカをデートに誘おうという意図が読み取れた。彼は魅力的ではあった。ただ、彼女が将来のパートナーに求めている、自由放浪なボヘミアン的、芸術的な輝きが彼にはなかった。たとえピーターとうまくいかなくても、ダンみたいな堅物(かたぶつ)の経営コンサルタント見習いと一緒になるなんて、ジェシカにはイメージが湧かなかった。
彼女は携帯電話のボタンを両手の指で押し続けた。数字や文字を入力するたびに甲高いビープ音が鳴り響き、彼女以外の家族全員にはそれが耳障りだった。
こんにちは、ダン。返事が遅くなっちゃって、ごめんね。テヘペロ😜 今、家族とフランスなうなの。来週は無理だけど、それ以降なら大丈夫かな? 返信してね😘
送信ボタンを押してすぐに、なぜ「返信してね」なんて付け足してしまったのか、自分の気持ちを不思議に思った。礼儀として書いたのよ、と一応結論付けた。1ヶ月後くらいに、夏が終わったら私は再びロンドンへ引っ越す。その時の友達として、一応彼をキープしておきたかった。大学時代の友達のほとんどは、卒業後に故郷の町や村に帰ってしまった。まるで壊された巣から一目散に逃げ出す蟻たちみたいに、散り散りになってしまった。今もロンドンにいるのは、ダルストンで母親と暮らしてる、元々ロンドンっ子のナタリーと、ピーターくらいね(といっても、ピーターはそのうちバンド活動が忙しくなって、ツアーでなかなか帰ってこなくなるんだろうけど)。それから、スチュ・アンダーソンもいるけど、彼は、私の友人というよりは、パトリックの連れで、今はゴールドスミス・カレッジの1年生。マーケティングの学位を取ろうとしてるみたい。そんな感じで、あまり知り合いがいないロンドンに、ダンみたいな、親しみやすい友人がいると安心するのよね。
「ランチよ! みんな集合!」スーがコテージの中から声を張り上げた。さっき10分でできると言っていたが、あれからすでに30分近く経っていた。
パトリックが最初に駆けていき、カースティがそれに続いた。ジェシカはアンドリューと話をしようと、彼の方へ寄っていった。彼はその週、存在感を消しているように静かだったから、少し心配だった。
「釣りはどうだった?」
「いい感じだったよ。2、3匹釣れた」と彼は言った。「でも、どっちかというと、パパの活躍かな?」
「あなたも釣り好きだと思ってたけど」
「まあ、好きは好きだよ...でも、他にも好きなことがいろいろあるから」
「写真を撮る方が好き?」
「そうかもね。でも、パパには―」
「言わないわよ」とジェシカは言った。
「今の感じがパパにとってはいいんでしょ? 家族の絆とか、そういうのが好きだから。もし僕らの誰も手を挙げなかったら、パパは、そうか、と言って、一人で釣りに行っちゃうよ」
「あなたはパパのことまで心配しなくていいのよ」
「それはわかってるんだけど、ただ...僕らがみんな成長しちゃったらさ、こういうこともできなくなるだろうし。君だって、なぜかまたロンドンで暮らそうだなんて、妙なこと考えてるんだろ? パトリックもロンドンにアパートを借りるとか言ってるし。そうすると、僕とカーストだけになっちゃうでしょ」と彼は、カースティの子供の頃からのニックネームを口にした。
「それで、あなたはどうなの? 大学進学とか考えてるわけ?」
「たぶんね。パパが言うには、僕には家業を継ぐ素質があるってさ」
「パパはみんなにそう言ってるのよ。あなた自身が本当に興味あるかどうか、そこを見極めないとね」
「ほら、二人とも早く来なさい」とジェリーがテーブルから声をかけてきた。ジェシカは、自分とパトリックがまだプールサイドでぐずぐずしていることに気がついた。
「あなたなら大学でもうまくやっていけるわ。あなたには光るものがあるんだから」
「でも大学なんて、ちょっと時間の無駄って気がする。そうじゃなかった?」
「全然そんなことなかったわ。新しい場所に行って、いろんな人と出会う。働くのはあとからでも、それこそ何十年だってできるんだから」
「かもね」と彼が言ったところで、二人はテーブルにたどり着き、食卓についた。
ジェリーはアンドリューの前にフレンチ・ラガービールの小瓶を置き、ジェシカの前にはグラスに入った白ワインを差し出した。みんながパンをほおばり始め、大きなボウルに入ったサラダを取り分けたり、プレートからハムを小皿に移したりしている間に、ジェリーはトランプをみんなの前に配った。
「よし。ババ抜きするぞ」と彼は言った。
「縦に一列だぞ」ジェリーが自転車の隊列の最後尾から呼びかけた。翌朝のことだった。その日が最終日で、翌日には荷造りをしてキャンピングカーでイギリスに戻る予定だった。彼らは自転車でまっすぐな並木道をゆっくりと、一番近い町へと向かっていた。ジェシカが先頭を走り、パトリック、カースティ、スー、アンドリューと続き、最後尾でジェリーが、まるでツール・ド・フランスのアシスト選手のように、前のメンバーを観察し、統制していた。
ラ・フレーシュという町は、サルト川が枝分かれして細くなったロワール川沿いにあって、小さいながらも賑やかな市場町(いちばまち)だった。市場は朝から賑わっていて、野菜や肉、衣服や家畜などを買い求める地元の買い物客でごった返していた。中には観光客も混じっていて、はにかみながら「ハムを8切れください」と言ったり、あるいは、屋台の店主の誠実さを信頼して、おすすめの野菜を見繕ってもらったら、一家では食べ切れないほどどっさりと、大量の野菜を受け取るはめになったりしていた。
町に着くと、ジェシカは、自転車をチェーンで繋いでおける脇道へとみんなを誘導した。彼女は他の家族よりも、ラ・フレーシュに詳しかった。みんなに内緒で、今週すでに3回もここを自転車で訪れていたのだ。町のインターネットカフェに入り、ピーターからEメールが届いていないか、メールアカウントを確認するのが主な目的だった。それから彼女は、河原のベンチに座って、川の流れを時折り見下ろしながら、面白くもないサルトルの小説を読みつつ、フランスのタバコ〈ゴロワーズ〉を吸う時間が好きだった。
「みんな一緒に行動しようじゃないか、な?」とジェリーが言った。質問のような言い方だったが、実際には命令だった。休暇も残り少なくなってきて、できるだけ長く家族を一つに繋ぎとめておこうと、彼は必死だったのだ。
「なんでだよ? パパ」とパトリックが言った。「俺は、いい感じのバーを探したいんだ。パパとママはバーベキューの材料を買うんだろ? アンドリューは、ガチョウか、なんていう鳥だか知らないけど、河原でそういう写真を撮りたいんだろうし。女子二人は洋服を見に行きたいんだろ」
「性差別主義者ね」とジェシカが言った。
「は?」と彼は顔をしかめて言った。その言葉を聞いたこともなければ、ましてや自分がそうだと言われたことなど一度もない、というような顔だった。「俺が言いたいのは、みんなそれぞれ自分のことは自分でできるだろ?ってことだよ。俺たちは迷子になんてならない。もう6歳じゃないんだから」
「もういい。わかった」とジェリーががっかりしたように、弱気な口調で言った。「じゃあ、1時間後に、またここに集合しよう」
家族は解散した。パトリックが真っ先にその場を離れ、フランスの安いラガービールが飲め、英字新聞が置いてあるようなバーを探しに行った。カースティは両親について行くことにした。先日、携帯電話のバッテリーの件で姉に怒鳴られて以来、まだ少し怯えが残っていて、姉と一緒にいたくなかったのだ。その場には、アンドリューとジェシカだけが残った。
「君について行ってもいいかな?」と彼が言った。「もしよければ」
「もちろん。私はピーターへのお土産に何か探そうと思ってるの。チーズがいいかな。でもパトリックには内緒よ。フランス産の臭いチーズをひとたま車に積み込んでイギリスまで帰るなんて言ったら、文句を言い出すに決まってる。けど、言わなきゃ絶対気づかないから」
アンドリューは微笑んだ。言えてる、と思った。パトリックはまさにそんな感じなのだ。先に口が出る性質(たち)で、いつも何かに文句を言っている。そのくせ現実に対処することは後回し。そのことで、ジェリーはよくパトリックをからかっていた。商売人の素質がある、と言わんばかりでもあった。〈カドカン・ファミリー・建築士事務所〉に出入りしている請負業者のほとんどが、口八丁で文句ばっかり言ってる人たちだったから、その文化がすでに身に付いていたのだ。
「あなたは何したい?」と彼女が聞いた。
「僕は何でも構わないよ」と彼は言いながら、カメラを構えた。彼はカメラを二つ所有していた。一つはクリスマスにもらったデジタルカメラ。今手に持っているのはもう一つの方で、高価なフィルムを使用し、フラッシュを取り外せるキャノン製のカメラだった。彼が卒業制作のアートプロジェクトで使ったもので、ギャントン通りの邸宅の1階のトイレに暗幕を張っては即席の暗室をこしらえ、彼は自分で写真を現像していた。
「いい写真撮ってよ」と彼女は、カメラを目の高さまで持ち上げた彼にエールを送った。彼は、ローストチキンを買おうと屋台の店主にお金を差し出す老人の写真を撮ろうとしていた。
「昨日君が言ってたことについて、考えてたんだ」と、カメラを覗きながら彼が言った。「大学とか、そういうこと」
「よかった。大学は行った方がいいわ」
「こんなこと言うと、君はどう思うかな?」
「何?」
「軍隊。入隊しようかなって考えてるんだ」
ジェシカはショックを受けたようだった。彼が軍隊に興味を持っていることは彼女も前から知っていた。―彼は青春時代の多くをボーイスカウトの活動に費やし、その年月を、いわば入隊への見習い期間として考えているらしいことも知ってはいたが、軍隊を生涯にわたる職業として考えた時、その考えは捨てたものと思っていた。10代のアンドリューはあまりに繊細で、内気な性格だったから、軍隊の中でやっていくのは到底無理だという印象だった。
「何?」と彼が聞いた。
「ちょっとびっくりしちゃって。大学へ行くのかと思ってたから」
「大学なんか行ったって、僕には学ぶべきことがないよ」
「写真は?」
「写真は趣味だよ」と彼は言った。「パパがなんて言うか考えてみて。ミッキーマウスに関する学位でも取るのか?って。ほら、マリアンヌがファッションを勉強してるって言った時も、パパはそういう反応だったじゃないか、そんなの意味ないって感じでさ」と彼は、いとこのマリアンヌを引き合いに出した。
「セントマーチンズで芸術を学ぶとか」と彼女は言った。アンドリューは大して魅力を感じなかったが、彼女の声に真剣な重みを感じたので、一旦受け止めることにした。
「そうだね。まあ、来年が僕の高校生活最後の年になるから、今決めなくてもってことでしょ? 考える時間はたっぷりある。ただ問題なのは、僕には他に何も得意なことがないってことなんだ。君もそう思うよね? ママに言われて数学のAクラスを履修しちゃったけど、さっぱりついていけないし。数学は苦手。あと歴史も」
「でも、美術は得意でしょ?」
「まあ、多少はね。職業にするほどじゃないけど」
彼が殻に籠(こも)ろうとするように萎縮していくのを、ジェシカは感じ取った。二人は道路を渡り、ロワール川にかかる灰色の石橋までやって来た。彼女は橋の欄干(らんかん)に背中をつけ、空を仰いだ。彼の眼下では川が静かに流れ、茶色の水面(みなも)に太陽の光が降り注いでいた。小さな島のように地表が浮き出ている箇所がいくつか見受けられる。アンドリューは、カワセミが青い羽をきらめかせながら、水面を滑るように横切っていくのを見た。
「私が言いたいのは、考えた方がいいよってこと。それだけ」
「もう考えることなんて何もないよ」
「え、じゃあ、もう決めたってこと? それが軍隊?」
彼は頷いた。
「希望は落下傘連隊。あのドキュメンタリーを見て、入りたいって思った」
「グラスゴー芸術大学とか、どこかの入学案内を私が持ってきたらどうする? それで起こりうる最悪の事態は何?」彼女はそう言うと、ハンドバッグを開けた。
ジェシカはタバコとライターを取り出し、市場の方をチラッと振り返ってから、アンドリューに背を向け、タバコに火をつけた。
「ねえ。これはママとパパには内緒よ」
「僕も...いい?」と彼が言った。
「あなたも...吸うの?」
「時々ね。家では吸わないけど、外でたまに」
彼女はパッケージを彼に差し出した。彼はそこからタバコを一本抜き出し、ライターも受け取った。
「ママとパパはなんて言うと思う? このことを話したら」
「軍隊のこと?」
アンドリューは頷きながら、タバコを一服吸い込んだ。
「それは反対するでしょうね。ママは危険だって思うだろうし。パパも、もどかしい気持ちになるんじゃないかな。おじいちゃんの影響でそんなことを言い出したんだって、パパは思うんじゃない?」
「おじいちゃんは関係ないよ。堅物(かたぶつ)で、偉そうで、真似したいなんて思わない」
「じゃあ、なんで?」
アンドリューはタバコを吸う手を止めて、しばらく考え込んだ。
「誤解を恐れずに言えば」と彼は切り出した。「僕は今まで、自分が馴染めてるっていう感覚を持ったことがない。故郷というか、ブライトンが自分の町だとは思わないし、あの辺りにずっといたいとも思わない。軍隊は人生の選択になるでしょ? 入隊したらあちこち遠征に出るし、この先の仕事とか、友達とか、くだらないあれこれを心配する必要もない。すべてはそこにあるんだ」
「あなたがそう言うのなら」ジェシカは幅の広い欄干の上にひょいと腰を下ろし、足をぶらぶらさせた。タバコの煙をふーっと吐き出して、髪を耳の後ろにかき上げたところで、後ろから風が吹き付け、再び髪の毛がさらっと顔にかかった。「あなたは正しいことをするのよ」
「そのまま、そこに座ってて」とアンドリューが言って、カメラのレンズを外し、付け替えた。ジェシカがタバコを口にくわえている間に、彼は立て続けに3枚の写真を撮った。これこそ、この不確かさこそ、デジタルカメラでは味わえない、フィルムの醍醐味だった。背景に写り込んだものが、意図したイメージとは完全に異なる写真にしたり、風やタバコの煙で、姉のシャープな顔立ちが隠れたり、むしろ乱れた髪がメインに強調されたり。そんな不確実性があるからこそ、フィルムカメラは手放せない。
「やばい」とジェシカが言って、欄干から飛び降りた。「タバコを消して。みんながこっちに来る」
アンドリューは首にカメラをかけたまま、半分吸ったゴロワーズの火を欄干に押し付けるようにして消し、吸い殻を川に投げ捨てた。ジェシカがこっそりと彼にミント・キャンディを差し出しながら、近づいてきた両親とカースティの方に顔を向けた。
「全部買い終わったの?」とジェシカが言った。
「お父さんが言うには、まだだけど」と、スーは重そうな野菜の袋を二つ持ちながら言った。「でも、これ以上は持てないわ」
「じゃあ、食料が足りなくなったら、お前の見込み違いってことだな」
「なんか、この辺りはタバコの匂いがするわね」とスーは言いながら、タバコを吸っている人が近くにいないか、辺りを見回した。
「ここはフランスだぞ。どこもかしこもタバコの臭いがプンプンしてるんだ」とジェリーが言った。
「フランスも路上喫煙を早く禁止した方がいいわ」
「フランス人にそう言ってみろ」とジェリーが言ったところで、パトリックが道路を横切って、ゆっくりとした足取りでやって来た。「じゃあ、みんな揃ったことだし、いい機会だ。みんなで写真を撮ろうじゃないか」
「僕が撮るよ」とアンドリューが手を挙げた。彼はカメラの前に立つよりも、後ろからレンズを覗き込む方が幸せを感じるのだ。
「ダメ。誰かに撮ってもらいましょ」とスーが言って、通りすがりの買い物客の方を指さした。
「ちょっと待って」とアンドリューが言った。「みんなこっちに来て、このベンチの前に並んでみて」
家族全員がそうすると、彼は川を見下ろす塀の上にバランスよくカメラを置いた。
「私のカメラでも撮ってみて」とスーが言って、彼女のデジタルカメラを彼の方へ差し出した。「デジカメだとどんな風に写るのか見てみたいわ」
銀色の小さなデジカメと、自分の一眼レフを並べ、彼はそれぞれの見え方を確認すると、タイマーを10秒後にセットした。
「準備はいい?」と彼が声を上げた。そして、カドガン家のみんなが身支度を整えたところへ、彼も駆け寄り、カースティの肩に腕を回しているジェリーの隣に立った。数秒後、2つのカメラが連続してカシャカシャッとシャッターを切る音がして、彼はカメラを回収しに戻った。
アンドリューが母親にデジタルカメラを手渡すと、彼女はすぐさま画像を確認し、家族全員が写った最後の休暇旅行の写真を眺め、ワーッなどと甲高い声を上げ始めた。彼はカメラをいじりながら離れて行き、ジェシカも彼の後を追った。
「それで、みんなに言うつもりなの? あなたが将来どうしたいのか」
「最終的には、そうだね」
「やっぱり考えてみた方がいいと思うの。大学のこと」
「わかってる」と彼は言った。「でも僕は行かないよ」
みんなが自転車を置いた場所までたどり着くと、ジェシカはため息をつきながら、全員分のチェーンの鍵を開け始めた。
「あの写真、私にくれる? 私が一人で写ってるやつ」と彼女は言った。「現像したら、ちょうだい」
「欲しければあげるよ。写りがいまいちかもだけど」
「きっと素晴らしい写真よ。私たち全員の集合写真はどうかしらね? あれはママに渡すの?」
「さあ」と彼は言った。「あれは自分で持っておこうかな。入隊したら、部屋の壁に貼っておけるから」
アンドリューは微笑むと、自転車にまたがり、真っ先にスタートしたパトリックを追うように、ペダルを踏み出した。他の家族はまだ、買い物袋を自転車のカゴに入れたりしている。ジェシカも自転車をこぎ出そうとした時、母親が彼女を呼び止めた。
「彼は大丈夫?」
「ええ。大丈夫だと思う」
「なんだか、おとなしいみたいだけど」
「彼は元気よ、心配しないで。今はちょっと考え込んでるだけだから」
ジェシカはサドルにまたがると、後ろを確認し、道路に向かって勢いよく自転車をこぎ出した。彼女はすぐに二人の弟に追いつき、リズムをとりながら家まで走行した。そんな風に、彼らは休暇の最後の一日を満喫した。
グレットナ
ジェシカ
「ちょっと待ってて」と彼女は言って、お茶を飲み干した。
ジェシカはキャンピングカーの後ろに行って、自分の荷物をかき回すように、あるものを探し始めた。バッグの中から日記帳を探(さぐ)り当てると、その背表紙に挟めておいた写真を引き抜いた。アンドリューがラ・フレーシュの橋の上で撮った写真だ。風に髪をなびかせる自分の姿を見て、彼女は一気に昔の自分に引き戻された気がした。タバコを手に持ち、体にぴったりフィットした赤いTシャツを着て、デニムのショートパンツから白い腿(もも)がむき出している。夫のダンでさえ、彼女がかつてタバコを吸っていたことを知らない。アンドリューとピーター以外は、誰も知らないんじゃないかと思う。(ちなみにピーターは今、Facebookを見る限りでは、アムステルダムで投資ファンドの会社を経営しているらしい。)
「見て」ジェシカはそう言って、写真を二人の前に置いた。それはまるで昔の雑誌の広告のようだった。路上喫煙が嫌厭(けんえん)される前の、まだタバコが若者にとって憧れの習慣だった時代を思わせた。「家族みんなで集合写真を撮ったでしょ。その直前に彼が撮ってくれたやつ。現像してフレームに入れて、私の誕生日にくれたの」
「ずっと手元に持ってたわけ?」
「普段はベッドサイドテーブルの引き出しの中にしまってる。ほとんど見ることはないんだけど。私もこの旅に参加するって決めた時、なぜか持っていこうって思ったんだよね。彼もここにいるべきだと思ったんだと思う。父の遺灰を撒くのなら」
「引き出しの中じゃなくて、飾っておいた方がいいんじゃない?」
「どうすべきかわからないのよ。この写真を見ると、多くの疑問が生じちゃうでしょ。そういう写真のような気がするから。誰が撮ったのか、どこで、なぜ撮ったのか。それに、私はタバコを吸ってるし―」
「お前がタバコを吸ってることはみんな知ってるよ、ジェシカ」とパトリックが口を挟んだ。「ママも、パパも、俺たちも、ダンさえも知ってる。お前は隠すのが本当に下手くそだからな」
「ダンも?」
「彼が初めてママとパパに会いに来た時、もうだいぶ前の話だけど、みんなで中庭にいた時、お前が洗面所に消えて、そしたら窓のすき間から煙が立ち込めてきたんだ。ダンも一緒に、みんなで煙を眺めてたよ。さすがにパパが、戻ってきたお前に注意の一つもするのかと思ったけど、しなかった。注意は逆効果だと思ったんだな。お前がタバコを吸っていようがいまいが、誰も気にしてないぞって無視した方が、やめると踏んだんだ」
ジェシカはどう言い返そうかと反論の言葉を探したが、実際、弟の言うことはまったく正しかった。
「飾っておくべきよ」とカースティが言った。「彼はいい写真家だったわ。職業にして、それで食べていけるくらいの腕があった」
「おかしいわね。あの子が高校を卒業したらどうするのか、そういう話をしていた直後に、この写真を撮ったのよ。彼は軍隊に入るって言ってた。私は大学に行って、写真の道に進むように言ったんだけど」
「そうしてたら、どうなっていたんだろうな?」とパトリックが言った。
三人はそれぞれに紅茶をすすりながら、テーブルの上に置かれたアルバムの最後の写真を見た。ジェリー、スー、アンドリューが、あのコテージの前に立っている。ジェシカは自分がカメラを構えて、この写真を撮ったことを思い出した。この後、家族は二手(ふたて)に分かれて家路についたのだ。―カースティは両親と共にフランスのディジョン、ルクセンブルグ、ベルギーのブルージュをめぐってから帰ることにした。私はアンドリューとパトリックを車でホーブまで送ってから、電車に乗ってロンドンへ向かった。私はあの頃、ロンドンで自分の生活を築こうとしていたから。
アルバムをめくっていた途中、ジェシカは、なぜパパがこのアルバムを選んだのか不思議に思っていた。家族で出かけた最後の旅行だったことを除けば、他の家族旅行と比べて、特に際立った特徴はないように思えたからだ。けれど、橋の上での会話を思い出した時、納得がいった。
帰国した翌週、アンドリューは両親に、卒業試験が終わったら落下傘部隊に入隊するつもりだと話した。両親の反応は予想通りだったが、構わず彼はそれを実行に移した。
フランスへのあの旅行は、家族で過ごした最後の休暇だったというだけでなく、アンドリューにとって、人生の転機となった旅だったのだ。父親と釣りをしながら将来を考え、橋の上で私と話しながら、彼は自分の行く道を決めたのだ。もしアンドリューが軍隊に志願するよりも、大学で勉強した方がいいと判断していたら、その後、彼の身に起きたことは何も起こらなかったでしょう。
しかし、そんなの仮定の話だ、とジェシカは自分に言い聞かせた。手に負えない、どうしようもないことだってあるんだ。
「かわいそうなアンドリュー」とカースティが呟いた。考え込むような、1、2分の沈黙の後だった。ジェシカは、彼女がいつでも被害者の味方をすることに納得がいかなかった。でも今回ばかりは、彼女の呟きは理にかなっていると思った。
「考えたことある?」とジェシカは言いかけたが、途中でやめた。周りにダンしかいない時や、気楽な自宅のキッチンなら、思ったことをつい口に出しても問題ないが、今は状況が違う。
「考えるって何を?」とパトリックが聞き返した。
「気にしないで。どうでもいいことだから」
「明らかにどうでもよくないだろ」
ジェシカはしばらく考え込んだ。これを言ってしまったら、どうなるか? 吉と出るか凶と出るか、どちらにも転ぶ可能性があった。けれど、せっかくこうしてみんなで集まっているのだから、一か八かぶつけてみたくなった。
「私が聞こうとしたのは、彼の本質みたいなことを考えたことあるのかな?って。つまり、彼は私たちの近くにいつまでもとどまっているような人じゃなかったんじゃないかな? 残酷な話に聞こえるかもしれないけど、ちゃんと最後まで聞いてほしい」
弟と妹の顔を見た。二人とも今にも私を激しく叱りつけようという表情にも見えたが、同時に、とりあえず弁明の機会を与えようという気配も漂わせていた。
「つまりね...世の中には、決して年を取らないように運命づけられている人もいるって知ってるでしょ? カート・コバーンとか、エイミー・ワインハウスとか、挙げれば切りがないけど、そういう人たちみたいにね。ロケットみたいにやみくもに飛んで行っちゃって、どこか遠くの彼方で燃料が切れて、燃え尽きちゃう、みたいな。アンドリューもそういうタイプだったんじゃないかな? 彼が私たちと一緒にいるつもりはなかった、というか、そういう運命ではなかった。それに気づくのに時間がかかっただけで」
「彼は家族だったわ」とカースティが言った。
「それはわかってる。私は彼を愛してる、これからもずっとよ。でも、家族を選ぶことはできない。そうでしょ? よく言われることだけど、間違ってない。アンドリューは、それならって考えたんじゃないかしら。そして唯一の抜け道を見つけた。家族を持たないことを選ぶことはできるって」
「要するに、彼はずっと私たちを嫌ってたってこと?」
「そうじゃない...カースティ...説明するのは難しいんだけど、私が言いたいのは、彼はある年齢になって、自分は違う、一人だけ違うって悟ったのよ。だから彼は去った。私の言ってる意味がさっぱりなのはわかってる」
「じゃあ、彼はカドガン家の一員じゃなかったってこと?」
「たぶんね」とジェシカは言った。「私が思っていたのは、そういうことかもしれない」
「なんか、あなたたちの話を聞いてると、自分を正当化しようとしてるだけに聞こえる」
「カースティ」と、パトリックが、それは言うなと注意するような口調で言った。
またもや、三人ともに黙り込んでしまった。高速道路を行き交う車の音だけが聞こえてくる。時折、雷鳴のようなトラックの通過音が轟(とどろ)き、その風圧でキャンピングカーの薄い壁がガタガタと揺れた。ジェシカは、パトリックの目が少し涙ぐんで、赤みを帯びていることに気がついた。アンドリューは、彼らにとっては、いわば遺体のない死だった。彼はいつの間にか行方をくらまし、さよならを言うチャンスさえなかった。
「子供たちにはどう伝えたの?」しばらくして、カースティが聞いた。「リヴィもどんどん成長してるから、そろそろアンドリューのことを話さないとね」
「私は、マックスが10歳になるまで待って、きちんと説明したわ。それまでもマックスは、アンドリューおじさんがもういないってことを受け入れてたけどね。エルスペスにはまだちゃんと話したわけじゃないけど、彼女もなんとなく受け入れてる。前はアンドリューおじさんがいたけど、今はいないんだって」
「うちも同じだよ。マギーは大して彼のことを聞いてこなかった。彼女はアンドリューに会ったこともないし、寂しい思いをすることもなかった。マックスだけだな...」と彼は言って、言葉を濁した。
何がおかしいのか、ジェシカが、ふふっと笑ったから、他の二人は彼女の顔を見た。
「ごめんなさい」と彼女は言った。「ちょっと考え事をしてたのよ。なんだかサンタクロースみたいな存在だなって。『お兄ちゃんだけにわしの存在を教えてあげるけど、妹たちには内緒だよ』みたいな」
パトリックは微笑んだが、カースティが「マックスだって、そんなに会ったことないでしょ」と言うと、その微笑みはすぐにしぼんでしまった。
「そうね」とジェシカが言った。「それはそれとして」
彼女は妹と弟を見た。二人とも、同じ家で育ち、どこかへ飛び立っていったアンドリューの思い出に耽っているようだった。そしてジェシカは、みんながまだ疑問に思っていることを、ここでもう一度取り上げ、自分の考えを言わなければならないと思った。
「どうしてパパは私たちを、アイラ島に行かせようとしてるんだと思う?」
「ジェシ、またそれ?」とカースティが言った。「パパとママの思い出の地だからでしょ」
「ええ、それはわかってる。けど...もっと他に、何か別の理由があるとしたら?」
「ジェシ」
「認めましょうよ、カースティ。あなただって、そのことについて考えてるんでしょ? 私たち三人とも、もしかしたらって思ってる。もしパパが何かを、っていうか、誰かをそこで見つけたとしたら」
「でもどうやって?」
「わからないわ。でも今回のことはすべて、そこにつながってるような気がするの」
「彼がそこにいれば、パパがそこで彼を見つけたのなら、私は気づくわ」カースティはきっぱりと言った。「彼はいない。さっき私がパトリックにそう言ったのを、あなたも聞いてたでしょ?」
「パパが相当気をつけてて、あなたが気づかなかったとしたら?」
「気づくって。あなたは自分の気持ちが楽になる考えにしがみついてるだけよ」と彼女が言った。その言葉自体は少し嫌味を醸し出していたが、彼女が口調を和らげ、同情するように言ったことで、嫌な感じは中和されて耳に届いた。「彼がそこにいるのなら、それがこの旅路の最終的な目的なら、あなたはすべてに対して反省しなくて済むからね。でも、心の奥底ではわかってるはず」
「何を?」
「ジェシ。もう二度と私たちが彼に会うことはないの。こんなこと言いたくないけど、それが真実よ」
そう言いながら、カースティは立ち上がろうとした。しかし、パトリックが彼女の腕をつかんだ。
「話はまだ終わってない」と彼が言った。彼は眉をひそめ、険しい表情でテーブルを見つめている。「実は、二人に話したいことがあるんだ。もう話してもいい頃だろう」
パトリック
「アンドリューのことだよ」とパトリックは言った。旅が進むにつれて、彼は本当のことを言いたくてたまらなくなっていた。今日も何度か口を開きそうになったのだが、その瞬間はやって来なかった。しかし、明日までには、海岸に到着するまでには、言っておかなければならないと思っていた。カースティが立ち上がった時、今しかないと思った。この瞬間を逃したら、もう話せなくなる。
「何?」と彼女が聞いた。「彼がその島にいるなんて、もう二度と言わない方がいいわ。だってそんなの絶対―」
「それじゃない」彼はそう言って、彼女の発言を制した。「彼が軍隊を辞めた時のことだよ。さっきお前たちが二人で話してたじゃないか」
「退役のことなら私たちも知ってるわ」とジェシカが言った。「メディカル検査に通らなかったんでしょ? 喘息で」
「実際はそうじゃなかった。それとは関係なかったんだ」パトリックはいったん息を飲むように間を空けた。今が話すべき時だった。「アンドリューは、あれより6ヶ月も前に、すでに軍隊を抜けていたんだ。彼は2度目の遠征のメンバーから外されたんだよ。1度目の遠征で彼の評価が下されて、次の遠征は君には無理だと言われ、最後は暴れて出てきたらしい」
「でもママが―」
「ママは知らなかったんだよ」パトリックはジェシカの言葉を遮るように言った。「誰も知らなかった。俺以外は」
「どういうこと? パトリック。ママもパパもきっと―」
「待ってくれ」と彼は言った。パトリックは釣り具箱からウィスキーのボトルを取り出すと、自分のグラスに注いで、一口喉に流し込んだ。「今話す。続きがあるんだ」
カースティとジェシカの視線が自分に集まっているのを感じた。二人がどんな反応を示すのか、これを話したことで、この旅は終わってしまうのか、見当もつかなかった。
「軍隊を辞めてすぐ、アンドリューは家に帰らなかった。ロンドンへ向かったんだ。彼の友人が俺のメールアドレスをネットで見つけて、何が起こったのかを知らせてくれた」そこでパトリックは、次のことをどう言ったらいいか迷った。「ランベス区のホームレスシェルターで、俺は彼を見つけた」
顔を上げると、ジェシカとカースティの二人が、唖然として目を見張っていた。口を少し開けたまま、彼がその時の状況を説明するのを待っている。
「俺はしばらく彼を探していた。そしたら、そのシェルターのすかした野郎が情報をくれたんだ」
「彼はホームレスだったの?」
パトリックはうなずいた。「彼自身が言うには、外では寝ない、いつもシェルターで過ごしてる、なんて言ってたけど、俺は信じなかった」
「それならパパが―」
「言ったとおりだ。誰も知らなかったんだよ」
「どのくらい?」とジェシカが聞いた。「つまり、彼はどのくらいの間そこにいたの?」
「しばらく。2、3ヶ月くらいかな。彼はいずれは家に帰るつもりだって言ってたよ。ただ、みんなにどう話せばいいのかわからないって。それで結局、少しの間、俺のところに身を寄せることにしたんだ。俺が基地まで迎えに行って、家に連れ帰ったことにしようって俺が提案した。彼がメディカル検査に落ちたっていうのも、俺が考えた口実だよ」
ジェシカはウィスキーのボトルをぼんやりと見つめていた。彼女がこの告白をどう受け止めたのか、その視線が十分に物語っていた。
「じゃあ、彼が消えたのは2回目ってことね」何時間にも思える長い沈黙の後、彼女がようやく口を開いた。「前にも失踪したことがあったってことでしょ?」
パトリックはうなずいた。10年前、ロンドンでアンドリューを探した日々が脳裏に蘇る。彼を探すのは2度目だったから、ロンドンの中でも、以前彼を見つけた地区を重点的に探した。あの時、彼の写真を見せて回ったのだが、なかなか見覚えのある人は現れかった。ランベスのシェルターには、まだあの職員の男がいて、アンドリューのことを覚えていた。彼はパトリックの連絡先をメモして、アンドリューを見かけたら連絡すると言ったが、それから一度も連絡はない。
数週間探し回って、アンドリューはおそらく、今回は首都には向かわなかったのだろうという結論に達した。首都を通り越してさらに北へ向かったか、南の海峡を渡ってヨーロッパを目指したか、どちらかだろうと。
「彼がいなくなってから、俺はまたそこを探したんだ。もう一度シェルターにも行ってみたし、あらゆるところを探したよ」
「どのくらい彼はロンドンをさまよってたの? 最初の失踪の時」とカースティが聞いた。「軍隊を飛び出してから、あなたが彼を見つけるまでどのくらい?」
「そんなに長くないよ。数週間かな」
「数週間?」彼女はショックを受けたように言った。
「わかってる」とパトリックが言った。「なんで話さなかったんだってことだろ? でも、俺の立場から考えてみてくれ。あのメールを受け取った時、俺は彼が麻薬か何かで大変な状況にいるって思ったんだ。彼が他の家族に会う前に、俺だけで解決してやりたいって思った。そうすれば、もしかしたら...」パトリックは尻すぼみに言葉を失った。あの時、なぜ自分があのような行動をとったのか、うまく説明できなかった。妻のスザンヌだけには事の成り行きを話してあったが、彼女にも自分の行動の理由を説明することはできなかった。唯一、たぶんこうなんだろうと言えることがあるとすれば、両親を守ろうとしたんだと思う。息子が軍隊を離れて、何百万人もが密集する都市のどこかをさまよっていることを知ったら、彼らのうちにとめどなく生じるだろう心配を、予め食い止めたかった。
「そうすれば、もしかしたら...何?」とジェシカが、優しい口調で聞いた。
「わからない。たぶん、俺は彼を助けられると思ってたんだと思う。実際しばらくは、助けられたって思ってたんだけど...」
パトリックは涙をこらえた。そのことを思うたびに、もっとこうしておけばよかった、なんで考えがここまで及ばなかったんだ、と悔やんでばかりいた。アンドリューが完全に姿をくらまして数ヶ月後、パトリックは、退役軍人が定職に就くのはかなり大変な場合が多いことを知った。そのメールを送ってくれたアンドリューの旧友に会って、色々な話を聞くうちに、彼がPTSDに苦しんでいる可能性が高いことに気づいた。アフガニスタンに派遣された際、アンドリューのまさに隣に立っていた仲間が撃たれ、死んだそうだ。
アンドリュー・カドガンに関することは、彼が失踪した後になって、様々なことが明らかになった。彼に関するあれこれを知っていくうちに、パトリックは、彼の最初の失踪、つまり軍隊からの逃亡に関しては、決して口外しないと腹をくくった。
「長い間、自分を責めていたんだ」とパトリックは言った。「彼がそうするのはわかっていた。彼にはそういう衝動があって、実際俺は、彼が街をさまよっているのを見たんだ。あの時、メルが」と言ったところで、何かが彼の言葉をせき止めた。
「メルが何?」とカースティが聞いた。
「彼女が妊娠した」とパトリックは言った。「彼がビジネスでトラブルに巻き込まれる直前のことだった。彼女は妊娠したけど、二人の仲が悪くなって、結局中絶したらしい。一度アンドリューがパブで話してくれたんだ」
「それであなたは決して―」
「言えなかった」と彼は間髪を入れずに言った。「アンドリューとの約束だったから」
「そして彼はどこかへ行っちゃった」とカースティが言った。
「彼が戻ってきたらどう思うだろうって、いつも考えてた。俺はことごとく、彼との約束を破ってきた。彼に秘密を守ると言った時、俺はいつも本気だった。そうは思えないだろうけど、本当に本気だったんだ」
「じゃあ、なんで今になって話すの?」とカースティが聞いた。
「彼はもう戻ってこないだろうから」とパトリックは、目に涙をいっぱいに浮かべて言った。
その言葉だけが永遠にそこを漂っているような沈黙が訪れた。しかし、ついにジェシカが口を開いた。
「わかったわ」と彼女は言った。「怒ってもいいんだけどね。私たち二人とも、あなたに怒ってもいいんだけど、でも、もしアンドリューがあなたじゃなくて、私たち二人に話していたらって思うとね。私たちだってどう反応したかわからないし」
ジェシカは手を伸ばし、パトリックの手に彼女の手を重ねた。彼は顔を上げ、涙ぐんだ目でカースティの目を見た。
「私もよ」と言って、彼女も、パトリックとジェシカの手の上に、手を重ねた。
パトリックは、二人が本心で言っているのかどうか、完全には二人の気持ちをつかめたわけではなかったが、二人の理解に感謝し、弟について自分が知っていることをようやく彼女たちに話せて、胸のつかえが下りた気がした。
ジェシカ
彼女はこのことを旅の後半で話すつもりでいた。アイラ島に着いてからか、あるいは家に帰る道中で話そうかと考えていた。しかし、正直者の妖精が舞い降りたかのように、ジェシカは考えを改めた。
「私も、話したいことがあるの」と彼女は静かに言った。そして促されるのを待つことなく、続けた。「私とダンは、彼を救済することができたの。セラピーを受ける必要があるのなら、そのお金を工面できたし、建築士事務所を立て直す手助けもできた。実際貯金もあった。ママとパパの家で、あんな風に家族会議が断ち切れになって、家に帰ってから、二人で話し合ったの。私たちの家を改築するために貯金していたお金を、アンドリューのために使おうかって。なんとか二人で協力してやりくりすれば、それくらい後から回収できるって」
「ダンがノーって言ったんだな?」とパトリックが聞いた。彼女の夫に、ブーツの先でけりを入れてやりたい衝動が、いつにも増して湧き上がった。
「いいえ」と、ジェシカが少しためらいがちに言った。「ノーと言ったのは私」
その言葉は、しばらく空中を旋回し、不穏な空気をまき散らしていた。ジェシカは時々このような状況を引き起こす。彼女が言ったことが、その場を凍りつかせ、そこにいる全員を激しく怒らせたり、ひどく動揺させたりする。そんな修羅場が直後にやってきそうな雰囲気だった。
「あなたがノーって言ったの?」とカースティが言った。
「彼の助けになるとは思わなかったのよ。正直に言えば、今でもそう思ってる。あの時、急場しのぎで彼を救えたかもしれない。でも、それで本当に彼の問題は解決したのかしら?」
「彼は出て行かなかったかもしれないわ、ジェシカ。家族に支えられてる、みんなに愛されてるって、そういう感情が彼に芽生えたかもしれない」
「彼は支えられてたし、みんなに愛されてたわ。お金の問題じゃないでしょ。何千ポンドあげたって、それはその人を支えたり、愛することにはならないのよ。彼が変わるのを手助けしてあげないと」
「お金では、彼が変わる手助けにならなかった?」
ジェシカは一瞬、言葉に詰まった。あの時、自分がどう感じていたのか、うまく表現できなかった。そう、確かにあの時、両親に負担をかけずに、弟を救い出し、家業も存続させるだけの資金があった。ダンは、ビジネス・コンサルタントとしての経験を生かし、〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉を、2008年の大恐慌の余波から引き揚げ、再び軌道に乗せることができたはずだし、アンドリューも事務所のスタッフとして留まり、給料をもらいながら、セラピーとかを受けて、軍隊で負った精神的な傷を癒せたかもしれない。
しかし、そんな仮定の話は、どこかしっくりこない。家を改築するための資金が貯まったからこそ、私たちは引っ越さずに済んだのだし、ダンはあの頃、地元の政治に参加するようになって、初めて選挙に出馬するんだと意気込み、周りを巻き込み騒ぎ立てていた。
それに、アンドリューは以前にも、困難な人生から抜け出す方法を示され、手を差し伸べられたにもかかわらず、それを拒否したことがあった。もしあの時、私たちが彼にお金を渡して、それで計画が失敗したら、それこそ最悪の事態になっていた。家は改築できず、ダンは〈事務所〉を立て直せなかったことで、彼のコンサルタントとしての経歴に傷がついていただろうし、アンドリューは相変わらず荒れた生活を続けていた可能性だってある。
「何が起こるかなんてわからなかったの」とジェシカは、弁解するように言った。「彼があんなことをするなんて、ちょっとでも、彼が失踪するとか考えていたら、もちろん、私は彼にお金をあげたわ。何でもしたわよ、カースティ。何でもね」
「あのね」と、彼女は手厳しく言った。「彼の顔を見ながら、そのくだらない言い訳ができる?」
「もうやめてくれ、カースティ」とパトリックが言った。
「いいえ、やめないわ。彼女はすべてを防ぐことができたのよ。彼女が自分のことと自分の家のことだけを考えてるから、こんなことになったの。そうでなければ、私たちの仲がこんなに悪くなることもなかったし、こうして、こんな旅に出ることもなかったでしょうね」
「おいおい」
「彼女はお金を貯め込んでるくせに知らん顔だから、ママとパパが彼を救済したのよ。あの家を売って、全部を穴埋めしようとした」
「それは言うな」とパトリックが言った。普段は日和見(ひよりみ)の弟が、自分を擁護する側に回っていることに、ジェシカは驚いていた。
「どうして言っちゃダメなわけ? 明らかに相関関係があるでしょ。ママが死んだ時、パパに家の売却を迫ったのは、彼女だけよ」
「だってね、あの家をいつまでも抵当に入れておいても、借金が莫大に膨れ上がっていくだけだったのよ!」とジェシカが言った。「それを返し続けるために、家業を続けなければならないなんて、パパが気の毒じゃない。もう引退していいはずの歳なのに、まだまだ働くなんて」
「パパは働くのが好きだったのよ」と、カースティが跳ね返すように言い放った。「あなたがもっと彼の家を訪れて、彼と話していれば、そういうこともわかったでしょうけど」
調理台に寄りかかっていたジェシカが身を起こした。カースティをひっぱたこう、という衝動がどこからともなく降ってきたようだった。まるで操られるようにして、彼女の手が伸び、パシッと乾いた音を立てた。
ジェシカは、最後に平手打ちの喧嘩をした時のことを思い出そうとした。あれはたしか学校で、ホッケーの試合の後だった。相手は思い出せないが、妹ではなかったことだけはわかる。私たち姉妹は、年の差が結構あるためか、口喧嘩はしても、手を出したりすることはなかった。カースティの10代から20代前半にかけては、むしろ相談に乗り、助言をしていた。絶縁に近い状態に陥るまでは、ほとんど母性的なつながりがあったのだ。
顔をひっぱたかれた直後、カースティはテーブルに座り込み、放心状態で、赤くなった生身の頬を手で押さえた。
「カースティ、私は―」
「グラスゴー空港で降ろしてあげるわ」とカースティが言った。「そこから飛行機で家に帰れるわ。最初からあなたは来るんじゃなかったのよ。明らかに嫌がってたものね」
そう言うと、彼女は立ち上がり、姉の横を通って、寝台の上の段にのぼり、中に入ってカーテンをピシャリと閉めた。1、2分後、妹のくぐもった嗚咽(おえつ)とすすり泣きが聞こえてきて、ジェシカは罪悪感にさいなまれながら、彼女にもう一度謝りに行こうとした。なぜ叩いたりしたのか、その理由を説明したかった。しかし、梯子(はしご)に伸ばした腕を、後ろからつかまれるのを感じた。
「今はだめだ」と、パトリックが静かに言った。「たぶん、彼女は―」
「ハイホー! こんちはー!」という船乗りのような陽気な声が、パトリックの発言を遮るように聞こえてきた。キャンピングカーのドアがひらき、パサパサにふやけたパイ生地みたいなハゲ頭がにょきっと現れ、ついで笑顔が顔を出した。「パトリック・カドガンさんでよろしかったですか?」
「そうです。そうです」とパトリックは陽気に答えた。ジェシカの耳元で話していた深刻な口調を急に切り替え、建築現場で同僚に話しかけられた時のような、自然な応対だった。―同僚たちの中で揉まれたことのないダンには、これができないんだよね、とジェシカは思った。「さあどうぞどうぞ、入ってください。というか、船に乗ってください」と彼は言った。
「私はキースと申します」と、その訪問者は言った。明るいオレンジ色のオーバーオールに全身を包み、黒くてがっしりした厚底ブーツを履いている。彼はクリップボードを脇に挟むと、手を差し出し、パトリックと握手を交わした。ジェシカには挨拶すらしなかった。「〈THE ADVENTURER(冒険家)〉だなんて、かっこいいですね。船かと思いましたよ。アドベンチャラー号の冒険を再開できるように、手を貸します」と彼は微笑みながら言った。「車輪のことですね?」
「ええ、そうなんですよ。パンクしちゃって、自分でタイヤ交換しようとしたんですけど、完全にハマっちゃってるみたいで」
「そうですね。さっき声をかける前にちょっと見てみたんですけどね。砂利とか泥とか、もういろんなもんがこびりついてましてね」彼はそう言うと、クリップボードの書類に何やら書き込んだ。「問題ありません。解決はできますが、ここでちょっとお待ちいただくことになっちゃいますね」
「どのくらい?」とジェシカが聞いた。彼女の心はすでに、空港に着き、何かちゃんとした物を食べてから、帰りの飛行機で眠ろうという考えに流れていた。彼女は昔から飛行機ではよく眠れる性質(たち)だった。
「1時間くらいですかね。砂利とかを全部取り除いてから、タイヤ交換するんで、もう少し長くかかるかもしれません。私があなただったら、中でゆっくりくつろいでますね」とキースは言って、「楽しい思い出を」と付け加えた。テーブルの上にひらきっぱなしのアルバムを指差して、微笑んでいる。
ジェシカは腕時計を見た。午後1時を回ったところだった。ここから空港へ向かい、飛行機に乗るにはまだ十分な時間がある。他の二人はフェリーに乗るために、まだ300キロ以上運転しなければならない。この時点で、彼女はそこまでする意味を見失っていた。この旅で、カドガン家のきょうだい三人が、ある程度までは礼儀正しく振る舞えることはわかった。けれど、いつまでも一緒にいると、結局は険悪なムードになり、不幸な結末を迎えることになるのだ。それが、今の三人の関係だった。無理もない。私たちの関係は、不倫と裏切りの末の夫婦のようなものなのだ。どんなに過去のことは忘れて、平然と接しようとしても、そういうことは常につきまとってくる。
パトリックは書類にサインをしてから、キースに紅茶をいれようと、調理台の方を向いた。
「これはあなた方の車ですよね?」とキースは、キャンピングカーの中を見回しながら、ジェシカに尋ねた。
「私たちのパパのものだったんです」
「幸運な男ですね」と彼は言った。「ずっとこういうのが欲しかったんですよ」
彼女はよっぽど彼に「あげますよ」と言おうかと思ったが、黙ったまま微笑んで自分の寝台に戻り、そこで、もう少しで終わるこの旅の残りをやり過ごすことにした。
チャプター 8
グラスゴー郊外のどこか
カースティ
キャンピングカーがガタゴトと発進する音を感じて彼女は目を覚ました。口喧嘩の末の平手打ちの後、カースティは寝台に戻った。スマホで、アンドリューのFacebookをスクロールし始めたのは覚えている。どうやら、そのまま寝落ちしちゃったみたいね。
ジェシカに平手打ちされたことよりも、このFacebookのページが、カースティの気持ちをざわめかせた最たる理由だった。末っ子であることは、兄との思い出が最も少ないということでもある。アンドリューの人生に衝撃を与えたいくつかの出来事は、彼女がまだ幼かった頃に起こった事で、当時もあまり認識できていなかったし、何年も経ってから振り返ろうにも、手掛かりがほとんどなかった。もっと言えば、正直なところ、私は幼い頃から10代の半ばまで、彼をうっとうしい兄としてしか認識していなくて、ようやく友達のように思えてきた頃には、彼は軍隊に入ってしまった。つまり、人生で彼と関わった期間が短すぎて、それがとてもつらかった。
不思議なことに、彼女は昨日、アルバムを取り出す前からアンドリューのことを考えていた。三人がそれぞれに、ときおり亡霊のような彼の面影を傍らに感じていたのだ。そして、キャンピングカーがプレストンの辺りを走行している時、カースティは口には出さなかったが、メルとの思い出が心中に去来していた。―メルは、アンドリューの唯一の、長く付き合ったガールフレンドで、プレストンは彼女の出身地だった。
彼女は背が低く、丸みを帯びた顔立ちで、いつ見ても頬が赤く染まっていた。ブロンドの髪はショートボブっぽく、首のあたりで切りそろえられ、ブラックジーンズと、ロックバンドのロゴ入りTシャツを着ることに(私からすれば、ありがちだけど)こだわりを持っていた。アンドリューが言うには、ブライトンの共通の友人を通じて彼女と知り合ったという。けれど、二人がオンライン上で知り合ったことは、ほぼ間違いないだろうと、みんなが思っていた。というのも、メルには、ブライトンにほとんど友達がいなかったからだ。彼女はサセックス大学の修士課程の学生だった。同じ学生寮に住んでいる女友達はいたが、彼女たちがアンドリューとつながりがあったとは思えない。メルの専攻は犯罪学と刑事司法で、それを活かして、彼女は再犯者の問題に取り組みたいと考えていた。当然のごとく、彼女は最悪の部類に属する人物に、病的なまでに興味を抱き、おぞましい殺人事件が起こる小説を貪(むさぼ)るように読んでいた。
家族の誰もがメルを好きだった。彼女とアンドリューは2年間付き合っていたが、彼がふらっと、誰にも理解できない理由で失踪する前に、二人は別れた。アンドリューは別れた理由を話そうとはしなかった。
アンドリューから何か聞いていないかと、スーが彼女に連絡を取ってみた。しかしメルも、私たち家族が知っている以上のことは知らなかった。その時点では、彼女はすでにブライトンを離れていて、マンチェスターに住んでいるとのことだった。アンドリューが、海岸沿いの街と彼女をつなぐ唯一の存在だったようだ。
カースティは昨日、Facebookでメル(正式にはメラニー)のことを調べてみた。私たち家族が知っている彼女の名字(キャッチポール)はカッコでくくられていて、その前に彼女の新しい名字が「バナー」と書かれていた。彼女のプロフィール写真には、なじみのあるショートボブ、バラ色の頬、そして丸っこい満面の笑みが写っていたが、今の彼女は、夫と2人の男の子という家族に囲まれていた。要するに、メラニー・キャッチポールから、結婚してメラニー・バナーに変わったらしい。彼女の名前の下には、「あなたとメラニーには共通の友人が1人います」と、Facebookの仕様で表示されていたが、タップするまでもなく、カースティはそれが誰なのかわかった。
彼女は寝台のカーテンを少し開けて、車内を覗き込んだ。ジェシカはテーブルに向かって座り、スマホをいじっている。パトリックが運転していた。あとどれくらい走れば、空港に着くのだろうと思った。そこで姉を降ろして、それからは彼と二人旅になるわけだ。
「今、何時?」とカースティは、絶え間ないエンジン音に負けじと声を張った。
「もうすぐ4時」と彼が、後ろを振り返ることなく答えた。
「もうそんな時間? 私たちはどれだけ足止めを食らってたのよ」
「それは言うな」
「そうよ」
「えーと、ここはどこ?」
「グラスゴーの近く」と彼が言った。
カースティは寝台の梯子を下り、テーブルの方へ歩いた。走行中の車の中を歩くのは、不思議な感覚だった。足元が不安定だと、不安な気分になってくる。
一瞬、ジェシカと向かい合って座ろうかと思ったが、それはあまりにも気まずい。自分がクビにしたばかりの社員の隣で仕事をするようなものだ。彼女はテーブルを素通りし、ギアスティックとハンドブレーキを乗り越えるようにして、パトリックの隣の助手席に座った。
助手席からの眺めの方がずっと良かった。スコットランド第二の都市グラスゴーが不規則に触手を伸ばし、広がってきたような広大な郊外を見渡すことができた。家々、庭、フェンスが整然と並び、倉庫やタワーマンションが時折り、墓地の樹木のように地面からそびえ立っている。
「セルティックパークだよ、ほらあれ」とパトリックが言って、斜め前方を指差した。彼の指の先に視線を向けると、巨大な四角い建造物が遠目に見えた。サッカースタジアムらしいが、カースティには、人差し指で押されるのを待っている四角いボタンに見えた。
「魅力的ね」と彼女は皮肉っぽく言った。しかし内心では、パトリックが少年の頃と少しも変わっていないことが喜ばしかった。昔、家族でドライブ旅行に出かけた時も、彼は同じようにサッカースタジアムを指差して興奮していた。それを心得ていたパパは、わざわざ回り道をしてでも、リバプールの〈アンフィールド〉や、マンチェスターの〈オールド・トラッフォード〉などのサッカースタジアム、はたまたイギリス中に点在する教会や大聖堂が見える道路を走行することがよくあった。
懐かしい気分になる一方で、カースティは不安な気持ちも抱えていた。パトリックが今運転しているということは、グラスゴー空港でジェシカを降ろした後は、自ずと自分が運転する番になるということだ。となると、トロサックス国立公園を抜けて、ローモンド湖や、湖畔の小さな町を越えて、ケナクレイグのフェリー乗り場まで、自分がハンドルを握らなければならない。―普段乗っている〈日産マイクラ〉で街中を走ることには慣れていた。狭い道路でも、時速35キロを超えることはほとんどないから、すいすい走れた。しかし、スコットランドの田園地帯の、危険をはらんだ曲がりくねった道を、川を流れる流木のようなキャンピングカーで走るのは、私にはきっと無理だ。
そして、空港の標識が目に入り、カースティは深く息を吸い込んだ。いよいよその時が来る。少なくとも三人の旅は、ここで終わる。
ジェシカ
この旅もあと数時間後には終わりを告げる。そう思うと、カースティに謝っておこうかな、と彼女が考えたのは事実だった。何しろジェシカは平手打ちをしたのだ。ここ何年も、誰かを平手打ちなんてしたことがなかった。とはいえ、プライドが高くて、知的な彼女には、当然そんな過去もあった。(学生時代、シェアハウスでルームメイトが食器を割ったことに過剰に反応し、つい手を出してしまったことがある。思い出したくもない過去の一幕ね。)
やっぱり旅を続けようか、という考えがよぎったことも事実だったが、考えれば考えるほど、ここで降りるという判断は正しいものに思えてくる。パパが何を意図していたにせよ、キャンピングカーに娘と息子を押し込んで、家族の絆を取り戻させようなんて、そんなのあり得ない。いったいいつから、キャンピングカーは絆を深める装置になったというのか?
こんなことで元通りになるわけがない。カドガン家は、―カドガン家の名残といった方が正しいかもしれないが、―とにかく私たちは、粉々になったクリスタル・ガラスみたいなもの。修理するにはあまりにも細かく、バラバラに散らばってしまった。もうどうしたって修復なんて不可能だ。どんなに礼儀正しく振る舞おうが、必ずどこかに欠けた破片が転がったままで、平然としたまま終われるはずがない。それは出発の時点で私が感じていたことで、何も変わらなかった。帰り道もこれを続けるなんて、無理な話ね。
「じゃあ、ここは俺がいっちょ運転すっか?」と、パトリックが名乗り出てくれた。あの極端に陽気な整備士のキースがタイヤ交換を終えて(彼の見積もりよりも、さらに丸々1時間長くかかった)、いよいよ再出発するという時のことだった。彼が口先だけで、一応そう聞いてくれているのはわかったし、彼がお酒を飲んだのも承知していたけれど、タイヤがパンクして、車体が滑り、縁石に乗り上げた時の感触が生々しく残っていて、私が空港まで運転する、とは言い出せなかった。
「ええ、そうしてくれると...」
「よっしゃ」と、彼は思ってもいないことを口にした。彼の顔には、あからさまな不快感が浮かんでいた。パトリックは感情を隠すのが、昔から下手くそなのよね。
「私がいなくても問題ないわ。あなたたち二人でなんとかなる。私はこういうことに向いてないみたい」
それを聞くと、彼は運転席へ向かい、座り心地の悪いグレーのシートに座った。シートの縫い目にたまったポテトチップスやビスケットのかすや、パンの耳をわざわざ払い落とそうとはしなかった。私は一人でテーブルの椅子に座った。カースティは寝台で寝てしまったか、怒りで煮えくりかえっているのだろうと思った。そのうち、彼女が寝台から下りてきたが、横柄(おうへい)な態度で私を見ようともせず、不格好な体勢で前のめりになって、部屋履きのスリッパをギアスティックに引っ掛けそうになりながら、パトリックの隣に乗り込んだ。
「あと15分」とパトリックが言った。スコットランドのサッカースタジアムについて、その中で行われているかもしれない試合の熱気を想像していて、ふとそこから現実に戻ってきたような言い方だった。もしカースティに嫌気が差していなければ、私は彼女に同情したかもしれない。私はもうすぐ降りるからいいけど、彼女はあと数日間、パトリックのくだらない話に付き合わなければならない。それを思うと、少し可哀想ね。というか、遺灰を海に撒いた後、彼らはどうするつもりなのだろう? バイキングの葬式みたいに、このキャンピングカーを船に見立てて、火をつけて海に流すとか? しかし、そんな冗談を今口に出したら、それこそ火に油ね。
「了解」とジェシカは静かに言った。これでいい、と思った。もう後戻りはできない。というより、もうこれ以上進むことはできない、と言った方が正しいわね。実際には、飛行機でかなり後戻りすることになるわけだから。
彼女は、スマホで〈イージージェット〉のアプリを開き、ルートン空港行きの次の便を探した。タイミングが悪く、次の便の出発まであと4時間もある。でもそんなの大したことじゃない、とジェシカは思った。グラスゴー空港には、カフェや本屋や、小さなバーだってあるでしょ。散々だった数日間にたまった疲れを、空港で癒すことができるはずだ。彼女は、残り少ない空席を予約し、1時間足らずの空の旅に、200ポンド(約3万円)近くも支払った。
哀しいかな、今回ばかりはそれだけの金額を払ってでも、飛行機に乗りたい気分だった。
パトリックが高速道路の出口へと左にハンドルを切った。その反動で、ジェシカの体が右へよろめく。体勢を立て直しつつ、窓の外を見ると、グラスゴー空港が視界に入った。飛行機が低空飛行をしながら、だんだんと大空へと上昇していく。かと思えば、別の飛行機が緩やかに下降してきて、空港の滑走路に降り立った。きっと多くの乗客が、私みたいに早く家に帰りたいと思っていることでしょう。
ジェシカ:今のところ順調よ。一度か二度、口喧嘩はしたけど、今知らせるべきことは特にないわ。あなたたちが旅行から帰って来たら、全部話すね😘
彼女はメッセージの〈送信〉を押した。画面上部の細い線が伸びるように青く満たされ、ダンへの送信が完了した。順調だなんて、嘘もいいところね。少し忍びない気持ちもあったが、スポーツタイプの自転車でツーリングに出たサイクリストが、山道で息も絶え絶えになって、のぼってきた坂道を逆戻りして下(くだ)り始めるみたいな現状を、つらつらと書き連(つら)ねでもしたら、ダンから電話がかかってきて、途中で引き返すなんてよせ、と説得されるのが目に見えていた。それなら、彼らが休暇旅行から帰ってきてから、すべてを説明した方がいい。それでも、ジェシカに平手打ちしたことや、パトリックの飲酒、アンドリューの思い出話などの詳細は省いてしまうかもしれない。というか、私もダンたちとバカンスへ出かけるはずだったのよ。
グラスゴー市に入ってから、ゴーボールズ地区の灰色の街並みを抜けて空港までの道のりは、ほんの数秒のうちに過ぎ去ったように感じられた。ジェシカはその間、自分の判断が正しかったのかどうか、流れる街並みを眺めながら考えていた。数秒おきに、パトリックに声をかけて、やっぱり私も車に残るわ、と言おうかどうしようか迷っているうちに、キャンピングカーが空港の敷地内に入ってしまったので、彼女は黙っていた。
「駐車場に停めるよ」とパトリックは言って、立体駐車場の方へ車を向かわせた。この大きなキャンピングカーをあそこに入れるのは、かなり苦労しそうだ。
「いい」と彼女はすぐに言った。「大丈夫。その辺で降ろしてくれれば」
「いいのか? 俺が払うよ」
「お金の問題じゃないのよ」と彼女は言った。ほんの少しの間の駐車料金、3ポンド(約500円)の話ではなく、何千ポンドの話をしているかのようだった。
パトリックは彼女の言うことを受け入れ、送迎車が行き交う小さな平面駐車場で彼女を降ろすことにした。
「ったく、ふざけんなよ」と彼は呟きながら、平面駐車場の手前で車を減速させた。
「何が?」
「高さ制限だとよ」と彼は言って、高さを測るバー付きの入場門の数メートル手前で停車した。背後の車がクラクションを鳴らし、さらに3つのクラクションが後に続いた。それぞれが違う音色で、オーケストラのごとく、『苛立ち』という名の曲を奏で始めた。
「うるせえ!」とパトリックは運転席に座ったまま、誰にともなく、というより、楽団員全員に向かって叫び返した。
「もうここで降ろして」と言って、ジェシカがテーブルから立ち上がり、バッグをつかんだ。
「ここで降ろすわけにはいかないよ」
「どうして? 私を降ろしたら、バックして道路に戻ればいいじゃない。後ろの人たちがほら、こんなにイライラしてるんだから」
少しためらった後、パトリックはキャンピングカーを右に寄せ、左側に車が通れるスペースを空けた。そして、クラクションを鳴らし続けながら、すぐ横を通り過ぎようとした車の運転手に向かって、「一回でわかるよ!」と叫んだ。ジェシカが車から降りようと、ドアを開ける。
飛行機の燃料と、渋滞待ちの車の排気ガスが混ざったような臭いが立ち込めていて、彼女は思わず、うっと鼻を押さえた。パトリックが「まだ降りちゃダメだ」と言った。
「どうしてダメなの?」
「ちゃんとさよならを言ってないだろ」
「そうね」彼女は、なるべく優しいさよならの言い方はないかと言葉を探した。「じゃあ、ね、さよなら」
ジェシカはハンドバッグを肩にかけ、スーツケースから取っ手を引き出すと、それを握って歩き出した。目の前の小ぶりな駐車場では、たくさんの人たちが、ちゃんとしたさよならを交わしていた。実家を出るのか、若者を両親が抱き締めている。逆にふるさとに帰ってきた人を抱き締め、迎え入れている家族もいたり、しばしの別れを惜しむ恋人や、友人たちでごった返していた。デニムのショートパンツに麦わら帽子をかぶった女の子が、父親と抱き合っている。父親は、この18年間の出来事をめくるめく思い出しているのか、うるうるしているように見える。彼女は、駐車場の向こうからやって来た女の子を見ると、一緒に上京する友達なのか、甲高い声を上げた。さらに、筋肉に張りつくような、ピチピチのTシャツにジーンズ姿の若い男の3人組が、ワゴン車から降り立ち、談笑しながら並んで歩き出した。搭乗前に一杯飲むつもりか、空港のバーはどこだ? などという会話が聞こえてくる。
ジェシカが振り返ると、パトリックが車をバックさせ、入場を拒(こば)まれた入り口からゆっくりと離れていく。この入場門が、私たちのちゃんとした別れも阻(はば)んだのだ。彼はフロントガラス越しに、申し訳程度に小さく手を振っている。カースティはうつむいたまま、こちらを見ようともしない。
今、ジェシカは一人になって、ターミナルへと歩き出した。
パトリック
15分ほど黙々と運転した後、彼はようやく落ち着きを取り戻し、口を開いた。
「ったく、馬鹿馬鹿しい」と彼は言った。
「そういう決まりなんでしょ。もういいじゃない。落ち着いてよ。入場門を塞いで渋滞をつくってたのは、あなたなんだから」
「そうじゃなくて」と彼は返した。
「まあ、さっさと帰りたがってたのは彼女の方だけどね」カースティは彼の言いたいことを察したようだった。
「こうなってみると、味気ないっていうかさ。なんか違うよな? お前も何か言ってくれれば、こんなことにはならなかった。謝るとか」
「謝る?」その発想自体が信じられないといった様子で、彼女は語調を強めた。「彼女が私をぶったのよ、パトリック。もしかして見てなかったとか言わないわよね?」
「お前もさんざん彼女をこけにしてたんだから、お前の方から謝っていれば、彼女だって、こっちこそごめんなさい、くらい言っただろ。彼女の性格を知ってるよな? 昔からああいうやつなんだよ。彼女のせいじゃない、だろ? しょうがないやつなんだよ」
「だからって、なんで私が謝らなきゃいけないの?」
パトリックは何も答えずハンドルを切り、再び高速道路に乗った。グラスゴーから北へ向かって、無数の車がビュンビュンと疾走している。隙間をついて、その流れに紛れ込んだ。
「今ここには、現在進行中の大きなものがあるんだ。でかいことをやってるんだよ。父さんは俺たち三人が一緒にやることを望んだ。それが彼の最後の望みだったんだ。そして、結局それは実現しなかった」
「まあ」とカースティは言ったが、そこで自分自身を制止した。今は揚げ足取りや議論をしている場合ではないのだ。正しいとか間違ってるとか、そんなことはどうでもよくて、ただ三人が、ちょっとずつお互いにずれてるだけ。これ以上口論しても何も解決しない。
「そうね」彼女がそう言った時、キャンピングカーは長いアースキン橋に差し掛かった。
パトリックは窓の外を見た。橋を上から支える鋼(はがね)のケーブルが揺らめきながら流れていく。眼下のクライド川と、その横の土手や木々、そして遠くに見える町の景色を、揺らめく縦線が歪めている。まるで子供の頃、〈ゾーエトロープ〉を覗いた時みたいに、流れる縦線の隙間から風景が浮かび上がってくるようだった。
「でも何とかなるわよ。二人でやり遂げましょ」と彼女が言った。
チャプター 9
インバラレイ、スコットランド
カースティ
午後6時過ぎ、その日最後の交代のために車を停めた。ファイン湖畔にあるインバラレイという町のガソリンスタンドの前だった。パトリックが後で食べる食料と、さらにワインも買いに行っている間、カースティは体をほぐそうと、道路を渡った。小さな砂浜が、ガラスのような水面まで続いていた。
この日、日中の空は晴れ渡っていた。そのため、ピンクとオレンジの美しい夕陽が、湖面や山肌で跳ねるように、キラキラと眼前に迫ってきた。その色彩は、現実とは思えないほど淡く美しく、まるでエフェクトを使った写真のように幻想的だった。スコットランドのこの辺りは、大都市のような人工的な光がほとんどないため、夕焼けがだんだんと暗闇に包まれていくさまが手に取るようにわかった。水面(みなも)に木々や山の影が映し出されていった。それから、月のシルエットまでも湖面に揺れるように浮かんだ。湖の中腹から彼女が立っている浜辺に向かって、ゆっくりと流れてくるかのような月の輝きを眺めていた。
「素敵な夜ですね」彼女の背後から、見知らぬ声がした。カースティが振り向くと、60歳くらいの女性が犬を連れて立っていた。少し太った小型犬〈ジャック・ラッセル・テリア〉が、リードなしで彼女のそばをちょこちょこと歩いている。
「そうですね」
「旅行ですか?」
「まだこの先まで行くんですけど、ちょっと休憩で」と彼女は言った。先程までトロサックス地方の森林を走行していた。彼女は助手席に座ったまま、うんざりするほどだらだらと続くラジオのサッカー中継と、ときおり歓声の後に挟み込まれるパトリックの熱い解説を、聞くともなく聞いていた。口数の減らないパトリックに対し、カースティはグラスゴー空港でジェシカを降ろしてから、ほとんど何も話さなかった。人情で声をかけてくれたこの女性に失礼にならないよう、「私たちはアイラ島まで車で行くんです」と彼女は付け加えた。
「そうするとあなた方は、ウィスキー愛好家ですか?」
「そんなところです」カースティは振り返って、道路の向こうを見た。パトリックがキャンピングカーにガソリンを入れている姿が見えた。
「それ以上言う必要ないわ」とその女性は言った。明らかに彼女は、私たちを夫婦だと勘違いしているようだった。無理もない。一目見ただけで、だんだんと絶望的になっていく任務を実行中の、口喧嘩の絶えない兄妹だと当てられたら、そっちの方が怖い。
彼女の犬が波打ち際まで駆け寄って、湖の水に濡れた小石や砂利をくんくんと嗅ぎ出した。「私にはあの子がいるから」と彼女は言って、犬の後を追うように歩き出した。その時、犬の首にネオンの輪っかが付いていることに気づいた。暗くなっても見失わないよう、光る首輪を付けているのだとわかったが、まるで放射線を放つフリスビーか何かのように見えた。
「またどこかで」とカースティは言ったが、言った直後、その見知らぬ女性と再びどこかで巡り会うことはまずないだろうな、と思った。
彼女は一人、澄み切った夜空を見上げた。藍色に滲むビロード生地みたい天蓋(てんがい)で、星々が瞬(またた)いている。遠くから、ひときわ大きな彗星のような光が飛んできた。ゆっくりと着実に進みながら、夜空を横切っていく。飛行機だった。しかしその飛行機がどの方向へ飛んでいくのかまではわからなかった。初めて来た湖のほとりで、完全に方向感覚を失っていた。ふと、ジェシカの姿が頭に浮かんだ。彼女は今、どこかの夜空を飛ぶ飛行機の中にいて、スマホを叩きながら、4Gの電波が届く地上に早く着陸してよ、と苛立っている。そんな気がした。
次に姉に会うのはいつだろうと、彼女はその時の再会シーンを思い浮かべようとした。しかし、それがいつになるかは想像つかなかった。実家はもぬけの殻で、売りに出されているから、ブライトンと彼女をつなぐものは何もない。かといって、カースティがジェシカの家を訪れるかといえば、それはもっとない。自分が全世界の中心に住んでいると勘違いしていて、市議会議員だか、町議会議員だか知らないけど、そこの住人の代表気取りで暮らしている夫婦のところへなんて、行く気しないわ。
おそらく次に会うのは、誰かの葬儀の時だろうな、と思った。親戚が死んだ時にだけ顔を合わせる、そんな家族に成り下がったも同然だった。円盤状のヴォロヴァン・パイを取り囲み、冷めたチキン・グジョンをかじりながら、お互いをチラ見して、気まずい会話を交わすのだ。そして、ほとんど見覚えのない大人たちに囲まれて緊張ぎみの姪や甥に、過度になれなれしく話しかける。そんなうっとうしがられるだけの叔父叔母になるのだろう。マックスの身長が前に会った時よりも、30センチくらい伸びていることに目を見開いて、「大きくなったね」などと言う。もっとしょっちゅう会っていれば、急激な成長に驚くこともなかったはずなのに、そのことにすら気づかないまま、作り笑いを浮かべている。
パトリック
彼は道路の向こう側に目をやった。妹が湖の水面を、考え込むように見つめている。まるで水面に答えが浮かび上がってくるのを待っているかのようだ。カースティはそういうタイプだった。人生が次々と投げかけてくる問題について考える時、周りの自然に目を向ける。真実が実際にあるかもしれない自分の内側を見るのではなく、むしろ外側に目を向けるのだ。
パトリックはスマホを耳に当て、着信音を聞きながら、彼女が電話に出ることを願っていた。少し前にも、ガソリンスタンドの脇の、ガスボンベや薪(まき)の入った袋を保管している場所に隠れるようにして、クロエに電話をかけてみた。けれど、留守電につながっただけだった。
今度もまた同じメッセージが流れた。
「留守番電話サービスへようこそ。あなたがかけようとしている相手は現在、電話に出られない状況です」
「ったく、出てくれよ」
いつの間にか、カースティが犬を連れた女性と話している。なぜ彼女は見知らぬ人の気を引くのか、神のみぞ知るだな、と思いながら、パトリックはキャンピングカーの中へ戻った。買ってきたピザを小さな冷蔵庫に入れた。冷蔵庫には、昨晩の残りのサラダが半袋と、ジェシカが置き忘れていったコーヒー豆も入っていた。上等な紙袋に保管されていて、いかにも高級そうだ。
その時、ポケットの中でスマホが震えるのを感じた。
「もしもし?」
「電話した?」
「ああ、うん」彼はカースティの視界に入らないよう、ドアに続く段差に腰を下ろした。「ごめん、なんていうか...」
「いいのよ、べつに。今、子供たちの夕食を準備してたところ」とクロエが言った。パトリックは時計を確認した。マギーもそろそろ、ステュとサラと一緒に食事をしている頃だった。そしてあと数時間もすれば、彼らはマギーをベッドへ連れていくはずだ。彼は、なるべく早くマギーとビデオ通話をしよう、と心のノートに書き込んだ。「どうしたの? なんだかあなたの声がちょっと...」彼女はそう言って、言葉を濁した。
「そうなんだ。ちょっと動揺してるかもしれない」と、パトリックは神経を落ち着かせながら言った。「もしここで、この旅をほったらかして、家に帰ったりしたら、ひどい男だと思うかな?」
クロエが「ちょっと待ってて」と言って、スマホを置いたようだった。背後で子供の甲高い悲鳴が聞こえ、皿かナイフかフォークが、ガシャンと床に落ちたか、叩きつけられた音がした。
「いいえ」と、ようやく彼女の声が返ってきた。「ひどい男だとは思わないけど、でも...わからないわ、パトリック。いったい何があったの?」
「ジェシが帰っちゃって。カースティと喧嘩したんだ。それで、今は二人だけになった。こんな旅に本当に価値があるのか、もうわからなくなってる。まだフェリー乗り場の近くにさえ行けてない。今ここで終わりにしたら、明日の朝までには帰れる...」
「それが、あなたのやりたいことなんでしょ?」と彼女は言った。彼女の声には、判断や強制の響きは全くなかった。まだお互いの行動に口出しするほど、親しくはなっていないということだろう。問題は、俺にはこんな時、他に頼れる人がいないということだ。親戚の誰かに電話すれば、カドガン家の不和を解決する方法について、口うるさく言ってくるかもしれないが、求めているのはそういうことではないのだ。
「わからない。本当にわからないんだ。わかってるのは、これは父さんが望んだことではないってことだけ。なんだか二人で、ただ意地になって続けてるだけのような気がしてきた。昔の殉教者みたいに、聖地にたどり着く前に命を落としそうだよ」
「じゃあ、彼は何を望んでたの?」
「俺たち兄妹が再び結び付くこと。再び家族になること。でも、そうはならないよ。よく言うじゃないか、過去は取り戻せないって。橋の下を流れる濁流と同じだよ。っていうか、橋すらもう残ってないけどね」
「それで、彼はそう言ったの? それとも手紙?」
「いや、まあ」とパトリックは言った。「それはいいんだけど」
「ねえ、聞いて。私はあなたのことなんてどうでもいいとまでは言わないけど、あれこれ指図するつもりは毛頭ないの。でも、あなたは私に話した。お父さんがアイラ島の浜辺に遺灰を撒いてほしいって。そうだよね?」
「そうだね」
「それで、そこへ向かってるんでしょ」
パトリックはそのことについて少し考えた。俺たち三人は、それぞれが違った解釈で父からの手紙を読み取った。あの釣り具箱には、ウィスキー、写真集、キャンピングカーの鍵が入っていた。彼の意図は何だったのだろう? アンドリューの居場所を知らせるためか、兄妹の和解のためか、それとも残された子供にも、自分の好きだったことを享受してほしいのか。ウィスキー、キャンピングカーでの旅、旅先でのキャンプ生活、どれも父が生前楽しんでいたことだ。もし釣り竿のセットもそこに含まれていたら、アイラ島で釣りでもして旅を満喫しろ、というメッセージが、彼の意図として最有力候補になっていただろう。
しかし彼の手紙には、それらの意図はどれもなかったという可能性もある。「お前たちはまた、3人それぞれ違った意見を言い出すんだろうな。ただ、今回だけは俺のためにこれをやってくれ。アイラ島に行って、ポート・エレン蒸溜所のある浜辺から、俺の遺灰を撒いてほしいんだ。」という文面通り、単純に彼がその場所をこよなく愛していた。それだけのことかもしれない。ただ、パトリックはちょっとショックだった。父の指定した場所が、長年暮らしたブライトンではなく、彼の妻がついに発見された海岸でもなかったことに。もっと言えば、彼が生まれ育った町、ハーフォードシャーでもなかったことに。
「まだ向かってる途中なんでしょ?」とクロエが聞いた。
「まあ、一応」
「じゃあ、途中で引き返すなんてやめなよ、パトリック。そのまま続けるより、今帰ったら、もっと後悔することになるよ」
「君の言う通りだってわかってる」
「けど...」と彼女は先を促した。
「今、キャンピングカーの中の段差に座ってて、外にいるカースティからは見えない。到着まであと何時間運転すればいいのかわからないんだ。どうやって乗り切ればいいのか、さっぱりわからなくなってる」
「きっと乗り切れるわよ。ただ、それを彼女に話してみて。私はあなたの妹のことをほとんど知らないけど、あなたが私に言ったことから察すると、もし家族のごたごたを元に戻したいって思ってる人がいるとすれば、それは彼女よ」とクロエは言った。「私がごたごたなんて言っちゃって、出過ぎた真似だったかしら?」
「いや」と彼は言った。むしろ「ごたごた」という表現は、実際の状況よりもマイルドかもしれない。
「ともかく、決めるのはあなたよ。ボールは今、あなたの側にあるの。どう打ち返そうが勝手だけど、そうね、もし途中で引き返してきても、あと1週間は、私はあなたに会わないことにする」
パトリックは笑った。「じゃあ、もしこの旅を続けたら?」
「それでも5日間は無理ね。子供たちにあなたのことをそれとなく伝えなくちゃ。いきなりだとびっくりしちゃうから」
彼はまた笑って、クロエに「それじゃあ、また」と言って電話を切った。段差から立ち上がると、さっきスーパーで買ってきたばかりの缶ビールをリュックに入れて、外へ出た。カースティはまだ道の向こうで、星や湖を眺めながら、新鮮な空気を吸い込んでいた。空気ってこんなに澄んでいたんだ、と肺が驚くくらい不慣れな空気だった。
父親のことを頭の片隅に置きながら、そして車の荷台に置いてある父親の遺灰を思いながら、彼は道を渡っていった。
カースティ
「ピザを買ってきた。湖で牡蠣(かき)でも獲れたのなら、それを食ってもいいけど」とパトリックが言って、彼女の隣に現れた。「そろそろ行こうか。今夜はもうフェリーには乗れないだろうけど、泊まるところを探さないと」
「素敵じゃない?」と彼女は、彼の話をほとんど聞かずに言った。
「見入っちゃうな。けど、カースティ、もうかなり遅れてるから」
「何をそんなに急いでるの?」と彼女は言った。「ちょっとここに座ろうよ。泊まるところなら、港の近くにちょっとしたいい場所がある。ネットで見つけたんだ」
カースティは湿った砂浜の上に腰を下ろし、ファイン湖を眺めた。パトリックはしばらく立ったままだったが、彼女の隣に腰を下ろすと、背負ったリュックから冷えた缶ビール〈オールド・スペックルド・ヘン〉を取り出し、彼女に手渡した。彼はまだ先を急ぎたい感じでそわそわしていたが、彼女は「これといった理由もなく港へ急いだって仕方ないでしょ。白兎に追い立てられてるわけじゃあるまいし」と断固として腰を上げなかった。
二人は缶ビールを開け、ぐびっと一口飲んだ。この種のビールはカースティの好みではなかった。なんだかぬめぬめと喉にまとわりつくようで、美味しくない。しかし外に選択肢がない以上、これで我慢するしかなかった。
「私がベジタリアンだって覚えてた?」と彼女は聞いた。
「そりゃね」とパトリックは返した。私の目を盗んで、ピザからペパロニのスライスを抜き取るのではないか、と思わせる言い方だった。
「パパはこうなることを予想してたと思う? どうせうまくいかないって」
「正直に言うと、予想してなかっただろうな。こういう特別な機会を設(もう)ければ、いつもみたいにはならないだろうと踏んだんじゃないか? 結局、口論の末に計画は台無しだけどな」
カースティは同意したくはなかったが、うなずく他なかった。ジェリー・カドガンは今頃、私たちを見下ろしながら残念がっていることでしょうね。彼が死ぬ間際に思い描いていたはずの筋道から、だいぶ逸(そ)れてしまった。
「もっとよく考えるべきだったよな、パパは。俺たち三人を数日間、一台の車に閉じ込めれば、そりゃあ、殴り合いになるに決まってるだろ」
「それは言わないで」
「本当のことだろ」
「本当のことでも、聞き心地がよくないわ」カースティはそう言うと、缶を大きく傾け、ぐびぐびとビールを喉に流し込んだ。「さっきまで彼女のことを考えてたんだ。あの飛行機の中で、一人きりで座ってる彼女のことを」
「本でも買って読んでるだろ」
「パトリック」
「何?」
「ただね、悲しいなって思ったの。彼女も今ここに、私たちの隣に座ってるべきよ。私たちは三人一緒にやらなきゃ。だってね、こんな機会一度きりよ...わかるでしょ」
「遺灰を撒く?」
「そう」
「だから何? せっかくここまで来たのに」と彼は言った。
「やめようって言ってるわけじゃないの。二人でも撒くべきよ。ただ、少し残しておいた方がいいと思うの。少しだけね、つまり、ジェシカの分を」
「そんなの完全におかしいだろ。でもまあ、お前がそうしたいのなら、べつに構わないけど」
「じゃあそうしましょ」と彼女は言った。
パトリックは頭を後ろに反らして、缶ビールを飲み干した。
「お前も飲み終わったか?」と彼はカースティに聞いた。
「いいえ」と言って、彼女は半分ほど残った缶を彼に手渡した。「残りは全部飲んじゃって。私はこういうお酒が嫌いなの」
「任せろ」
パトリックは、よっこらしょ、と立ち上がろうとしたが、重い体がふらついて、一瞬上がった腰が再び砂利の上に落ちた。もう一度腰を浮かそうとした時、カースティが彼のパーカーを掴み、「待って」と言った。
「何?」
「車に戻る前にもう一つ」
「何?」と彼は繰り返しながら、顔を上げた。湖が月を映している。さらにその向こう岸に目を向けたが、小高い丘々は闇に飲まれ、すっかり見えなくなっていた。
「こうなるのはいつものことだと思う? 私たちが喧嘩別れするのは」
パトリックは、またそれかよ、と言いたげにため息をついた。それに対する答えはすでに何十回も言ってきただろ、と。
「あのさ、ジェシカが―」
「この旅行中のことじゃなくて、一般的な話として、家族ってそういうものだと思う? なんかね、アルバムの写真を見返してたら、なんだか別の家族のように感じられたの。いつもお金のこととかで喧嘩してる家族って、そういう家族があるのは昔から知ってたけど。でも、私たちがそうなるとはね、思ってもみなかった」
パトリックはビールを一口飲んで、「俺も思ってもみなかったよ」と言った。「気づかないうちに、すべてが台無しになってたな。あの夜、喧嘩別れした後、俺たちの誰かがすぐに謝っていれば、家のこととか」
「違ってたかもしれないわね。私もいつもそう思う。アンドリューがいなくなって。ママもいなくなって」
「そんなこと考えてもしょうがないけどな。アンドリューは消えた。ママは死んだ」と彼は言った。「そうなっちゃったんだから、もうどうしようもない。もしかしたら、今とは違う未来が来るかもしれないし。でも、そうも思えないんだよな、なんとなくだけど」
「いつもは楽観的なくせに」
「俺が何を考えてるのか、本当に知りたいのか?」
「たぶんね」と彼女は、ためらいがちに言った。
「おそらく、避けられなかったんだと思う。友情は決まっていつか崩壊するもの。家族をまとめてる唯一のものは、義務感とかいうふざけたものだけだ」と彼は言った。「パパはいつも俺たちに言ってただろ、友達みたいに仲良くしろって。まあ、最終的に崩壊したってことだな、友達なんだから」
「愉快ね」
「俺が言いたいのは、もしそれがアンドリューではなく、ママでもなかったら、違う何かになっていただろってこと。俺たちは大人になっちゃったんだよ」
「そして離れ離れになった」
パトリックが再び立ち上がろうとした。今度は彼女は、彼を引き止めはしなかった。
「こういうこともあるさ」と彼は言って、カースティに手を差し伸べた。彼女が彼の手を掴むと、彼は思い切って彼女を引っ張り上げた。砂利の岸辺から体がふわっと持ち上がる。「けど、ここで終わりにするわけにはいかない。俺たちは先に進まなきゃ、だろ?」
彼は道路を横断した。ぽつんと一つだけ光る街灯の下で、キャンピングカーが誇らしげに鎮座している。カースティは彼に続いて道路を渡ると、運転席に乗り込んだ。凍えるような寒さに、彼女はこれから始まる夜が心配になってきた。熱がどんどん逃げていく薄っぺらな壁に囲まれ、キャンプ場まであと一歩のところにいることも忘れてしまいそうだった。
「頑張れ、アウェイドライバー。敵地のスタジアムで戦うようなものだな」とパトリックが冷やかし半分で言うのを聞きながら、彼女はキーを回した。車が重く震えるような大きな音を立て、エンジンがかかった。ヘッドライトを点灯させると、水辺に面した小さな町が照らし出された。視線を上げると、空気の密度のせいか、夜空の黒まで深く見えた。星が散りばめられ、満月が漆黒にひときわ明るく浮かび上がっていた。
キャンピングカーが動き出し、ガクンと縁石から下りると、道路に出た。パトリックはラジオの音を大きくし、ビールをもう一缶開けた。
パトリック
港の近くにちょっとしたいい場所がある、とカースティは言っていたが、結局それは港近くの駐車場になりそうだった。ネットでは良さそうだと思った二つのキャンプ場は、どちらも実際にはいい場所ではなかったらしく、彼女はそこを素通りした。一つ目のキャンプ場は、ケナクレイグのフェリー乗り場から遠すぎるという理由で、もう一つは人がまばらすぎて、なんだか殺人事件が起きるドラマのロケ地のようね、と言って彼女は却下した。
「ていうか、なんでこんなに人がいるんだ?」とパトリックは、人でごった返す駐車場を見て、不満そうにぼやいた。もう夜はだいぶ深まっていたし、お腹も空いていた。今日はかなり運転したし、車が動かなかった時間も含めて、とても長い一日だった。「10月半ばのスコットランドの田舎町だぞ。物好きな観光客がこんなにいるとはな。まあいい。早く車を停めてくれ」
しかしカースティは彼を無視し、さらに数キロの道のりを進んだ。黄色と黒のさびついた金属製の障壁があったが、それを横にどけると、海の方へどんどん進む。そして、2台のトラックを除いて他には何もない、だだっ広いアスファルトの広場に出た。
パトリックは真っ先にそこへ降り立った。チケット売り場らしきプレハブ小屋はあるが、人の気配はまるでない。翌朝、誰かが出勤してくるのだろう。桟橋(さんばし)にも人っ子一人いない。あの桟橋に横づけされるフェリーに、明日乗り込むことになるはずだ。数羽のカモメが、溢れたゴミ箱の周囲に群がり、そよ風に白い羽を揺らしている。それ以外は動くもののない、灰色で静かな場所だった。
彼は波打ち際まで行き、〈ターバート入り江〉を見下ろした。ゆるやかな波が岩場に打ち寄せている。静かで、澄んだ夜だった。彼は深く息を吸い込み、肺が新鮮な空気で満ちる感覚を味わった。ダブリンやロンドン、ブライトンでさえも、こんな空気は吸えなかった。いつでもどんよりとスモッグが立ち込め、人間が群がって暮らしている街とは全く違った。
時々、こんなところで暮らせたらな、と思うことがある。頭の中で、人里離れた田舎町で暮らす、シンプルな生活を思い描いたりもする。マギーと二人きり、他の人間関係はほとんどそぎ落とした暮らし。けれど、そんな生活はすぐに欲求不満が溜まり、寂しさを感じることになるだろうことも、同時に確信していた。ほとんど他者との交流がない、身内だけの小さなコミュニティーは、その強烈な親密さゆえに、いくら空気が澄んでいても、逆に息苦しくなるはずだ。
彼は小石を拾って海に投げ入れた。その時、カースティの声がした。「最初の一枚を入れるよ!」キャンピングカーのオーブンは小さくて、ピザを一度に一枚ずつしか焼けないのだ。
「頼む」と彼は返事をし、〈オールド・スペックルド・ヘン〉の缶を開け、ごくごくと体内に流し込んだ。ファイン湖のほとりで飲み始めてから、3本目(カースティの飲み残しを入れれば、3.5本目)だった。車内の電灯をつけ、オーブンも使って、それで夜が明けるまでキャンピングカーのバッテリーがもてばいいが、と思ったが、余計な心配はさせまいと、妹には言わないことにした。
広場の縁にある小さな縁石に腰を下ろし、パトリックはスマホを取り出すと写真のアプリを開いた。画面をスクロールし、数ヶ月前に撮った写真で指を止めた。スザンヌとマギーと自分が写っている。夏休みに、アイルランドのコーク州キンセール近くの岬まで行った時に撮った自撮り写真だった。三人はにっこりと笑みを浮かべ、スザンヌとマギーの長い髪が強風に吹かれて、二人の髪が一緒くたになっている。背後には、大西洋がかすかに見える。あの日は天候が荒れていて、眼下の岩に荒波が猛烈な勢いでぶつかっていた。恐ろしく、魅惑的な光景でもあったのを覚えている。
その日の夕方、借りていた小さなコテージに戻ると、風光明媚な海岸の景色を眺めながら、彼は三人分のパスタを作った。そしてマギーを寝室で寝かせた後、リビングのソファでスザンヌとセックスをした。―セックス自体、かなり久しぶりだった。
妻のことはよく知っているつもりだった。そんな彼女が二重生活を送っていたとは、今でもまだ信じられずにいる。俺と娘に囲まれ、こんなに幸せそうに微笑んでいるのに、この時にはすでに、彼女の人生にはパークがいた。(後になってわかったことだが、)この時すでに、俺の妻はパークとベッドに入っていた。どんなに過去を笑い飛ばそうとしても、どんなに今はクロエのことが好きでも、スザンヌから受けた衝撃は消えやしない。その痛みの渦中で、今でも俺は途方に暮れている。この旅が終わって現実の生活が再開された時、自分と娘を支えるために、俺はいったいどうしたらいいのだろう。
彼はスマホをチェックした。ステュとサラから何通かのメッセージが届いていた(一つは明らかにマギーが書いたものだった。)しかし、クロエからメッセージは届いていなかった。彼はそれを自ら打開することにした。
パトリック:まだ旅を続けてるよ。今、港に着いたところ。今夜、君もここに来たかったら、来ても構わないよ😘
クロエ:いいね!😘
クロエ:PS ほんとに構わない?😘
パトリック:全然いいよ。ていうか大歓迎だよ😘
クロエ:ならよかった😘
彼は微笑み、再び返信しようとした。その時、カースティが広場の向こうで「準備できたよ!」と、彼を呼んだ。パトリックはスマホをロックし、キャンピングカーに向かって歩き出した。何もない港の広場で、そのライトはひときわ輝いていた。―闇夜に光る灯台のようだった。
彼女はお皿を2枚と、ワイン用のグラスを2つ並べていた。テーブルの隅にはウィスキーのボトルも、2つのタンブラーグラスと一緒に置かれている。3つ目のグラスがないのが気になった。
カースティは袋入りのサラダを開け、オリーブオイルで和えていた。
「それ、どこで買ったの?」と彼は、イタリアンレストランのディスプレイからそのまま出てきたような、おしゃれまブリキのボトル入りのオリーブオイルを指差した。
「ジェシカが置いていったのよ」
「ジェシカは自分専用のオリーブオイルを持ってきてたのか?」
「彼女だったらそれくらいやるでしょ」と彼女は言った。「とにかく、このオリーブオイル、胡椒が効いててすっごく美味しいわ」
座ったばかりの彼の目の前に、彼女が〈サラダのオリーブオイル和え〉を置いた。
「あなた、大丈夫?」と彼女は、1枚目のピザをオーブンから取り出し、2枚目を入れながら聞いた。
「大丈夫だよ」と彼は、弱々しい笑みを無理に浮かべて答えた。「大丈夫に見えない?」
「見えないわね、うーん...見えるかな、つまり、あなたのことなんだから自分でわかるでしょ」
「そりゃそうだ」とパトリックは言った。カースティに「なんだか表情が怖いわ」などと言われたとしても、驚きはしなかっただろう。今日は1ヶ月分の感情やら後悔やらが、ぎゅっと濃縮して詰め込まれた1日だった。アンドリューのことを思い出し、姉妹がケンカして、それから自分の人生について、つい最近の出来事を思い起こし、少なくとも自分なりの解釈で妻のことを考え、つらい気持ちになった。
食事が終わると、カースティはピザのプレートを横にどけて、〈フォーマイカ・テーブル〉のつるつるした卓上にスペースを空けた。プレートには、すぐに冷たく乾いて固くなってしまったスーパーマーケットピザの食べ残しが何切れか残っていたが、彼女はその横に3冊目のアルバムを置いた。今回のアルバムは黒で、最初のアルバムと同様に金の縁が欠け、擦り切れていた。
「ジェシカがどうしたって?」
「どうしたっていうか―」とカースティは言いかけた。間違いなく辛辣(しんらつ)な嫌みが飛び出すと思ったのだが、彼女は自分を抑えたようだった。「いったん始めたことなら、最後までやり通さないとね。これも同じよ」彼女はそう言ってアルバムを指差し、タンブラーグラスにウィスキーを注いだ。
「ダメだ」と彼はきっぱりと言った。「彼女なしではダメだ」
「だから何なの、じゃあもう二度とこのアルバムを見ないってこと?」
「もしかしたら、いつかまた三人で見れる機会が来るかもしれない」
「なんなのよ、まったく、パトリック」彼女は苛立っていた。彼女の気持ちもわからないではない。両親の一番近くにいたことで、俺たちに対して、より大きな主張ができると思っている。それがカースティなのだ。さっきクロエが「彼女に話してみて」と言っていたが、今がそのチャンスかもしれない。ひょっとしたら、妹のやりきれない表情を乗り越えて、その向こうの奥深いところまで迫れるかもしれない。
「パパは理由があって、これらのアルバムを選んだんだ。他にも何か望んでいたかもしれないが、少なくとも、俺たちが三人で一緒に写真を見て、話し合ってほしい、それが彼の望みだったんだよ。だから、お前一人で目を通すか、彼女を待つか、どちらかだ」
「じゃあ、絶対に見ないってわけね?」カースティはグラスを傾け、ウィスキーを飲み干すと、再びグラスをウィスキーで満たした。彼女の話し方は落ち着いていた。ここでは声を荒げることはなかったが、緊張しているのは明らかだった。おそらく彼女自身も、それはわかっていた。
その時、港に到着した1台のトラックに、しばし意識を持っていかれた。広場の端の駐車スペースにバックで停めようとしているらしく、トラックが旋回を始めた。そのヘッドライトが、キャンピングカーの内部を照らし出すように、ゆっくりと横切った。まだ洗っていない食器類が乱雑に置かれたキッチンや、数日分の靴跡や泥で汚れたリノリウムの床が浮き彫りになった。
「かもな」とパトリックが言った。
「もしこれっきり、こんな形では二度と彼女に会えないとしたら? 私たち三人が集まるのは、せいぜい葬式とか、結婚式だけになっちゃうとしたら?」
「質問があるんだ」と彼は彼女を無視して言った。彼女は返事をしなかったが、彼は彼女の沈黙を、どうぞ何でも聞いて、という意味だと受け取った。「なんで俺に対しては腹を立てなかったんだ? つまり...さっき、三人で彼のことを話してた時」
「だってそれは...」と彼女が口を開いた。「彼女なら防げたでしょ? お金の問題だったんだから。彼女はアンドリューを救えたのよ、パトリック。彼女も自分でそれを認めたじゃない」
「でも、俺も救えたとしたら? もし最初の失踪の時、包み隠さずすべてをみんなに話していれば、彼は何らかの治療を受けることになったかもしれないし。あるいは、パパは彼が不安定だとわかっていれば、彼に家業を任せたりはしなかっただろ」
「あなたがそれを内緒にしていた理由は理解できるわ。あなたはママとパパを守ろうとした。ジェシカは自分自身を守ってただけ」
「馬鹿馬鹿しい」と彼は彼女の発言を一蹴した。「悪いけど、カースティ。それは買い被りすぎだよ、全くのでたらめだ。俺がどうしてあんなことをしたのか、自分でよくわかってる」
「じゃあ、どうして?」
「決まってるだろ。いつものことだよ。みんながそう思ってるのもわかってる。手遅れになるまで何も言わない。俺は昔からそういうやつなんだ」
「なるほどね。じゃあ、あなたにも腹を立てるべきってことね?」
「たぶん」とパトリックが言った。カースティは2杯目を飲み干すと、怒ったようにテーブルから立ち上がり、狭い車内で可能な限りの早足で、嵐のごとく歩き去った。そして彼女は寝台に入り込んだ。
一方、彼はウィスキーのボトルを手に取り、グラスにもう一杯注いだ。
パート 3
チャプター 10
ケナクレイグ、スコットランド
カースティ
兄より先に目を覚ましたカースティは、静かに寝台を出ると車内の床にそっと降り立った。窓は曇り、思わず両腕を抱えてしまうほど空気は冷たい。最悪の眠りだった。顔のすぐ横の小窓は外の風にガタガタと揺れっぱなしだったし、あの後、酔っ払って寝たに違いないパトリックの、うめき声やら大きないびきに安眠を邪魔された。毎晩のように、あれの隣で寝ていたスザンヌに、両腕を抱え突っ立ったまま同情している自分がいた。
昨日は大変な1日だったけれど、ある意味カタルシスだった。パトリックの告白には衝撃を受けた。ジェシカはその内容に驚いていたようだけど、私にはむしろ、彼がまともなことを言い出したこと自体が衝撃的だった。ジェシカが途中で帰らなければ...と思いながら、やかんをそっとコンロに置く。
お湯が沸くのを待つ間、彼女はテーブルの上の食器棚に手を伸ばした。車の振動で食器棚が開かないように留めてあった小さな掛け金を静かに外し、そこから父親の遺灰が入った箱を取り出す。彼女はテーブルに置いたその箱を見つめて、微笑んだ。まるで、中に入っているものが人間の姿になり、彼女の目の前に立ち現れたかのような微笑みだった。今日がその日なのだ。ジェシカやパトリックは、アイラ島でアンドリューに会えるんじゃないかとか、何かのサプライズを期待していたみたいだけど、今日、この遺灰を浜辺に撒いて、彼が望んでいた方法でお別れすることになる。
「フェイセズをかけてくれ」彼がそう言っていたのを思い出した。彼の死の2週間ほど前、葬儀の段取りやその後のことを彼は彼女に指示していた。「ロックバンドだ。知ってるよな」
もちろん知っていた。中でも『ウー・ラ・ラ』が彼のお気に入りの曲で、誕生日会や家族のパーティーでは必ずと言っていいほど流れていた。そして葬儀の時、彼の柩(ひつぎ)はこの曲とともに運ばれた。(火葬の時は、彼の指示通り曲を変えて、チャス・アンド・デイヴの『スヌーカー・ルーピー』を流した。この曲は彼が好きだったからというより、これが流れることにより場が和むだろう、という彼の計らいだった。)パトリックはその後のお別れ会で、酔っ払ってこの曲を歌っていた。ジェリーの古くからの仕事仲間たちも一緒になって歌っていたが、彼らは父とは違い、長年の喫煙とビールと激務の代償として、早死にすることはなかった。
パトリックの熊のようないびきが、彼がまだ眠っていることを告げていた。カースティはスマホのSpotifyのアプリを開き、画面の一番上にあるプレイリスト「パパ」を見た。島では電波が届かず、肝心な時に彼の好きな曲をかけられない恐れがあるので、葬儀の時にかけた曲を予めダウンロードしておいたのだ。
彼女はキャンピングカーのドアを開け、広場に出た。明るく晴れ渡った朝だった。反射した光線が、穏やかな海面の上でキラキラと踊っていた。その上を一隻の小さな漁船が、サケの漁場に向かってまっすぐ疾走している。自分の吐く息が白く舞い上がり、その向こうには緑と茶色の丘が見えた。丘の天辺にはほとんど木がなく、禿げているように見える。実際、「禿げ頭」を意味する愛称で地元の人にも親しまれていたのだが、カースティは自分が見ている場所が何と呼ばれているのかまでは知らなかった。
周りには、夜のうちに到着したらしい車やトラックが数台増えていた。そのうちの1台は車体を鮮やかな水色で染め、〈ブルイックラディック〉と側面に大きな文字が入っている。あれはたしか、リビングの棚に並べられたパパのウィスキーのコレクションの中にあったはずだ。あんな色のボトルに入っていて、そんなようなブランド名だった。きっと〈ブルイックラディック〉の熱狂的な愛好家が、アイラ島のウィスキー蒸溜所を目指しているのだろう。ちなみに、パパのコレクションの数々は、今ではそのほとんどがパトリックか、彼の1人か2人の友人の手に渡っていた。
「なんでウィスキーなの?」と数ヶ月前、彼女は父親に聞いてみた。がんでウィスキーが飲めなくなったことを嘆く父にそう聞いたところ、彼は少し考え込む仕草をした。美味しいからだよ、という単純な答えでは、彼女が納得しないことを彼は知っていた。
「唯一無二だからだな。同じ工程を経ても、ボトル一本一本が違うんだ。樽も違えば、水も違う。同じものは二つと存在しない。時間をかけて、信頼して待つしかないんだよ」と言って、彼は、3年以上リビングの棚に置かれたままの赤紫と白の箱を指差した。「あれはボトルに入れる15年も前に蒸溜されたものだ。その間ずっと倉庫で眠っていたんだ。樽の中で何が起こっているのか、誰も知らない。蒸溜した本人が、完成を見ずして死んでしまうことだってある。そしてボトルに入った瞬間、それはもう二度と変わることはない。コルクで栓をした瞬間、いわば歴史に凍結保存されるんだ」
「タイムトラベルみたいだね」
「ちょっとな」と、彼は笑った。「たしかにそうかもしれん。樽から出した瞬間のウィスキーを、そのまま口の中で味わえるんだからな。海風が吹き込む海辺で飲んでも、咳き込みながら飲んでも、ちゃんと熟成された味は変わらず残ってる。それがウィスキーの醍醐味だ」
海の向こうの遠くから、フェリーと思しき船がこちらへだんだんと近づいてくるのが見えた。それはゆっくりと移り行き、海面に突き出た岩礁を迂回する様が、水色のキャンバスに大きな弧を描いているように見える。
アイラ島のアスケーグ港へ向かうフェリーが8時15分に出発するまで、まだ30分もあった。それでも、この時間はほんの一瞬で過ぎ去るように感じられた。この旅を始めたブライトンから1,000キロも離れた目的地へ、私たちを運んでくれる船が、次第にその大きさを露わにしつつあった。
彼女はキャンピングカーに戻った。父親のウィスキー談義に引き続き思いを巡らせながら、彼女は釣り具箱を開けて、〈ポート・エレン〉を取り出した。なぜこの1本なのだろう? と彼女は思った。上の方から物音がして、彼女は飛び上がった。
パトリック
「それはちょっと早くないか?」と、彼は冗談めかして言いながら寝台から首を突き出し、カースティが手にしているウィスキーのボトルを見下ろした。
「びっくりさせないでよ、パトリック。あやうく心臓発作を起こしそうだったじゃない」
「ていうか、それを落とすなよ。後で一杯やるんだから」
彼女はウィスキーを釣り具箱に戻すと、蓋をしてテーブルの下に押し込んだ。
「ところで何してるんだ? こっそりアルバムを開こうなんて無しだからな」と、彼は陽気な口調で言った。昨夜の口論には触れないことで、事態を沈静化させようという意図らしい。まるで翌朝目を覚まし、お互いに自分が間違っていたことに気づいた夫婦のように。
「そうじゃなくて」と彼女は言った。「私はただ...」
「ただ何?」
「何でもない。さっき、ふと思ったんだけど。でも、何でもないの」と、彼女は少し身構えるように言った。「おでこのたんこぶ、だいぶ小さくなったわね」
「よかった」と彼は言ったが、指で触れてみると、それが起こった時の衝撃が、まだ痛みを伴ってありありと思い出された。
「もう準備した方がいいわ。フェリーが海を渡ってるの。もうすぐ着くよ」
カースティは自分の寝台に一旦引っ込むと、パトリックの視線を遮るようにカーテンを閉めた。
彼はあくびをした。昨夜は疲れていたが、そわそわとエネルギーが内側でうごめいていて、寝床に入ってからも何時間も眠れなかった。明け方かろうじて眠れはしたが、それまでずっと気がたかぶっていた。おそらくそれは、昨日アンドリューに関する秘密をようやく吐き出せたことから来る安堵感だったのだろう。あるいは同程度に、真夜中、酔ったまま寝台でクロエと交わしたメッセージのせいだったのかもしれない。
彼は彼女からの最新のメッセージを再び読んだ。
クロエ:明日というか今日はがんばってね。あなたたち二人の(特にあなたの)幸運を祈ってる。途中で投げ出さずに続けたあなたを誇りに思うわ😘
パトリック:ごめん。寝ちゃった。ありがとう。今日は大変な一日になるだろうけど、少しは解放感があるといいな。なんだか楽しみになってきたよ。変かな?😘
クロエ:いいえ、全然そんなことないわ。どう感じても自由よ。みんな自分なりの対処法があるんだから😘
パトリックはそれに対する返信を書いていた。―付き合い始めのカップルしか気にしないような、意味のない「おはよう」のメッセージだ。―その時、フェリーの到着を知らせる汽笛が爆音をとどろかせ、彼は頭を揺さぶられたように夢想から覚めた。そして、キャンピングカーのドアがノックされた。
「ちょっと待ってもらってもいいですか?」と彼は声をかけながら、カースティはまだ寝台の狭い空間で、もぞもぞと着替えている最中だと気づいた。
「出てくれる?」と彼女が声を上げた。
「わかった」
パトリックはジョギングパンツに〈AC/DC〉のバンドTシャツという格好のまま、ぎこちなく体をくねらせ、運転席に乗り込むと、窓を開けた。無精ひげを生やし、古ぼけたニット帽をかぶった若い男が、ガムを噛みながら立っていた。メモ帳のような紙の束とペンを手にしている。
「チケットは買いました?」
「まだです」とパトリックは言った。朝の日差しが顔面にもろに当たり、まぶしくて顔をしかめてしまう。ぼんやりと腑抜けた顔をぐにゃりと曲げ、自分がどれだけひどい顔をしているか、想像もつかなかった。
「じゃ、30ポンド(約4,800円)」
「了解。ちょっと待って」彼は手を伸ばし、助手席の小物入れを開けると、財布を取り出した。「カードは使える?」
男は頷き、紙の束に何かを走り書きすると、一番上の紙をちぎってパトリックに手渡した。
「車のまま乗船ですね」彼はクレジットカードを受け取ると、ベルトに付けたホルスターから銃を抜くような仕草で、読み取り機を取り出し、それにカードをかざした。「さあ、今すぐ乗船してください。もうすぐ出発しますよ」と彼は言った。
彼が歩き去りながら、「クソ、イングランド人め」と呟くのをパトリックは確かに聞いた。
「オーライ」パトリックは車内に響き渡るように叫んだ。「つかまれ、出発するぞ」
キャンピングカーを発進させると、「ダメ」とか「ちょっと待って」という叫び声が聞こえたが、それを無視してフェリーへと直進する。彼らは今、旅の最終区間に突入した。
チャプター 11
アスケーグ港、アイラ島
パトリック
航海は約2時間だった。広々とした川のような〈ターバート入り江〉を西へ進んでいると、いつしか開けた海に出た。しばらくすると視界の遠くにビーチや岬が見えてきたが、人影はほとんど見当たらない。その後、アイラ島への狭い海峡に入り、フェリーから降りることになる小さな港へ向かった。
彼は航海の大半をデッキで過ごした。かつての両親のようにウィスキーのテイスティングが目的だと思われる人たちもいたし、仕事でアイラ島へ向かうトラック運転手たちもいたけれど、彼らからは距離を置き、救命ボートや産業機器みたいな機械が置いてあるデッキで、彼は流れる景色を楽しんでいた。金属製の湿った椅子に腰を下ろし、海風や、青緑の海面から吹き上げる、冷たく塩辛い水しぶきを新鮮な気分で浴びていた。
パトリックは海面をくまなく見つめ、クジラを探した。スコットランドのこの地方に、クジラが生息している、あるいは旅をしていると聞いていたからだ。一方その頃、カースティは女子トイレで吐いていた。トイレから出てきた後も、カフェ兼休憩室で体を二つ折りにして、膝の間に顔を埋めていた。彼女自身が「軽い二日酔い」と呼ぶ症状に、海面の穏やかな揺れが重なり、彼女の一日は始まる前から、すでに最悪の様相を呈していた。
そういうわけで、アスケーグ港に着いた後も、すぐには島の南部にあるポート・エレンのビーチへ向かわず、二人は自然と車を降り、休憩がてら小さな防波堤に並んで腰を下ろしていた。ジュラ島を眺めながら、カースティは深く、ゆっくりとした呼吸を繰り返している。
「あのウィスキーのせいよ」と彼女は言った。
「1杯だけだろ」
「2杯」
「そうか、自分で注ぎ足したんだな。それは俺のせいじゃない」
カースティはそれには答えず、スコットランドの新鮮な空気を再び大きく吸い込んだ。まるで二日酔いを魔法のように取り除いてくれる霊薬が、ここの空気には含まれていると言わんばかりに。
「パパが言ってたけど、美味しいウィスキーは二日酔いにならないんだってね」
「そうか。彼がでたらめを言ってた可能性もなきにしもあらずだな」
「なんてこと」彼女はまた吐きそうになってえずいたが、なんとかこらえた。
二人はしばらくの間、肩を並べて座ったまま海を眺めていた。風の動きだけが感じられた。小さな港を囲む木々の間をゆるやかな、時折り強い風が吹き抜けていった。海峡の向こう岸には、ジュラ島の海岸沿いに崖が見える。崖の上は緑豊かな岸辺で、その向こうには岩だらけの丘が続いている。パトリックは、魚やカエルが断続的に引き起こす水面の波紋を眺めていた。すると、顔に水滴が1滴、2滴と落ちてくるのを感じた。雨なのか、それともその辺の葉っぱについた滴が風に飛ばされたのか。
「それで、これからどうする?」と彼が聞いた。
「さあ、どうしましょ」とカースティは答えた。「こういうことは初めてだから」
「ママの時は?」
「あの時とはちょっと違うんじゃない? 人数も多かったし」
「そうだな」パトリックは、スー・カドガンに最後の別れを告げたホーブのビーチを思い出していた。あの時は、ジェリーもジェシカもそこにいた。今、6人中、2人しかここにいない。他の家族はさまざまな理由で不在だ。
ジェリーが「落とすなよ」とか、「これは彼女の足だ」などと言いながら、妻の遺灰を一握りずつみんなに分けていた。妻を亡くしてから毎日抱えてきた強烈な悲しみを、少しでも和らげるための儀式のようだった。3つ数えて、遺灰は空中に舞い上がり、いくらかは浜辺に散った。そして、みんなで家に帰り、ソーセージを焼いて、サイダーを飲んで、彼女を偲んだ。それから1ヶ月もしないうちに、彼らは再びホーブに集まり、家族を引き裂いたあの運命的な夜のキッチンテーブルを囲むことになった。
すでに全員が大人だったけれど、父親がいることで全体が引き締まる感じがした。今回はまとめ役が不在のまま、子供二人だけであれこれ相談している感じだ。
「また同じことをすればいいんじゃない?」とカースティが言った。「灰を分け合うのよ。つまり、遺灰を手のひらに載せて、パッと。それか、骨壺を二人で持って撒くのもいいかもね」
「かもな」パトリックは二人で骨壷を抱え、砂浜に中身をどさっと空け、砂の上でこんもりと山になった遺灰が、風で吹き飛ばされるのを待つ間の気まずさを思い描いた。「もう少し儀式的な要素があった方がいいような、誰かが何かを言ったりとか」
「え? あなたがその役を買って出る気?」
パトリックは笑った。父親が、いつも家族の中で演説をする人だった。咳払いをして声の調子を整え、ワイングラスを軽く叩いてみんなを静かにさせ、「ちょっと一言」と始めるのだ。彼のスピーチがちょっと一言で終わったためしはなく、家族の誰もが覚悟していた時間よりも、はるかに長くかかるのだった。
「BGMは持ってきたんだろ?」と彼がカースティに聞いた。
「準備できてるわ」と彼女は言って、二人の目の前にスマホを差し出した。ロック画面にカースティと彼女の娘が映っている。―パトリックはほとんど会ったことがない姪っ子だ。「曲は入れてきたんだけど、なんか物足りないのよね。ただ彼の遺灰を海に撒いて、さっさと退散するだけじゃ味気ないっていうか。それ以上のことをしなければいけないような気がする」
「かもな。何か考えよう」と彼は言った。「気分はよくなったか?」
カースティが顔を上げると、彼女の顔がまだ青ざめていることに気づいたが、そのことは言わない方がいいと思った。
「あんまり」彼女はそう言うと、海を臨む草むらから立ち上がり、彼に先立ってキャンピングカーへと戻っていった。
カースティ
アスケーグ港からポート・エレンまでの道行きは、この小さな島のほぼ全域を網羅することになった。キャンピングカーはまず南西へ、ブリジェンドまでの細くて静かな道を走り、そこから真っ直ぐに南下した。アスファルトの道路はところどころが歪んでいて、左右のどちらかが浮き上がる感覚をたまに覚えながら、不気味なほど真っ直ぐな1車線の道路をひたすら走った。両側には畑が広がっていて、時折、農場の建物やトラクターが視界に入った。音といえば、耳障りな楽器のようにいつまでも鳴り続けるエンジン音と、パトリックが田園風景を眺めながら語る泥炭湿原(でいたんしつげん)についての話だけだった。この島のウィスキーにこうばしい薫香(くんこう)を加えるために、泥炭を掘り起こすのだという。カースティはそんな話はどうでもいいと思ったが、同時に、彼はこれからしようとしていることから目をそらしたくて、そんなつまらない情報をさも得意げに披露しているのだともわかった。
やがて、小さな町が見えてきた。道の片側には灰色の平屋住宅が建ち並び、反対側には背の低い石垣が続いている。石垣が途切れた地点に、大きくて不格好な工場のような建物が現れた。
「あれがそう?」と彼女は聞いた。運ばれてきた原料をここでウィスキーにしているのではないか、と思った。
「いや、あれは麦芽(ばくが)製造所だよ。あそこで原料の麦芽を―」
「わかったから大丈夫」彼女はパトリックが工場で行われていることを説明し始める前に、彼の発言を遮った。そこを通り過ぎると、大きな湾に入った。アイリッシュ海のノース海峡、その最北端の海水が、眼前に広がるポート・エレンの浜辺に打ち寄せていた。
その湾は広く、U字型をしていて、周囲を芝生に囲まれた狭い砂浜が、ぐるりとカーブを描いている。砂浜には、ベンチがいくつか間隔を空け、海に向かって置かれていたが、座っている人は誰もいない。その向こうの海は、2種類の青色で分かれているように見えた。―浅瀬は明るい青、そして奥へ行くほど青が濃くなっていく。湾の反対側に目を向けると、夫婦が犬を連れて散歩していたが、他には人影は見当たらない。
パトリックは静かな道の脇に車を停め、エンジンを切り、ハンドブレーキをかけた。
「ようやく着いたのね」と彼女は言った。「じゃ、さっそく―」
「まず一杯飲まないか?」とパトリックが言った。「ほら、あそこにパブが見える。ちょっと緊張をほぐす意味でも。パパに乾杯してから...」
ほんの30分前にそう聞かれていたら、お酒なんて飲む気にならないわ、と拒んでいたでしょう。しかしこうしてポート・エレンに到着し、目の前には砂浜があって、ジェリー・カドガンの遺灰を撒く準備が整ってしまった今となっては、それを遅らせるためなら何でもしようという気持ちだった。
「ソフトドリンクか何かなら、いいかな」
「じゃ、そうしよう」と彼が言い、二人はコートを羽織ると、海岸へと続く道に出た。カースティは、父親の遺灰を入れた黒と金色の骨壷を抱えていた。
風が強く吹いていた。乾いた砂が巻き上がり、道路と海岸を隔てているぶ厚い海草の間を吹き抜けていく。カースティは、この風が散骨にどう影響するかを心配していた。突風が父親の遺灰をまき散らし、彼女の顔に吹き付けて、洗っていないベタベタの髪の隙間に消えていくのを想像し、急に不安を覚えた。
パトリックが先立って、二人で海岸沿いの道を歩いていくと、町の中心地らしき場所に出た。中心地とはいっても、実際には生協のスーパーと小さなホテル、そして〈アードビュー・イン〉というパブがあるだけだった。彼がドアを開け、彼女を先に店の中に入れた。彼女がテーブルを探している間、彼はカウンターで飲み物を買っていた。しばらくすると彼が、ギネス・ビールを2杯と、チューリップ型のグラスに入ったウィスキーを2杯ずつ持って戻ってきた。
「ちょっと何やってんのよ、パトリック」と、カースティが懇願するように言った。「私はスパークリング・ウォーターが飲みたかったの。この後、私は運転しなきゃなのよ。っていうか、あなただってそうでしょ」
「それまでまだ何時間もあるだろ。帰りの船は6時半までないし」
彼女は腕時計を見た。まだ正午を回ったばかりだった。
「それに今は気分が最悪なのよ、無理だわ」彼女はそう言って、ギネス・ビールの入ったグラスに視線を落とした。
「今日はお前のための日じゃないだろ? これは彼が望んでいたことなんだ」
「パトリック」と彼女は言った。「あなたって時々、とんでもなく生意気な、ティーンエイジャーみたいな顔をするわね」
「さぁ、乾杯だ。このビールは旅のために。そして、このウィスキーは親父のために」
カースティは一瞬反対しようかと思ったが、彼の言う通りだと思い直した。もしパパがここにいたら、まずこのパブに来ていたことでしょうね。
「てか、私はギネスなんて好きじゃないのよ、反吐が出るわ」
「パパは好きだったよな」と、パトリックが悪戯っぽく微笑んで言った。「お前って、あれだな。ファッキンって言う代わりに、反吐が出るってよく言うよな? 汚い言葉を避けてるつもりなんだろうけど、ある意味―」
「うるさい」と彼女が遮った。
「じゃあ、彼に乾杯」と、パトリックが気取った感じの笑みを浮かべながら言った。
彼がグラスを骨壷に軽く当て、空に向かって乾杯した。カースティも視線を外に向けると、パブの窓に雨粒がぽつぽつと落ちてくるのに気づいた。そういえば、母親の遺灰を散骨した時も、ひどい天気だった。あの時の雨と風と寒さが思い出される。
二人を同じ場所に埋葬できないのなら、せめて同じような別れをさせてあげたい、と思った。
それから、しばらく窓の外を眺めていると、見覚えのある顔が横切った。すぐに通り過ぎていったが、カースティはそれが誰なのか、はっきりとわかった。一目見ればすぐに認識できる顔だ。
「何?」と、パトリックが彼女の異変に気づいて言った。
「そんなはずはないわ」
「だから何が?」今度はより強く、切迫したように言った。
チャプター 12
ジェシカ
「まだ撒いてないんでしょ?」彼女はそう言いながら、まるでぼろぼろの服を着た冬の旅人がようやく見つけた旅館に駆け込むように、荒々しくドアを開けて入ってきた。
そこは天井の低い、みすぼらしいパブだった。白い壁と年季の入った木製の家具が置かれ、装飾といえば並べられたウィスキーくらいで、あとは窓の下にジュークボックスがぽつんと置かれているだけだった。こんな店に自ら好んで入るはずもないが、この湿原ばかりの小さな島では、選択の余地などないんでしょうね。
「ジェシ?」とカースティが言った。彼女は唖然としつつ、イライラしているようでいて、かつ喜んでいるようにも見えた。ジェシカは驚かなかった。妹はいつもこんな感じで、同時に複数の感情を露わにしがちなのだ。彼女が言うことには、だいたい隠された意図があると思って間違いない。
「彼はまだその箱の中にいるの? パパのことだけど」
ジェシカはハンドバッグを、隅の椅子の上に投げ出すように置いた。近くのテーブルでは、蒸溜所のロゴが入ったお揃いの野球帽をかぶった一団が、体験してきたばかりのウィスキーの試飲についてメモを取りながら話していたが、ちょうど昼ドラが始まると、手を止めて、主人公の行く末を案じるような目つきで熱心に見入り始めた。
「ええ、もちろん彼はまだこの中よ。っていうか、あなたは何...ここで何を―」
「気が変わったの」
「スマホでチケットを買ってたよな」とパトリックが言った。
「まあ、そうね。買ったけど、今言ったように、気が変わったの。せっかくだし、見逃せない重要なシーンってあるなって思ったの」
ジェシカは足元に目をやりながら、そう話した。それは昼ドラをチラッと見てひらめいた、悪意のない噓だった。実際は、空港のセキュリティゲートで、いざパスポートを見せる段になった時、それが入っているはずのハンドバッグの内ポケットのジッパーを開けてみると、〈フルーツ・パスティル〉の包み紙と、名刺が一枚入っているだけだったのだ。ちなみにその名刺は、かつて新しい通信システムを売り込むために彼女の花屋を訪れた、魅力的な男性のものだった。
もちろん、彼女はすぐに電車を調べ、どうやって家に帰ろうかと別の方法を考えた。電車賃は高くつきそうだったが、そんなことはどうでもよかった。この大失敗の顛末(てんまつ)をダンに話せば、彼もわかってくれるでしょう。
しかしその時、テレビ画面ではなく、実際の空港のロビーで、15歳そこそこのまだあどけない少女が、涙ながらに父親を抱きしめているシーンを目撃した。
ジェシカはその少女に自分を重ね、空港の片隅で自分の若い頃を思い出していた。父に別れを告げた時、あるいは父と過ごした時間が蘇ってきた。私は彼にとって、初めての子供だった。父親と長女、二人きりで過ごした貴重な時間...そして、彼女は自分の視点から物事を見るのではなく、ついに彼の視点から世界を見た。それは子供たちを育て上げ、大人になった一人一人が、それぞれ異なる形で自分から離れていくのを見てきた男の視点だった。
ジェリー・カドガンが私を初めて学校に連れていったシーンが見えた。校門のところで泣きながら、家に帰りたいと駄々をこねていた私。(数十年後に彼が打ち明けた話によると、)彼は車の中で泣きながら、家に帰ってきてほしいと願い、校舎に入る娘の背中を見送っていたらしい。〈カドガン・ファミリー・建築士事務所〉とロゴが入った〈フォード・トランジット〉には、ポテトチップスの袋やら、ランバート&バトラーの煙草の空き箱やら、パリパリに日焼けしたデイリー・ミラー紙やらが無造作に置かれていた。私はその助手席に乗り込み、荷台に私の全財産を詰め込んで、大学に行くためにロンドンまで送ってもらった。その道中チラ見した、運転席の彼の横顔が思い出される。彼が妻のスーの(鼻持ちならない)両親に気を遣い、形だけもう一度結婚式を挙げたのと同じ教会で、私も結婚式を挙げた。長女に寄り添い、バージンロードを歩く直前、教会の入り口の外側で、その時を待っていた彼の緊張した面持ち。そして、数時間前に生まれたばかりの孫を抱く彼の笑顔。
ジェリー・カドガンは、カースティ、パトリック、アンドリュー、そして私にも多くを求めなかった。親としての要求は、愛と理解以外にはほとんどなかった。しかし今、彼は何かを求めている。そして、3人でその何かを実行に移そうとしていた。けれど、再び責任の擦り付け合いが勃発し、私は途中で車を飛び出してしまった。自分の娘や息子が互いにいがみ合っていることに、彼は長年心を砕いてきたというのに。
私がいなければ、彼の依頼を最終的に実行するのは、彼の子供のうち、たった2人だけになってしまう。彼の4人の子供の半分だ。空港であの少女を見た瞬間、そして父親と過ごした人生を思い返した瞬間、彼にそんな仕打ちをするわけにはいかないと思った。死後の世界なんて信じていないし、通夜の席で遠い親戚たちに慰められたような、「彼は上から私たちを見下ろしている」などという意味不明な提案も受け入れていない。それでも、彼の漠然とした存在感はあった。実体はないし、霊的なんて言葉を使ったらたちまち白けて、立ち消えてしまうような微かなものだったけれど、そこはかとなく彼を感じていた。親が子供に対して抱く感情の中で、最も破壊力のある「失望」の原因に、またしても自分がなることに耐えられなかった。
その時、私は気づいた。今後も人生という長い旅を続けるつもりなら、始めたことは終わらせるべきだと。そこから遠くへ逃げるのではなくね。
「ていうか、なんでパブにいるの?」と彼女は聞いた。
「彼を送り出すのに最良の方法だと思ったんだよ。1杯はこの旅のために、そして―」
「気が利いてるじゃない、彼もパブに連れて来るなんて」と彼女は言いながら、骨壷を指差した。周りの酔っ払いたちは、これを何だと思っているのかしら。
「とにかく座れ」パトリックが勢いよく席を立ちながら言った。「もう1杯買ってくるから」
「ウィスキーはやめて」と彼女は言いつつ、彼を目で追った。カウンターでバーテンが、球根のような変な形のグラスにウィスキーを注ぎ出したのを見て、「パトリック、ウィスキーはやめてって言ったでしょ」と付け加えた。
「まあまあ、ほら」と言いながら、彼がテーブルに戻ってきた。
「ギネスビールとウィスキーなんて」と彼女は言った。「パパ好みだけど」
「いい組み合わせだから、一度飲んでみろ」と彼が言った。「舌が肥えて、味を覚えるかもしれないぞ」
「それはどうかしら」
「飲んでみなきゃわからないだろ。味を覚えるには、少しの時間と努力は必要だけどな」
「いったいなんで時間と努力を費やしてまで、好きでもないものの味を覚えなきゃならないの? 正気の沙汰じゃないわ」
ジェシカはようやくテーブルの上座に腰を下ろした。カースティとパトリックは左右から向かい合っている。外はまだ雨が降っていて、さっきより少し強くなってきたようだ。散骨の儀式はどうなってしまうのだろう、と心配になってきた。ふと、二人の視線が自分に注がれていることに気づいた。
「何?」
「まさかお前、何があったのか、俺たちに話さないつもりじゃないだろうな?」とパトリックが言った。
「何を話せって言うの? 気が変わって、それでここに来たのよ」と彼女は言った。空港での出来事まで話を広げるのは何としてでも避けたかった。〈フルーツ・パスティル〉の包み紙が、虚しく、あるいは、突然の啓示のように目に飛び込んできたなんて言えるわけないわ。
「何がきっかけで気が変わったのかは置いといて、じゃあ、どうやってグラスゴー空港からこのパブまで来たんだ?」
「バスよ」と彼女は単刀直入に言った。「グラスゴーからフェリー乗り場までバスが出てるの。あなたたちが乗った朝一番の船には乗り遅れちゃって、それからが大変だったわ。次の船が来るまで、あの小さな掘っ立て小屋で、2時間も待ちぼうけよ」
パトリックとカースティは何も言わずに、グラスに口をつけ、お酒をすすった。
「何なのよ?」とジェシカが促した。
「べつに」とパトリックが言った。
「べつに、じゃないでしょ。何が言いたいの?」
「正直言って、ジェシ。お前がバスで来たことに驚いてる。飛行機をチャーターして、この島まで飛んできたのかと思ったよ。ところで、お前の荷物は?」
「車の中よ。っていうか、あなた鍵をかけなかったでしょ」
「パトリック!」と、カースティが叱りつけるように言い放った。パブにジェシカが入ってきた時に、思わず彼女の名前を口にして以来、カースティが初めて発した言葉だった。
姉妹二人で解決すべきことがあると感じたのか、パトリックはトイレに行くと言って席を立ち、二人をテーブルに残して消えた。それとも、姉妹の間でバチバチと繰り広げられていた無言の対立を見ていられなくなったのか。
しばらくの間、カースティはジェシカを見ようともしなかった。まるでパブが混みすぎていて、相席を余儀なくされた他人のようだった。意味のある会話をしようと苦心するよりも、相手を無視してスマホを見つめることの気楽さを選んだように俯いている。
「じゃあ、私から話すわ」ジェシカがそう切り出した。カースティは目だけを鋭く上に向けた。靴に唾を吐かれたかのような睨みを利かせてきたが、それでも何も言わなかった。「ねえ聞いて。まず、ごめんなさい。大丈夫? なんであんな風になったのか、自分でもわからないの。それに、誰かを殴ったことなんて、大人になってから初めてよ」
「それならなおさら、何か大きな意味があったってことでしょ」
「カースティ、お願い」
カースティが椅子をジェシカの方へ向け、正面から彼女を見据えた。
「平手打ちだけじゃないでしょ」と彼女は言った。意外にも、カースティは怒っている感じではなかった。むしろ苛立っているような、動揺しているような声だった。「いろんなこと全部よ」
「全部? 全部に対して謝れって言うの?」
「違う―」
「じゃ何、私という存在すべて? 私のやることなすこと全部?」
「そうじゃない。ジェシカ、頼むから聞いてちょうだい」
カースティが大きく息を吸い込んだ。これからスカイダイビングかバンジージャンプでも決行するかのような意気込みで、姉に歩み寄るつもりは毛頭ないらしい。
「わかってるでしょうけど、私はいっつもいろんなことを背負わされてきたの。そうでしょ? ママとパパのことよ。私は彼らの近くに残った。あなたたち二人は、とっとと出て行ったけどね。また始まった、それをネタにいっつも突っかかってくるわねって思ってるんでしょうけど」
また始まった、とジェシカは思ったが、口には出さなかった。
「とにかくそうなんだから、仕方ないでしょ。私が一番頑張ったの。あなたたちよりずっとね」
「それはそうでしょうけど、避けて通れなかったんでしょ、カースティ。あなたが彼らの近くにいてくれたことには感謝してるわ。もしあなたがいなかったら、どうなっていたんでしょうね」
「私がいなくても、彼らは二人でうまくやってたんじゃない? たとえそうだとしても、私はそんなこと絶対に認めないけどね。ってか、もしかして私、必要とされたかったのかな」
あなたは必要とされたかったのよ、とジェシカは思ったが、それも呑み込んだ。
「あなたもどこかへ引っ越そうと思ってたんでしょ? 大学を卒業して、何年かロンドンに住んで? それから海外?」
「ええ、思ってたわ」
「じゃあ、どうしてしなかったの?」
「さあ、どうしてでしょうね。ただその気になれなかっただけ。ぐずぐずしてるうちにリヴィが生まれて...あとはもうね、わかるでしょ」
ジェシカは頷いたが、カースティの言うことはあまり信じられなかった。妹がブライトンに残ったのは、両親のことを第一に考えたからだと、ジェシカは内心では思っていた。近くに子供が一人もいないなんて、彼らが気の毒だと思ったからでしょ。アンドリューは両親の近くにいたけど、いなくなっちゃって。彼がいなくなった頃には、私とパトリックはすでに新天地でそれぞれの人生を始めていた。カースティはまだ10代で自分を確立している途中だったから、兄を失ったことが、私たち二人よりもはるかに大きく、彼女の決断に影響を与えた可能性は高い。ダラム大学を中退して、故郷の近くの大学に入り直したことも、決して相容れないボーイフレンドと付き合って妊娠したことも、その影響でしょうね。彼女は、自分が育った実家から目と鼻の先で生活し、自分の家庭を築こうとしていた。
「あなたが決めた人生なんだから、何の問題もないわ」
「でもそれが問題なのよ。決めた、とか言われても、ほんとに私が決めたのかどうか。まずあなたが出て行ったでしょ、それからパトリックも。アンドリューもなぜか出て行った。でも私は残った。ママとパパと一緒にね。いつも近くにいて、頼りになる存在だったと思う。結局私は、私自身の居場所を見つけることができなかったけどね」
ジェシカは笑った。「いったい私が何を手に入れたと思ってるの?」と彼女は言った。「パトリックが何を? 聖者気取りで勝手な思い込みはよしてよね、カースティ。彼は今、スチュアートの家のソファで寝泊まりしてるのよ!」
「あなたはかなり落ち着いてるじゃない」
「そうね、落ち着いてる。でもそれは巡り合わせでそうなっただけで、私が決めたわけじゃないわ。今の場所に留まってるのは、ダンの政治家としての野心のせいよ。あの町が好きだからじゃない。私はただ彼に付いて行っただけ。ダンに会った時、私はロンドンに住んでたの。彼もそうだった。家族を作るには引っ越した方がいいって彼に言われて、私は賛成した。今はお店もあるし、友達もいる。だけど、もし全部捨てて別の場所に引っ越さなければならないとしたら、私はそうするでしょうね。パトリックも同じ。スザンヌに言われればどこへでも行ったでしょ。彼がどこかの時点でアメリカへ渡らなかったことが驚きだったくらい」
「かわいそうなパトリック」とカースティが言った。この旅が終わったら彼はどこへ帰るのかしら? と彼の行く末を心配しながら、彼女は窓の外へ目をやった。「妻はデジタル遊牧民だかなんだか知らないけど、あちこち移り住んでて、その間彼はあの子を一人で育てなきゃならないなんて」
「あなたの知り合いにもそういう人たちがいると思ってたわ。ブライトンは結構進んでる街なんだから」とジェシカは言いつつ、自分の言い方に嫌気が差した。話し方で損をしていることは前からわかっていた。それが自分を実際より10歳年上に見せ、10倍も保守的な印象を周りに与えてしまっている。
「そうね、何人かは知ってるけど、あいつらは役立たずのバカよ」とカースティが言った。「とにかく、あなたは自分の評価を下げてるわ。あなたがそれで幸せなら、あなたは付いて行っただけじゃないし、それに、あなたは自分の時間を持てるじゃない」
「そうかもね」とジェシカは言った。そして、少し間を置いてから続けた。これから言おうとしていることは、自然と口をついた言葉ではなかった。本心を打ち明けるのは昔から勇気の要ることだった。赤ワインを2、3杯飲んで舌を緩める必要があったし、常に身にまとっている感情的な拘束衣を脱がなければ何も始まらなかった。
「大丈夫?」とカースティが聞いてきて、心配されるほどあからさまな苦渋(くじゅう)が自分の顔に表れているのかと、気勢をそがれた。
「うん、そうね...大丈夫じゃないかな」と言って、彼女はギネスビールを一口飲んだ。その濃厚でピリッとくる味は、これぞアイルランド! という味で、大学時代に一時期アイルランドに嵌(は)まっていた時期を思い出した。当時はこのビールを飲みながら、アイルランド人作家の小説に夢中になり、アイルランド人の男の子(彼は今どうしてるのかしら?)と付き合っていた。「あのね、カースティ。私はもう一度謝りたいの。そして...これは馬鹿げたことに聞こえるかもしれないけど...でも、すべてのことを考えた上で、私たちはもう一度、仲良くやっていくことはできないかなって―黙って聞いて」と彼女は言った。妹が今にも反応して、流れを断ち切ろうとしてくるのを察知して、それを前もって阻止したのだ。そんなことになったら、また同じことの繰り返しで、もうどうしようもなくなってしまう。「だってほら、駆け引きとか、家族の中の権力争いみたいな? いろいろあったけどさ。でもまあ、なんていうか、この旅は、実際役に立ったわ。私でさえそう思う。いい旅だった。あなたたちと一緒に過ごせて楽しかったし、もう一度...」と彼女は言った。「もう一度私たちに戻れそうね」
ジェシカは飲み物をもう一口飲んで、それ以上しゃべらないという意思表示をした。カースティも1分ほど何も言わなかった。代わりに、彼女は手を伸ばすと、ジェシカの手の上に自分の手を乗せた。そして、その手に少し力を込め、上から握り締めた。ちょうど、カースティが動揺したり、ストレスを感じたり、あるいは気分がすぐれない時に父がよくそうしてくれたように。
「こっちこそ」と、長い沈黙の後、彼女は言った。「私こそ、ごめんなさい。私たちはもっと早く仲直りするべきだったわね、あなたが途中で...降りる前に...」
「いや、もういいのよ」
「でも」と彼女が言ったところで、パトリックがテーブルに戻ってきた。
「ああ、よかった」彼はそう言って座ると、ビールをぐびぐびと、少なくともグラスの4分の1ほどを一気に飲んだ。「いざこざはもうよそう」
「いざこざなんかじゃなかったのよ」とカースティが言った。
「くだらないいざこざだよ」
「何て呼ぼうと勝手だけど」とジェシカが口を挟んだ。「もう過去の話よ」彼女は、カースティの笑みを自分の顔に映したように微笑んだ。
「私たちはただ、この旅が役に立ってるって話してたのよ」とカースティが言った。「楽しい、ともね」
「楽しい?」パトリックが少し驚いたような声で言った。「どの場面がそんなに楽しかったんだ? 唾をかけ合うような激しい口論か? タイヤが吹っ飛んだことか? それとも、ひどい思い出話か?」
「パトリック」とカースティが言った。
「ごめん。冗談だよ」
「要するに」とジェシカは言った。「一緒に過ごせてよかったって意味よ」自分の気持ちにもっと正直に、あなたたち二人をまた友達みたいに思いたい、とか、あなたたちを私の人生の一部にしたい、とか言いたかったけれど、そう言うのが精一杯だった。「それと、私が一番好きな場面はね、明らかに、あなたの告白ね。〈フィットビット〉を通して、ファックしてることまでわかっちゃうなんて」
「傑作だろ」とパトリックが笑顔で言うと、カースティとジェシカが声を上げて笑った。
「ごめんね、笑っちゃって。違うのよ。そんなことになるなんて、大変だったわね」
カースティはにやけたまま、今度は兄の手に自分の手を添えた。ジェシカがその上に手を重ねる。
「正直、もういいんだ。それに関しては、もう気持ちの整理がついてる」
「あの女の子は?」とカースティが聞いた。「名前は何だったかしら? キャロル?」
「クロエ」
「ああ、その彼女。あなた...その気はあるの?」
「わからない。まだちょっと早いかな?」
「好きなら早いも遅いもないわよ、パトリック」
「それはそうなんだけど」と彼は微笑みながら言った。
さらに数人のウィスキーマニア(ウィスキーの銘柄が入った野球帽を被っているから一目でわかる)がパブにのらりくらりと入ってきて、彼らの近くの空いたテーブルを見つけた。一方、カドガン家の子供たちは話をやめて、お酒を味わい始めた。
ジェシカは、1ヶ月前、あるいはほんの1週間前と比べても、3人でいる時の沈黙に、確かな変化があることに気づいた。前は、もっと張り詰めたような緊張感に満ちていた。言葉を発していないというだけで、3人の間の空気には無数のボールが飛び交い、いがみ合い、点数を競い合っていた。今の沈黙は、試合終了のホイッスルが鳴った後のような、心地よさを感じられる。古くからの友人の間に流れる静寂のように、互いに話すことはなくても、一緒にいるだけで幸せな気分になれる。
もし今、そんな状態になれたとしたら、おそらくこの計画はうまくいったことになるんでしょう。1台の車で旅に出て、過去を訪ね、3人で話し合い、正直に胸の内を共有し、心を通わせることができたのかもしれない。同じ血を分け合った3人は、何年も前に途絶えていた幸せな家族に近い状態に戻れたということかしら。
彼らがビールを飲み終え、ウィスキーも飲み終える頃には、雨はやんでいた。しかし空はどんよりと、隙間なく厚い雲に覆われている。太陽の光が神の思し召しのように差し込んでくることもなく、入り江の波打ち際は暗い海水をぴちゃぴちゃと弾いている。それでも、これはこれでいいと思えてくる。これからよくなる可能性を秘めたまま、まだ灰色で、不穏で、予断を許さない関係のままで。
「それで、どうやって撒くの?」とジェシカが聞いた。
「ちょうどそれを考えてたところなんだ」とパトリックが言った。「お前がこの島に来る前に、2人で話し合ってたんだよ。カースティが流す曲を用意してくれた。で、曲を聞いたら、3人で少しずつ分ける感じかな?」と彼はためらいがちに言った。
「私が何か言った方がいいかしらね。2人がよければだけど、どう? 誰かが何かを言わないといけない気がする。パパのために」
「それでいいんじゃない」とカースティが言うと、3人は椅子を後ろに押し広げ、立ち上がった。カースティが骨壷を手に取り、店の外に出ると、パトリックと並んで歩き出した。ジェシカは少し歩を緩め、2人から距離を取った。目の端に浮かんで今にもこぼれ落ちそうな涙を拭いながら、戻ってきてよかった、と思った。
カースティ
お店から砂浜に向かって歩いていると、カースティは顔に数滴の雨粒が触れ、頬を伝って落ちていくのを感じた。空は少し明るくなってきたものの、天気はまだどちらに転ぶかわからない状況だった。彼女は骨壺をしっかりと抱き締めながら、道路を渡ってビーチに出た。少しの草むらを横切って、砂浜に足を踏み入れる。湿った砂は固まっていて、一歩進むごとにひび割れ、くぼみができた。
「どこがいいと思う?」とジェシカが、広い入り江を眺めながら聞いた。父親がどこに遺灰を撒いてほしいと望んでいるのか、3人ともさっぱり見当がつかなかった。見晴らしの良い場所がいいのか、彼にとって特別な意味を持つスポットがあるのか、そういうことは何も書かれていなかった。
「もう少し海に近い方がいいかな。半分は海へ、半分はこの島の砂と、混ぜる感じで」とカースティは言いながら、「混ぜる」という言葉を口にするのに少し抵抗を感じたが、他にいい言葉も思いつかなかった。
2、3分砂浜を歩いただろうか。海に近づくほど、徐々に足元の砂が柔らかくなり、3人が歩いたは足跡がくっきりと後ろに残っていった。その数は、家族全員で来ていれば、この砂浜についたはずの足跡の、ちょうど半分だった。
頭上では、空がさっきより暗くなっていた。雨も少し強まり、風も強くなってきた。パトリックはコートの襟を立てると首元を隠すようにして、ギリギリまで水辺に近づく決意を固めた。
その時、カースティはあることに気がついた。
「忘れてきちゃった」
「何?」ジェシカが、一人で立ち止まったカースティの方を振り返った。
「ウィスキーを持って来なくちゃ」
ジェシカが視線をそらし、空を見上げた。その顔は、それくらいいいじゃない、と言いたそうだった。
「そうしなきゃいけないのよ、ジェシ。わかってるでしょ。パパの―」
「そうね」ジェシカはそう言って、海辺からこちらへ戻ってくる。パトリックがカースティに車の鍵と釣り具箱の鍵を手渡した。
彼女は早歩きで車に戻り始めたが、背後からジェシカの、急いで、という声が聞こえ、砂浜を蹴るように走り出した。泥や汚れにまみれた古いキャンピングカーは、何かの記念碑のように道端に佇んでいた。
カースティは車内に入ると、まずプラスチックのコップを3つ手に取り、それからウィスキーが入っている釣り具箱を開けた。それを取り出すと、ボトルが入った箱に何かが記(しる)されているのに気づいた。
BOTTLED IN 1983.(1983年、瓶詰め)
今朝、父親から聞いた話を思い出していた。瓶詰めのこと、樽の中で何年も熟成させること。ボトル1本1本がどれも唯一無二で、ボトルにコルク栓を差し込んだ瞬間、中に時間、場所、歴史が凍結保存されるということ。
このウィスキーは35年前、今、兄と姉が立っている浜辺からほんのちょっと行った所にあるポート・エレン蒸溜所で、その工程を経た。そして瓶詰めされた後は、何が起きようと、どこに運ばれようと、誰が所有しようと、中身のウィスキーは35年前のまま、ここに収まっているのだ。
彼女はそのボトルを手にしながら、ジェリー・カドガンがこれを選んだ理由を考えていた。1983年に瓶詰めされたウィスキー。この島でコルク栓がはめられる数ヶ月前か、あるいは数ヶ月後に、アンドリュー・カドガンが、ここから600マイル南にあるブライトンで生まれた。
カースティは急いで車を降りると、砂浜を走って、再び強まってきた雨と風と寒さを凌(しの)ごうと、2匹のペンギンみたいに身を寄せ合っている姉と兄のところへ駆け寄った。
「それじゃ、それを?」と、パトリックは彼女が持ってきたコップを指差しながら言った。「急ごう。ここはクソ寒くて、凍えそうだ」
「少しだけ時間をちょうだい」と彼女は言った。彼女の声は、吹き付ける風の音に紛れ、揺れていた。「あなたたちに言わなくちゃいけないことがあるの。アンドリューのことで」
「アンドリューのこと?」とジェシカが聞き返した。
カースティは頷くと、言った。「彼はここにいるのよ。なんとなく―」
彼女が発した「なんとなく」という言葉は風にかき消されるように、二人の耳には届かなかったようで、「彼はここにいる」と言った直後から、二人は彼女に向かって、どこで、どうやって、いつ知ったのか、と続けざまに質問を浴びせ始めた。
「違う! 待って」と彼女は言った。「ちゃんと聞いてる? なんとなく、そんな気がするって言ったのよ」
「ふざけんなよ、カースティのカスが」
「彼はこのウィスキーなのよ」と彼女は言った。二人の顔に困惑の色が浮かぶのが見て取れた。「つまりね、このボトルの日付を見てよ」
「1983年」とパトリックが言った。
「彼が生まれた年よ。数ヶ月前、パパに聞いたの。なぜそんなにウィスキーが好きなのかって。そしたら、瓶に詰めると中で時間が止まるからだ、みたいなことを言ってた。このコルク栓を抜くまで、決して変化しないんだって」と言って、彼女はそのボトルを少し持ち上げた。「そしてこれは、アンドリューが生まれたちょうどその年に、ここで瓶詰めされたものなのよ」
二人は彼女をぽかんと見つめていた。
「残念だけど、彼はここにはいないわ」彼女はそう言って、足元の砂を指差した。「彼はおそらく一度もここに来たことがなかった。だけど今、彼はここにいる。パパがこのウィスキーを、つまり彼を、私たちと一緒にあの車に乗せて、ここに送り込んだのよ。今朝、そのことをずっと考えてた。だからこそ彼は私たちに、数ある浜辺の中からアイラ島を指定して、ここに行けと言ったんだわ」
カースティはボトルを指差した。『ライオン・キング』の冒頭で猿がライオンの赤ちゃんを天高く掲げるように、よっぽど彼女はそれを天高く掲げようかと思ったが、やめておいた。彼女はただボトルを抱えたまま、そこに立っていた。2人はそんな彼女を、雨でずぶ濡れになりながら、見守っていた。
「なるほどね。パパらしいというか、奥ゆかしいというか、深すぎて気づかないところだったわ」とジェシカが骨壷を見下ろしながら言った。「パパ、私たち、そしてここに...アンドリューの身代わり」
「そうは思わない?」とカースティが聞いた。
「ある意味、そう思うかな」と彼女は渋々といった感じで同意した。「アンドリューの代わりになるもので、私たちに持たせるのに一番いいものがこのボトルだって、パパが思ったのなら、そうなんでしょう」
「だからパパはこれを買ったのよ。このラベルを見て、彼の思い出の品にって」
「センチメンタルね」とジェシカは言った。しかしそれは批判というより、同意の意思表示に聞こえた。
パトリックが「じゃあ、開けようか」と言うまで、3人はしばらくそのボトルを見つめていた。
波打ち際まで歩いていき、カースティがホスト役を務めようと、コップにウィスキーを注ぎ出した。2つのコップに注いだところで、パトリックがしゃらくせぇと言わんばかりに瓶の首根っこを掴み、ボトルごと、ぐびぐびと飲み出した。
海に目を向けると、あちこちで波が立ち、海面が荒く波打っていた。左右2つの桟橋が海に突き出し、パレードを両脇から見守る儀仗兵(ぎじょうへい)のように真っ直ぐに伸びている。右手の向こうに見える麦芽製造所から煙がもくもくと立ち昇り、手前では桟橋につながれた小さな漁船がゆらゆらと上下に揺れている。冷たいアイリッシュ海が、この入り江を徐々に削り取ろうとしているかのように、岸壁(がんぺき)に海水を打ち付けていた。浜辺に打ち上げられた青いナイロン製のひもや岩に、昆布が張り付くように顔を覗かせている。
「じゃあ、準備はいい?」とジェシカが言った。パトリックはウィスキーをカースティに渡し、彼女は一口飲んでから姉に渡した。ボトルはもうほとんど空になっていた。あと一人一口ずつ(パトリックは二口分)残っているくらいだ。
ジェシカは骨壷の蓋を取ると、カースティとパトリックに差し出した。二人は無造作に詰め込まれたビニール袋に手を入れ、灰褐色(はいかっしょく)の遺灰を一掴みずつ手に取った。その骨壺は大きさとしては宝石箱くらいで、今はジェリーが入っているけれど、ジュエリーなども収納できそうだった。そして、ジェシカも遺灰を手に取った。
「ここまで来たわよ、パパ」と彼女が言った。カースティは自分が言おうとしていた「台詞」を姉が先に言い出したことに気づいたが、この場は姉に任せることにした。用意してきた曲も、少なくとも今は、流さないことにした。「私たちは途中で断念しそうになった時もあったけど、というか、私が断念しかけたんだけど」彼女はそう言うと、申し訳なさそうな顔をして2人を見た。「でも、私たちはたどり着いた。そして、あなたの計画が素晴らしいものだったと気づけた。すべては...あなたの思し召しね。私たちはちゃんと話し合ったわ。胸を割って正直に話した。そして、私たちは再びつながったの。だから、きっとパパは、よくやったって言ってくれるわね。あなたは良い親だった、最後の最後まで、というか、それ以降の延長戦までもね。パパ、いつもいつも簡単じゃなかったのはわかってる。辛い時期もあったし、ひどい時期もあった。でも、いつだって私たちはあなたと、あなたの愛を疑ったことはないよ。あなたがいなくて、私たちは寂しい」
パトリックとカースティも涙を浮かべながら、最後のセンチメンタルな言葉を繰り返した。それから、ジェシカが「スリー、ツー、ワン」と言い、3人は一斉に遺灰を海に向かって投げた。
雨にさらされながら海水の上に落ちたものもあれば、風に押し戻され、カースティのジーンズを灰色に、細かな砂粒がパウダー状にかかったように染めたものもあった。残りは濡れた砂の上に落ちた。
3人は再び骨壺に手を入れると、もう一度投げるために遺灰を一握り掴んだ。パトリックがブーツの底を海水につけて、ジェリーの遺骨を海に撒いた。遺骨はしばらくの間、水面に浮かんでいたが、やがて海へと消えていった。
パトリックとカースティが再び骨壺に手を伸ばした。最後の一握りになりそうだった。
「待って」とジェシカが言った。「少し持って帰ろうよ。ママも眠ってるブライトンの浜辺にも撒こう」
パトリックもカースティも、それに対して何も言わなかった。2人の沈黙は十分に同意を示していた。すると、パトリックがウィスキーのボトルを手に取り、残っていたわずかな量を口に流し込むと、父親の遺灰を少しだけ手に取った。
「何を―」とカースティが聞きかけたが、すぐにわかった。
パトリックは手のひらを丸めて、1983年にこのスコットランドの小さな町でその生涯を始めたボトルの口に、父の遺灰をそっと注ぎ入れたのだ。そして入り江の水でボトルを満たし、いわば遺灰と海水のカクテルを作ると、コルク栓をして、ラベルにキスした。
彼がボトルに向かって「ごめんな」と呟く声が、カースティには聞こえたような気がした。
彼がボトルの首を持って、頭上に振りかぶり、それを海に投げ入れようとした。その時、犬の鳴き声が聞こえ、彼女は振り向いた。
かなり離れたところに、ゴールデンレトリバーを散歩させている男がいた。遠すぎて顔立ちまではわからなかったが、濃いブルーのジーンズにウェリントンブーツを履き、ジャケットに野球帽という出(い)で立ちだった。時々立ち止まってはテニスボールを拾い、砂浜の進行方向に向かって投げては、愛犬に取りに行かせていた。
瞬間的に、彼かもしれない、と思った。アンドリューかも。年齢も体格も彼と似通っていた。腕を弓なりに反らしているパトリックを制止しようかと思った。けれど、その男が近づいてくるにつれ、彼がただの見知らぬ男であることに気づいた。知らない人だ。アンドリューではない。私の兄ではない。パパの息子ではない。
喉の奥からうめき声を発しながら、パトリックがボトルを海に向かって投げた。30メートルほどくるくるとアーチを描いたところで、それは小さな水しぶきを上げて海面に落ちた。浮いたまま沖へ流され漂流するのか、波に押し戻され岸辺に戻ってくるのか、それともポートエレンの入り江の底に沈んでいくのか、遠すぎて判別できない。
「よし」パトリックは2人の方を振り向くと言った。「じゃ、行こうか?」
「うん」とカースティが答え、3人は砂浜を横切って、キャンピングカーへと戻っていった。あと1冊、まだ探索していないアルバムがテーブルの上に残っていた。
カースティはすでにその中を見ていた。今朝、パトリックはまだ眠っていたが、こっそりと表紙をめくってみたのだ。最初のページの写真が目に飛び込んできて、すぐにいつ撮った写真かわかった。それは、新しい命が誕生し家族が増えたと思ったら、原因不明の失踪で家族が減った直後の家族写真だった。
アンドリューがいなくなった後の冬。
2009年のクリスマスと大晦日 ―
ギャントン通りの邸宅、ホーブ
ジェリーは、テーブルの上に積み上げた椅子に載せたカメラの後ろに立ち、ファインダーを覗き込んだ。
「ダン、もうちょっと前へ」と、彼は手をパタパタとはためかせて指図した。「ジェシカ、お前は一番前だ。マックスちゃんを前面に押し出すようにして、彼が笑顔を見せてるかどうか確認しろ。なんてったって、彼が主役だからな」
彼はにんまりと、孫を愛おしそうに見つめながらそう言った。それから少し警戒するように視線をずらし、末娘のカースティを見やった。20歳になったにもかかわらず、時々、マックスが家族の全注目を独り占めしていることに、彼女は嫉妬しているような雰囲気があった。おかげで自分は用済みだとでも、彼女は思っているようだった。しかし、今夜ばかりは嫉妬している場合ではないと思ったのか、彼女はすまし顔で佇んでいた。
「スー」と彼は妻を呼んだ。「スー!」
「一度目で聞こえたわよ」
「じゃあ、なんですぐ返事しないんだ?」
「どうしたの?」と彼女は、それには答えず言った。
「このなんだかよくわからん機械は、どうやってタイマーをセットするんだ? ロケット工学の学位が必要なのか―」
「時計の上についてる小さなボタンを押すんだよ、パパ」とパトリックが言った。
「そんなこと俺が知るわけねぇだろ?」
「時計っぽい液晶画面があるだろ、その上の小さなボタンだよ」
「生意気なやつめ」とジェリーは言いながら、ボタンを押した。「10」という数字が画面に表示され、彼は急ぎ足で家族の元へ戻った。その場から離れながら、カメラを載せた椅子がテーブルから崩れ落ちるのではないか、と心配がよぎった。「よし。その立ち位置をキープだぞ」
「みんなソーセージと言って、せーの!」
「ソーセージ!」と、全員がスーの掛け声に続いて言った。まるで牧師に続いて「アーメン!」と、声を合わせる信徒たちのようだった。約2秒後、彼らの表情が和らぎ、半笑い状態になった頃、フラッシュがたかれ、カシャッとその一瞬が保存された。
カドガン家の面々と、そのパートナーたちは歓声を上げた。ダンとジェシカは幼い息子を取り囲むように寄り添っている。一方、パトリックはスザンヌの手を取り、お酒を飲み直すためにキッチンへ向かった。カースティはソファに一人で座り、大学時代から付き合っているブラジル人のルイスに、またメールを書いた。彼はその夜、ロンドンの南部、ストックウェルの友人宅で開かれているパーティーに参加していた。
大晦日を一緒に過ごすというのは、ジェリーとスーから言い渡された義務のようなものだった。クリスマスに関しては微妙で、政治的な判断も必要だったため、ジェシカとダンは、お互いの両親の元を、一年ごとに交互に訪れることにしていた。今年はダンの実家を訪れる番だった。(孫が生まれたことにより、どちらの実家にも気を遣い、やはり交互に訪れるのが一番いいと、決意を新たにしたのだった。)パトリックとスザンヌはニューヨーク行きのチケットを予約し、12月30日までは彼女の実家で過ごすことにした。カースティだけが留守番だった。
「お父さんと私はね」と、スーが電話越しに言ったのは10月のことだった。どうやら家族みんなに電話をかけ、まるでコールセンターで台本を読んでいるかのように、全く同じ台詞をみんなに言い聞かせているらしかった。「新年だけは一緒に迎えたいって思ってるのよ。クリスマスが無理なら、新年だけはって。今年はほら、家族みんなにとって辛い出来事があったでしょ。だから、新たな年はできるだけ仲良く、みんなで集まって始めることが大事なのよ」
パトリックは断れないと思った。スザンヌは、大晦日にはプリムローズ・ヒルに登って、ロンドンの街を見下ろし、テムズ川の向こうで打ち上がる花火を眺めながら、2010年を迎えたいと言っていた。それは彼女が今までに経験したことがない新年の迎え方だった。しかし、このような例外的な状況にあっては、それはお預けにするしかなかった。
ジェシカとダンには特に何の予定もなかった。親子で新年を祝うことは、子供が10時以降も起きていることになるので、なるべく避けたい、くらいの意見しか持っていなかった。
カースティだけは、なんとしてもルイスたちと一緒にストックウェルへ行くことを熱望していた。パーティーで彼が仲間たちと何を飲み、何を吸い、そしてその影響下で何をやるのか、気がかりで落ち着かなかった。
家族写真を撮った後、ジェシカとダンはマックスを寝かしつけに行った。パトリックはスザンヌに付き添ってタバコを吸いに外へ出た。ジェリーとスーはキッチンでビュッフェの準備を始めた。一人取り残されたカースティは、リビングの一角を占拠している特大のクリスマスツリーをしばらく眺めていた。ツリーが邪魔して、庭に面した窓は見えない。
彼女はソファから立ち上がると、テレビ横のキャビネットの前に立った。その上には、家族それぞれの写真が飾られている。例外なく1人につき2枚ずつ、母親が公平に並べたものだ。カースティは黒のパーカーを体に巻きつけ、ジッパーを閉めた。その勢いで、剝がれかかっていたバンド名〈ストロークス〉のロゴが少し剥がれ落ちた。
そこには家族みんなの写真が、一見するとランダムだが、母親だけが知っている意味のある順番で並べられていた。
ジェシカの2枚は、卒業式と結婚式の時のものだった。パトリックのは、ワトフォードがリーズを3-0で破ったチャンピオンシップのプレイオフ決勝をジェリーと観戦した直後の親子写真と、もう1枚は、彼がワゴン車に寄りかかっている写真だった。父親の家業とは区別して、彼が自分で住宅改修業を立ち上げた時に買った新車だ。カースティの写真は、彼女がレベルAの卒業証書を手にしているものと、ステージでベースを弾いているものだった。大学進学を機に解散した、過激なパンクバンドだった。
そして、もう2枚の写真があった。家族それぞれの人生からは見えなくなってしまった男の写真だったが、家族の記念ギャラリーにはちゃんとその姿が写っていた。
1枚目は、アンドリューが軍服姿の写真だった。キャッタリックでの訓練を終えた日に撮られたもので、ジェリーとスーが彼に会いにこの地を訪れたのだ。もう1枚は昨年のもので、ガールフレンドのメルと一緒に写った写真だった。今年の初め、彼が失踪する直前に、2人の関係は破局を迎えていた。
カースティはメルが写った写真を手に取ると、独り言にもならないほど微かな声で、「あなたがいなくて寂しいよ、お兄ちゃん」と言いながら、そっと写真を入れ替えた。神経が張り詰め、抑えきれない想いがこみ上げてくる。また、彼がいないことに泣きそうになっている自分に気づく。
その夜は、主にジェリーがカメラを持って、家族がゲームをしたり、食事をしたりしている姿を撮っていた。何をやるにもその場を支配していた強制的な楽しさは、世界中のサラリーマンが耐えている、あの強制感みたいだ、とジェシカは思った。社員の結束を高めるとかいう謎の名目の元に、大々的に敢行される日帰り旅行のようだった。彼女は、マックスのせいで疲れたからもう眠いわ、と言って、さっさとベッドルームに退散しようか、と何度も思っては、なんとかこらえるのに必死だった。いっそのこと、リビングのソファで寝たふりをしようか、とさえ思った。(ダンの友人たちとのディナーパーティで、早く帰りたい時に何度か使った技だ。)しかし、ゲームに参加するほどではないにせよ、より大きな善意が彼女をその場にとどまらせた。
11時半頃になると、ゲームも一旦お開きになった。スーは新年を祝うためにチョコレートフォンデュ用の器具を出してきて、キッチンでチョコレートを溶かし始めた。ジェリーは「真夜中に飲みたい人?」とパトリックとダンだけを見て聞くと、書斎に保管してあるウィスキーを選びに行った。
スザンヌが再びタバコを吸いに外へ出て行くのを見て、パトリックも後を追うかな、とジェシカは思ったが、彼は腰を上げなかった。外は寒く、小雨が降っていた。
「どんな感じ?」とジェシカは、テレビに面した大きなソファに座っているパトリックの横に腰を下ろしながら聞いた。(他の2つのソファは1人掛けで、少し斜めに置かれているので、テレビを見るには不向きだった。)
「疲れた。そういうことじゃなくて?」
「それはわかるけど、パパとママは大丈夫だと思う?」
「正直言って、俺らがここにいる限りは大丈夫だろ。心配なのは明日だよ」
「明日になればすべてが見えてくるでしょ?」
「何が?」
「新年の幕開けは、物事を見極めるのにうってつけじゃない。新たな年をどうスタートさせるのか考えるのよ。自分が持っているもの、持っていないもの。頭の中を整理して、哲学的な時間にもなるわ」
「そうだな」とパトリックが言った。「それに、彼らは二日酔いだろう。そうなると、すべてが悪くなるな」
「うーん」ジェシカは、そういうことじゃなくて、と思い、弟の単純明快な思考回路に感心すると同時に呆れた。彼の思考回路には、高速道路が1本走っているだけで、そこを真っ直ぐに進んでいれば、真理にたどり着くらしい。
「あのさ、今夜はそのことに触れないつもりだったんだけど―」
「何よ?」とジェシカは聞いた。「彼女が妊娠したとか?」
「いや。それは...ない」と、彼は自分自身に確認するように言った。「そうじゃなくて、今夜は言いたくなかったんだけど、スザンヌに新しい仕事のオファーが来たんだ。昇進だよ、栄転ってやつだ」
「よかったじゃない。神様が良い知らせを授けに舞い降りたのね」
「まあ、それはそうなんだけど、そうでもないっていうか、その仕事はアイルランドにあって、ダブリンに引っ越さないといけない」
「あら」
「タイミングが理想的じゃないのはわかってるけど―」
「じゃあ、彼女はもうオファーを受けたんだ」
「いや、そういうわけでもなくて、俺たちはまだ...なんていうか」
「パトリック。タイミングが理想的じゃないのはわかってるけど、とか言ってる時点で、もう受けたも同然なのよ」
「正式にはまだだよ。でも、給料がすごいんだ。IT部門は今ダブリンで大きく発展している。それに、俺の仕事はここでなきゃできないってもんじゃない。アイルランドにも壁を塗って欲しがってる人はたくさんいるだろ?」
ジェシカはラム酒とコーラのカクテルに口をつけると、グラスの中にパンくずが落ちているのを見つけ、小指ですくい取った。彼女は着ている赤いジャンパーにも手を走らせ、パンくずがついていないか確認している。
「おい、何か言ってくれよ」
「何を言わせたいの? 明らかに、引っ越す気満々じゃない。タイミングは、これ以上ないってくらい最悪なのに。子供が1人いなくなってまだ半年しか経ってないっていうのに、もう1人遠くへ行っちゃうなんてね」
「そうか。言いたければ、彼らに言えばいい。お前は気楽だな、10年も前にこの地を離れて、行ったきり戻ってこない。スザンヌはアメリカからロンドンに来て、それからここに引っ越してきた。彼女が俺についてきてほしいって―」
「なぜ私たちがロンドンの近くに住んでるのか、わかるでしょ。ダンは1人っ子だし、彼の両親がマックスに会えるのはいいことなのよ。それに、私は自分のビジネスを立ち上げて、あそこで自分の人生を築いてきた。あなただって今までここで自分の人生を築いてきたんでしょ―」
「2人は何を言い争ってるの?」とカースティが言った。2人とも、彼女が部屋に入ってきて、ソファの肘掛けの上に腰を掛けたことに気づいていなかった。彼女は缶入りの洋梨の発泡酒を飲んでいる。
「パトリックがアイルランドに引っ越すんだって」とジェシカが言った。
「ジェシ」
「だって、そうなんでしょ」
「パトリック」とカースティがイライラした口調で言った。「それって半年くらい待てなかったの?」
「スザンヌの栄転なんだよ」と彼は言った。
「そう。それで、あなたはあそこよね、ベーコンズフィールドだっけ?」と、カースティはジェシカを指さしながら聞いた。
「バーカムステッドよ」とジェシカは訂正した。
「どうでもいいけど。私は大学があるから、これから6ヶ月間ダラムにいるのよ。あなたがダブリンに行っちゃったら、彼らは2人きりになっちゃうじゃない。2人きりにしてはいけない時に」
「戻ってくるよ」とパトリックがカースティに言った。「俺たちはどこかの時点で戻ってくる。一時的なものだよ」
「そうでなくなるまでは一時的よね」とジェシカは言った。
「それで? 私はこの辺りに居残って、じっとしてればいいってわけ?」とカースティが言った。「私は何? 両親の番人?」
パトリックはもううんざりだった。彼はビールの残りを飲み干すと、必要以上に力を込めてグラスをテーブルに置いた。
「あのな。ママは昔から、親のためにこの近くに居続ける必要はないって言ってただろ」
「状況は変わるものよ、パトリック。人生は変わるの」とジェシカが言った。
「じゃあ、お前がここに戻ってくればいいだろ?」
「私の生活を丸ごと移転させるのは大変なのよ。これから数ヶ月間あなたがここにとどまるのは、それほど大変じゃないでしょ。私が言ってるのはそういうこと」
「何も言わなければよかったな」とパトリックが嘆くように言った。
「今回は言ってくれてよかったわ。じゃないとまた、あなたが引っ越す前日になって、え? あんた引っ越すの?って、私たちは知ることになったでしょうね」
「彼女の言う通りよ、パトリック」とカースティも言った。「あなたはいつもギリギリまで待ってから、何でも言うのね。それがどんなに重要なことであっても」
いつもじゃない、と彼は言いたかった。たまにはそういうこともあるけど、自分の中には、先を見越して行動する力もあるんだ、と。自分が積極的に行動していなければ、アンドリューはもっとずっと早く、この家を出て行っただろう。そしておそらく、もっと悪い結果をもたらしたはずだ。
「そうだな。引っ越すのを少し延ばせないか考えてみるよ、それでいいか? ただ、今夜はもうそのことで言い争うのはやめよう」と彼は言った。そして、2人の沈黙を同意とみなして、彼は空になったグラスを掲げ、「休戦」と言った。姉と妹もグラスを掲げ、3つのグラスを軽く合わせて、「休戦」と繰り返した。パトリックが飲み物を取りに行こうと、ソファから立ち上がった時、リビングのドアが開いて、ジェリーとスーが入ってきた。2人はそれぞれ、カメラと、チョコレート風味のスナック菓子〈トゥイグレッツ〉が山盛りに入ったボウルを抱えている。
「全員そろってるな」と言って、ジェリーはカメラを構えた。「さあ、2人ともそのままそこにいて。パトリックも戻って座れ」
彼が父の指示通りにソファに戻ると、ジェリーは立て続けに少なくとも6枚、3人が一緒に写った写真を撮った。
「10年前にも、まさにこんな感じの写真を撮ったんだよ、覚えてるか?」と彼はスーに聞いた。「当時はどぎついピンクのソファに座ってたけどな。あれは、巨大な怪物のようだった」と彼は笑いながら言った。「たしか、あそこにあったな」彼が部屋の隅を指差した。めったに使われないピアノの上に、フレームの縁が真鍮や銀で光る写真のコレクションが並んでいる。「取ってくれ。見てみよう」
一番近くにいたカースティが、その写真を手に取って見た。明らかに、10年よりもはるかに前に撮られたものだった。過ぎ去った年月が父の中で圧縮され、キュッと束ねられ、時間と記憶を曖昧にしているのだろう。彼女はまだ赤ん坊で、ジェシカの膝の上に座り、姉の長い茶色の髪の束を、ぽっちゃりとした小さな手で掴んでいる。
それを見てすぐに、カースティは写真をピアノの上に戻そうとした。父には渡したくなかった。しかし、彼はそれを奪い取るように掴むと、自分とスーの目の前に差し出した。途端に、2人の顔から陽気な笑顔がすっと消えた。スーは泣きそうになるのをこらえるように、急いで部屋を出て行った。ジェリーは4人が写った写真を持ったまま、「知らなかった、愛しい息子よ。俺は覚えていなかった...」みたいなことを呟いていた。
彼の手から写真がするりと滑り落ち、彼は部屋を出ていった。床に落ちた写真をジェシカが拾い、ソファに座った。カースティとパトリックも彼女の両脇に座った。
ガラスに大きなヒビが入っていた。フレームの端から端まで水平に亀裂が伸びている。それでも彼らは、なぜこの写真を母親がピアノの上に飾っていたのか、すぐにわかった。
その写真の主役は、姉の膝の上に座っている赤ん坊のカースティではなかった。妹を上から見つめているジェシカでもなかった。〈ワトフォード〉の紫と緑のアウェイ用ユニフォームを着て、隅っこでうつむいているパトリックでもなかった。彼はカメラを見てさえいない。
そう、この写真の主役は、ソファの真ん中に座り、にっこりと歯を見せ、両手を広げているアンドリューだったのだ。兄や姉がカメラを無視している中、一人あふれんばかりの快活さで、おちゃらけるようにポーズをとっている彼こそが、この写真が撮られた理由だった。他の人たちは、ただ写っているだけのエキストラに過ぎなかった。
それは、数十年後にジェリーが「まさにこんな感じの写真を撮ったんだよ」と言って、期待したような、3人で写っている写真ではなく、彼が決して再現することの叶わない写真だった。
「ったく」とパトリックが吐き出すように言った。母親の泣き声が聞こえてきた。深く、息苦しく、激しい嗚咽だった。彼女がそこまで取り乱したことはそれまでなかった。彼女自身の母親が死んだ時でさえも、そんな泣き方はしなかった。それは、時間とともに必然的に亡くなっていく人への悲しみではなく、悲劇的で予期せぬ喪失への鋭い叫びだった。
その時、玄関ホールの大時計が鳴った。午前0時を回ったのだ。
しかし誰も、新年あけましておめでとう、などとは言わなかった。
チャプター 13
ポート・エレン、アイラ島、スコットランド
カースティ
1ページ目をめくる時には、みんな涙を流していた。2ページ目には、3人がソファに座っている写真が現れた。パトリックがアイルランドに引っ越すことについて口論になったことが思い出される。その直後に撮られた写真だ。もちろん、彼はアイルランドに行った。それは誰もが予想したことだった。スザンヌがそう決めたのなら、彼も、他の人も、彼女の気持ちを変えることはほぼできなかった。
その年の大晦日の記憶は、長く尾を引くことになった。2010年は、アンドリューのいない生活に慣れなくてはいけなかったのだが、慣れるどころか、さらなる悲しみと痛みをもたらした。父親は息子を探す方法はないかと懸命に知恵を絞り、母親は彼が自分の意志で帰ってくることを信じ、探すのをやめるよう父親に懇願し続けた1年だった。
「時期が来たら、きっと帰ってくるから」
このように2010年に起きたことを思い出すと、ほとんどすべての出来事がアンドリューを呼び起こすきっかけとなる。あの年、スーが地元のスポーツジムの受付嬢として久方ぶりに仕事に復帰したのは、アンドリューが家業を破産寸前まで駄目にしてしまったため、住宅ローンの借り換えが必要になったからだし、パトリックが隔週でダブリンから実家に帰ってきたのは、彼なりに罪悪感があったからだろう。彼はなるべく両親のそばにいようとした。何か恐ろしいことがあった後では、人はいつもより注意深く行動するものだ。でも、1年か2年も経てば、大抵はまた離れていってしまうのも人の常だった。
その年の後半、ジェシカが再び妊娠したことを発表した。彼女がもう一人子供をつくろうとダンを説得したに違いない、とカースティは思った。壊れた家族を修復する最善の方法は、新たな命をつくることよ、という彼女の声が聞こえてくるようで頭を振った。一人の人間の欠落を別の人間で埋める。失恋して新たな恋を探すみたいで嫌だったが、彼女はそのことを決して口にはしなかった。
「大丈夫?」とカースティはジェシカとパトリックに聞いた。
「なんてことないよ」と彼は答えたが、ジェシカはただ頷いただけだった。「もっとウィスキーを飲みたかったけどな」と彼は付け加えた。
「パパがこの写真を現像してたなんて知らなかったわ」
「これを撮ったことすら忘れてたよ」
「マックスが、おじいちゃんおばあちゃんと初めて過ごしたクリスマスだったのよ」とジェシカが言った。「彼はカメラを持ったきり、ほとんど手放さなかったわ」
「たしかに」とカースティは言った。
「もっとあるかしら?」ジェシカは妹からアルバムを受け取ると、過去の集合写真がもっとあるんじゃないかと期待しながら、というか、むしろハラハラしながらページをめくった。
しかし、もう写真はなかった。代わりに、次のページを開くと、テープで貼られた封筒が目に飛び込んできた。封筒はボロボロで変色し、しわくちゃだった。表面にはドイツの郵便切手が貼られ、その上に押された青いインクの〈エアメール〉スタンプが少し滲んでいる。日付は2019年8月、父親が亡くなる1ヶ月余り前のものだ。宛先の住所は手書きだったが、カースティには見覚えのない乱雑な筆跡で書かれていた。
ジェリー・カドガン様
6 ギャントン通り
ホーブ、BN6 7JP
イングランド
その住所の上に、ジェリーが書いたとわかる不安定な筆跡で「これを開けろ」と書き込んであった。
「私が開けようか?」とカースティが名乗り出て、他の2人は頷いた。
彼女は封筒をアルバムから剝がし、裏に折り込まれた糊代(のりしろ)を持ち上げてみた。乾ききった糊はほとんど粘着力がなく、するりと中身を取り出すと、テーブルの上に置いた。
それは3、4枚の紙の束で、1枚目のA5のメモ用紙には、封筒の表に書かれた住所と同じ字体で、こう綴られていた。
あなたに知らせておいた方がいいと思いました。私はあなたの家族以外では、一番あなたのことを知っている人だと思います。
とても残念です。
ジュディス
胸の高鳴りが喉の奥から聞こえてきそうだった。カースティがメモを脇に寄せると、200字にも満たない短い新聞記事が露わになった。記事の上には、まぎれもないアンドリュー・カドガンの写真が載っていて、故、マシュー・スターリングというドイツ名が付されていた。
「マシュー・スターリング? マシュー島のムクドリって意味か?」とパトリックが言った。彼は少し驚き、少し混乱し、おそらく少しは期待もしているような声音(こわね)だった。
「素敵な名前ね」とカースティは言った。冬の夕方、ブライトンの海岸で見たムクドリの群れを思い出した。空に小川のせせらぎが浮かび上がったかのように、何千羽もの鳥が一体となって、流れるように移動していた。誰一人排除されることなく、誰一人取り残されることなく、ゆらめきながら遠ざかっていく鳥たち。アンドリューが自分の新しい名前を決めた時、それがいつだったにせよ、その光景を思い浮かべたとは思えないが、その名前の詩的な本質が彼女の中に染み込んでくるようだった。
「どういう意味―」とジェシカが言い始めた。
「ちょっと待って」と言って、カースティは記事に目を通した。ドイツ語で書かれていて、翻訳機もなかったが、その必要はなかった。カースティは高校で習ったドイツ語の基礎的な知識を使い、読み進めていった。最も突出していて、最も恐ろしい事実を読み取るには十分だった。
彼女は唾を飲み込み、こみ上げてくる恐怖を無理やり押し下げ、そして口を開いた。
「彼は死んだ」と彼女は、新聞の切れ端に視線を落としたまま言った。兄と姉の顔を見ることができなかった。「去年の6月って書いてあるんだと思う。詳しい内容までは読み取れないけど、交通事故があったみたい」
「ちくしょう」とパトリックが言った。彼は妹から新聞記事をひったくると、まるで睨んでいれば目から光線でも出て、全ての単語が英語に再構築されるとでも思っているかのように、鋭いまなざしを向けた。彼が高校でドイツ語の授業をほとんど受けたことがなかったことをカースティは知っていた。お前の兄はドイツ語の授業をさぼっては、フィッシュ・アンド・チップス店にしけ込み、タバコを吸ってばかりいた、と教師が冗談めかして言っていたからだ。
「あなたには無理よ―」
「誰だ?」とパトリックが、カースティを遮るように聞いた。「このアンナ。アンナ・スターリングってのは誰だ?」
カースティは彼から新聞を受け取ると、もう一度できる限り頭を働かせて読み返した。個々の単語はなんとか頭に入ってくるのだが、フレーズ単位ではあまり意味が浮かんでこない。それにもかかわらず、この未知なる名前を説明する言葉がパッと頭にひらめいた。
「彼の娘よ」と彼女は静かに言った。「アンドリューに娘がいたんだわ。娘のアンナと、妻のジュディスが生き残ったって書いてあるんだと思う。アンナは4歳よ」
「同い年だな...」とパトリックは言いかけたが、尻すぼみに小声になった。
娘のマギーと同じ年頃の姪がいるという現実を急に突きつけられて、彼は戸惑い以上の息苦しさを感じた。2人はいとこであると同時に、友達になれるかもしれない。別の可能性、近々起こりうる世界では、カドガン家に新たなメンバーが2人増えることも考えられる。そうしたら、両親が亡くなったことでもたらされた喪失感を少しは埋めてくれるだろうか。「くそったれ」と彼は言った。「アンドリュー」
カースティは記事と手紙をジュディスから送られてきた封筒の中に戻した。
外では、雨がキャンピングカーの薄い天井をしつこいくらいリズミカルに叩き続けている。頭上に広がるダークグレーの空のせいかもしれないが、なんだか暗さが増してきたような気がする。父親の遺灰が眠っている浜辺は、汚くて、好き好んで訪れたいような場所ではなかった。コーラの空き缶やペットボトルが、網(あみ)や鮮やかな緑色の海藻に絡まっている。まるで初めて見るような景色だとカースティは感じた。
「ジェシカ」と彼女は言った。「あなたも何か言ってよ」
「そうすると、彼は知ってたってことね」と、彼女は1、2秒考えてから言った。「パパは全部知っていた。この子のことも、奥さんのことも。アンドリューの新しい名前も、そして死んだことも」
「まあ、送られてきたこの記事に載ってることだけでしょうけどね」
「でも彼は言わなかった。言わずに彼は―」
「同じことだろ?」とパトリックが言った。「もし彼が、死ぬ2週間前とかにアンドリューのことをお前に話したとして、そしたらお前はどうした?」
「私は...その」とジェシカは言葉に詰まった。その場合、自分がどういう行動を取ったのか、明らかに彼女はわからないようだった。他の2人も同様にわからなかった。「彼はきっと、私たちに考えさせようとした...」
「いいえ、そうじゃないわ」とカースティは言った。「彼がどこにいるのか、そんなの考えたってわかりっこないし、堂々巡りを繰り返すだけ。パパはどうしても私たちにこの旅をさせたかったのよ。その結果、私たちは前よりいい関係になれたじゃない。もしアンドリューのことを、こういう七面倒なことをする前に私たちに話していたら、どうせ私たちのことだから口喧嘩を始めて、お互いに責任の擦(なす)り付け合いになっていたでしょうね。そしてパパには、そうなることがお見通しだったのよ」
それは単なる仮説に過ぎないと、カースティはわかっていた。ジェリー・カドガンがなぜ、遠く離れた場所で暮らしていた、今は亡き息子の知らせをアルバムの最後に載せたのか、理由は知る由もないが、彼が指定した順番の最後にこれを持ってきたということは、一番重要なことだったのかもしれない。残された3人の子供が再び仲良くなること、それ以外にも、彼の望みはあったのかもしれない。
「得たものはあった。というか、大きな収穫だったわ」とジェシカが言った。彼女の声に嫌味な響きはなく、代わりに悲しみと、少しの後悔が感じられた。
「俺たちが手にした何かは、この封筒には入りきらないものだな」とパトリックが言った。
カースティは釣り具箱を取りにテーブルを離れた。
中身はもう空っぽだった。ウィスキーは飲み干した。アルバムは探索し終えた。遺灰は撒いた。彼女は昔の思い出の詰まった重いアルバムを手に取ると、釣り具箱の中に入れた。一緒に、ウィスキーの箱と、アンドリューの記事とジュディスからのメモが入った封筒も、中に入れる。
彼女は、この女性とその娘、つまり姪っ子にいつか会うことはあるのだろうかと考えた。それはない気がした。彼女たちはアンドリュー・カドガンの家族ではなく、マシュー・スターリングの家族なのだ。彼女たちは、彼の友人、彼の人生、彼が歩んできた歴史を、彼の口から聞くことで共有してきたのだろう。彼が妻と娘に語ることに決めた人生が、どんなバージョンだったのか、私には想像もつかない。血の繋がりはあっても、それ以外はアンドリューとほとんど共有してこなかったホーブの家族とは、かなり形態の異なる家族を、彼女たちは彼とともに築いてきたのだ。
このメモは、繋がりを持とうというより、むしろ親切心で送られてきたものだろう。家族の絆を何よりも大切にし、家族の幸福を守りたいと願った一人の男への、そう願いながらもそれを果たせなかったジェリーへの、思いやりだったのだ。
カースティは釣り具箱を閉じて鍵をかけ、テーブルの下にそれを置くと、帰路につこうと立ち上がった。まだ座ったままのパトリックとジェシカを見下ろす。二人ともぼんやりした表情で、〈フォーマイカ・テーブル〉の上で組み合わせた両手を見つめている。まるで2人でチェスをしていて、お互いに次の一手を考えているかのようだった。
「そうね」と彼女は言った。「目的は果たしたし、祝杯をあげたい気分だね。パブでも行っとく?」
〔感想〕20220625
今日は午前中訳そうとしたら、野暮用で飛んで、午後訳そうとしたら、気温が37度とかで(体温を超えて)頭がぼんやりして、夜(今)訳そうとしたら、寝ないと集中力が回復しそうにないから、明日でいっか!ってなった...汗(笑)
久しぶりに感想を書こうかな。
海辺で遺灰を撒いたシーンで泣いて、アンドリューの記事で泣いて、最近は泣きながら訳してばかりだけど、1年近く前に訳したプロローグを読み返してみたら、我ながら、訳がうまっ!ってうなってしまった!!笑
そこじゃなくて、ちゃんとアンドリューの伏線が張ってあったんですね。プロローグを訳してる時は、ジェリーの妻のスーに関係してる何か(不倫とか?)かと思ってた...笑←なんで不倫??笑笑
我ながら、引きの力があるというか、訳した作品がまた「当たり」だな!←それいつも書くけどさ、出版されてるって時点で全部「当たり」なんじゃね!笑←えっ、売ってるアイスの棒全部に「当たり」って書いてないだろ!
パート 4
チャプター 14
バーカムステッド、ハートフォードシャー州
ジェシカ
「よしっ」と彼女は声を上げた。「みんな、準備できた?」
「もう少しだ」とダンが叫び返す。
階段の下にある棚からコートや靴を引っ張り出す物音が、がさごそと聞こえてくる。それだけで、夫も子供たちも、まだ準備ができていないことがわかった。11時ちょうどに出発する予定だというのに、彼らはスマホやらゲームやらでぐずぐずしていて、すっかり時間を浪費してしまった。
「11時に出発するって言ったでしょ。もう10時過ぎよ」
「運転で挽回するよ」とダンが叫び返した。
「近道はやめて。スピードの出し過ぎもダメ」と彼女は言った。キャンピングカーの運転中にタイヤがパンクして以来、高速道路での事故を極度に恐れ、用心深くなっていた。もっとも、グレットナでの事故があったからこそ、そのあと兄妹3人は、まさに彼らが必要としていた時間を過ごすことができたのだが。
ジェシカはスマホを確認した。〈エアビーアンドビー〉を通じて知り合ったブライトンの家主からメッセージが届いていた。今日の午後、到着したら近所を案内してくれるという。ブライトンは生まれ育った街だからその必要はないわ、とでも返信を打とうと思ったが、考え直す。ここ数年、南海岸で過ごす時間がほとんどなかったので、大きく様変わりした街を案内してもらうと助かるかもしれない、というのが実情だった。
3人がまだ慌ただしく騒いでいる中、もうしばらくかかりそうだった(ダンはいつも子供たちに支度させるのに手間取り、私ほどすんなりこなせない)ので、ジェシカはリビングへ向かい、つい最近本棚の隅に追加されたばかりの写真立てを手に取った。
ポート・エレンの海辺を背景に、雨に濡れ、風に吹かれているパトリックとカースティ、そして彼女自身が写っている。あれからパブに向かう途中、犬を連れた男が通りかかり、カースティが彼に頼んで、3人の写真を撮ってもらったのだ。
ジェシカとパトリックが困惑して彼女を見ると、カースティは「後世に残すためよ」と説明した。長い間行方不明だった兄が亡くなっていたことを知った直後のこの瞬間を、なぜ彼女はデジタルプリントして、神棚に祭るみたいに後世まで飾っておきたいのか、その時の2人には理解できなかった。「今日のことはしっかり記憶に焼き付けなきゃね」
彼らはもうへとへとで、感情がぶれ気味だった。パトリックとカースティは無理してカメラに向かって微笑んだ。ジェシカは、自分の気持ちを表すというよりは、ポーズを決めるみたいに、半笑いのような表情をしていた。
その後、パブでギネス・ビールが溢れそうなグラスに口をつけながら、パトリックがある提案をした。それがきっかけとなり、ジェシカと彼女の家族は、これから南へ向けて出発しようとしているわけだ。
「考えてたんだけどさ。また一緒に大晦日を過ごさないか。すべてがわかった今こそ、前みたいに。こんなこと言いたくはないけど、きっとパパもそれを望んでるだろうし」
ジェシカは、彼の言う通りだとすぐさま思った。3人の間に亀裂を生じさせた難問が、ようやく解けたのだ。アンドリューの失踪で生じた不和も解消された。もう、3人が友達にならない理由はどこにもない。こうして一緒に今年を終え、来年を迎えることは当然の成り行きだった。
「あと10秒で出発するわよ」とジェシカが家の中に呼びかけた。ダンと子供たちが、コートやバッグ、帽子やマフラーでぐるぐる巻きになった状態で廊下に出てきた。マックスとエルスペスは真っ先に玄関を出て、車まで走っていった。ダンが防犯ブザーをセットし、リビングルームの明かりがついていることを、またチェックしている。何万回確認すれば気が済むのかしら?
「準備はいいかい?」と言うなり、彼がジェシカの唇にキスをした。彼は最近、以前より愛情深くなり、優しく接してくれる。これもポート・エレンへの旅がもたらした功名なのかもしれない。2人の関係から少し血が抜け、プレッシャーから解放された気分だった。
「ええ、いいわ」
約2時間後、ジェシカはハンドルを握り、幼い頃から慣れ親しんだ道路を走っていた。さながら観光ガイドのように、ランドマーク的な建物を指差しては、子供たちに説明していた。前回来た時は2人ともまだ幼かったので、あまり覚えていないらしい。
「ほら、この教会の前で、おばあちゃんとおじいちゃんが結婚式の写真を撮ったのよ」と彼女は、セント・フィリップ教会を通り過ぎたところで言った。
「でも、結婚した場所じゃないんでしょ?」とマックスが言った。ジェシカはアイラ島から戻ってすぐ、2人の子供に古い写真を見せたのだ。そして初めて、自分の家族について、醜い部分もさらけ出して真実を話した。
「そうよ、教会の前で写真を撮っただけ。あれが戸籍役場だった建物よ。今はマンションになっちゃったみたいね」
「何でもかんでもマンションになっちまうな」とダンがぼやくように言った。
「私たちはあそこで結婚したんだけどね」と彼女は、ダンのぼやきを打ち消すように明るく言い添えた。「パパと私が結婚した場所よ」
数分後、彼女は角を曲がって、もう二度とお目にかかることはないだろうと思っていた道に出た。ギャントン通りだ。その先にある、古くて白い邸宅に向かってゆっくりと車を走らせ、邸宅の脇の小道に車を止めた。彼女は玄関へと続く踏み段に目をやった。さらに視線を上げ、1階の窓を見て、2階の窓も見る。どの窓も、通行人や近所の人が、中を覗けるくらい大きな窓だ。(彼女は10代の頃、通りに面した2階の部屋を使っていて、思春期に外からの視線を痛いほど感じていた。)
「さあ、着いたわ」と彼女は、声のトーンを安定させようと気を配りながら言った。自分でも予期していなかったのだが、ジェシカはここに帰ってきたことに感激し、こみ上げてくる熱い想いでいっぱいだった。まるでこの家が、家族とともに保存され、待っていてくれたような気がした。
彼女が先導しながら、4人はそれぞれバッグを抱えて、小道を歩いた。玄関には、これ見よがしにライオンの口の形をした大きなドアノッカーがついている。ジェリーが買ってきて取り付けたところ、スーに怒られた代物(しろもの)だ。彼女はノッカーを掴むと、3回音を鳴らした。
出てきたのはカースティだった。彼女はブルーのデニムシャツに、虹色のストライプのセーターを着ていた。その色合いを見てジェシカは、エルスペスの去年の誕生日に作ったケーキを思い出した。
ギャントン通りの邸宅 ― ホーブ、サセックス
カースティ
「ああ! もう着いたのね」と彼女は、少し面食らったように後ずさり、間を空けてから続けた。「ちょうど言ってた時間ね。あなたのことだから、どうせ遅れると思ってたんだけど」
「そんなに驚かないでよ」
「どうぞ、入って」と彼女は、ジェシカの発言を無視して言った。一緒に育った家に姉を招き入れるのは、なんだか不思議な気分だった。「パトリックは今...あれね...」何の最中(さいちゅう)なのか、具体的なことを言うのがなんだか気恥ずかしくて、言葉に詰まった。兄と暮らすようになってよかったと思うことはたくさんある。彼のガールフレンドが泊まりに来た翌朝、物音や会話が聞こえ、彼の行動が手に取るようにわかるのは、よかったこととは言えないけど、10代に戻ったような気分にはなれる。兄や姉の行動に目を光らせつつ、いろんな行為に見て見ぬふりをしていた思春期の頃に、一気に引き戻された気分だった。「家の中の、どこかその辺にいると思う」と彼女は言った。
ジェシカ、ダン、マックス、エルスペスの4人家族は、彼女の後を追ってキッチンに入って行った。彼女はお湯を沸かし始めると、3つのマグカップにティーバッグを放り込んだ。
「あなたたち2人は何にする?」と彼女は、マックスとエルスペスに聞いた。2人とも、大晦日に祖父母の古い家に来ても、大して感激しているようには見えない。とはいえ、他にどんな反応を示せというのだろう? と、これが現実的な気がしてきた。「スカッシュ・ジュースがあるわ。それか水ね」
カースティは飲み物を用意すると、テーブルの4人に加わった。これもまた、少し妙な気分だった。アイラ島から帰ってきてすぐに、パトリックとここで暮らし始めた。その時以来、キッチンだけは手入れをせず、そのままの状態で使っている。食器類は2人の共有ということにして、壁には元々あった絵が数枚かかっている。表向きはまだ父親が使っていた頃のままで、この家で唯一、父親の指紋が完全には取り除かれていない場所だった。
「それで、どんな感じなの? 実家に戻ってきて」とジェシカが聞いた。
「快適よ。でも、すっかり私たちの家って感じるようになるには、もうしばらく時間がかかりそうね。やっぱりまだ、ママとパパの家って感じするし」
ギャントン通りの邸宅で暮らすことは、帰る道すがら、キャンピングカーの中で決めたことだった。
最初は、ヘブリディーズ諸島からサセックスまで、一気に帰ろうとした。しかし、マンチェスター辺りで一泊する必要があるとわかり、ウォリントン近くのサービス・エリアに直結したホテルに泊まった。
ジェシカはさっそくシャワーを浴びて、キャンピングカーの中で寝た日数分の汚れを洗い流していた。カースティとパトリックは、四方をそれぞれのファーストフード店の売店に囲まれた、広々としたレストラン・スペースでまず食事を取ることにした。半分くらいの席が埋まっている。
「あなたをどこで降ろせばいい?」とカースティが聞いた。2人は〈バーガーキング〉のフライドポテトをつまみながら、向かい合っていた。
「ロンドンが近づいてきたら、どこか適当な場所で。ステュには明日の夕方には戻ると言ってある」
「わかったわ」と彼女は言って、チョコレートミルクシェイクをズズズと吸い込んだ。「その後は、どうするの?」
「どういう意味?」
「これからのことよ。またイングランドで暮らすのなら、いつまでもステュの家のソファで寝泊まりしてるわけにはいかないでしょ?」
パトリックはこれに対して何も言わなかった。彼がシングルファーザーで、仕事もなく、住むところもないという現状をはっきりと思い知らせているみたいで、自分があまりにも残酷で、無遠慮すぎたかな、とカースティは考えた。
「わかってる」と彼は、老舗百貨店〈マークス&スペンサー〉が自社生産している缶ビールをごくごくと飲みながら言った。
「ロンドンに行けば、どこか見つかるかもしれないわ。ロンドンのちょっと郊外ならたぶん」と彼女は提案した。さすがに都市部は家賃も高いし、広々とした素敵な部屋に住むのは無理だろうとはわかった。
「ロンドンには住みたくないよ。アイルランドに戻ろうかと思ってるんだ」
「ブライトンに戻ってくる? それともホーブ?」と彼女は言った。パトリックが何か考え込んでいるのに気づいて聞いた。「どうしたの?」
「ホーブがいいかな。さっきから考えてたんだけどさ。ママとパパの家とか?」
「内見はあったけど、まだ誰も申し込んできてないよ。でも、そのお金を引っ越しの当てにするのはどうかと思うけど。それに、ホーブは一応高級住宅地だし、家賃だって―」
「いや、そこに住もうかと。俺とマギーで」
その考えに彼女は面食らった。カースティは家を売って、そのお金を3人で分けるものだと思っていた。ギャントン通りの邸宅は、パトリックとマギーが2人で住むには広すぎるのだ。
「本気じゃないんでしょ、パトリック。あの家に戻りたいってこと?」
「かもね」彼はそう言うと、すぐに付け加えた。「でも、いくらかお金は渡すよ。お前とジェシは...あれだろ...」
「そうね」
「もしくは」と彼が、少しためらうような声で提案した。「お前も引っ越してくればいいじゃないか。リヴィと一緒に」
「え? あなたと一緒に暮らすってこと?」
「考えてみてくれ。お前はあのアパートを持ってる。まあ、いい部屋だけど、風通しが悪くないか。隣人も変な奴ばっかりだろ。あの部屋を売り払えば、もちろん俺もアイルランドの家を売るし、そうしてお金を合わせれば、あの家を買い戻せる」
「それはそうだけど、でも、一緒に住むってことでしょ」
「それのどこが悪いんだ?」
彼がそう言った瞬間、カースティは何も悪いことはないと気づいた。あの家は十分広いから、一人になりたい時には、ちゃんと自分のスペースを確保できる。それに、ブライトン周辺の小さなアパートや賃貸住宅に2人が別々に住むよりは、確実にいい。
「あの女ね、だから引っ越してきたいんでしょ? あなたがメールしてた、クロエ」
「いや」と彼が、にやつきながら答えた。その表情を見てカースティは、やっぱり、と思った。ほぼ間違いなく、クロエのことも理由の一つではあるようだ。「そういうわけじゃなくて、そろそろホームに帰る頃合いかなってね」
旅を終えた2日後、さっそくパトリックはスチュの家からホーブに引っ越してきて、売りに出していた古い実家を取り戻した。そして、マギーが通う学校を探して手続きをした。さらに、家の所有権を移し、パトリックとカースティの共有にした。ジェシカには、アイルランドの家を売った売却益から、それ相応の金額を渡した。
それから数ヶ月の間に、パトリックは各部屋を装飾し、改装した。かつて父親がスーを説得して、多くの可能性を秘めたボロ家に引っ越してきた時の様子が蘇ってくるような、不思議な感覚を味わっていた。この家を改装していた父親が乗り移ったような妙な感覚だった。そこは次第に、両親の家と自分たちの家のハイブリッドになっていったが、いずれにしても、カドガン一家の家であることに変わりはない。
「彼がもうすぐ下りてくるわ」とカースティは言った。2階の床板がきしむ音でパトリックが階段の方へ移動しているのがわかったのだ。ちょうどジェシカを連れて、1階の各部屋を案内し終えたところだった。ラウンジも見違えるように改装されていた。両側の壁がダークブルーに塗り替えられ、家具の位置も様変わりし、パトリックのインテリアデザイナーとしての才能を感じさせた。父親が使っていた仕事部屋には、テレビとソファが置かれ、くつろげる個室のようになっていた。ラウンジのテレビで何を見るかについて意見が分かれた時のための、隠し部屋的な空間らしい。(たいてい、サッカーを見たいパトリックと、それ以外の人たちで意見が分かれるのだ。)
「べつに急いでないからいいのよ」とジェシカが言った。「またここに戻ってこれて嬉しいわ。私がまた、ここに帰ってくるとは思わなかったけどね」
「私もよ。彼はうまくやったでしょ? この壁とか」
「そうね。ホームって感じがする。でも、少し違うかな、新たなホームって感じね。言ってる意味わかる?」
カースティは微笑んだ。広々とした全面窓から庭を見ると、マギー、リヴィ、エルスペスが、数日前に降って溶けかかった雪で、どろどろの雪玉を作って遊んでいる。マックスはラウンジのソファに座り、両手で握り締めた携帯用ゲーム機に夢中だった。彼は四六時中そのゲーム機を掴んだままで、彼からそれを引き剝がすのは不可能に近かった。
庭だけは、やはりジェリー・カドガンの作品だという印象が強かった。草花の位置、芝生、池、池のほとりのベンチなど、彼が配置したそのままだ。彼が植えたアジサイは、今の季節は茶色の茎(くき)だけの状態だが、時期が来れば、薄いピンクの花を豪勢に咲かせるだろう。ラベンダーも、今は抜け殻のようなさやが萎(しお)れているだけだが、夏には紫の花を咲かせるはずだし、花壇に埋まった球根も、数ヶ月間冬眠した後には、むくむくと芽を出すだろう。
彼女とパトリックは、庭はこのままの形で残すことに同意していた。手入れは2人が引き継ぐことになるが、パパのものであることに変わりはない。
「じゃあ、ここで幸せなのね?」とジェシカが聞いた。「パトリックと暮らすのは、あまり苦にならない?」
「全然平気。むしろ気に入ってるわ。キャンピングカーより断然ましだしね」とカースティは言った。
2階でキーッとドアが開く音がして、遠くてまだよく聞こえないが、2人の話し声が階段を一足先に滑り降りてくる。
パトリック
「君はきっと気に入られるよ」と彼は言った。振り返ると、彼女はまだ口紅を塗っていた。それは普段使いの薄めのリップだった。ディナーやバーに出かける時は、もっと明るい、赤や紫の口紅をつけていたが、さすがに今日は控えめだ。彼女は髪を後ろで束ね、ポニーテールにしてから、鏡を覗き込んだ。そして、ため息をつくと、ポニーテールをほどき、また髪を下ろした。
「パトリック、あなたのお姉さんに最後に会ったのは、あなたのお父さんのお別れ会の会場だったわ。私はバーメイドをしてたのよ」
「それが?」
「なんかちょっと変じゃない? この前はウォッカ・トニックを差し出しながら、「お悔やみ申し上げます」とか言ってた人が、次に会った時には、幸せな家族気取りだなんて。それに、あなたの話を聞いてると、あなたのお姉さんって相当、怖そうっていうか」
「言いたいことはわかるけど、彼女は変わったんだ」と彼は言った。「まあ、少しだけど。彼女は...なんていうか、前より気楽な感じだよ」
「でも、前に比べたらってだけで、実際にはそんなに気楽でもないんでしょ?」
パトリックは少し考え込んでしまう。あの姉が、たとえ最高に機嫌のいい状態だったとしても、細かいことを気にせず、物事を成り行きに任せるような態度をとることがあるだろうか。
「いい感じ」とクロエが言った。彼女は前髪をさっとかき上げ、鏡に向かって微笑んだ。にっと笑顔をつくって、鏡で入念に歯を確認している。
「なんでそんなに緊張してるのかわからないな」
「大イベントでしょ? お正月をみなさんと過ごすのよ。あなたの家族と一緒によ。私たちが1階に下りるのが遅いから、きっとみなさん、私たちが...上でまだ」
「それはどうかな。彼女たちはそんな―」
「言わなくていいわ」と彼女が言った。
クロエがベッドに腰を下ろしたまま、腕を伸ばして靴を取り、それを履いている姿を、パトリックは横から眺めていた。正月早々、ぐうたらした午前を過ごしてしまった。空になったティーカップ、トーストの粉やマーマレードの残りがついた皿、ベッドの下に投げ出されたままの半分よじれた靴下や下着など、部屋のあちこちにその名残が散見している。パトリックが早朝、寒さに震えながら彼女のために買いに行った新聞は、しわくちゃになってベッドサイド・テーブルに置かれていた。
昨日は、ほぼ一週間ぶりに2人が一緒に過ごした夜だった。一週間前のクリスマス、彼女はバースの実家で過ごしたのだが、子供たちがおじいちゃんと過ごしている間、少し外出して、バースのホテルで彼と会ったのだ。パトリックはその後、ステュとサラの家に寄り、再びソファで寝泊まりしたのだが、数ヶ月前にそのソファを借りていた時よりも、ずっと気楽で幸福感に包まれていた。
人生が逆戻りしたみたいで不思議な気分だった。10代後半や、20代前半の頃に戻ったような甘酸っぱいときめきがあった。お互いの部屋に泊まったり、やがて自分の歯ブラシを洗面台の横に置きっぱなしにできるだけの自信がついたり、相手の友人や家族に会って緊張したり、2人とも結婚歴があるからこそ、そんな時期はもう二度と訪れないと思っていた。新しい関係の息吹がもたらす興奮やら、この先どうなるかわからない不安やらを、再び経験することになろうとは思ってもみなかった。
それにしても、いい気分だった。クロエと一緒にいるのが心地よかったし、彼女も自分と一緒にいるのが心地よさそうだという実感が湧いてきた。お互いの子供たちは十分に仲良くなり、それぞれの元パートナーは、自分が失望させたはずの相手が前に進んでいることを知ると、少し身構えるようになった。すべては、あるべき姿になっていった。
「どう? 私いい感じでしょ?」グレーのラムズウールのセーターに、黒のジーンズ、赤いコンバースを履いて、彼女が目の前で立ち上がった。
「ひどいな」
「パトリックったら」
「君は何を着たって素敵だよ。いつだってそうさ。さあ、行こう」
クロエは彼の後について寝室を出ると、階段を下りて1階の廊下に出た。
パトリックは、マギーと引っ越してきて間もなく、廊下の壁をクリーム色に塗って、そこに家族の写真を並べるように飾った。中でもここを通るたびに彼の目を引き付ける写真が2つあった。1つはアイラ島の浜辺で姉と妹と3人で写っている写真だった。そしてもう1つは、何年も前のクリスマスにソファで4人が揃っている写真だ。真ん中でアンドリューが両手を上げている。
旅から帰ってきて以来、弟のことがパトリックの頭から離れることはほとんどなかった。この数週間、彼はジュディスに連絡を取ろうかと考えていた。1人の男が接点となり、微かに重なった全く別々の家族の間に、何らかの関係を築こうかと考えた。しかし、Facebookで検索する前に手を止め、パトリックは、アンドリューが去ったのには理由があったんだと自分に言い聞かせた。その解釈は、家族それぞれが自分の胸によく聞いて嚙み締めればいいのだが、それを尊重してやることが重要なんだ。ジュディスは直接連絡を取らず、そっと新聞記事だけを送ってきた。彼女はそれだけを望んでいて、誰にも、それ以上の関係にまで広げようとする権利はない。
「やっと来たわね」とジェシカが言って、写真が並んだ廊下を抜け、キッチンに入っていった2人を出迎えた。クロエがすでに彼女に対して尻込みしているようで、その様子を見て彼も少したじろいでしまう。
「黙れ」と彼は茶化すように言いながら、姉を抱き締め、義理の兄の手を握った。「ここまで、いい旅だった?」
「よかったわ。でも、その話はしたくないの」ジェシカはそう言うと、彼を押しのけ、両手を広げながらクロエに近づいた。「こちらはたしか―」
「クロエだよ」とパトリックが言った。「クロエ、彼女がジェシカ」
2人はまるで昔からの知り合いのように抱き合った。少なくともジェシカはそう振る舞っていた。クロエの方は少し緊張しているように見えた。ジェシカは意識してそういう振る舞いができることを彼は知っていた。
「会えてすごく嬉しいわ」とジェシカが言った。
「またまた。そんな」
「あのね、最初にあなたたち2人が話してるのを見た時...」と彼女は、最後にクロエを見かけたのは父のお別れ会だったはずだが、その話題を避けて言った。「私は彼がバーメイドを口説いてるのかと思ったのよ。で、彼をこっぴどく叱ったの」
「たしかに、彼は口説いてきました」とクロエが言うと、ジェシカは声を上げて笑った。冗談で言ったつもりが正しかったから、というよりも、彼女を受け入れた感じの笑い方だった。クロエは印象を良くしようとして、そう言ったのだろうか? パトリックには真意がわからなかった。
「とにかく」と彼が口を挟んだ。「これからの計画は?」
「そうね、まずみんなで散歩でもしようかと思ってるんだ」とカースティが言った。「海岸沿いを歩いて、いい場所を選びましょ。それから一旦ここに戻ってきて、夕食を食べてから、実行しましょう。真夜中にね」
「いいね」ジェシカは紅茶を一口すすってから、言った。「いい感じ」
パトリックが料理した夕食を食べ終え、デザートも食べ、ワインをみんなで分け、ボトル1本をほぼ空にしたところで、カースティ、ジェシカ、ダン、クロエと彼の5人はコートを着込んで、古い邸宅の玄関で待ち合わせた。その日の朝、彼は新聞を買いに出たついでに、秋からキャンピングカーを停めっぱなしの近くの駐車場まで行って、釣り具箱を車から運び出し、家に持ってきていた。
「凍えそうじゃない?」とジェシカが言った。
「マイナス2度って言ってたわ」とカースティが言った。
「マジかよ。じゃあ、さっさと済ませた方がよさそうだな?」
パトリックは5人の小さな一団の先頭に立って、玄関前の踏み段を下り、通りに出た。道を進み、漆喰(しっくい)の壁が建ち並ぶ邸宅街へと向かう。道の突き当りに〈キングス・エスプラネード通り〉があって、その向こうが海岸だ。その途中、キャンピングカーを停めてある駐車場を通りかかった。再び土や埃を被ってしまったが、パトリックは、まだそれを売る気にはなれなかった。
小さなスロープを下りると、子供の頃によく過ごした砂利ばかりのビーチに出る。パトリックは、iPhoneをトーチ代わりにして前方の足元を照らしながら、早足で歩いた。(予想以上に寒かった。)他のみんなも同意見らしく、凍えそうだよ、などと呟きながら彼の後についてくる。
「この辺りでいいかな?」と彼は、横殴りの風の音と打ち寄せる波の音にかき消されないように声を張った。昼間、子供たちも連れてここに来た時、ビーチ小屋の前にある古いコンクリートの壁に向かって、ボールを蹴って遊んだ場所だ。
「どこでもいいわ」とジェシカが叫んだ。「とにかく急ぎましょ!」
「待って。これは深遠なる儀式のはずでしょ」
「寒すぎて深遠になんかなれないわね」
パトリックは釣り具箱を砂利の上に置くと、それを開けた。まず最初にウィスキーのボトルと、カップを5つ取り出し、それをみんなに回して、それぞれに少しずつウィスキーを注いでいった。 次に彼は、ポート・エレンで少し残しておいたジェリー・カドガンの遺灰が入った骨壺と、妻のスーの残りの遺灰を納めた骨壺を取り出した。暖炉の上に何年も祀(まつ)ってあった壺だ。彼は両方の壺を開き、姉妹に一握りずつ取るように促した。3人は右手と左手を、ジェリーとスーの遺灰を合わせると、靴の底がちょうど水際を踏むところまで歩を進めた。
「準備はいい?」と彼がクロエに呼びかけると、彼女はポータブル・スピーカーの再生ボタンを押した。彼が父のリクエスト曲を用意しておいたのだ。『ウー・ラ・ラ』のギターリフが流れ出し、パトリックが「スリー、ツー、ワン」と声を上げた。
パトリック、ジェシカ、カースティ、カドガン家の3人は、一斉に宙に向かって両手を広げた。
〔訳者あとがき〕
藍はやっぱりジェシカが好きだな。タバコを吸っていることを隠しているつもりが、全員にバレてるとか、爆笑
帰ろうと思ったらパスポートがないとか、笑
色々ユーモアに溢れているというか、コーヒーメーカーを旅に持参しちゃうとかね! 実は藍もコーヒー好きなんですよ!←知らねーよ!!
あと、藍もきれい好きだから、旅から帰る道すがら、マンチェスター辺りで一泊したら、ジェシカみたいに真っ先にお風呂に入るだろうな!(一旦冒険したり、雨に打たれたりしないことには、その後の爽快感って味わえないんだよね。by 藍)
タイトルの『The Way Back』は、もちろん「ホームに帰る」って意味もあるんだろうけど、あと藍の予想では、「過去に遡る」ですね! あれこれ、フランス旅行とかを振り返ってましたよね~! あと何を思い出してたっけ?(思い出せねー笑)
そんな、老いが始まっている藍ですが、プロローグで描かれていたジェリーの晩年の悲哀を知るには、まだまだ青二才の甘ちゃんですね。実はドイツに旅立っていたアンドリューに憧れている藍です。笑
スマートウォッチで浮気がバレたというエピソードは、藍的には、何かの海外ドラマ(『Younger サバヨミ大作戦!』だったかな?)で見たことがあったので、そんなに驚きませんでした。そういうトリッキーさよりも、人間同士のガチンコのせめぎ合いですね、この小説の醍醐味は! 血を分けた兄妹だろうが、ゆずれないものはゆずれないし、腹も立ちます!
ただ、折り合いをつけて、目をつぶるところは目をつぶって、欠点を受け入れて仲良くやっていきましょうね。たとえそれが遺伝子に逆行(way back)する行為だったとしても...
スーの死だけが謎のままでした。←人はみんな死ぬんだよ。
2022年7月3日 乃木坂に咲いた『君に叱られた』を聴きながら。←それって、「庭に咲いたヒヤシンスの花を眺めながら。」とかって締めるんじゃね!爆笑
閃いた! たぶん『The Way Back』を書いた時、著者の念頭にあったのは、ビートルズの『ゴールデンスランバー』だ!!
Golden Slumbers by Paul Mccartney / John Lennon
Once there was a way
To get back homeward
Once there was a way
To get back home
Sleep, pretty darling, do not cry
And l will sing a lullaby
Golden slumbers fill your eyes
Smiles await you when you rise
Sleep pretty darling, do not cry
And l will sing a lullaby
父へのララバイ(父よ、安らかに眠れ)ってことか♬
そうすると、『Our Life in a Day』はビートルズの『a day in the life』の変奏曲なんだ!←気づくの遅っ!!笑
〈追記〉
この〔訳者あとがき〕でビートルズの『ゴールデンスランバー』について書いたことがきっかけとなり、何年かぶりに伊坂幸太郎の『ゴールデンスランバー』を読み返していた。第一部~第三部は比較的短いので数日で読み通し、第四部の青柳パートに入った翌日くらいに、現実世界の事件が飛び込んできて、どっちが小説の中か見まがうくらいの衝撃を受けた。
それからというもの、リアルとフィクションの狭間でなんだかふわふわしている。
英語と日本語の間を揺れ動きながら、この小説を訳している時、ジェリーが好きだった曲が出て来るたびに、グーグルで検索し、実際にどんな曲か聴いてみた。どれもリアルに存在する曲で、でもそれらを聴いていたジェリーは、もういなくて...
ジェリーが好んで聴いた曲はどれもバンドとか、男性ボーカルの曲ばかりだった。←君が好きな曲はアイドルソングばかりだね...
No comments:
Post a Comment